不動産価格が高騰し続ける東京でアパート経営を始めたいものの、「どのエリアを選べば空室で悩まないのか」「高値づかみを避ける方法はあるのか」と不安に感じる方は多いでしょう。本記事では、東京都内で物件を選ぶ際に押さえるべき人口動態や交通網、利回り以外の評価軸までを網羅的に解説します。初めてでも迷わず判断できるよう、2025年9月時点の最新データと実務経験に基づいた視点で整理したので、読み終えたときには自分なりの立地戦略を描けるはずです。
東京市場の特徴を読み解く
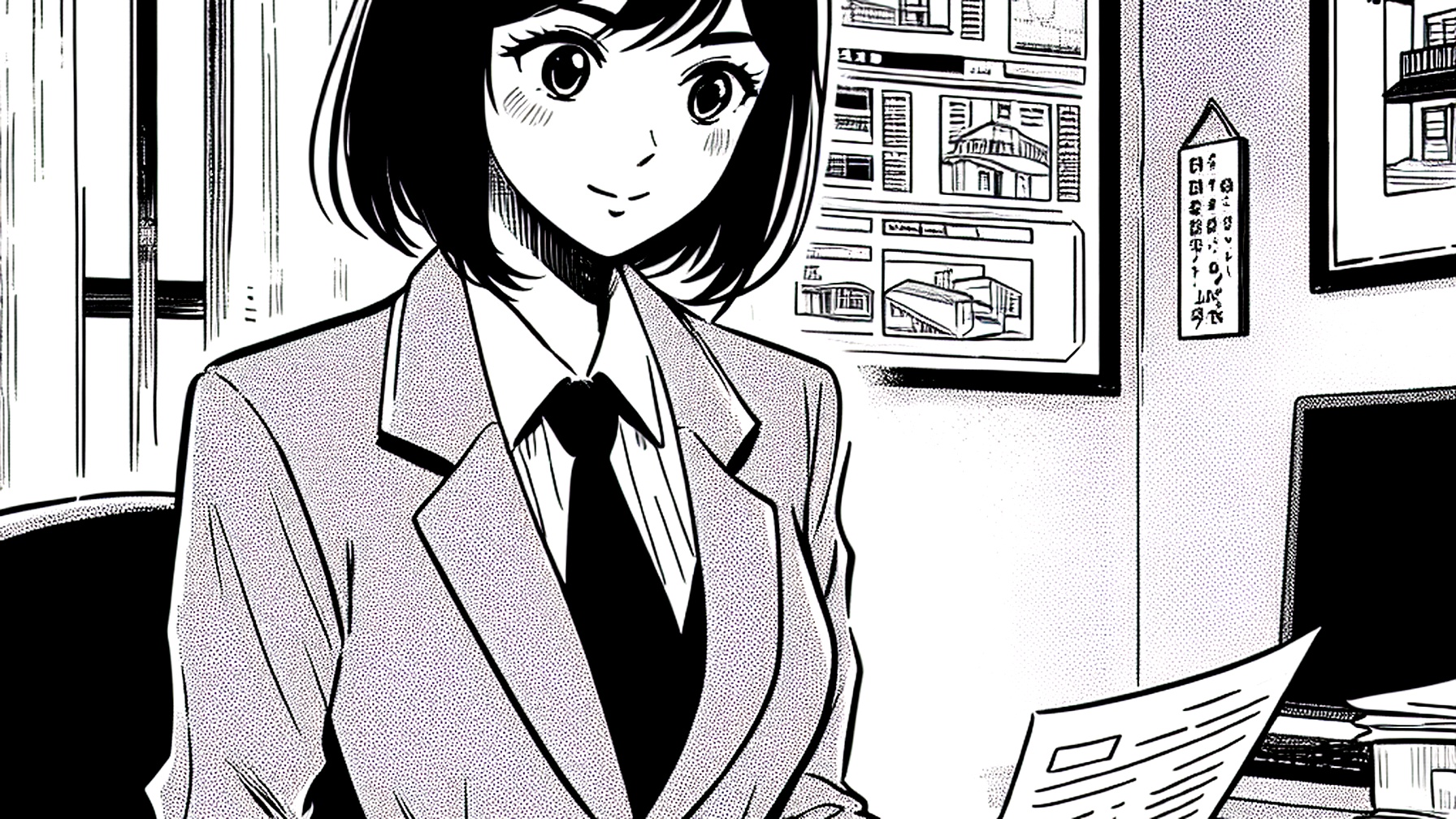
重要なのは、全国平均と東京固有の市場構造の違いを理解することです。国土交通省の住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%ですが、東京23区内に限れば13.4%と約8ポイント低く推移しています。この差は人口集中と雇用機会の豊富さによるものです。
まず、東京では単身世帯が増え続けており、総務省の住民基本台帳ベースで2024年から2025年にかけて1.2%の純増となりました。単身者向けの1Kやワンルームは依然として需要が底堅く、郊外に比べて空室期間が短い傾向があります。また、テレワーク定着により都心回帰の一服感も指摘されましたが、実際には「週3出社」が一般化し、アクセスの良い区部周辺駅が再評価されています。
しかし、賃料が高止まりする一方で、利回りは年々圧縮されています。2025年4月の民間調査では新築RC(鉄筋コンクリート)で表面利回り3.8%前後が平均です。数字だけを追うと魅力を感じにくいかもしれませんが、低利回りと低リスクは表裏一体です。空室期間の短さや賃料下落幅の小ささを加味すれば、実質的なリターンは地方高利回り物件と大差ないケースもあります。
このように、東京市場は「高値だがリスクも低減されている」構造であると理解しておくと、次のエリア選定がぐっと楽になります。
エリア別人口動態と賃貸需要
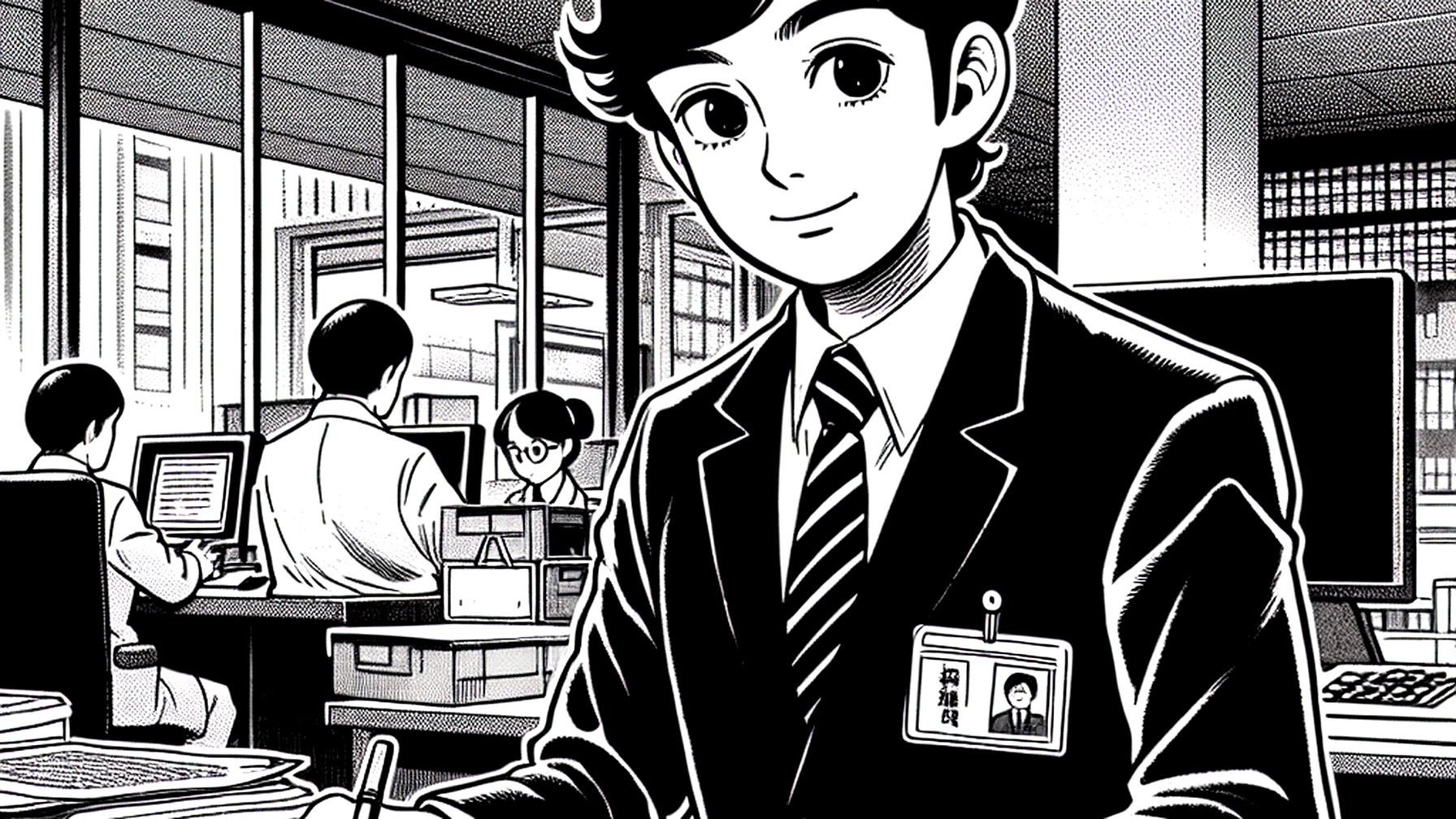
まず押さえておきたいのは、エリアにより人口動態が大きく異なる点です。東京都の総人口は横ばいですが、23区内では千代田・中央・港・品川・江東の湾岸部が増加し、多摩地域の一部では微減が続いています。特に江東区の2025年最新推計では年間0.9%の増加が確認され、若い共働き世帯が流入中です。
一方で、世田谷や杉並のような住宅系エリアはファミリー層中心で、単身向けより2DK以上の需要が高い傾向があります。つまり、同じ東京でもターゲット属性によって区を選ぶ必要があるわけです。賃貸需要を読み違えると、空室率の数字が低いエリアでも募集期間が長引きます。
地域人口の将来推計は東京都都市整備局の資料で無料公開されています。グラフだけを見るのではなく、人口増減の理由を把握してください。鉄道新線の開業、大学キャンパスの移転、再開発などが短期的に影響するためです。例えば、2029年に予定される品川地下新駅の周辺は、すでに地価が上昇傾向にあり、賃料も先行して上がる可能性が高いと考えられます。
このように、単純な人口増減の数値ではなく、背後にある雇用・教育・交通の変化を読むことで、10年先を見据えた立地選定が行えます。
交通アクセスと生活利便性の見極め方
ポイントは、乗換回数と徒歩分数の合わせ技で利便性を定量化することです。首都圏では「ドア・ツー・ドア40分以内」が通勤許容ラインと言われますが、乗換1回以内と徒歩10分以内の条件が加わると成約スピードが格段に上がります。
まず、徒歩分数は不動産表示の「1分=80m」ではなく、実際の生活動線を調べましょう。坂道や信号の待ち時間を含めたGoogleマップの実測値をレポートにまとめると、内見時の説得力が高まります。また、複数路線利用可と広告に記載する場合は、主要駅への所要時間も示すと反響率が上がります。
次に、生活利便性としてスーパーやドラッグストアの24時間営業の有無、救急対応の総合病院までの距離もチェックしましょう。単身者にとってはコンビニの密度よりも、夜間医療のアクセスが意外と重視されるという調査結果もあります。2024年に日本政策投資銀行が行ったアンケートでは、30代単身者の47%が「医療機関へのアクセス」を物件選定の重要要因に挙げました。
最後に、都市計画上の将来リスクも見逃せません。都市高速や幹線道路の延伸予定地に近すぎると騒音や日影の問題が発生する可能性があります。東京都の環境アセスメント情報を確認し、長期視点での住環境を評価することが不可欠です。
利回りだけに頼らない物件評価術
実は、東京でのアパート経営はキャッシュフローの安定性を最優先に考えるべきです。表面利回り5%と聞くと魅力的ですが、修繕積立や空室損を差し引くと手残りは大きく変わります。2025年時点で築20年の木造アパートを想定すると、大規模修繕費は10年以内に平均250万円かかるとの試算があります。
まず、ネット利回り(実質利回り)を算出する際は、管理費・共益費を含む年間運営費として家賃収入の15%を見込むのが無難です。さらに、金利は長期固定で1.3%前後が主流ですが、返済比率を家賃収入の50%以内に抑えると、空室3か月でも赤字になりません。
また、「外部評価額>購入価格」を実現できる物件に絞ると、安全域が確保できます。日本不動産研究所の収益還元価格を参考にしながら、差額が5%以上あれば、売却出口でも優位に立てるでしょう。固定資産税評価額だけでなく、近隣成約事例も徹底的に比較し、割高な案件を避けることが肝要です。
つまり、東京では表面利回りよりも、運営費率と金利、そして出口価格の妥当性を重視する姿勢が長期的な成功につながります。
2025年度支援策と金融環境の活用法
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続している「賃貸住宅省エネ改修支援事業」です。これは賃貸物件の断熱性能向上や高効率設備導入に対して、上限120万円まで補助が受けられる制度で、申請は工事前に行う必要があります。投資利回りを底上げする手段として検討すると良いでしょう。
金融環境では、日本銀行のマイナス金利政策は解除されたものの、長期金利は1%台前半にとどまっています。地方銀行や信用金庫では、自己資金30%を投入すれば0.9%台の融資を引き出せる例もあります。金利上昇リスクを抑えるには、変動金利で借りても借入期間20年以内に設定する、もしくは全期間固定を選ぶなど、出口戦略と合わせて決めることが大切です。
さらに、都内の一部自治体では、空き家対策として小規模アパートへの用途変更に対し固定資産税を3年間半額にする条例が2025年度も延長されています。対象地域、対象工事費は細かく定められているため、取得前に必ず自治体窓口で確認してください。
これらの支援策や金融条件は、単にコストを下げるだけでなく、投資期間全体のキャッシュフローを安定させる役割を果たします。制度利用の可否で事業計画は大きく変わるので、早い段階から専門家に相談するのが賢明です。
まとめ
東京でのアパート経営は物件価格が高く、利回りが低く見えるかもしれませんが、人口動態の強さと交通網の密度が空室リスクを大幅に下げています。エリア選定では、人口増の背景や将来の交通計画を読み解き、ターゲット属性に合った間取りと利便性を提供することが要です。さらに、運営費率と出口価格を重視する評価手法、2025年度の省エネ補助や自治体減税を組み合わせれば、安定収益を確保しつつ資産価値を守れます。まずは気になるエリアの人口推計と金融機関の融資条件を調べ、自分だけの立地戦略を具体化してみましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 東京都都市整備局 人口推計資料 2025年版 – https://www.toshiseibyo.metro.tokyo.lg.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 2025年6月 – https://www.boj.or.jp
- 日本政策投資銀行 生活者アンケート2024 – https://www.dbj.jp
- 日本不動産研究所 市場動向レポート2025年上期 – https://www.reinet.or.jp

