不動産投資を始めたいけれど、新築は高すぎて手が出ない。そう感じている方は多いでしょう。中古マンションなら価格を抑えながら、都心にも手が届く可能性があります。本記事では「なぜ マンション投資 中古」が今あらためて注目されるのかを解説します。価格差の理由、収益の考え方、具体的なリスクへの備え方まで整理するので、読み終えるころには最初の一歩を踏み出す自信がつくはずです。
中古マンション投資の魅力を整理する
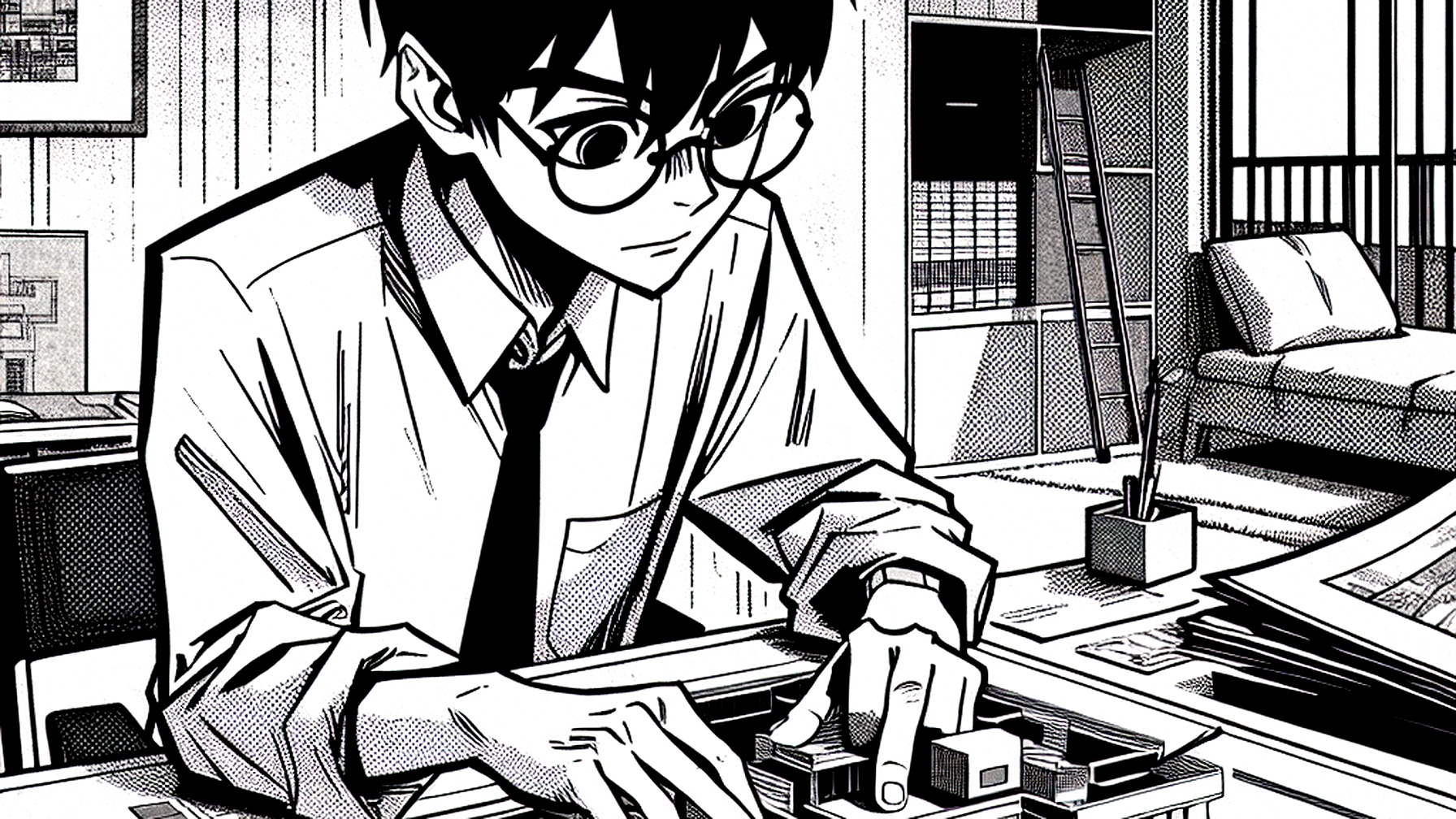
まず押さえておきたいのは、中古マンション投資が「情報量の多さ」と「収益の見えやすさ」で新築より優位に立つ点です。築十年以上の物件は賃料推移や修繕履歴が公開されている場合が多く、実績を基に収益計画を立てられます。加えて、新築プレミアムと呼ばれる上乗せ部分がすでに剝落しており、取得価格が相対的に低いことも見逃せません。つまり、数字の裏付けを取りやすく、利回りも高まりやすいのが中古の特徴なのです。
一方で、築年数が進むほど設備更新や修繕積立金の上昇が避けられません。しかしこれはリスクが見えやすい分、あらかじめ計画に盛り込めるという利点にもなります。国土交通省の「住宅市場動向調査」によると、築二十年前後の区分所有物件でも平均空室率は五%台で推移しています。需要が途切れない都市部を選べば、長期運用のハードルは想像ほど高くありません。
新築と比較した価格メリット
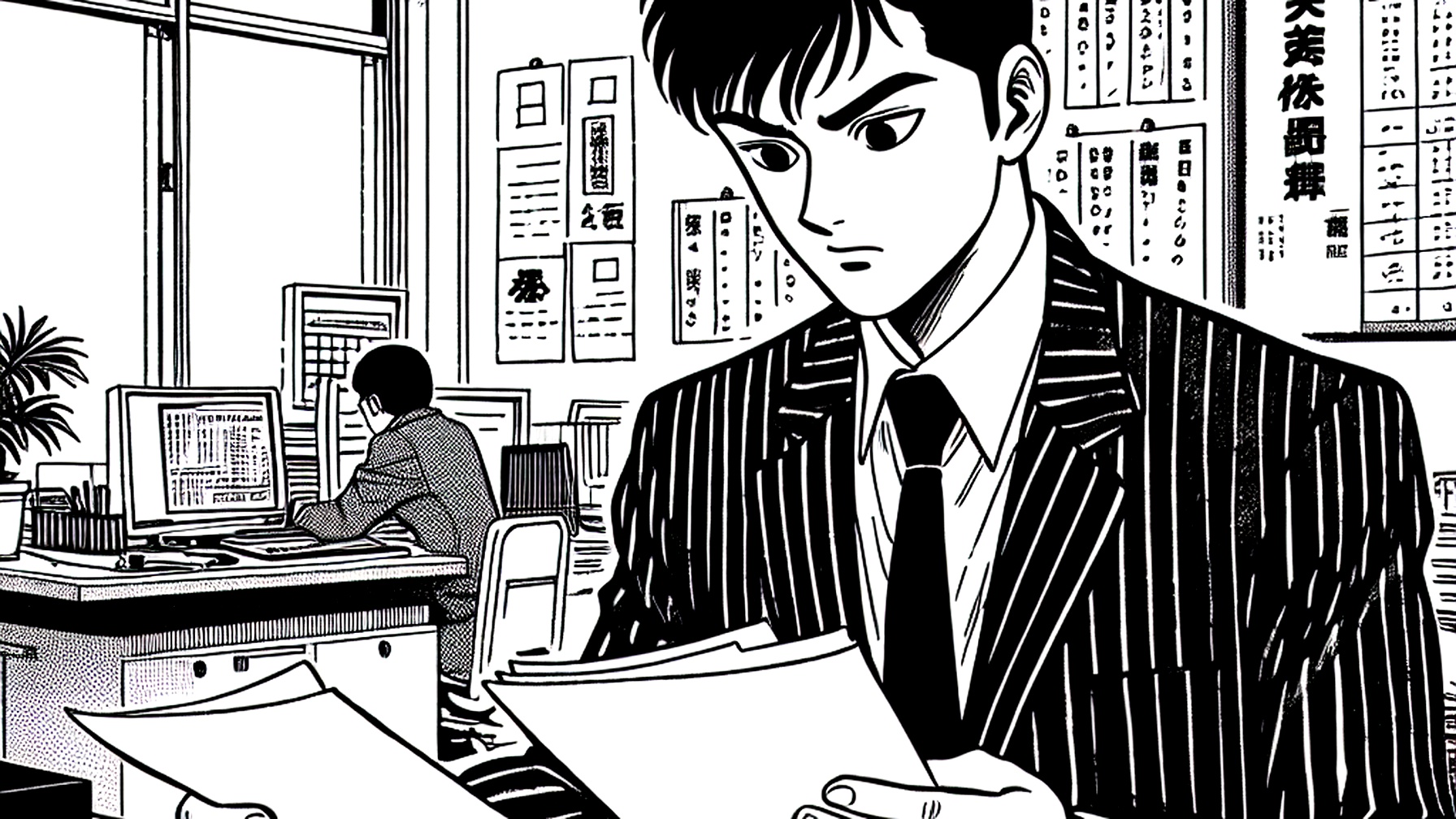
ポイントは、購入価格と家賃のギャップが利回りを決めるという単純な構図です。不動産経済研究所が二〇二五年九月に公表したデータでは、東京二十三区の新築マンション平均価格は七千五百八十万円でした。同時期の中古成約平均は約四千四百万円で、価格差は三千万円強になります。にもかかわらず、ワンルーム賃料は築浅と築十五年程度で一割しか違いません。
この「家賃は下がりにくいが価格は下がる」という現象が中古の利回り向上を生みます。実は融資審査でも、表面利回りが六%を超えると、自己資金二割で融資期間三十年を引き出しやすい傾向があります。月々の返済比率が家賃収入の七割以下に収まれば、キャッシュフローが前向きになる確率が高まるからです。
しかし、築古過ぎる物件では管理積立金が相対的に高くつき、利回りを圧迫します。購入時点の利回りではなく、五年後に想定される修繕費を含めた「実質利回り」を計算することが欠かせません。価格メリットは大きいものの、数字の裏側を丁寧に読み解く姿勢が成功への近道です。
収益性を左右する立地と管理状態
重要なのは、立地と建物管理が中古マンション投資の成否を決めるという事実です。特に単身者用ワンルームでは、駅から徒歩七分以内かどうかで空室リスクが大きく変わります。総務省「住民基本台帳人口移動報告」によると、二〇二四年度でも都心三区への転入超過は継続しており、若年層の移動は依然活発です。
一方で、郊外駅徒歩十五分の築二十年物件は賃料を下げても空室が埋まらないケースがあります。言い換えると、立地は時間が経っても改善できないため、最初の選定が肝心です。また、管理組合が機能しているかどうかも見落とせません。修繕積立金の滞納率や長期修繕計画の有無を確認し、共用部の清掃状況を現地で確かめることが、将来の資産価値維持につながります。
管理状態が良好な物件は、築年が進んでも賃料下落が緩やかです。さらに、長期的に修繕が計画通り進めば、金融機関の評価も下がりにくく、リファイナンスの選択肢が広がります。このように、立地と管理は収益を支える両輪となるため、現地確認と書類チェックを怠らない習慣を身につけましょう。
資金計画とローン選びの基本
まず押さえておきたいのは、自己資金とローンのバランスです。自己資金二割を用意すると返済比率が下がり、融資金利も優遇されやすくなります。日本政策金融公庫の調査でも、自己資金比率が一割未満の場合と比べ、二割以上の場合は平均金利が〇・三ポイント低い結果が出ています。
さらに、固定金利と変動金利の選択はリスク許容度に直結します。変動金利は当面のキャッシュフローが良くなりますが、金利上昇リスクを抱えます。二〇二五年九月時点での主要都市銀行変動金利は年二%前後ですが、日本銀行が利上げに転じれば一気に上振れする可能性も考えられます。シミュレーションでは、金利二%上昇と空室率一五%のストレスシナリオを必ず試算しておきましょう。
また、団体信用生命保険(団信)の内容も商品によって差があります。がん診断で残債がゼロになるタイプは保険料が上乗せされますが、万一のリスクを大幅に下げます。月々一千円の追加で安心を買えるなら、長期投資では検討する価値があります。総合的に見て、ローンは金利だけで選ぶのではなく、返済期間、団信内容、繰上返済手数料まで含めて比較することが肝心です。
2025年度に活用できる公的支援と税制
実は二〇二五年度でも、中古マンション投資に使える制度は存在します。代表的なのが「住宅ローン控除」です。一定の耐震基準を満たす中古住宅を取得し、自己居住後に賃貸へ転用するケースでは要件を満たせば控除が適用可能です。控除期間十三年、控除率〇・七%という枠組みは二〇二五年度も維持されています。
また、固定資産税の軽減措置も見過ごせません。区分所有マンションの場合、築二十年以上でも耐震改修工事を行えば次年度の固定資産税が一棟あたり二分の一に減額される制度があります。期限は二〇二六年三月末までなので、対象になるなら早めの改修計画が得策です。
さらに、相続税の節税を視野に入れる方には、「小規模宅地等の特例」が有効です。賃貸用区分所有でも、要件を満たせば評価額が五〇%減額されます。ただし、取得後三年以上の継続賃貸が条件になるため、短期売却を前提とする戦略との相性は良くありません。制度を活かすには、中長期の視点で所有し、計画的に出口を考えることが重要です。
まとめ
中古マンション投資が支持される理由は、取得価格を抑えつつ実績に基づく収益予測が立てやすい点にあります。価格メリットと家賃の維持力が利回りを高め、立地と管理の見極めがリスクを軽減します。自己資金二割の確保と慎重なローン選びでキャッシュフローを安定させ、二〇二五年度も続く住宅ローン控除や耐震改修減税を組み合わせれば、長期にわたり堅実な運用が期待できます。まずは気になるエリアの成約事例を調べ、書類と現地の両面から物件を比較するところから始めてみましょう。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 住宅市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫 生活衛生融資調査 – https://www.jfc.go.jp
- 国税庁 小規模宅地等の特例 – https://www.nta.go.jp

