不動産投資に興味はあるけれど「多額の資金を用意するのは不安」「空室リスクが怖い」と感じている人は多いはずです。そんな悩みを解消する手段として注目されているのがREIT(リート)です。実際、東証REIT指数の分配金利回りは2025年9月時点で平均3.7%前後と、定期預金を大きく上回ります。しかし銘柄数が80を超える中で、どこから手を付ければよいか迷う人も少なくありません。この記事では、初心者が段階的に投資額とリスクを高めていく「ステップ投資」の考え方を軸に、主要REITの特徴を比較しながら選び方を解説します。読み終わる頃には、自分に合った銘柄を選び、今日から一歩を踏み出せる具体的な方法が見えてくるでしょう。
REITの基礎知識と投資メリットを整理しよう
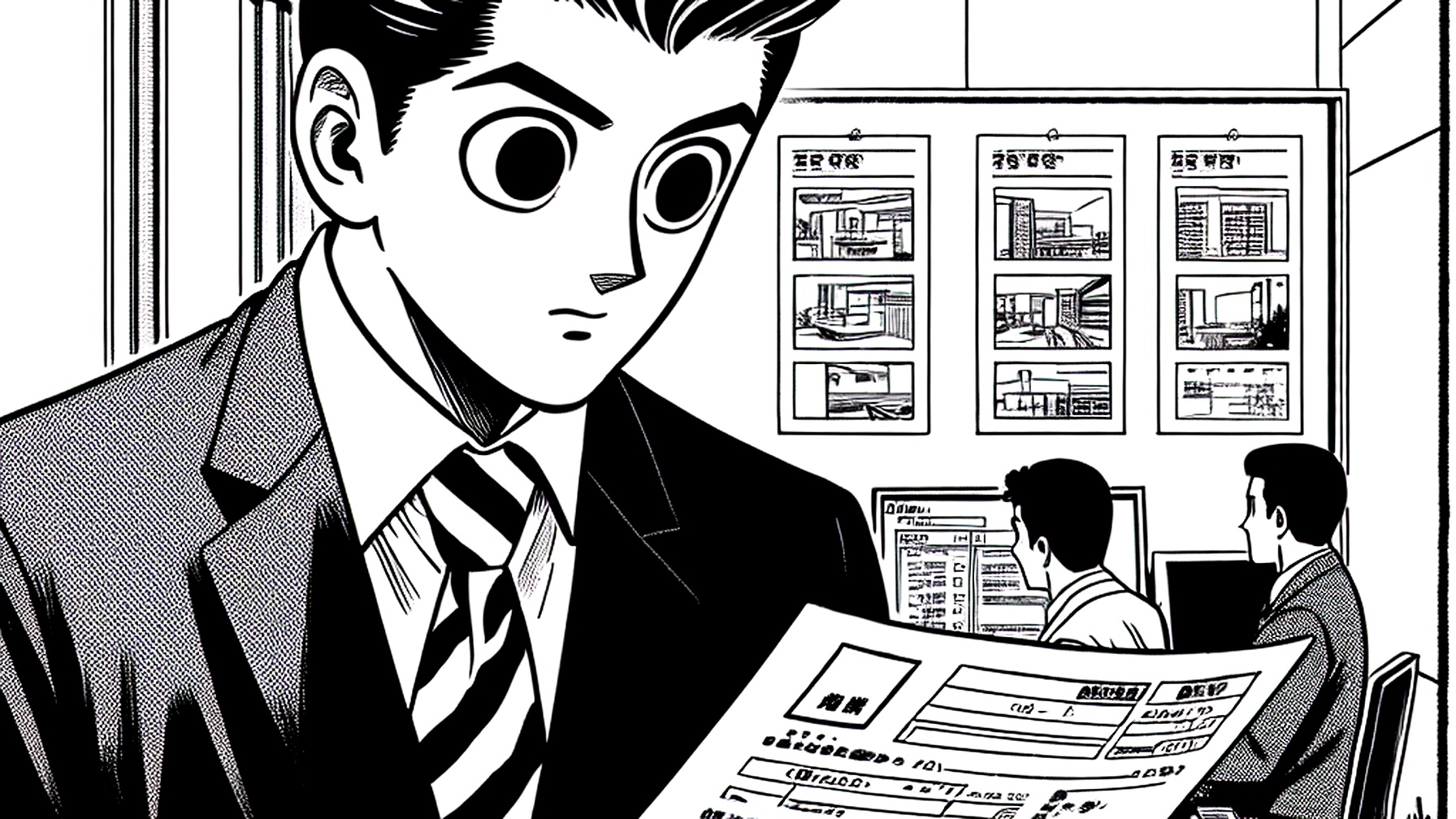
まず押さえておきたいのは、REITが「不動産投資信託」の略称であり、投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設などを保有・運営し、その賃料収入を分配する仕組みだという点です。株式と同じように証券取引所で売買できるため、1口数万円から始められる手軽さが魅力になります。
重要なのは、REITが賃料を源泉とする「インカムゲイン(定期収入)」と、不動産売却益や価格上昇による「キャピタルゲイン(値上がり益)」の両方を狙える点です。さらに、投資信託に適用される法人税の軽減措置により、利益の90%以上を分配すると実質的な法人税が非課税になるため、分配金利回りが高くなる傾向があります。
一方で、地震や金利上昇の影響を受けやすいというリスクも存在します。したがって、安定したポートフォリオを組むには、複数の用途や地域に分散されたREITを組み合わせることが必須となります。ここで活躍するのが段階的に銘柄を広げる「ステップ投資」の考え方です。
ステップ投資とは何か:少額から始めて学びながら拡大する
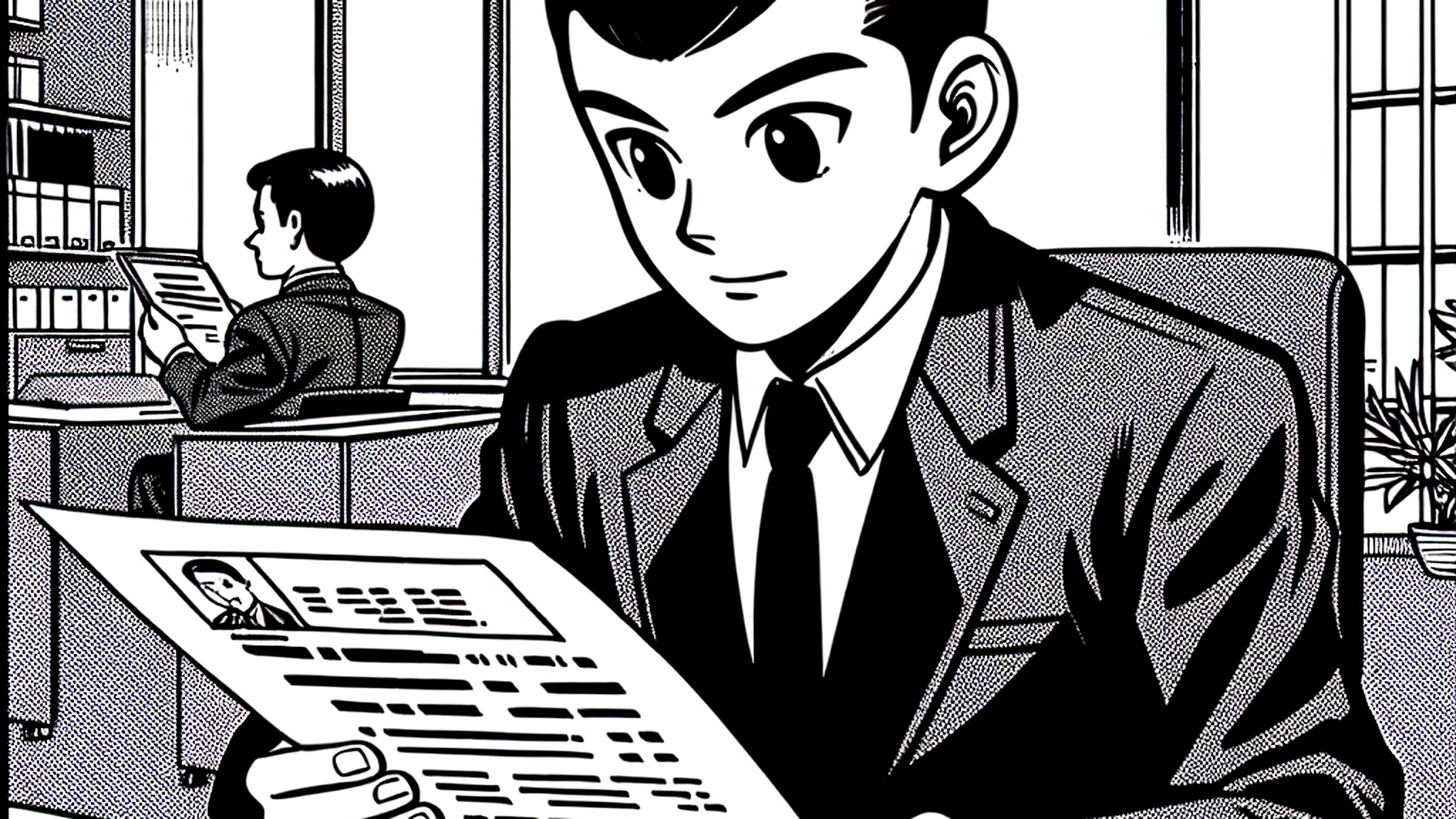
ポイントは、最初から多額を投入するのではなく、1銘柄あたり数万円の少額で購入し、相場変動や分配金サイクルを体験しながら投資範囲を広げていくことです。具体的には、第一ステップで1〜2銘柄に集中し、3〜6カ月ごとに運用実績を確認しながら銘柄数を増やします。
この方法には二つの利点があります。ひとつは、実際の値動きを肌で感じることで知識が深まり、書籍やネット情報だけでは得にくい経験値を積める点です。もう一つは、相場が急落した場合でも投入資金が限定的なため心理的ダメージが小さく、継続しやすい点にあります。つまり、ステップ投資はリスク管理と学習効果を同時に高める戦略だといえます。
また、2025年度のNISA制度拡充を活用すれば、年間360万円(つみたて枠+成長投資枠)の非課税投資枠を利用してREITの分配金をまるごと受け取ることも可能です。非課税期間が無期限化されたため、中長期で保有するステップ投資との相性は良好です。
用途別に見る主要REITの特徴とステップ REIT 比較
実は、REITは投資対象の用途によって値動きや分配水準が大きく異なります。ここでは代表的な四つの用途別REITを取り上げ、初心者が第一ステップで検討しやすいようシンプルに比較します。
- オフィス系REIT:東京中心部の大型ビルを保有。分配金利回りは3.0%前後で相対的に安定。テレワーク定着の影響で空室率が上昇気味だが、資金力のあるテナントが多く賃料の下落幅は限定的。
- 物流系REIT:EC需要拡大を背景に2020年代後半も強い。分配金利回りは3.5〜4.2%と高水準。地方拠点の新設で成長余地がある一方、金利上昇時の建設コスト増が懸念材料。
- 住宅系REIT:首都圏ワンルームを中心としたマンションが主力。利回りは2.7〜3.3%とやや低めだが、人口集中が続く限りは空室リスクが小さい。
- 総合型REIT:用途を分散して保有するため、個別セクターの不調を吸収しやすい。利回りは3.3〜3.8%。価格変動も平均的で、初期ステップに向く。
まずは総合型か住宅系を1口ずつ購入し、毎月の分配金を確認しながらオフィス系や物流系へ拡大していくのが王道と言えます。東証REIT指数が2025年夏以降に押し目を形成したタイミングで買い増しを狙えば、値上がり益も同時に期待できます。
初心者が陥りやすい三つの落とし穴と回避策
重要なのは、手軽さゆえの油断です。第一の落とし穴は「高利回りだけで選ぶ」こと。利回りが5%を超える銘柄は魅力的に映りますが、築古物件が多く修繕費負担が重いケースもあります。財務指標としてLTV(負債比率)が60%を超えていないか確認しましょう。
第二の落とし穴は「分配金の減額リスクを見落とす」ことです。分配金は賃料収入と物件売却益が原資なので、退去や賃料改定が続けば減額されます。運用レポートで平均賃料の推移を定点観測し、3期連続で下落している場合はポートフォリオの見直しを検討してください。
結論として、三つ目の落とし穴は「金利上昇を軽視する」ことに集約されます。REITは借入金で物件を取得しているため、長期金利が1%上昇すると分配金が5〜8%目減りする試算もあります。固定金利比率や借入期間をIR資料で確認し、固定化比率が70%以上ある銘柄を中心に選ぶと安心です。
2025年のREIT市場動向と今後のステップ戦略
ポイントは、インフレと金利動向を見極めることにあります。日銀は2025年春に長短金利操作(YCC)を完全終了し、長期金利は1%台前半で推移しています。金利上昇のスピードが緩やかなうちは、物流系と住宅系の堅調さが続く見通しです。
一方で、オフィス系は需要回復に時間がかかると見られています。ただし、賃料調整が進めば利回りは再び魅力を増す可能性もあり、中期的には買い場が訪れるでしょう。つまり、今は総合型と住宅系をベースに、物流系で利回りを底上げし、オフィス系は価格調整を待ってステップアップするのが合理的です。
また、2025年度の「グリーン不動産投資促進税制」は、環境性能の高い物件を組み入れたREITに対して保有税の軽減措置を継続しています。対象銘柄に投資することで、環境貢献とリターンの両立を図れる点も見逃せません。
最後に、ステップ投資を継続するコツは「半年に一度の資産配分チェック」と「分配金の再投資」です。非課税口座を活用し、複利効果を最大化すれば、10年後には元本を2倍近くに増やすことも十分可能です。
まとめ
ステップ REIT 比較を活用すれば、少額から始めて知識と資産を同時に育てられます。まず総合型や住宅系を1口購入し、半年ごとに用途と利回りのバランスを整えながら物流系やオフィス系へ広げる流れが王道です。高利回りだけに目を奪われず、LTVや固定金利比率を確認することで、金利上昇や分配金減額のリスクを抑えられます。読者の皆さんも今日から非課税NISA枠を使い、分配金を再投資するサイクルを回し始めてください。小さな一歩を積み重ねることで、10年後の資産形成は大きく変わるはずです。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 金融庁 NISA特設ページ – https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/
- 国土交通省 不動産市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/
- 日本不動産研究所 JREIレポート – https://www.reinet.or.jp
- 内閣府 経済財政白書2025 – https://www5.cao.go.jp/keizai/

