アパート経営に興味はあるものの、「自分で管理すべきか、それとも専門会社に任せるべきか」と迷う人は多いものです。管理方法の違いは、収益性だけでなく時間の使い方やストレスの大きさにも直結します。本記事では、両者の特徴を比較しながら、2025年9月時点で活用できる制度や最新ツールも交え、初心者でも無理なく判断できる視点をお届けします。
アパート経営における管理の基本構造
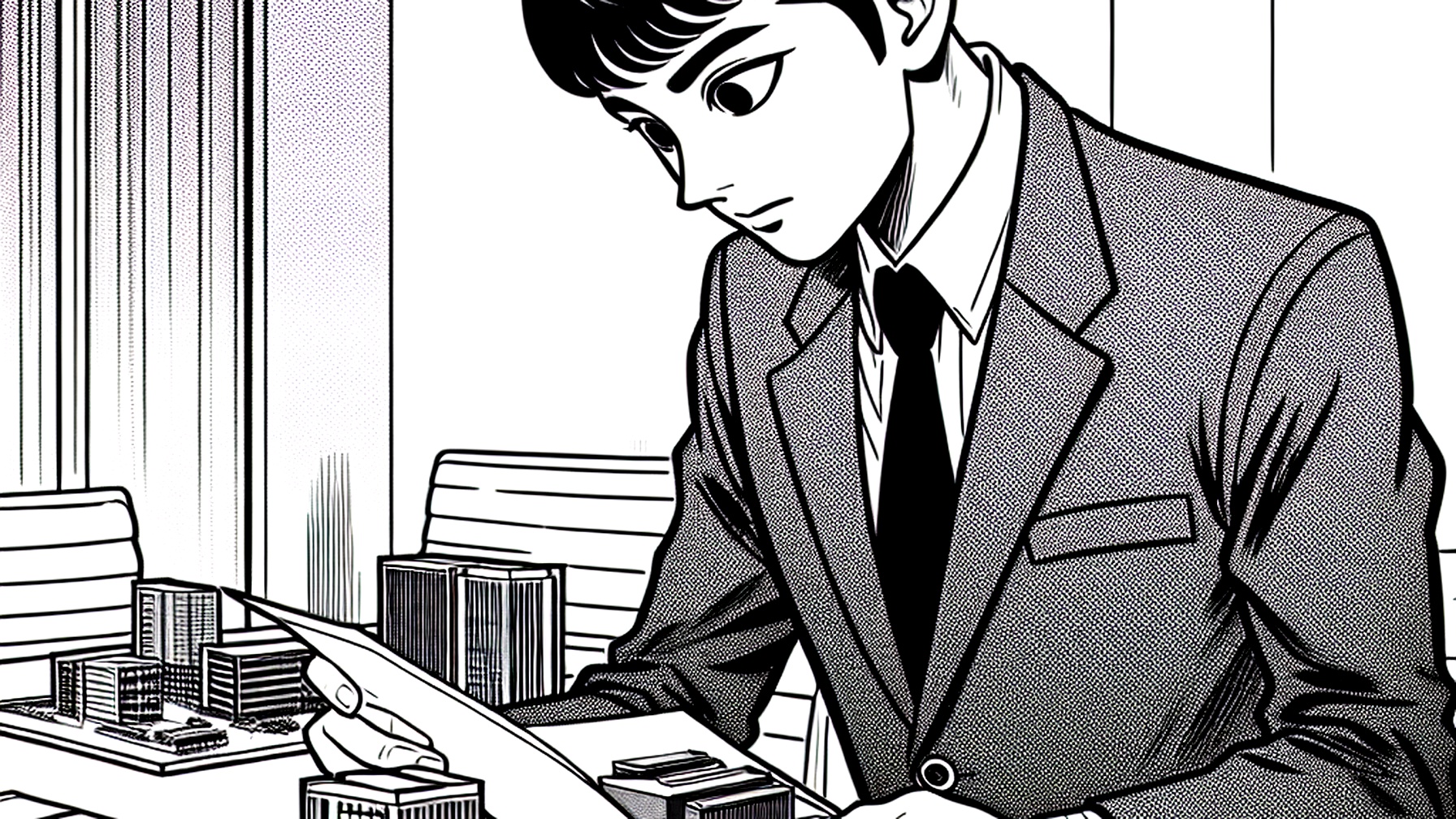
まず押さえておきたいのは、アパート管理が大きく「入居者管理」「建物維持」「家賃回収」の三つに分かれる点です。管理の質が低いと空室率や修繕費が増え、キャッシュフローが悪化します。国土交通省住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善しましたが、依然として五件に一件が空いている計算です。適切な管理は、この空室リスクを抑え、長期の安定経営につながります。
実務では、入居者対応の迅速さが満足度を左右します。例えば水漏れが休日に起きた場合、オーナーが直接対応できなければ評価は下がります。建物維持でも、雨漏り点検を年一回実施するだけで、将来の大規模修繕費を数十万円単位で減らせる可能性があります。また、家賃回収を滞りなく行うことで、金融機関からの追加融資審査でも高評価を得やすくなります。
一方で管理に時間をかけすぎると、本業や家族との時間が圧迫されます。そのため「どこまで自分で行い、どこから専門家に任せるか」を線引きすることが、経営の第一歩となるのです。
自主管理のメリットとリスク
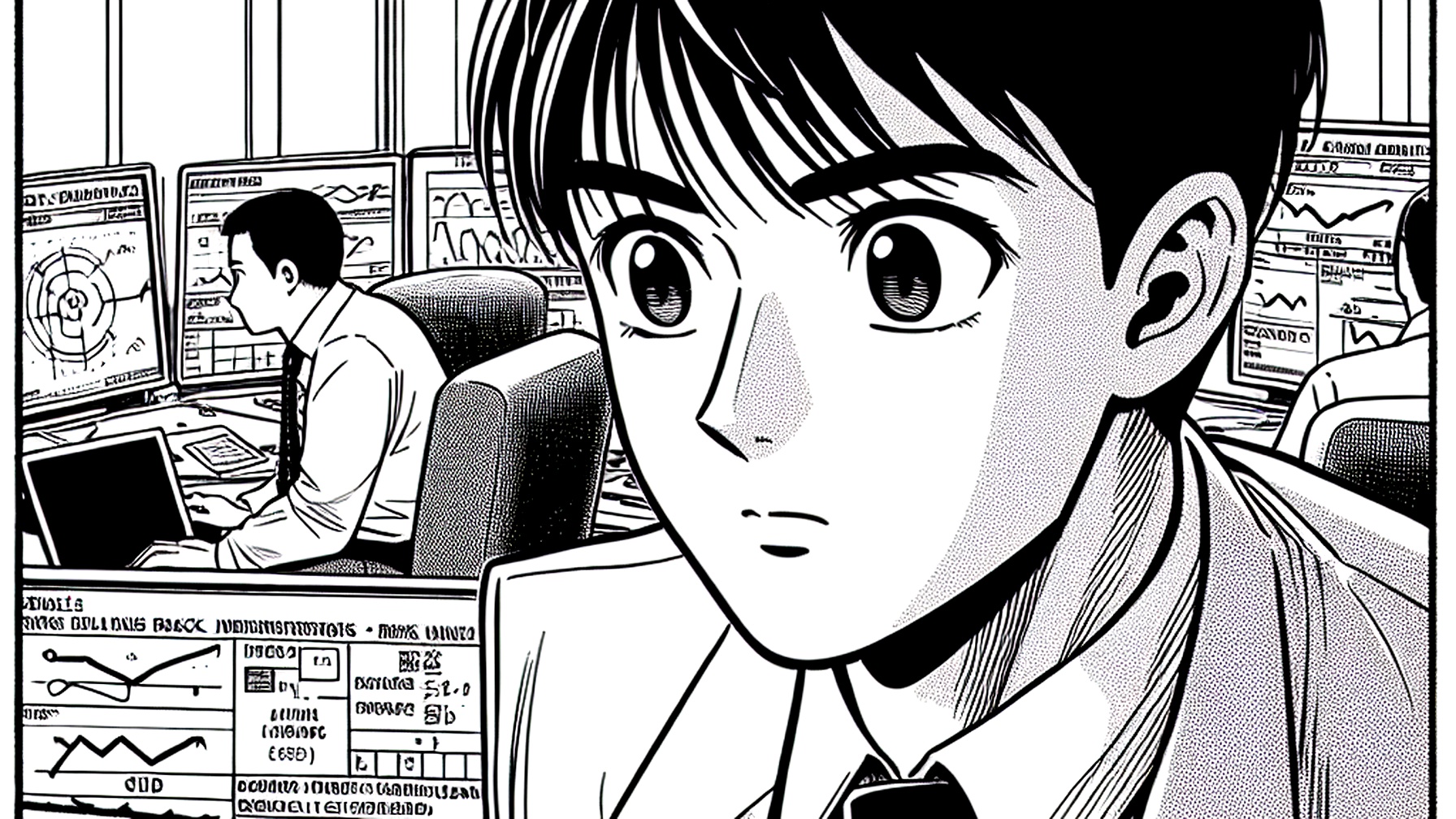
ポイントは、コスト削減と情報の鮮度です。自主管理は管理委託料が不要で、家賃収入がそのまま手元に残ります。また、入居者の細かな声を直接聞けるため、リフォームや賃料改定の判断を迅速に下せるメリットがあります。
しかし、法改正への対応は大きな壁です。2025年度も改正賃貸住宅管理業法が完全施行され、敷金精算や入居者トラブルの手続きが厳密化しました。知識を更新し続けなければ、気付かないうちに違反となり、最悪の場合は行政指導を受けるリスクがあります。さらに、夜間トラブル対応や滞納督促は精神的負担が大きく、長期的に続けるほど疲弊しやすい点も見逃せません。
収支面では、管理委託料を節約できても、外部業者への個別依頼が重なるとコストが膨らみがちです。例えばエアコン交換をその都度発注すると、委託管理より工事単価が二割ほど高くなるケースもあります。つまり、自主管理は手間を惜しまないオーナー向きであり、時間と知識を投資できるかどうかが成否を分けます。
管理会社委託のメリットとリスク
実は、管理会社委託の最大の利点は専門性よりも時間の買い取りにあります。月額家賃の3〜5%程度の手数料で、24時間対応や法的手続きを任せられるため、本業に集中したい人には魅力的です。また、大手管理会社は退去から原状回復、次の入居募集までを標準化しており、平均空室期間を一か月以内に抑える実績も珍しくありません。
一方で、委託しているからといって完全に安心とは限りません。担当者の経験値によって賃料査定が甘くなる場合があり、相場より低い設定で長期契約を結ばれると機会損失が生じます。さらに、修繕工事を系列会社へ発注する際に割高な見積もりが提示されることもあるため、オーナーによる定期的なチェックは不可欠です。
費用面では、年間家賃収入800万円の物件で管理料5%なら40万円が固定コストとなります。これを高いと見るか、時間的ゆとりへの投資とするかは、オーナーのライフスタイル次第です。重要なのは、委託後も月次報告書を読み込み、改善点を管理会社と共有する姿勢を持ち続けることです。
「VS」の視点で見る費用と手間の最適バランス
まず、比較の軸を「利益率」「時間」「リスク」の三つに整理すると判断しやすくなります。自主管理は利益率が高い一方で時間とリスクを引き受けます。管理会社委託はその逆で、利益率を犠牲にして時間とリスクを軽減します。どちらが優れるという単純な結論はなく、オーナーの属性によって最適解は変わります。
年収が高く本業にフルコミットしたい会社員オーナーは、手間を最小化する委託型が相性良好です。反対に、退職後の時間を活用し、地域密着で入居者コミュニティをつくりたい人は自主管理で差別化を図れます。また、ハイブリッドという選択肢もあります。例えば入居募集と家賃回収だけを委託し、日常清掃や簡易修繕は自分で行う方法です。これなら管理料を2〜3%に抑えつつ、入居者との距離感も保てます。
重要なのは、管理方法を固定化せず、年一回は見直す仕組みを設けることです。空室率が上昇したり、家族環境が変わったりすれば、管理負担を減らす方向へシフトする柔軟性が求められます。
2025年度制度とテクノロジー活用の現在地
さらに、2025年度はオーナーの負担を下げるテクノロジーが普及しました。代表例が電子契約システムで、国交省のガイドラインに基づきオンライン上で賃貸契約を締結できます。これにより、郵送や対面説明の手間が削減され、契約ミスも減少しています。また、IoTセンサーによる水漏れ検知やスマートロックは、入居者満足度を高めつつ管理工数を減らす有効な手段です。
制度面では、2025年度の住宅セーフティネット制度が継続し、高齢者や子育て世帯向けの登録住宅には税制優遇があります。対象要件を満たすと固定資産税が一部減額されるため、登録物件数は前年より8%増加しました。こうした制度を活用する場合、管理会社が手続きを代行するケースが多いものの、自主管理でも自治体窓口で申請可能です。
テクノロジーと制度を組み合わせれば、管理方法の選択肢はさらに広がります。例えば委託管理に加えて電子契約を取り入れ、書類管理を完全ペーパーレス化すれば、オーナーが海外にいても経営が滞りません。逆に自主管理でも、スマートロックにより鍵交換のたびに現地へ行かずに済むため、手間と交通費を同時に削減できます。
まとめ
アパート経営では「管理方法VS収益性」という構図で語られがちですが、実際には時間、リスク、制度活用の三要素をどう組み合わせるかが鍵となります。自主管理は高い利益率を得られる反面、専門知識と労力が不可欠です。一方で委託管理はコストを払うことで安心と時間を手に入れられます。まず自身の生活リズムと目標利回りを棚卸しし、年に一度は管理方法を見直す仕組みを作りましょう。それが、長期的に安定したアパート経営への近道になります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅管理業法ガイドライン – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 総務省 行政手続オンライン化資料 – https://www.soumu.go.jp
- 独立行政法人 住宅金融支援機構 金利動向レポート – https://www.jhf.go.jp
- 厚生労働省 住宅セーフティネット制度概要 – https://www.mhlw.go.jp

