木造アパートを所有しているものの、空室が続くと「家賃が入らないのにローンだけが出ていく」と焦りが募ります。また、鉄筋コンクリート(RC)物件と比べて築年数が経つほど競合物件も増え、差別化が難しいと感じる人も多いでしょう。本記事では、空室対策に悩む木造オーナーの疑問に寄り添い、建物の特徴を踏まえた改善策を具体的に解説します。読み進めれば、入居希望者に選ばれる物件へ変える手順と、2025年9月時点で使える公的支援情報まで把握できます。
木造アパートが空室になりやすい理由
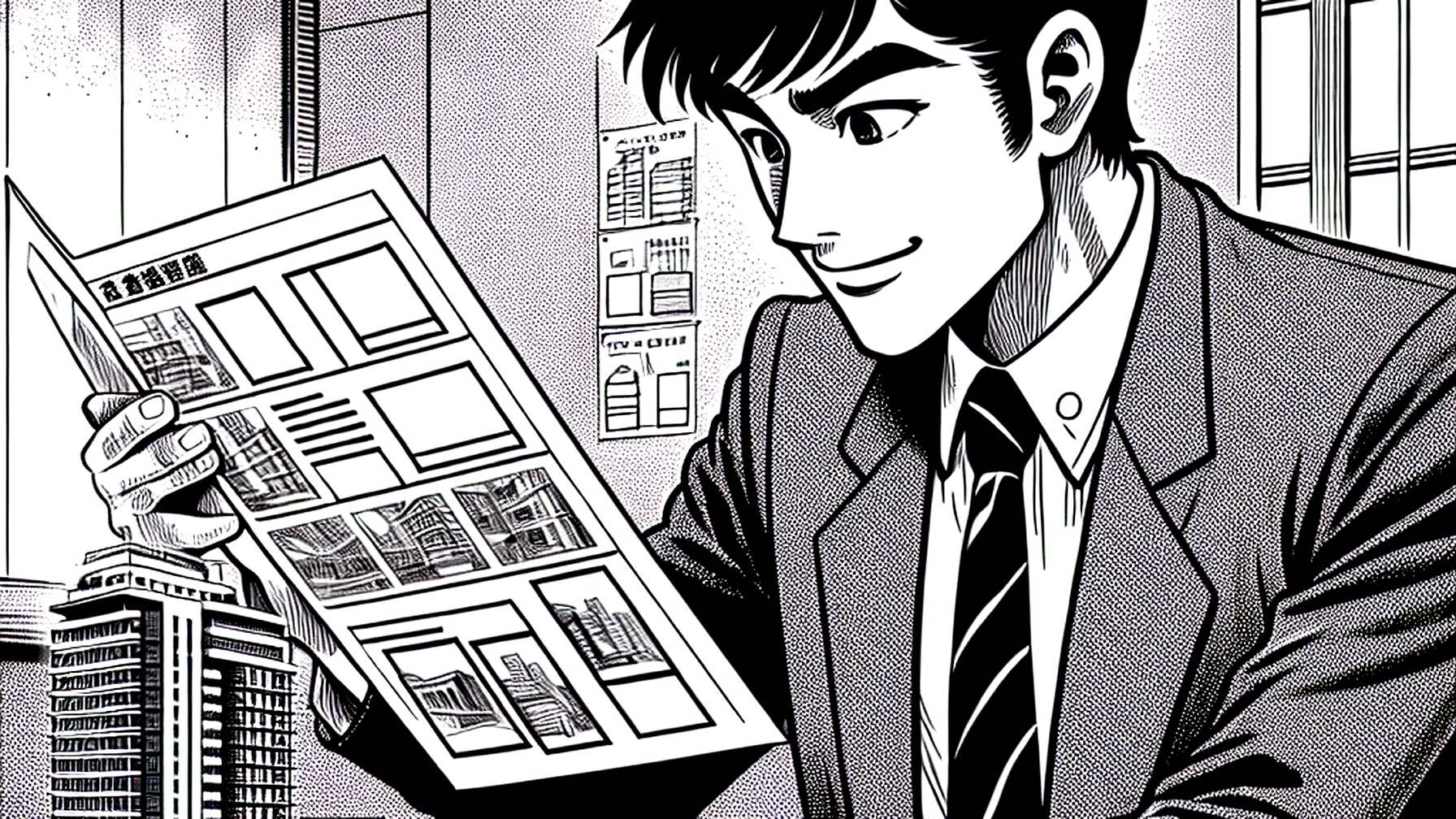
重要なのは、木造特有のデメリットを正確に把握し、それを打ち消す対策を組み立てることです。防音・耐震・老朽化という三つの課題が放置されるほど、入居者は敬遠しやすくなります。
まず音の問題です。総務省の住宅・土地統計調査によると、集合住宅の生活騒音に関する苦情の約六割が木造物件から発生しています。床材や壁の厚みがRCに比べ薄く、上下階の生活音が伝わりやすい構造が一因です。対策を怠るとレビューサイトにネガティブな書き込みが残り、募集のたびに不利になります。
次に耐震性です。国土交通省の資料では、1981年以前の旧耐震基準で建築された木造アパートは、現行基準と比べ最大で倒壊リスクが二〜三倍高いとされています。入居者の安全意識が高まる中、耐震補強の有無は内見時に必ず質問される項目です。
最後は老朽化の見た目です。外壁の塗装剥がれや共用部のサビは、実際の構造強度以上に“古さ”を印象づけ、賃料交渉の材料にされやすい要因となります。つまり、根本的な改修を先送りにすると、広告費やフリーレントで一時的に埋めても長期的な収益力は低下していくのです。
リノベーションと設備投資で魅力向上
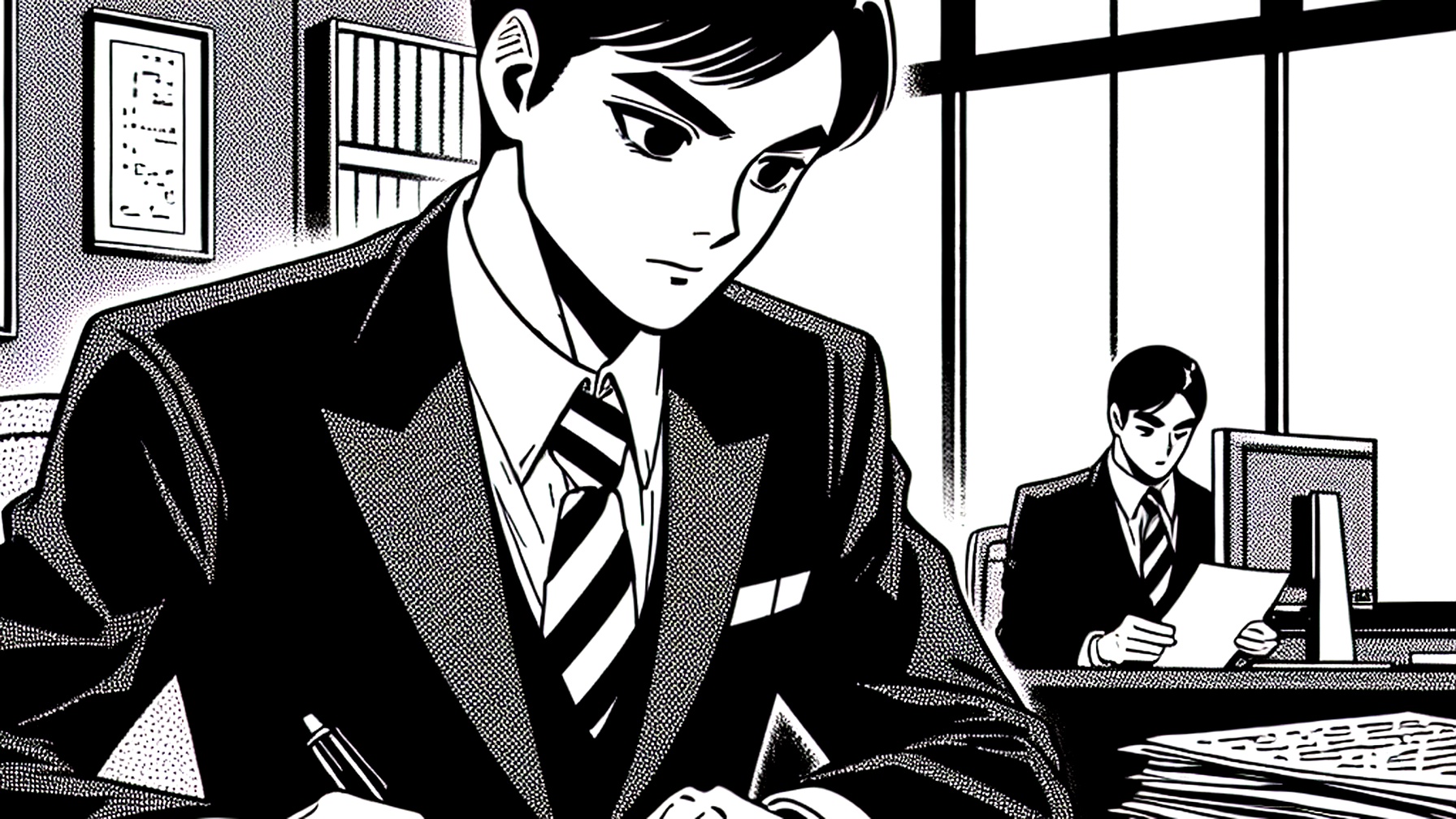
まず押さえておきたいのは、表面的なクロス張り替えだけでは差別化が難しい時代になったという事実です。新築の充実設備を知る入居者に、築二十年以上の木造物件へ目を向けてもらうには、生活の質を上げる改修が欠かせません。
ポイントはキッチンと水回りの刷新に加え、遮音・断熱性能を数値で示すことです。例えば床に二八ミリ以上の遮音フローリングを施工し、遮音等級LL-45を達成した事例では、家賃を三千円上げても平均空室期間が二カ月短縮されました。施工費は一戸当たり約四十万円でしたが、年間収支で見ると二年以内に回収できています。
加えて、IoT設備も検討すべきです。エントランスをスマートロック化すると、管理会社の内見対応が無人で行え、入居者は鍵忘れのストレスから解放されます。日本賃貸住宅管理協会の調査では、スマートロック導入物件の成約率が周辺平均より一五%高いという結果が出ています。
こうした投資はまとまった資金が必要ですが、2025年度も継続する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」で、工事費の三分の一(上限二百五十万円)が補助されるケースがあります。募集条件を改善しながら、国の支援で初期負担を抑えられる点が魅力です。
適正賃料と賃貸条件の見直し
実は、賃料設定を誤るだけで平均空室期間が倍以上に延びることがあります。日本不動産研究所の賃料指数によれば、築二十五年の木造アパートは新築時比で六割前後の水準が市場価格です。にもかかわらず、周辺相場とかけ離れた設定を続けるオーナーが少なくありません。
まず、類似物件の募集価格と成約価格を分けて確認しましょう。ポータルサイトの表示家賃は“希望”であり、実際の成約賃料は一割程度低いことが多いと報告されています。このギャップを認識したうえで、募集賃料を五百円単位でこまめに調整する方が、結果的に総収入は高くなります。
さらに、フリーレントは一カ月以内にとどめ、代わりに更新料や退去時クリーニング費用を適正化することが重要です。長期入居者が増えれば原状回復費も抑えられ、キャッシュフローが安定します。言い換えると、短期の見せかけ収入より、継続的な家賃収入を優先する姿勢が空室率の改善につながるのです。
入居者ターゲットを明確にする戦略
ポイントは、誰に住んでもらいたいのかを絞り込み、その層が“必ず欲しい要素”をピンポイントで提供することです。木造アパートの多くはファミリーより単身者向けに建てられており、実際、総務省の人口移動報告では単身世帯が過去最高を更新しています。
例えば、地方大学の近くであれば留学生を想定し、家具家電付きプランを設けるだけで問い合わせが急増するケースがあります。留学生は短期契約を希望する場合が多いため、一年未満の解約違約金を設定すれば収益面の懸念も抑えられます。
一方、郊外のベッドタウンでは在宅勤務が定着した若手社会人を狙い、無料インターネットとワークスペースの確保がカギとなります。六畳の洋室を四畳半+書斎コーナーへ改造し、集中できる環境をPRしたところ、従来の二十代男性中心から三十代の女性契約者が増えた事例もあります。
つまり、木造アパートの強みである間取り変更の柔軟性を生かし、ターゲットの生活スタイルに合わせて改修計画を組むことで、空室対策は一段と効果を発揮します。
2025年度制度を活用した資金計画
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続中のリフォーム関連補助金を上手に組み合わせると自己負担を大幅に減らせる点です。代表的なのが前述の長期優良住宅化リフォーム推進事業に加え、地域型住宅グリーン化事業(木造部分の省エネ改修)や、地方自治体独自の耐震補強助成です。期限はいずれも2026年3月完了分までとなっているため、施工スケジュールを逆算しましょう。
資金調達面では、住宅金融支援機構の「賃貸住宅リフォーム融資」が年0.8%台と民間より低金利で利用可能です。融資限度額は一億円ですが、耐震・省エネ工事を含む場合は金利が0.2%優遇されます。空室対策としてのリノベーションは収益改善が見えやすいため、金融機関の評価も得やすい傾向にあります。
また、木造アパートの固定資産税は築年数に応じて緩やかに減額されるものの、大規模修繕を行うと評価額が上がる可能性があります。税理士に試算を依頼し、修繕費を一括経費にできるか、資本的支出として減価償却するかを事前に判断すると、キャッシュフローの予測精度が向上します。
結論として、補助金・低金利融資・税効果を総合的に活用すれば、工事費の実質負担を三〜四割まで圧縮できる例も珍しくありません。資金の壁を乗り越えることで、空室対策 木造アパートの成功率は格段に高まります。
まとめ
ここまで、木造アパートが抱えやすい防音・耐震・老朽化の課題と、それを克服するリノベーション、賃料設計、ターゲット戦略、そして2025年度の支援制度までを解説しました。大切なのは「誰に住んでもらうか」を明確にし、そのニーズを満たす具体策を数字で示すことです。補助金や低金利融資を活用すれば初期負担を抑えられ、改修効果を早期に回収できます。今日紹介した手順を一つずつ実行し、選ばれる木造アパートへ生まれ変わらせましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp/
- 独立行政法人住宅金融支援機構 – https://www.jhf.go.jp/
- 一般財団法人日本賃貸住宅管理協会 – https://www.jpm.jp/
- 東京都都市整備局 耐震ポータル – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/taishin/

