マンション投資を検討していると、「新築は高すぎるし自分にはいらないのでは」と戸惑う声をよく聞きます。確かに価格が上がり続ける今、新築物件を買う意味があるのか迷うのは当然です。しかし実は、リスクと向き合いながら数字を読み解けば、判断基準はシンプルになります。本記事では、新築マンション投資のメリット・デメリットを整理し、代替策や最新制度まで丁寧に解説します。読み終えた時には、あなた自身の資金計画に照らして「いらない」と言い切れるかどうか、根拠を持って判断できるようになるはずです。
マンション投資が「いらない」と感じる理由
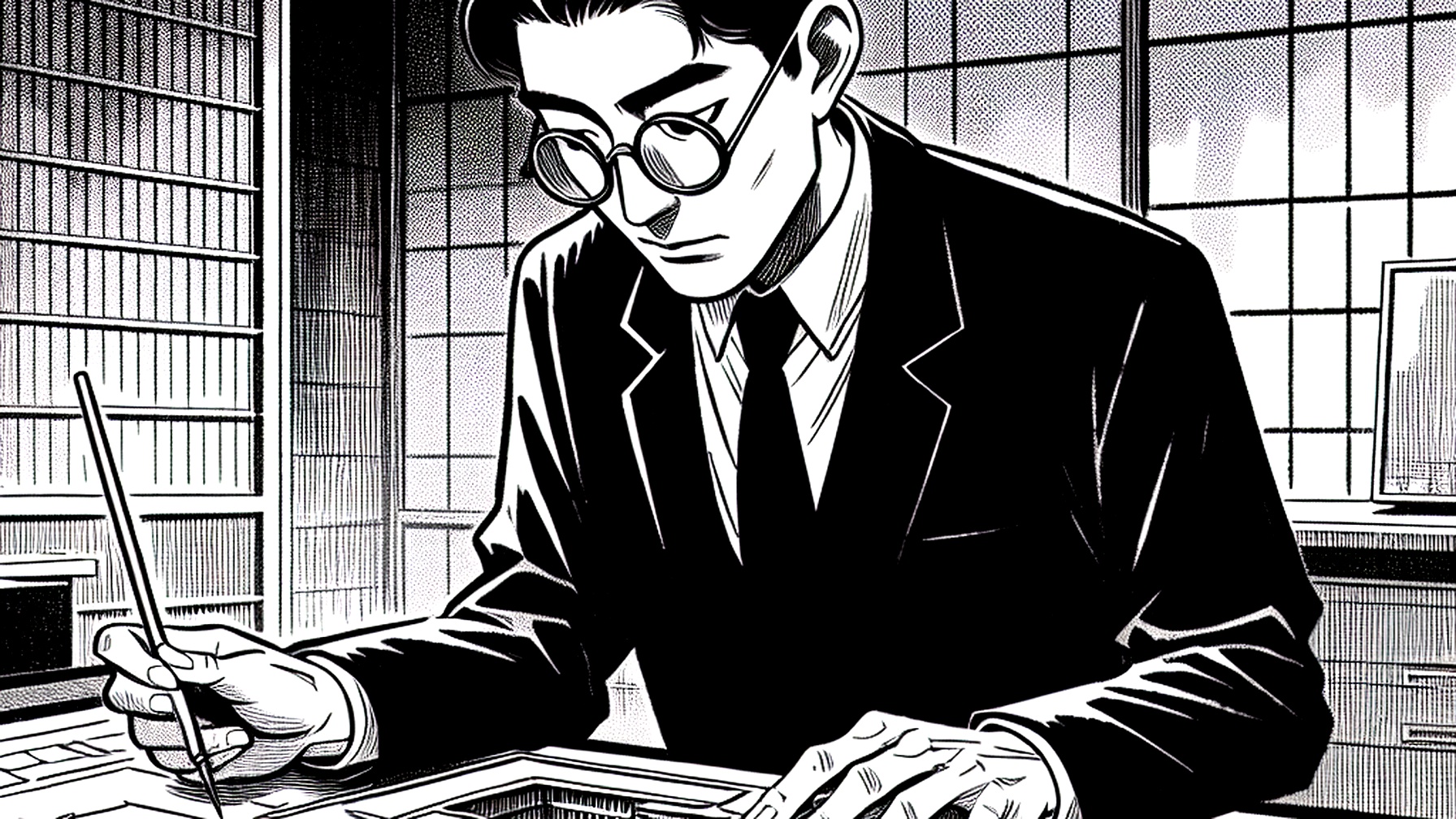
まず押さえておきたいのは、多くの初心者が感じるネガティブ要因です。価格の高さ、空室リスク、ローン返済の重圧などが主な理由ですが、背景を理解すると必要以上に恐れる必要はありません。
新築マンションの平均価格は不動産経済研究所によると2025年9月の東京23区で7,580万円です。前年比3.2%の上昇は確かに負担感を与えます。一方で平均賃料は過去5年で年2%前後の上昇にとどまり、利回りは縮小傾向にあります。投資家が「買っても割に合わない」と感じるのは、この利回り低下が大きな要因です。
さらに、人口減少が進む地域では長期的な賃貸需要に不安があります。総務省の推計では、2040年に全国で約1,200万人の人口減が見込まれ、特に地方圏の空室率は現在の18%から25%台まで上昇する可能性が指摘されています。こうした数字が、「マンション投資はいらない」という直感を強めます。
しかし、賃料相場を細かく見ると二極化が進んでいます。都心の駅近物件は高稼働を維持しており、逆に築浅かつ中途半端な立地が空室の温床になっています。つまり立地選定と出口戦略を練れば、価格上昇だけを理由に投資をあきらめる必要はありません。
最後に、税金や修繕積立金の将来的な負担が不安視されがちです。確かに長期修繕計画が甘い管理組合では追加徴収が起こり得ます。ただし購入前に管理状況を精査すれば想定外のコストはかなり抑えられます。ネガティブ情報は鵜呑みにせず、数字で裏付けを取る姿勢が大切です。
新築神話の落とし穴
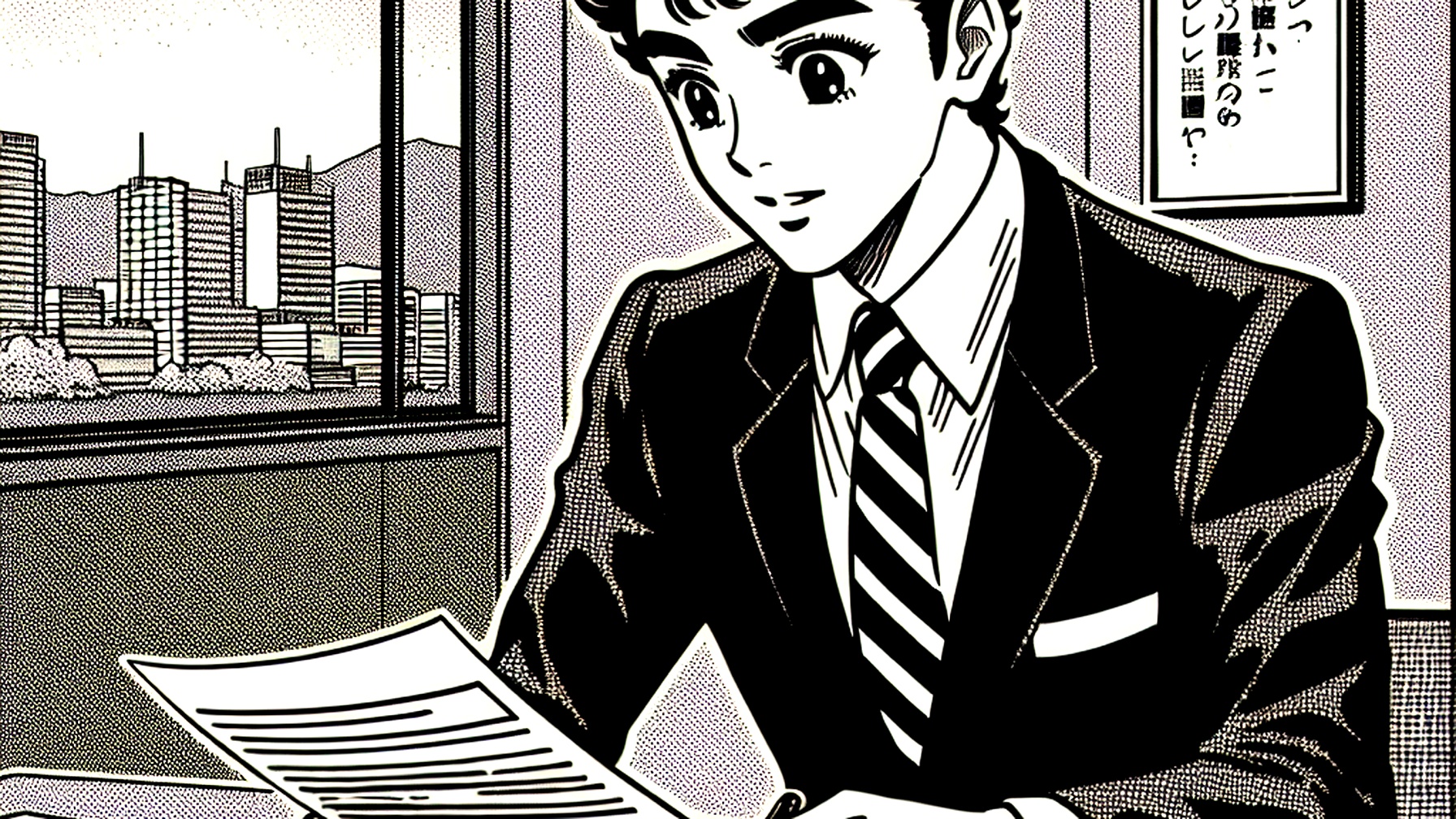
重要なのは、新築だから安心という固定観念を疑うことです。新築物件には瑕疵担保や設備保証が付くものの、それだけで高い収益を確保できるわけではありません。
まず、新築プレミアムと呼ばれる価格上乗せが存在します。完成後2〜3年で中古扱いとなると、販売価格が7〜10%下がるケースが珍しくありません。購入時に諸費用8%程度も加わるため、売却時には合計15%以上の値下がりを前提にキャッシュフローを試算する必要があります。
また、入居付けがスムーズなのは最初の募集時だけという実態があります。供給過多のエリアでは、次年度以降に周辺の築浅中古と競合し、賃料を下げないと成約しない事例が増えています。住宅新報社の調査によれば、2024〜2025年に竣工した都心ワンルームの再募集賃料は平均で初年度比4%の減額となっています。
設備仕様の新しさは確かに入居者に選ばれる要素です。しかし管理状況が悪ければ、たった数年で魅力が薄れます。とくに24時間ゴミ置き場や共用Wi-Fiなどランニングコストが高い設備は、修繕積立が不足すると撤去されることもあります。設備の豪華さと管理財務の健全性はセットで検討しましょう。
最後に、金融機関の新築優遇金利も注意が必要です。短期固定で低金利が提示される一方、5年後の見直し時に1%以上上がるケースがあります。金利上昇シナリオを組み込み、月々の返済比率が家賃収入の50%を超えないか確認することが欠かせません。
収益シミュレーションで見る現実
ポイントは、感覚ではなく数字で「いらない」かどうか判定することです。ここでは実際のシミュレーション方法を示し、判断軸を可視化します。
表計算ソフトで行う基本モデルは次の通りです。物件価格7,500万円、自己資金1,500万円、借入6,000万円、金利1.4%固定35年。賃料月22万円、共益費込み、運営費率25%を設定し、空室率5%を加味します。この条件では、年間手残りは約45万円となり、自己資金利回りは3%弱です。
一方で、中古築10年・価格5,200万円、同じ家賃設定の場合は運営費率を27%、空室率7%とやや厳しめに置いても年間手残りは約60万円です。自己資金を1,200万円に圧縮できるため、自己資金利回りは5%を超えます。この差が「新築いらない」と言われる最大の根拠です。
しかし数字の裏側を読むと、修繕積立金の増額幅が中古では大きくなること、耐用年数の残りが短い分だけ融資期間が25年程度に制限されることがわかります。結果として初期キャッシュフローは良くても、長期の純利益は逆転する可能性があるのです。
さらに、相続対策を目的にする場合は減価償却期間の長さが節税効果を左右します。新築なら47年償却、築10年なら残存37年ですが、木造アパートのように22年で終わるわけではありません。節税だけに頼る投資ではなく、保有期間トータルの手残り現金で比較する姿勢が求められます。
リスクを抑える代替戦略は何か
実は、新築か中古かの二択ではなく、リスク分散の視点を取り入れることで選択肢は広がります。ここでは初心者でも実践しやすい三つの戦略を紹介します。
第一に、築浅リノベーション物件の活用です。築5〜8年で設備がまだ新しく、価格は新築より10%以上割安になるケースがあります。軽微なデザインリフォームを加えることで、賃料を新築並みに設定できれば利回り改善が期待できます。初期投資を抑えつつ、新築と同等の競争力を確保する方法です。
第二に、区分所有を複数戸持つポートフォリオ戦略があります。たとえば都心ワンルームと郊外ファミリータイプを組み合わせれば、賃料変動のリスクを相殺できます。一戸当たりの投資額が小さいため、空室リスクの影響を限定できるのも魅力です。ただし管理会社の選定と家賃保証の条件は物件ごとに丁寧に確認してください。
第三に、J-REITや不動産クラウドファンディングを併用する方法です。自己資金50万円から分散投資ができ、流動性も高い点がメリットです。現物と合わせて保有することで、急な資金需要や市場変動への柔軟性が高まります。過度なレバレッジを避ける意味でも有効な選択肢です。
これらの代替戦略を組み合わせることで、「新築はいらない」と感じる理由である価格リスクや空室リスクを軽減できます。重要なのは、自分のリスク許容度を明確にし、物件タイプごとにベストな融資条件を引き出す交渉力を養うことです。
2025年度制度を活用した出口戦略
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続している住宅ローン減税と固定資産税の新築軽減措置です。これらは居住用が主対象ですが、投資家が自宅として数年間住んだ後に賃貸へ切り替える「転用戦略」と相性が良いといえます。
住宅ローン減税は、控除期間13年、控除率0.7%、上限残高5,000万円までが基本です。自宅として居住した年数分だけ所得税・住民税の還付が受けられ、その後の賃貸運用では減価償却や借入金利を経費にできます。これにより総合収益を底上げする効果が期待できます。
一方、固定資産税の新築軽減は3年間(長期優良住宅は5年間)で税額が2分の1になるものです。投資物件として取得すると適用されませんが、自宅転用ならメリットを享受できます。将来売却を視野に入れる場合でも、この軽減期間中にローン元本を早めに返済すれば、残債と売却価格のイールドギャップを縮めることが可能です。
さらに、国土交通省が2024年度に創設した「賃貸住宅性能表示制度」は2025年度も継続しています。省エネ性能や耐震性など、物件の質を客観的に示せるため、他物件との差別化に有効です。売却時の査定額が平均3%程度高まるとの事例も報告されていますので、登録費用とリターンを比較して検討するとよいでしょう。
最後に、出口としての住み替え需要を意識することが重要です。高齢化が進むにつれ、バリアフリー対応やサービス付き高齢者向け住宅への移行ニーズが高まります。バリアフリー改修に対する2025年度の「長寿命化リフォーム減税」を活用すれば、最大25万円の所得税控除が受けられます。改修後に高齢者向けに賃貸することで、安定した家賃収入と社会的貢献を両立できる点も魅力です。
まとめ
ここまで見てきたように、「マンション投資はいらない」と感じる主な理由は、価格上昇と利回り低下に対する不安でした。しかし重要なのは、数字に基づきリスクとリターンを比較し、自分の投資目的に合う戦略を選ぶことです。新築には保証や長期融資という強みがあり、中古やリノベ物件には初期コストの低さと高い自己資金利回りがあります。さらに2025年度の各種制度を組み合わせれば、出口戦略の幅も広がります。まずはシミュレーションで現実を可視化し、リスク分散を意識したポートフォリオを組むことが、長期的に安定した不動産投資への近道と言えるでしょう。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp/
- 国土交通省 住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
- 総務省 人口推計 – https://www.stat.go.jp/data/jinsui/
- 住宅新報社 賃料動向調査 – https://www.jutaku-s.com/
- 国税庁 タックスアンサー – https://www.nta.go.jp/taxes/

