不動産投資を始めたいものの、「やはり新築が安心なのでは」と迷う方は多いでしょう。しかし実際には、築年数だけで投資成果が決まるわけではありません。この記事では「新築 いらない」と言われる理由をデータで確認しつつ、中古物件でも安定収益を得るための具体策を解説します。読み終えれば、物件探しから資金調達、税制優遇の活用までを一貫してイメージできるはずです。
中古物件が注目される理由
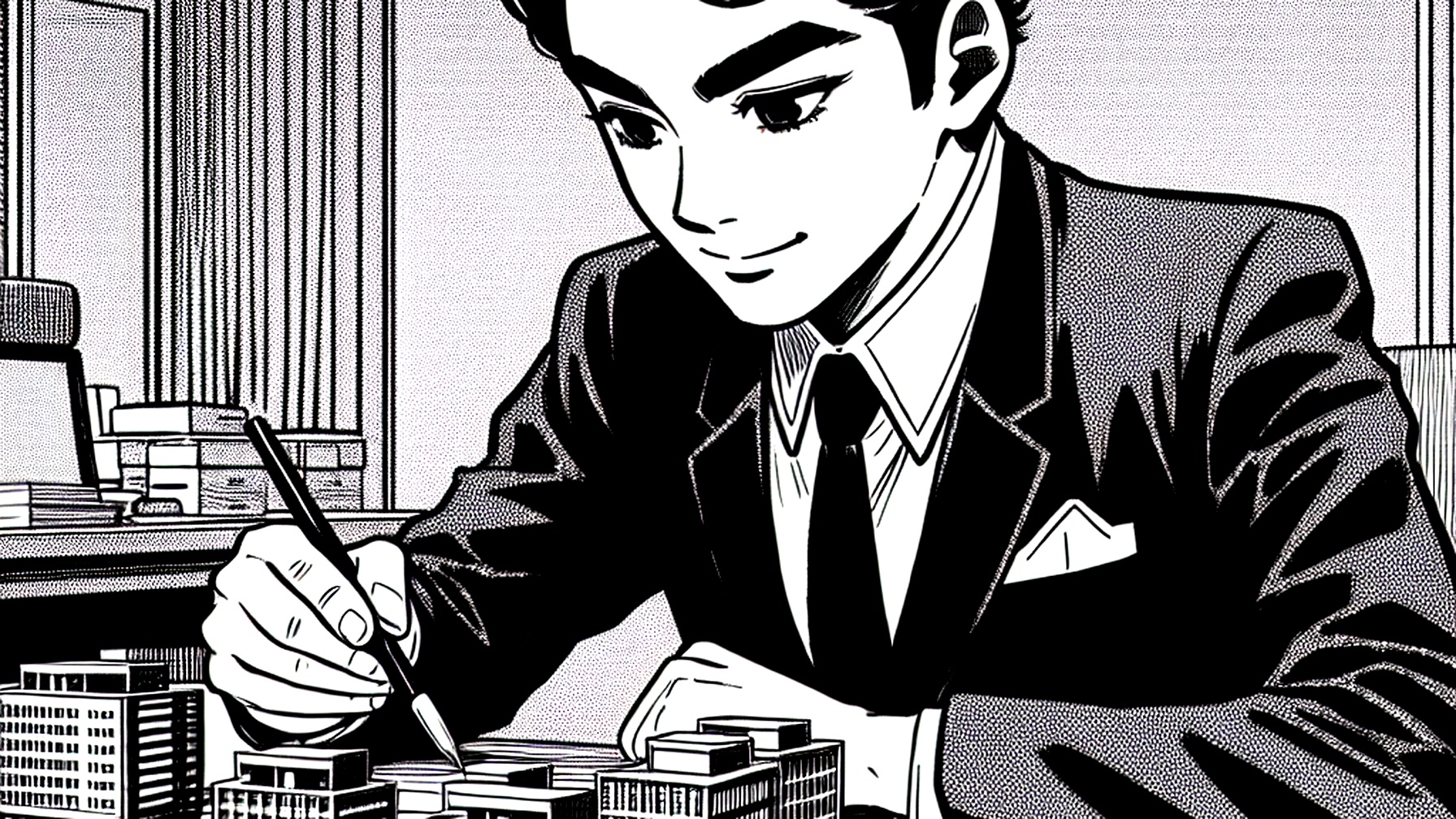
まず押さえておきたいのは、中古市場の拡大が続いている現状です。国土交通省の住宅市場動向調査(2024年度版)では、中古マンションの成約件数が新築供給の約1.8倍に達しました。背景には新築価格の高騰だけでなく、リノベーション技術の向上と情報開示の透明化があります。
価格が抑えられる点も大きな魅力です。同じ賃料が期待できるエリアでも、新築と比べ中古は2〜3割安く購入できるケースが珍しくありません。自己資金が限られる初心者にとって、購入コストが下がれば融資審査のハードルも下がり、手残りキャッシュフローが厚くなります。
さらに、築20年超物件でも建物寿命は十分残っています。日本建築学会の資料によると、適切に修繕される鉄筋コンクリート造の寿命は60年以上が標準です。つまり表面上の古さだけで投資対象から外すのは早計であり、修繕履歴や管理状況をチェックすれば安心材料は見つかります。
利回りを左右するコスト構造

ポイントは、購入時の総コストと保有期間のランニングコストを正しく見積もることです。新築は修繕費が当面少ない一方、取得価額が高く減価償却による節税効果も限定的です。対して中古は購入直後に修繕が必要な場合があるものの、取得価額が低く抑えられるため利回りが高くなりやすい構造です。
たとえば、都内城南エリアで家賃10万円のワンルームを想定します。新築で3,000万円、表面利回り4%、中古で2,000万円、表面利回り6%。管理費や税金を差し引いた実質利回りを試算すると、新築2.5%、中古4.1%となり、月々のキャッシュフロー差は約1.3万円です。10年保有すれば、およそ150万円の手残り差になります。
重要なのは「いついくら修繕するか」を計画に組み込むことです。築25年超であれば、屋上防水や給排水管更新など200万〜300万円の大規模修繕を想定します。購入前に専門家のインスペクションを依頼し、修繕積立金とのバランスを確認すれば、資金繰りを読み違えるリスクを大幅に減らせます。
法人化と資金調達の勘所
実は、総合的な税負担を抑えるには法人設立が有効な場合があります。所得税の最高税率45%に対し、法人実効税率は約30%。中古物件は建物価格比率を高めやすく、減価償却費を多く計上できるため、法人の節税効果がより大きくなります。
資金調達面でも中古向け融資は選択肢が広がっています。2025年9月時点で、地方銀行や信用金庫は築30年までを対象に、金利1.8%前後のアパートローンを提供しています。自己資金1〜2割を用意し、返済比率を年収の30%以内に抑えると審査は通りやすくなります。
一方で、築古物件は評価額が低く設定されやすいため、担保余力が限られます。複数棟を所有して規模を拡大したい場合、法人化して決算書を整え、金融機関との長期的な関係を築くことが不可欠です。収支計画書に加え、修繕計画と出口戦略を提示すると、融資担当者の信頼を得やすくなります。
2025年度の税制優遇を活かす
2025年度も不動産オーナー向けの税制優遇は継続しています。代表例が「住宅ローン減税」の投資版にあたる住宅取得控除です。一定の省エネ基準を満たす住宅を取得し、一定期間自己居住後に賃貸転用すると、控除枠を維持したまま家賃収入を得られます。具体的には、年末残高2,000万円を上限に0.7%を控除でき、最大10年間の節税が可能です。
固定資産税の軽減措置も見逃せません。築年数を問わず認定長期優良住宅に改修すると、翌年度分の固定資産税が半額になります。リノベ費用はかかりますが、空室対策としての付加価値向上と税負担の削減を同時に達成できる点が魅力です。
ただし、これらの優遇には期限があります。控除は2030年末入居分まで、固定資産税の軽減は2026年度課税分までが現行の適用期限です。制度変更が想定されるため、投資判断は早めに下し、申請書類の準備を怠らないことが肝心です。
リスクを減らす管理術
基本的に、管理の質が収益の安定性を決めます。築古でも設備が清潔に保たれ、入居者対応が迅速であれば、空室率は想像以上に低く抑えられます。総務省の住宅・土地統計調査(2023年)によると、管理会社が巡回を月2回以上実施する物件の平均空室率は9.2%と、巡回頻度が少ない物件に比べ約3ポイント低い結果が出ています。
リノベーションの際は、家賃を2万円上げる高額プランよりも、2,000円上げる小規模改修を定期的に行う方が費用対効果が高いことが多いです。水栓の節水化、LED照明化、宅配ボックスの設置など、入居者満足度に直結する設備を優先すると退去率の低下が期待できます。
最後に、入居者属性の分散も欠かせません。単身向けのみでは景気変動の影響を受けやすいため、ファミリー向けや高齢者向けの物件を組み合わせ、エリアも複数に分散することでリスクを平準化できます。地元自治体の人口ビジョンを確認し、将来の需要を見極める姿勢が求められます。
まとめ
本記事では、「新築 いらない」と言われる背景と、中古物件でも収益を最大化する方法を解説しました。価格の安さと高い利回り、税制優遇の活用など、中古ならではのメリットは想像以上に大きいはずです。とはいえ、修繕計画と資金調達を怠ればリスクは一気に高まります。今日からできるのは、気になるエリアの中古物件情報を集め、インスペクションの見積もりを取り、金融機関に事前相談を申し込むことです。小さな行動を重ねることで、将来の安定収益への道が開けます。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2024年度版 – https://www.mlit.go.jp
- 日本建築学会 既存住宅の耐用年数に関する研究報告 – https://www.aij.or.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査2023 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁 所得税率表2025年度 – https://www.nta.go.jp
- 中小企業庁 2025年度中小企業向け融資実態調査 – https://www.chusho.meti.go.jp

