アパートを運営していると、「空室を早く埋めたいが、募集コストはどれくらい見込めばいいのか」と迷う場面が必ず訪れます。広告費、仲介手数料、設備の入れ替えなど、支出項目が多く全体像が見えにくいのが実情です。本記事では、実務経験十五年の視点から、入居者募集に必要な費用の相場と抑え方を基礎から丁寧に解説します。読むことで、無駄な出費を避けながら高い入居率を確保するための具体策がつかめます。
入居者募集にかかる費用の全体像
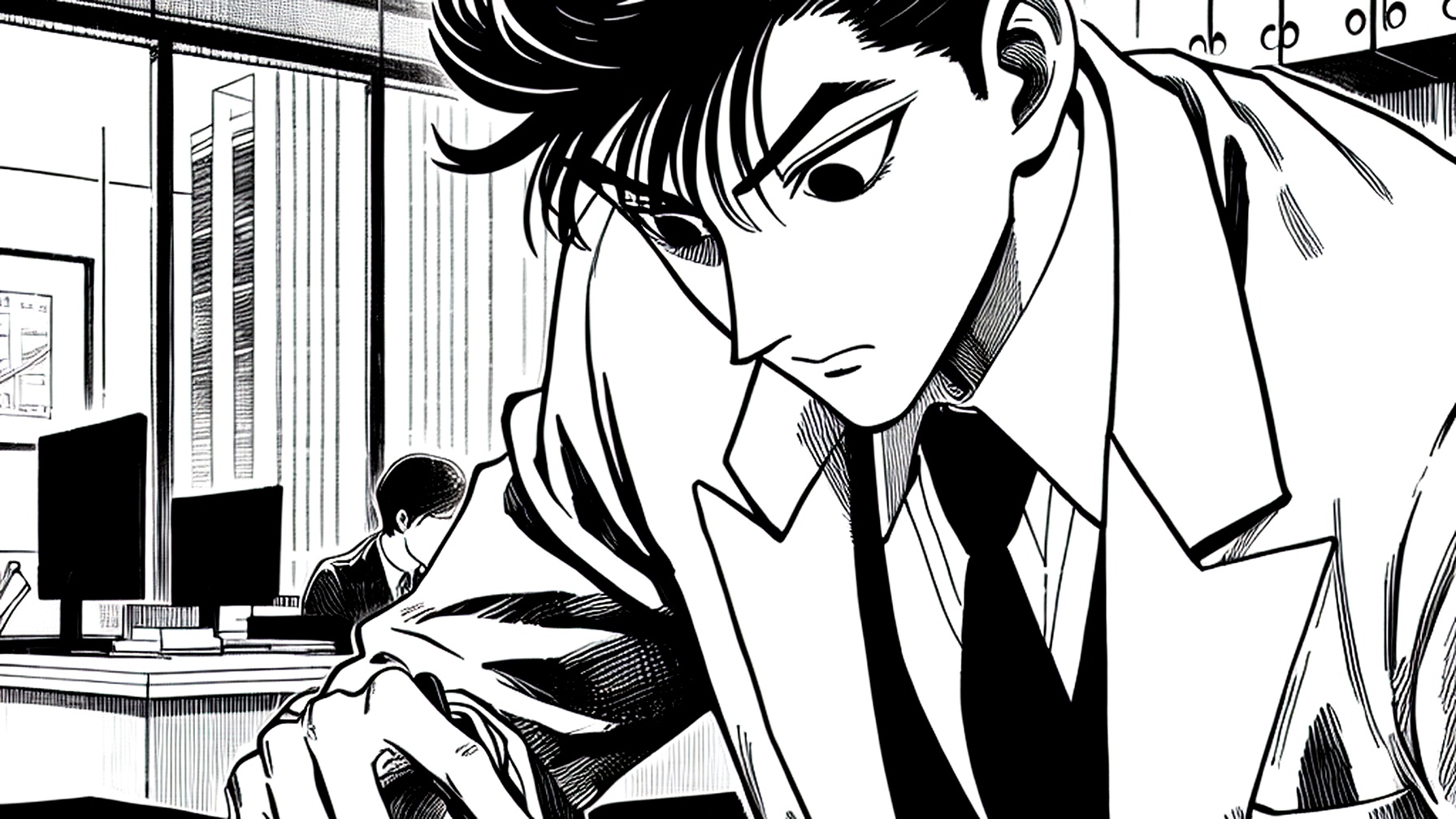
まず押さえておきたいのは、募集コストが単なる広告費だけでは完結しない点です。仲介会社へ支払う「広告料(AD)」、契約時の「媒介手数料」、室内クリーニングや鍵交換といった「原状回復費」、さらに募集期間中の「空室損失」がまとまって発生します。これらを合算した「総費用」が実際の負担額となるため、個別では小さく見えても合計で大きな差を生むことがあります。
国土交通省の令和七年住宅市場調査によると、首都圏の平均広告料は家賃の0.9〜1.1か月分、関西圏では0.7〜0.9か月分でした。加えて、原状回復費は戸当たり平均6.8万円という数字が示されており、築年数が古いほど上振れしやすい傾向が見られます。つまり、家賃6万円のワンルームを空室一か月で成約させた場合でも、募集関連で約14万〜16万円の資金が動く計算です。
重要なのは、この「総費用」を事前に資金計画へ組み込み、年度予算として管理する姿勢です。毎月のキャッシュフローだけを追っていると、突発的な空室で一気に現金が流出し、資金繰りを圧迫しかねません。長期的な修繕計画と同様、募集費用も年間サイクルで見積もり、あらかじめ口座を分けてプールしておくと安心です。
募集方法別に見る広告費の相場
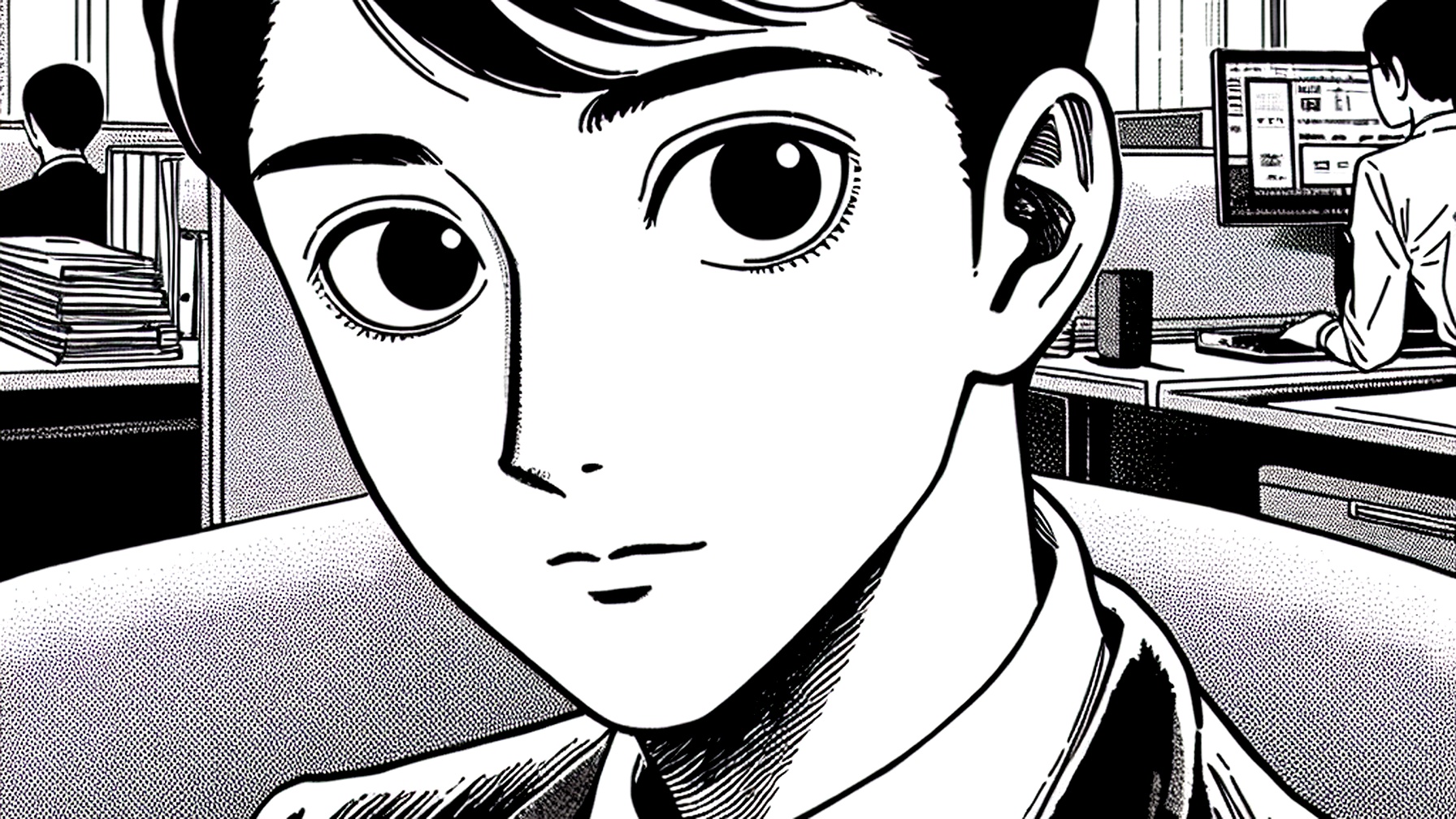
ポイントは、入居者募集のチャネルを選ぶことで広告費の幅が大きく変わることです。仲介会社任せであれば手間は減りますが、広告料や専任契約の縛りが発生しやすくなります。一方で自主管理に近い形でポータルサイトへ直接掲載する場合、掲載料は抑えられるものの内見対応や審査を自ら行う手間が増えます。
仲介会社経由のケースでは、2025年の首都圏平均で広告料が家賃1か月分、媒介手数料が0.5か月分という組み合わせが主流です。管理会社とサブリース契約を結んでいる場合でも、解約後の再募集で同程度の広告料を求められる例が多いとされます。対して、大家が不動産ポータルへ直接載せると、掲載料は1室2万円前後ですみますが、写真撮影や間取り図作成を外注すると追加で1万円ほど必要になります。
ただし、費用だけで判断すると成約までの期間が長引くリスクが残ります。特に全国平均空室率が21.2%(2025年7月、国交省)という環境下では、情報露出の少なさが長期空室へ直結しかねません。広告費を抑える戦略を取るときは、同時にターゲットを絞ったSNS広告や家具付きプランなど差別化策を用意し、成約スピードを確保する工夫が欠かせません。
設備投資とリフォーム費はどこまでかけるべきか
実は、入居者の決定要因として家賃とほぼ同じ比重を占めるのが室内設備です。インターネット無料や防犯カメラといった付加価値は、設備ランキング上位の常連であり、家賃一万円アップに匹敵する訴求力を持つと調査でも示されています。ところが闇雲に設備を追加すると、初期費用がかさみ利回りが低下するため、投資額と回収期間のバランスを計算する姿勢が必要です。
参考として、日本賃貸住宅管理協会の2025年報告によれば、インターネット無料の導入コストは戸当たり平均6万円、入居率の改善効果は4.5ポイントでした。単身向け物件で空室期間が一か月短縮できれば、家賃6万円なら年利換算で約12%の投資回収が期待できます。つまり初期投資を二年で回収できれば、その後は純粋なプラスキャッシュフローに寄与します。
一方で、水回りの全面リフォームや間取り変更は費用が跳ね上がりやすいです。築二十五年以上で家賃水準も下がっている物件なら、思い切ってファミリー向けに転換する価値が出てきますが、築浅なら原状回復中心にとどめたほうが収支にやさしい場合が多いと覚えておきましょう。
空室期間の機会損失を減らす考え方
基本的に、家賃収入がゼロになる空室期間は「見えにくい支出」として経営を圧迫します。家賃7万円の部屋が二か月空くと14万円の機会損失になり、前項で説明した募集費用と同程度の損失規模に達します。このため、費用を抑えるだけでなく、空室期間そのものを短くすることが経営の肝といえます。
空室期間短縮には、退去予告を受けた段階から次の募集を始める「先行募集」が有効です。退去後に室内を確認しないと募集できないと考える大家も多いですが、現行入居者と協議して内見可能な日時を調整すれば、実際の空室ゼロ日での成約も十分に狙えます。国交省の事例調査では、先行募集を導入した物件が空室期間を平均18日短縮したとの報告が出ています。
さらに、繁忙期と閑散期の賃料戦略を分ける柔軟さも欠かせません。三月の転勤・入学シーズンには家賃を据え置いたままでも成約率が高い一方、七月から九月の閑散期には短期的なキャンペーン家賃を提示し、早期成約を優先するケースが増えています。結果として、通年の家賃平均が大きく下がることなく、総収入の底上げが可能となります。
2025年度の補助金と税制優遇を活用する方法
重要なのは、設備投資を進める際に2025年度も継続している補助事業をうまく利用することです。たとえば経済産業省の「住宅省エネ2025キャンペーン」は、高効率給湯器や断熱窓の導入に対して一戸あたり最大20万円を補助します(申請期間は2026年1月末まで)。また、環境省の「既存賃貸住宅ZEH化支援事業」では、一定の断熱性能向上と太陽光発電設置を行えば、戸当たり100万円を上限とした補助が受けられます。
補助金を使うと、自己負担を抑えながら設備グレードを上げられるため、家賃維持と入居率向上を両立しやすくなります。さらに法人名義でアパートを所有している場合、投資額の一部を即時償却できる中小企業経営強化税制(2025年度適用)を組み合わせると、初年度の節税効果も期待できます。
ただし、補助事業は書類不備で不採択となる例が多く、スケジュールにも余裕が必要です。施工会社が制度に詳しいかを確認し、見積書の仕様が要件を満たしているかを二重チェックする癖をつけましょう。補助金と税制優遇を経営計画に組み込むことで、入居者募集に直結する設備投資をより低リスクで実行できます。
まとめ
空室を埋めるには広告料や原状回復費だけでなく、空室期間による機会損失まで含めた「総費用」の視点が欠かせません。仲介会社任せで早期成約を狙う方法と、自主管理で広告費を抑える方法のどちらを採るにしても、最終的に大切なのは年間キャッシュフローを安定させるバランス感覚です。設備投資では回収期間を数値で検証し、国や自治体の補助金・税制優遇を活用することで、家賃の下落を防ぎながら競争力を高められます。今日整理したポイントを基に、自身の物件に合った募集戦略と予算配分を見直し、継続的な満室経営を目指してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2025 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 住生活基本計画モニタリング調査2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 日本賃貸住宅管理協会「賃貸住宅市場景況感調査2025」 – https://www.jpm.jp
- 経済産業省 住宅省エネ2025キャンペーン資料 – https://www.meti.go.jp
- 環境省 既存賃貸住宅ZEH化支援事業概要2025 – https://www.env.go.jp
- 中小企業庁 中小企業経営強化税制ガイド2025年度版 – https://www.chusho.meti.go.jp

