子どもの学費が右肩上がりに伸びる一方で、預貯金だけでは将来が心もとないと感じていませんか。実は、家計の中長期的な柱として「マンション投資」を活用する家庭が増えています。本記事では「教育資金 マンション投資 ファミリー向け」というテーマに沿って、必要な基礎知識から物件選び、最新の税制優遇までを整理しました。読み進めることで、学費と資産形成を同時に叶える実践的なヒントが得られるはずです。
教育費が年々上がる現実と準備の課題
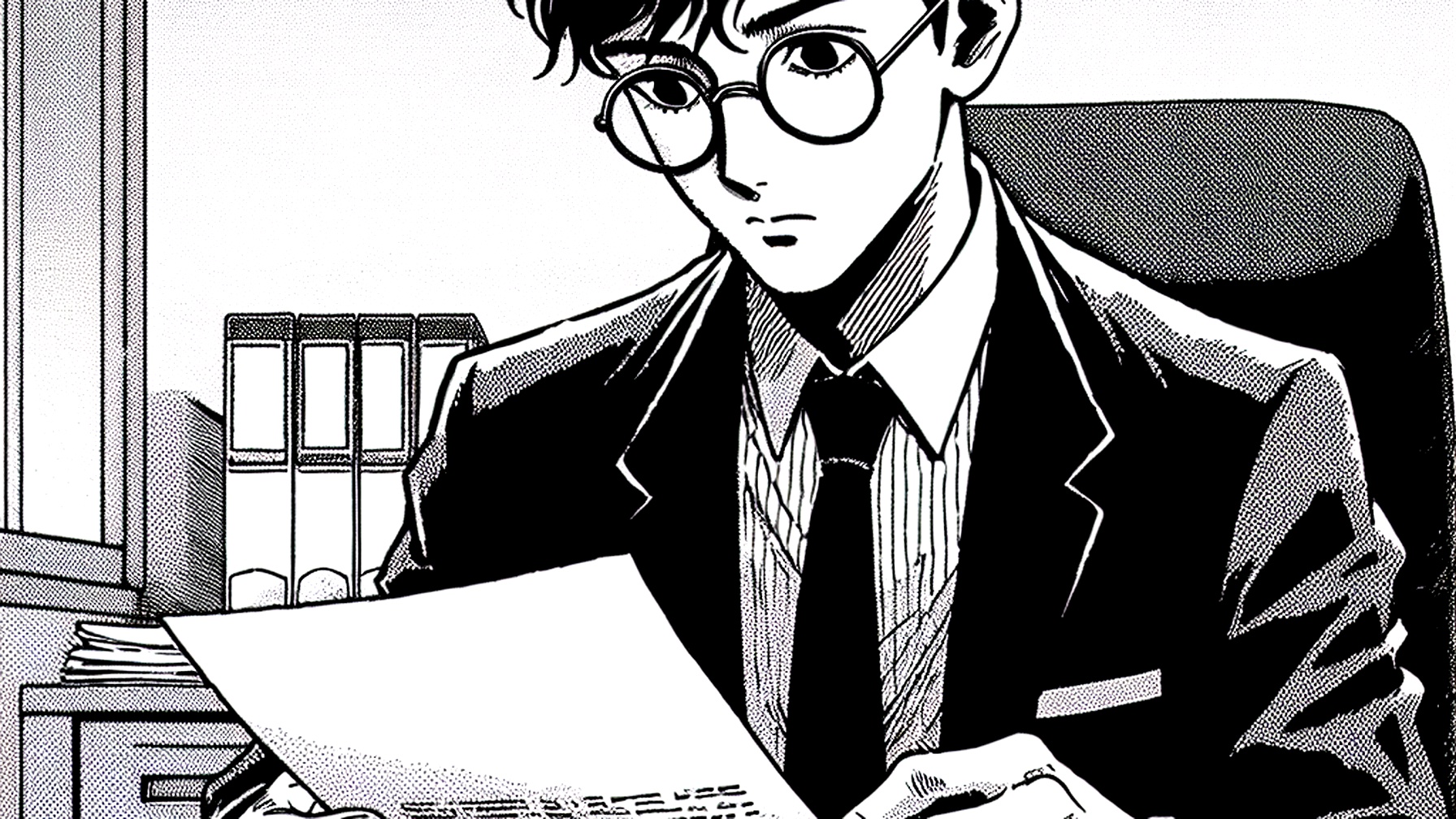
まず押さえておきたいのは、教育費の上昇ペースです。文部科学省の「子どもの学習費調査2024年度版」によると、幼稚園から高校までの15年間で必要な学習費総額は公立でも約550万円、私立の場合は約1,860万円に達します。さらに大学進学を想定すると、総額は2,000万〜3,000万円台へ跳ね上がり、インフレ率を加味すれば実質負担はさらに重くなると考えられます。
一方、総務省「家計調査」では、30代共働き世帯の金融資産中央値は440万円程度にとどまります。公的データを比べると、貯蓄だけで全額を賄うのは現実的に厳しいことがわかります。だからこそ、現役世代でも長期的にキャッシュフローを生み出す仕組みが必要になります。
株式投資や投資信託も選択肢ですが、値動きが激しい局面では短期的な現金化が難しい場合があります。そこで、毎月の賃料収入が見込めるマンション投資が教育費対策として注目されています。つまり、家計と学費を両立させるための“第2の収入源”を組み込む発想が重要になるわけです。
マンション投資で学費を賄うしくみ
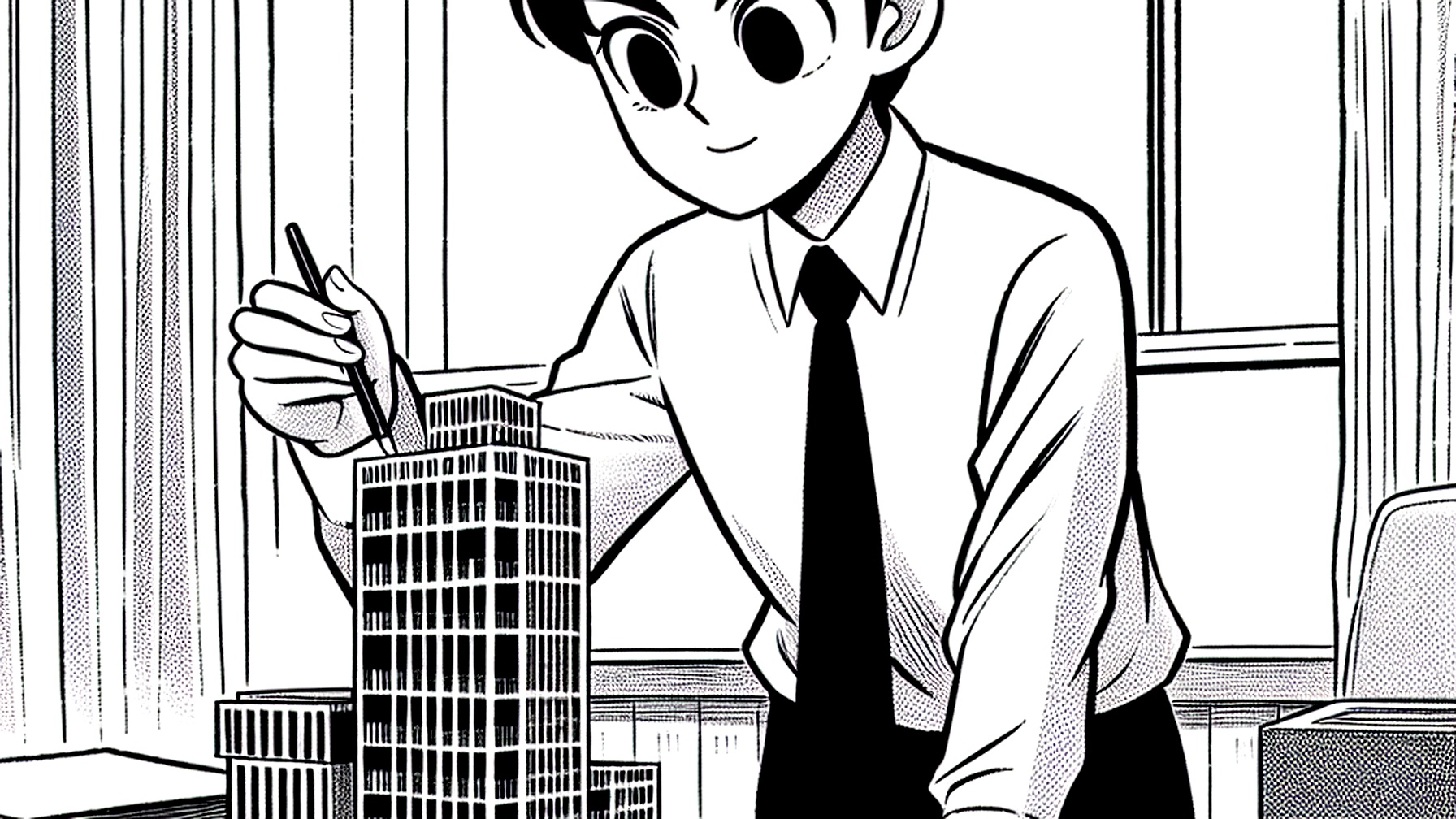
ポイントは、入学時期に合わせてキャッシュフローを設計することです。家賃収入は基本的に毎月入りますが、学費は入学金や納付金など大口の支出が集中します。そのため、年間収支表を作成し「家賃収入からローン返済・管理費を引いた残り」を教育資金にプールしていく計画が欠かせません。
実例として、東京23区で3,500万円のワンルームを購入し、35年ローン(固定1.5%)を組むケースを考えます。2025年の平均賃料水準を参考に月10万円で賃貸すれば、年間家賃は120万円です。管理費や修繕積立金、空室1カ月分を差し引くと、手残りはおよそ45万円になります。この金額を18年間積み立てれば、子ども1人分の大学入学時に800万円前後の原資を用意できる計算です。
また、家賃はインフレに連動しやすい特徴があります。総務省の消費者物価指数が年2%上昇した場合、家賃が同じペースで上がれば名目収入も増えるため、インフレヘッジとして機能します。学費インフレに備えるという意味でも、マンション投資は相性が良いと言えるでしょう。
ファミリー向け物件を選ぶときの視点
重要なのは、子育て世帯向けの立地と間取りを見極めることです。国土交通省「住宅市場動向調査2025」では、ファミリー層の賃貸ニーズが強いエリアとして「駅徒歩10分以内」「小学校まで1km圏」「保育園が近い」などの条件が挙げられています。これらを満たす物件は空室期間が短く、安定収益の源になります。
さらに、間取りは2LDK以上を基本に検討すると安心です。テレワーク需要の高まりで、1部屋を在宅ワーク用に使えるレイアウトが支持されています。加えて、2025年の新築マンション平均価格は東京23区で7,580万円ですが、中古の築20年前後であれば4,000万円台も狙えます。購入価格を抑えつつ賃料水準が下がりにくいエリアを探すと、投資効率が高まります。
リセールバリューも無視できません。実は、学費のピークを過ぎたタイミングで売却し、売却益を老後資金に振り向ける家庭もあります。将来的にどのくらいの価格で売れるか、近隣の取引事例や人口動態を確認し、出口戦略まで視野に入れることがファミリー向け投資のコツです。
資金計画とリスク管理のポイント
まず押さえておきたいのは、自己資金とローンのバランスです。金融庁の「家計の安定的な資産形成に関する意識調査2025」によると、家計が負担感なく返済できる安全圧縮率は可処分所得の30%以内が目安とされています。自己資金を物件価格の20%程度用意すれば、毎月の返済額を抑えつつ審査も通りやすくなります。
また、空室や家賃下落に備え、家賃収入の2〜3カ月分を予備費としてストックしておくと安心です。金融商品の一つとして、団体信用生命保険(ローン契約者に万が一があった場合に残債が完済される保険)も必ず付帯させましょう。これにより、世帯主の不測の事態でも家族が家賃収入を得続けられ、教育資金計画が破綻しにくくなります。
さらに、保有期間中の修繕は避けられません。国土交通省の「長期修繕計画標準様式」に基づくと、築15年目で外壁・屋上防水に1戸あたり平均70万円が必要とされています。キャッシュフローが黒字でも、このタイミングで大規模修繕が重なると赤字化リスクがあります。定期的に積み立て、将来の支出を平準化しておくことが肝心です。
2025年度の税制優遇と活用手順
実は、税制を味方に付ければ学費負担をさらに軽減できます。2025年度も適用される「住宅ローン控除」は、省エネ基準を満たす新築で年末ローン残高の0.7%(上限3,000万円)が13年間差し引かれる制度です。投資用住宅には直接使えませんが、自己居住用マンションを賃貸化する「転勤貸し」に切り替える場合など、家計全体で考えると節税効果が見込めます。
加えて、不動産所得と給与所得を損益通算できる点も見逃せません。減価償却費やローン利息を経費計上することで、課税所得を圧縮し、その分を教育費に充てられます。ただし、過度な赤字計上は税務署から否認されるリスクがあるため、専門家にシミュレーションを依頼すると安全です。
さらに、2025年度の「住宅取得等資金に係る贈与税非課税制度」は、子どもや孫が省エネ性能の高い住宅を取得する際に、直系尊属から最大1,500万円までの贈与が非課税になります。これを活用すれば、将来子どもが自宅を購入するときに学資とは別枠で支援でき、家庭内の資産移転をスムーズに行えます。期限は2026年12月契約分までと予定されているので、早めの情報収集が求められます。
まとめ
マンション投資を通じて教育資金を準備する最大の利点は、毎月の家賃収入が“学費積み立て”として機能する点です。ファミリー向け物件を選び、キャッシュフローと修繕費を押さえれば、18年後にまとまった資金を確保しやすくなります。もちろん、空室リスクや修繕負担は避けられませんが、立地選定と適切な自己資金比率、そして税制優遇の活用でリスクを最小化できます。今日から情報収集を始め、家族の未来を自ら設計してみてはいかがでしょうか。
参考文献・出典
- 文部科学省「子どもの学習費調査2024年度版」 – https://www.mext.go.jp/
- 総務省統計局「家計調査 家計収支編」 – https://www.stat.go.jp/
- 国土交通省「住宅市場動向調査2025」 – https://www.mlit.go.jp/
- 不動産経済研究所「首都圏新築マンション市場動向2025年9月」 – https://www.fudosankeizai.co.jp/
- 金融庁「家計の安定的な資産形成に関する意識調査2025」 – https://www.fsa.go.jp/

