マンション投資に興味はあるものの、「なぜわざわざ不動産にお金を入れるのか」と疑問に感じる方は多いでしょう。株や投資信託と比べて情報が少なく、リスクが大きいイメージもあります。しかし実際には、家賃という安定収入や税制優遇など、マンション特有の強みが存在します。本記事では初心者でも理解できるよう、投資の背景から運用のコツまで順序立てて説明します。読み終えたころには、自分の資産形成にマンション投資を取り入れる理由と方法がはっきり見えてくるはずです。
マンション投資が注目される背景
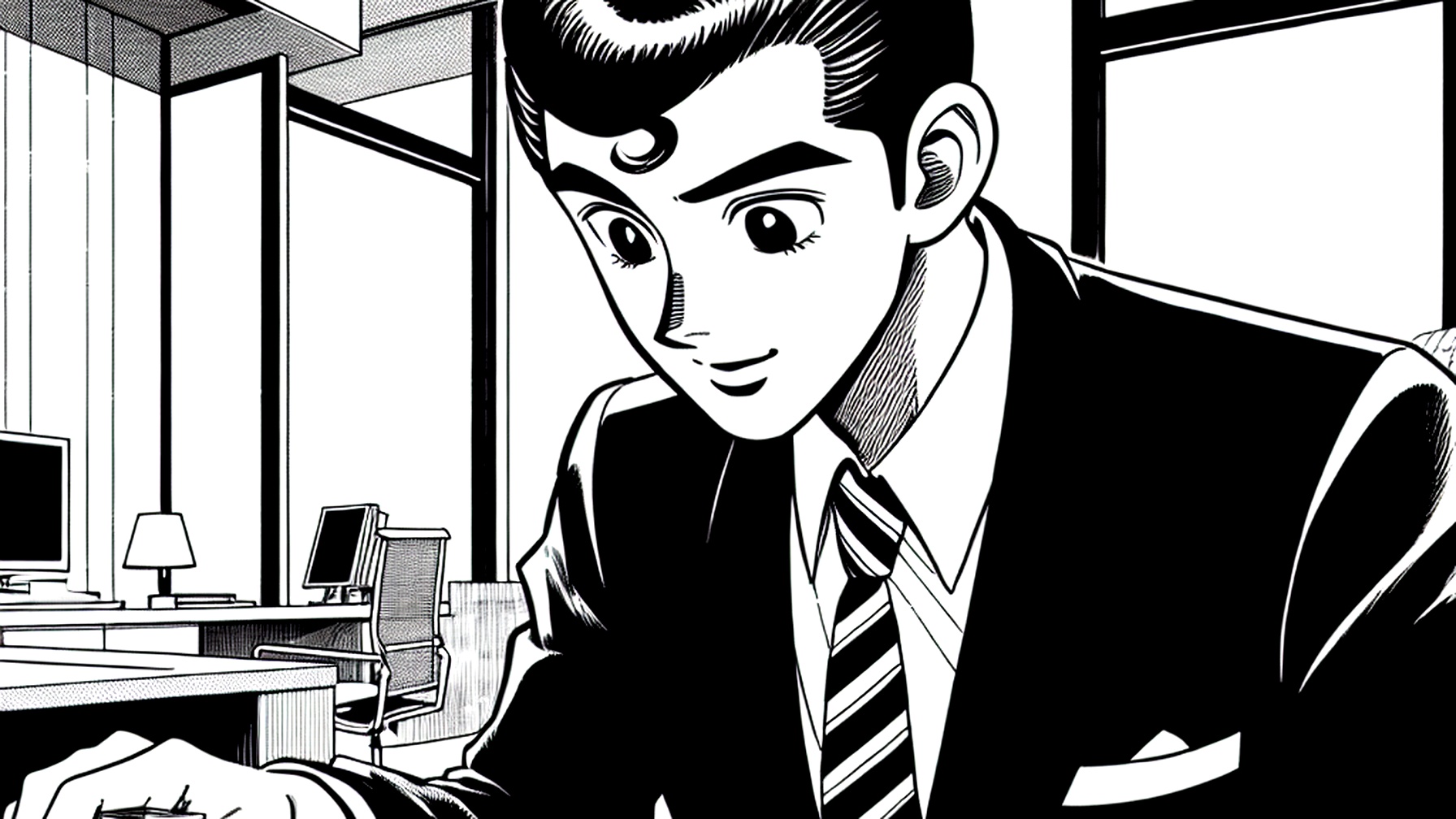
まず押さえておきたいのは、日本の都市部で住宅需要が底堅いという事実です。総務省の人口移動報告によると、2024年時点で東京23区への転入超過は11万人を超え、20代単身者が半数を占めます。つまりワンルーム需要が高い状況が続くわけです。加えて、不動産経済研究所の調査では2025年9月の新築マンション平均価格が7,580万円と、前年より3.2%上昇しています。価格が伸びる一方で借り手が多い都市部では、安定した賃貸市場が期待できるのです。
一方で、日本銀行が続けてきた低金利政策は投資家にとって追い風となっています。住宅ローン金利は2025年も変動タイプで年1%前後と歴史的低水準を維持し、レバレッジを利かせやすい環境が続きます。株式市場が世界情勢で大きく揺れるなか、現物資産に資金が流れやすい構図も投資熱を押し上げています。
結論として、人口集中と金融環境の二つが交差したことが「マンション投資 なぜ選ばれるのか」の根本的な答えと言えます。環境要因を理解することで、投資タイミングの妥当性が見えてくるでしょう。
家賃収入が生む安定キャッシュフロー
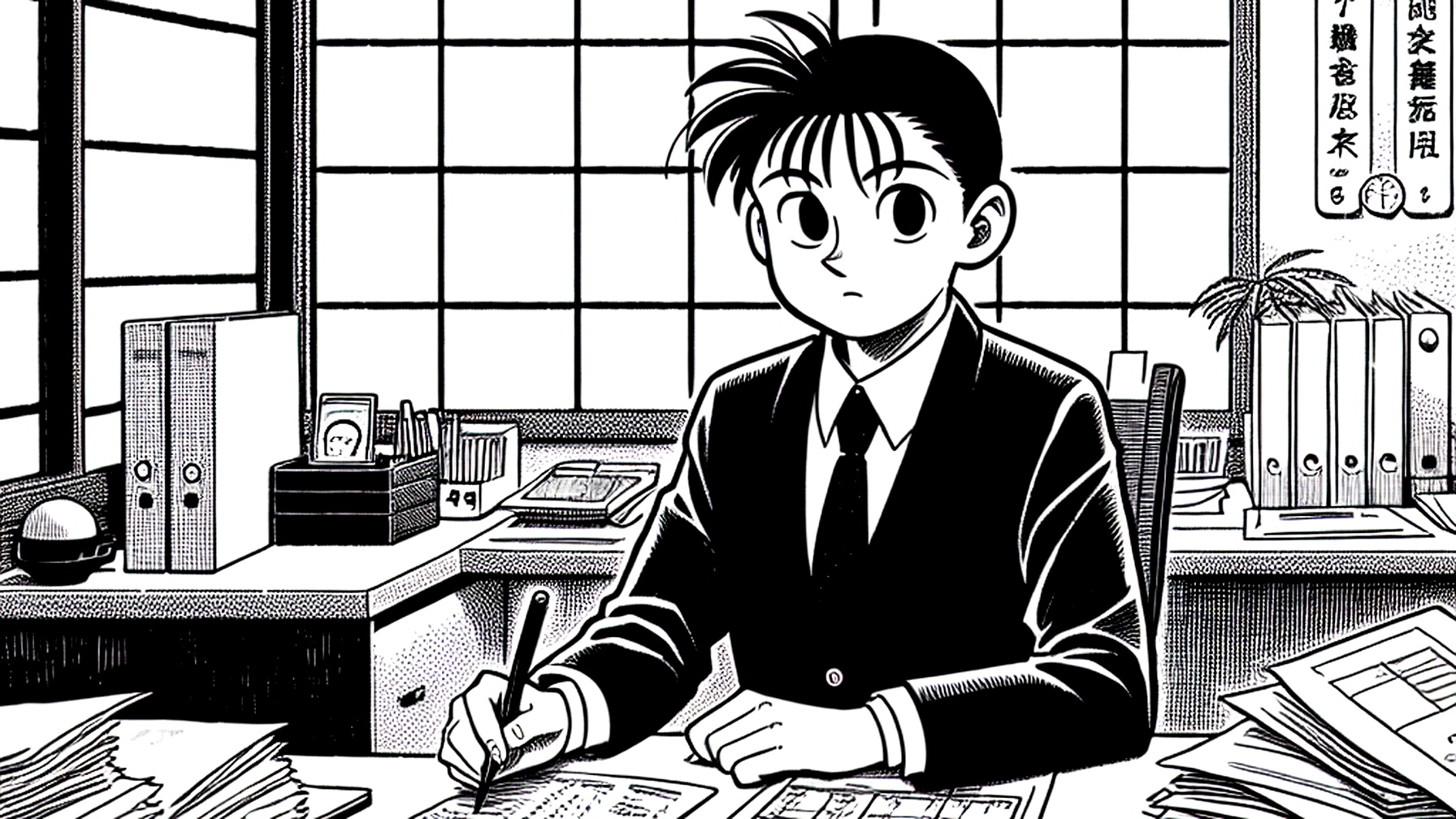
ポイントは、他の金融商品と比べて現金が定期的に入ることです。株式配当は年1〜2回が一般的ですが、家賃は月ごとに入金されます。そのため生活費の補填や再投資の原資を計画的に確保しやすいメリットがあります。
具体的にシミュレーションしてみましょう。都心ワンルーム(購入価格2,800万円、自己資金560万円、金利1.0%、35年ローン)を想定すると、月々の返済は約7.8万円になります。周辺の平均家賃が9.5万円であれば、管理費・修繕積立を差し引いても毎月1万円ほどの手残りが期待できます。言い換えると、借り手が途切れない限りローン返済を賃借人が肩代わりしてくれる構図がつくれるのです。
また、将来の売却益が得られなくても家賃でローン元本が減るため、資産が自然に積み上がります。実はこの「他人資本での返済効果」こそ長期保有戦略の肝です。家賃水準が下がりにくいエリアを選ぶことで、キャッシュフローの安定度はさらに高まります。
最後に、物件管理会社を使えば入居者対応の負荷を低減できます。手数料は家賃の数%ですが、自分の時間を生み出せる点を考えれば十分に合理的です。つまり家賃収入は労働時間に縛られない収益源となり、経済的自由度を一歩高めてくれます。
資産形成とインフレ対策の相乗効果
重要なのは、マンションがインフレに強い実物資産であることです。日本でも2022年以降、消費者物価指数は年3%前後で上昇し、現金の購買力は緩やかに目減りしています。一方、不動産価格は土地と建物コストが影響し、材料費や人件費の上昇が価格に転嫁されやすい構造にあります。
たとえば同じ3,000万円を預金とマンションに半分ずつ置いたケースを考えます。物価上昇率が年2%なら10年後の実質価値は預金部分で約2割目減りしますが、都心マンションは建築費上昇と需要で名目価格が2割上がる可能性があります。もちろん市場変動リスクは残りますが、現金のみよりトータル資産が目減りしにくいのは明らかです。
さらに、マンションを担保に追加融資を受ける「リファイナンス」もインフレ局面では有効です。資産評価が上がれば自己資本比率が改善し、低利の借り換えや追加投資がしやすくなります。つまりマンション保有は単なる防御ではなく、攻めの資産形成にもつながります。
最後に、老後の年金補完として家賃を受け取る選択肢があります。総務省の家計調査では65歳以上夫婦の実支出は月26万円前後です。年金だけで不足する分を家賃で埋めるプランを描ければ、インフレで生活費が上がっても対応しやすくなります。
税制メリットと2025年度の最新ルール
実は、税制優遇が投資収益を後押ししています。マンションの建物部分は法定耐用年数47年(鉄筋コンクリート造)で減価償却できます。新築を購入すれば、初年度から数十万円の経費計上が可能になり、給与所得と損益通算して所得税や住民税の負担を減らせます。
2025年度税制では、大きな変更点として「青色申告特別控除65万円」が電子帳簿保存とe-Tax送信を条件に継続されます。副業で不動産所得が20万円を超える場合、青色申告を選択すれば赤字繰越も最長3年間認められます。つまり初期費用や修繕で赤字になっても翌年以降の家賃収入と相殺できるわけです。
また、相続税評価額が時価より低く算定される仕組みも健在です。現金5,000万円を賃貸マンションに置き換えると、相続税の課税ベースが2〜3割下がる例も珍しくありません。家族への資産承継を意識する場合、この効果は見逃せません。
注意点として、減価償却の終了後は課税所得が増えるため、長期保有では将来の税負担を見込んだ資金計画が必要です。さらに、2025年度からスタートした「修繕積立計画認定制度」により、大規模修繕の積立不足がある物件は金融機関の融資審査が厳しくなる可能性があります。税と法規制の変化を定期的に確認し、専門家と連携しながら運用することが肝要です。
失敗を防ぐ物件選びと運用のコツ
まず大切なのはエリア選定です。都心駅徒歩10分以内で築10年以内という条件は、空室率が低く手堅い一方、利回りは4%台にとどまります。郊外なら利回り6%超が狙えますが、人口減少で賃料下落のリスクが高まります。自分のリスク許容度を見極めたうえで、収益と安全性のバランスを取ることが求められます。
次に重視したいのが管理体制です。国土交通省の「マンション総合調査」によると、大規模修繕を予定通り実施した管理組合は全体の63%に過ぎません。修繕履歴と積立金残高を確認し、長期修繕計画が現実的かをチェックしましょう。ここを怠ると、後から一時金負担や資産価値の下落を招きます。
融資については、複数の金融機関を比較し金利だけでなく融資期間と団体信用生命保険の内容も確認します。たとえば35年ローンで0.3%金利が高い場合でも、10年後に繰上げ返済するなら総返済額の差は小さくなることがあります。つまりシミュレーションは自身のライフプランに沿って行うべきです。
入居者募集では、ターゲットを絞った広告と内見対応が空室期間を短くします。最近は家具家電付きプランやIoT設備が若年層に人気です。こうした小さな差別化は費用対効果が高く、期待利回りを上乗せする手段になります。継続的に情報をアップデートし、物件の魅力を保つ姿勢が成功を左右します。
まとめ
マンション投資が選ばれる理由は、人口集中と低金利という外部環境、家賃収入による安定キャッシュフロー、そして税制メリットとインフレ対策の三本柱にあります。とはいえ、物件選びや管理体制を誤れば期待収益は簡単に崩れます。今日取り上げた視点を踏まえ、まずは自分の資金力とリスク許容度を棚卸しすることから始めてください。専門家に相談しつつ小さな物件で経験を積めば、将来的に複数戸を保有する道も開けます。行動に移すかどうかで、10年後の資産状況は大きく変わるでしょう。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp/
- 国土交通省「マンション総合調査」 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省統計局「人口移動報告」 – https://www.stat.go.jp/
- 日本銀行「金融経済月報」 – https://www.boj.or.jp/
- 国税庁「令和7年度税制改正の解説」 – https://www.nta.go.jp/

