不動産投資に興味はあるけれど、「資産形成と相続対策を同時に進める方法が分からない」という声をよく聞きます。確かに現金や株式だけでは、将来の税負担や家族への引き継ぎに不安が残ります。一方、アパート経営は安定収益を得ながら、相続税評価額を抑える仕組みまで活用できる点が魅力です。本記事では、初心者でも理解しやすいように、資産形成 アパート経営 相続対策を結び付ける考え方を解説します。開始のハードル、リスク管理、2025年度税制のポイントまで整理するので、読み終える頃には行動指針が見えてくるはずです。
アパート経営が資産形成に強い三つの理由

重要なのは、収益性と安全性のバランスをどう評価するかです。アパート経営は賃料を柱としたインカムゲイン(継続収益)と、物件価値の上昇によるキャピタルゲイン(売却益)の両面を狙えます。
まず、レバレッジ効果が高い点に注目してください。自己資金2,000万円に対し、融資8,000万円で1億円の物件を取得すると、表面利回り6%でも年間600万円の賃料収入が期待できます。自己資金利回りで見ると30%超になるケースも珍しくありません。
次に、物価上昇局面への強さです。総務省の消費者物価指数は2024年比で2.7%上昇しましたが、賃料は契約更新時に改定できるため、現金よりインフレ耐性があります。家賃の上昇がローン返済額に直ちに連動しない点もメリットです。
さらに、安定性の裏付けとして空室率の推移を確認しましょう。国土交通省住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で前年比0.3ポイント改善しました。地方の二極化はあるものの、管理体制と立地選定を徹底すれば収益の予見性は高められます。つまり、計画的に運営すれば長期の資産形成に適した仕組みとなるのです。
相続対策としてアパートを活用する基本
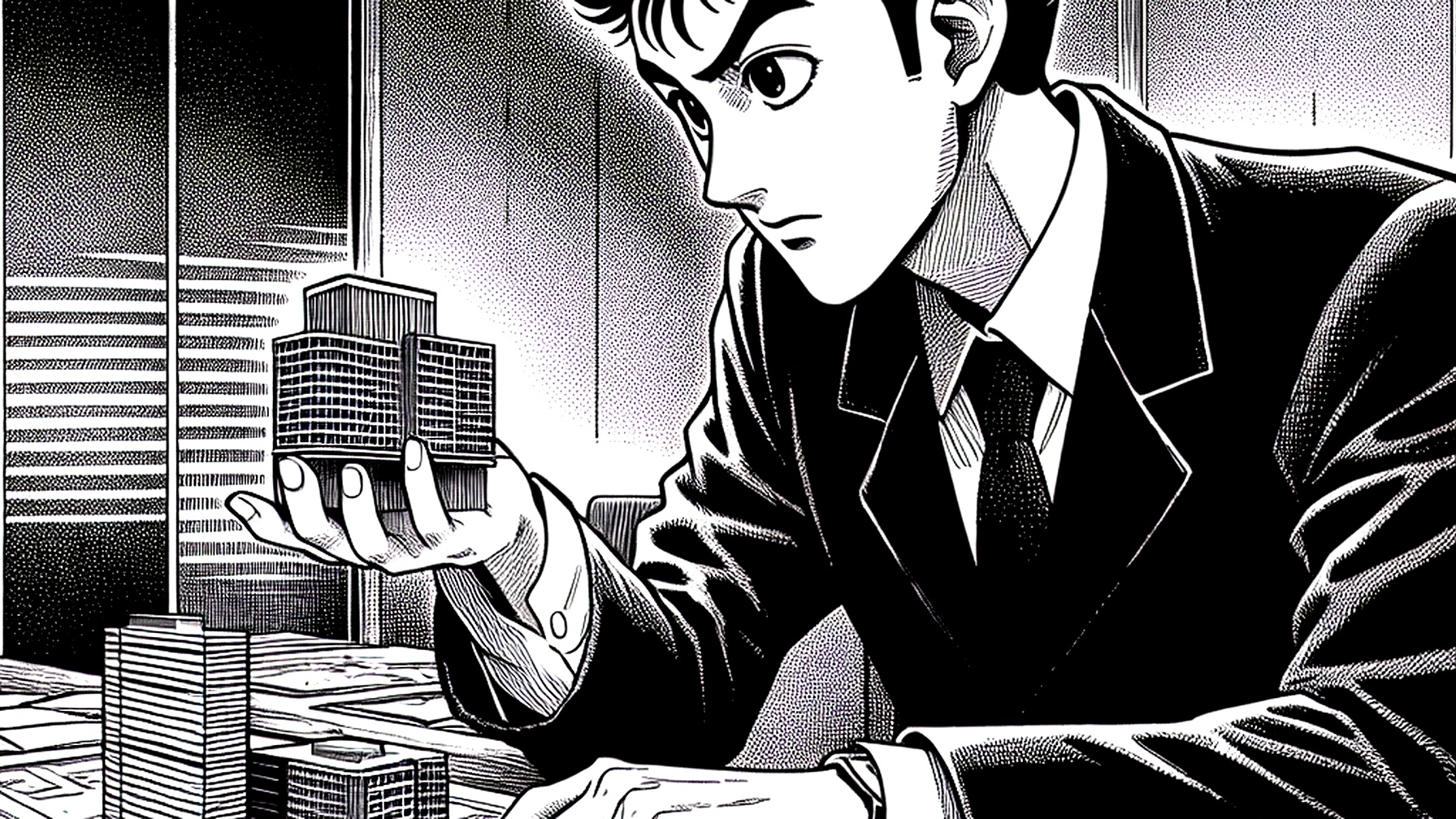
ポイントは、相続税評価額が建物と土地で異なる計算方法になる点です。現金1億円をそのまま遺すより、同額を投じてアパートを建てた方が課税対象は下がります。
建物部分は固定資産税評価額を基準とし、市場価格の60%程度に圧縮されるのが一般的です。土地については賃貸用となることで「貸家建付地」の評価減が適用され、最大で20%前後下がります。加えて小規模宅地等の特例を利用すれば、更地評価から50%〜80%減額を受けられる場合があります。
ただし、減額幅は利用状況や親族の居住要件で変わります。実は、相続開始前に三年以上の賃貸実績があると適用判断がスムーズになるため、早めに計画を立てておく方が有利です。また、2025年度税制改正では賃貸用建物の過大借入れを抑制する趣旨のガイドラインが示され、銀行融資も実質利回りを厳格に見る傾向が強まりました。収支計画の根拠を明確にし、税理士と連携した準備が欠かせません。
最終的に、相続税を抑えるだけでなく、次世代へ毎月の家賃収入という「仕組み」を引き継げる点がアパート経営の強みです。評価額の圧縮と収益継承、この二つを同時に実現できる投資手段は限られています。
収益を決める三つの指標を押さえる
まず押さえておきたいのは、キャッシュフロー、実質利回り、そして空室率です。数字を追うだけでなく、三つの関係性を理解することでリスクの所在が見えます。
キャッシュフローは家賃収入からローン返済と運営費を差し引いた手残り額を指します。仮に月額家賃総額が80万円、返済と経費で60万円なら、手残りは20万円です。ここで注意すべきは修繕積立や空室リスクを含めた長期的な平均値で見ることです。
実質利回りは年間の手残りを総投資額で割って算出します。同じ表面利回りでも、管理費や固定資産税で差が出るため、実質利回り8%を一つの目安にする投資家が増えています。
空室率は立地と物件特性で大きく変わります。全国平均21.2%に対し、駅徒歩5分圏内の築浅アパートは10%以下にとどまる調査結果もあります。つまり、立地とターゲット設定が数字に直結します。逆に空室率が上がればキャッシュフローが崩れ、実質利回りも影響を受けます。三つの指標を同時にモニタリングすることで、収益構造の弱点を早期に把握できます。
2025年度の税制と補助制度をチェック
実は、税制優遇の把握は手残りを増やす近道です。2025年度も、減価償却費を活用して課税所得を圧縮できる仕組みは維持されています。木造アパートは法定耐用年数22年ですが、中古取得なら経過年数に応じて償却期間が短縮され、初期数年の節税効果が高まります。
さらに、住宅金融支援機構の「賃貸住宅融資(2025年度版)」は長期固定金利を提供し、金利1.4%台からの融資事例があります。エネルギー効率を高める改修を行う場合、同機構のグリーンリフォーム融資が適用され、金利優遇▲0.2%が受けられる点も見逃せません。
補助制度では、国土交通省の賃貸住宅性能向上推進事業が継続中です。高断熱化やバリアフリー改修に対して、工事費の三分の一(上限200万円)の補助が2026年3月完了分まで認められます。交付申請には着工前の手続きが必須なので、計画段階で専門家に相談してください。
これらの制度を組み合わせることで、初期費用を抑えつつ物件価値を引き上げられます。結果として空室率の低減と家賃維持に寄与し、キャッシュフローの安定にもつながります。
長期安定運用のための管理と出口戦略
まず、日々の管理品質が将来価値を左右します。入居者対応を外部委託する場合でも、月次報告と修繕計画のチェックはオーナーが主体的に行いましょう。早期対応ができれば、退去抑制と口コミ評価の向上に直結します。
一方で、十年後、二十年後にどう出口を迎えるかも重要です。売却益を狙うなら築十五年程度で修繕履歴を提示できる状態が理想です。相続を見据える場合は、法人化や持株会社を活用し、共有名義のトラブルを未然に防ぎます。
資金繰りの余裕を保つため、毎年のキャッシュフローの三割を修繕積立に充てる運用例が増えています。金融庁の事業性評価ガイドラインでも、長期修繕計画の有無が融資審査項目に明記されました。つまり、計画的な内部留保は融資条件の改善にもつながるのです。
最後に、家族への情報共有を忘れないでください。遺言書や信託契約を通じ、アパート運営に必要な口座や契約書類を整理しておくと、相続時の混乱を大幅に軽減できます。
まとめ
アパート経営は、安定した家賃収入で資産形成を進めながら、相続税評価額を抑えるという二重のメリットを提供します。レバレッジ効果、インフレ耐性、税制優遇の活用が成功のカギですが、空室率とキャッシュフローを常に確認し、長期修繕計画を実行することが不可欠です。まずは信頼できる税理士や管理会社へ相談し、三年後、十年後のビジョンを数値で描くことから始めましょう。今日の一歩が、家族に受け継がれる安定資産への第一歩になります。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅統計 – https://www.mlit.go.jp/statistics/
- 総務省統計局 消費者物価指数 – https://www.stat.go.jp/
- 国税庁 相続税評価通達 – https://www.nta.go.jp/
- 住宅金融支援機構 2025年度商品概要 – https://www.jhf.go.jp/
- 金融庁 事業性評価ガイドライン – https://www.fsa.go.jp/

