アパート経営に興味はあるものの、「本当に儲かるのだろうか」と不安を抱えていませんか。周囲から「やめとけ アパート経営 収益性が低い」と忠告されると、踏み出す気持ちが揺らぐのも当然です。しかし、収益が出ない理由を具体的に知り、改善策を理解すれば、リスクを抑えた運営は可能です。本記事では最新データと実例を交え、失敗の要因から対処法まで丁寧に解説します。読み終える頃には、自分に合った投資判断を下すヒントが得られるでしょう。
投資前に押さえておきたい市場環境
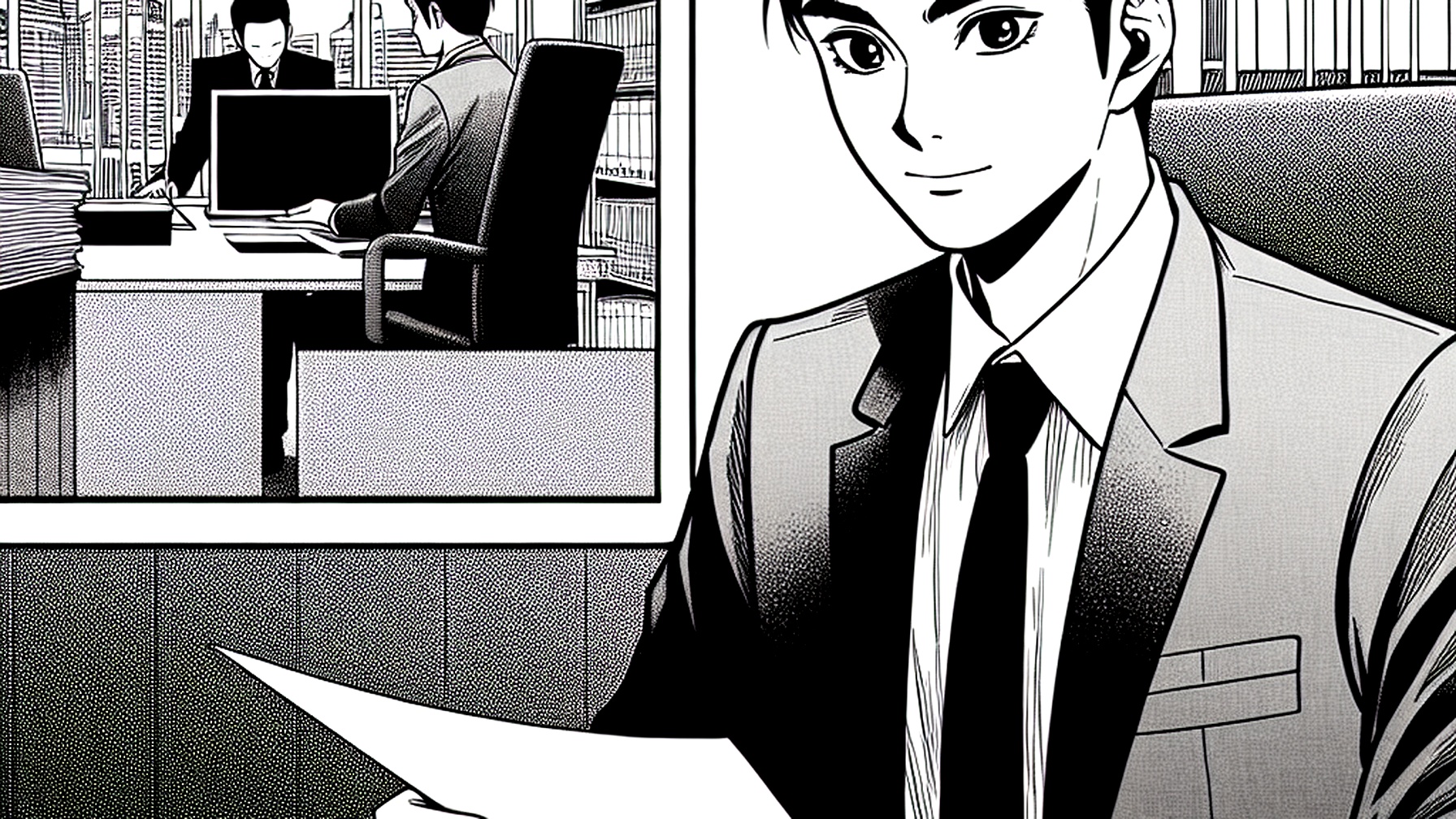
重要なのは、市場全体のトレンドを把握したうえで投資判断を行うことです。2025年7月の国土交通省住宅統計によると、全国のアパート空室率は21.2%で前年比0.3ポイント改善していますが、依然として高水準といえます。
まず人口動向に注目しましょう。総務省の推計では、全国人口は2030年代半ばまで減少が続く見通しです。人口が減る地域では、賃貸需要の先細りが避けられません。また、日本銀行が発表する政策金利は過去最低水準を維持しているものの、長期的には上昇リスクがあります。つまり、今後は「賃料は横ばい〜下落、借入金利は上昇」という逆風も想定しておく必要があります。
一方、都市部の再開発エリアでは賃貸需要が底堅く、家賃の維持が期待できます。地方でも大学や工業団地の近くなど、特定需要が集中するエリアは存在します。市場環境を総合的に分析し、自分の投資エリアがどちらに属するかを見極めることが第一歩です。
家賃下落と空室率の現実を知る
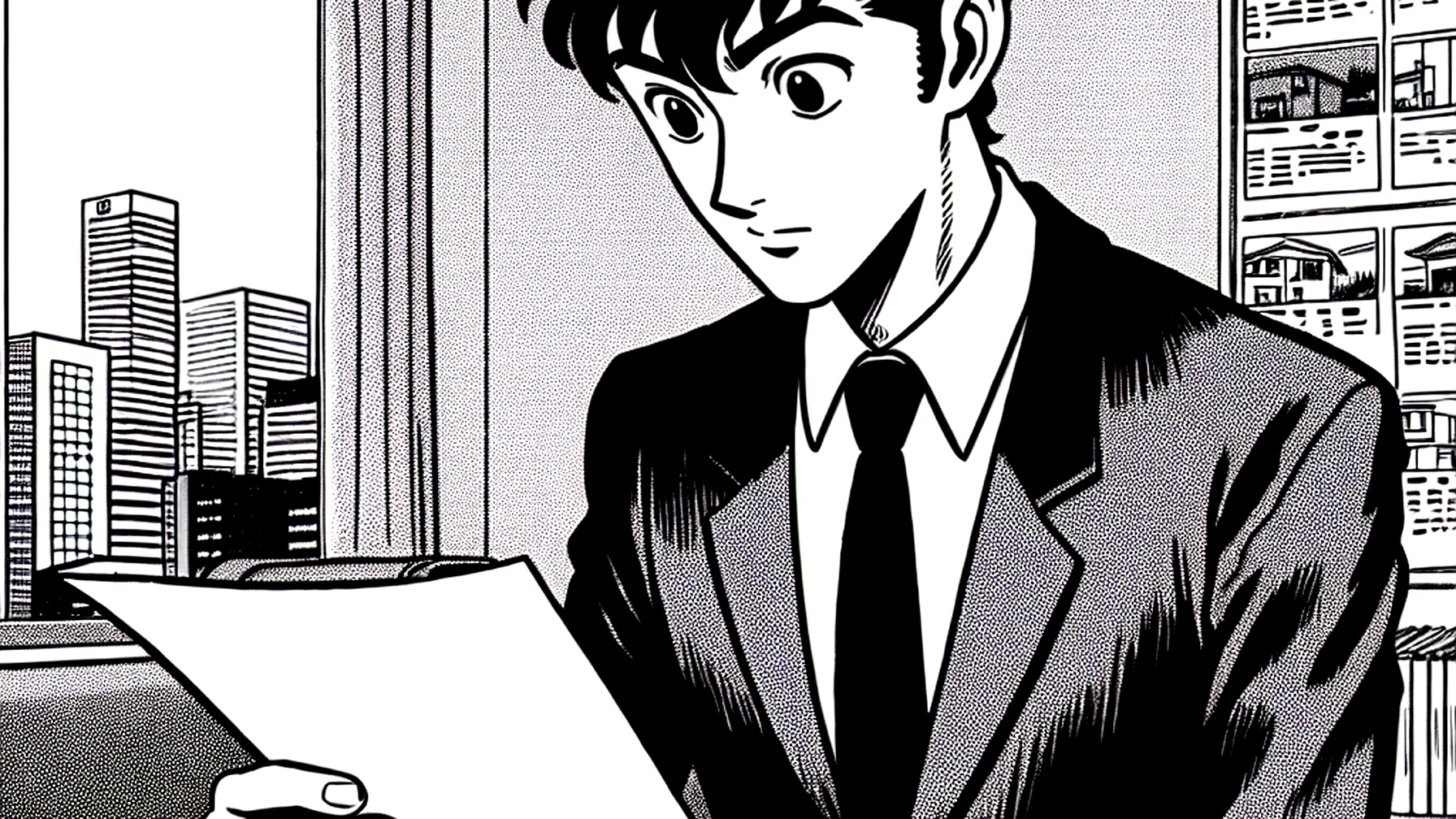
ポイントは、表面利回りだけを見て判断しないことです。家賃下落と空室率が収益に与える影響は想像以上に大きいからです。
たとえば年間家賃360万円、利回り8%の想定で購入した物件があるとします。空室率が10%に上昇し、家賃も2%下落すると、実質利回りは約6.3%まで低下します。しかも空室が長期化すると、広告料やリフォーム費が追加で発生し、さらに利回りを圧迫します。国土交通省のデータが示す21.2%の平均空室率は、地域差をならした数字です。地方の一部では30%を超えるケースも珍しくありません。
家賃の下落幅はエリアによって異なりますが、総務省の消費者物価指数における「家賃」項目は、2020年代後半にかけて横ばいから微減で推移しています。つまり保守的なシミュレーションを行うなら、家賃が年間1〜2%下がっても耐えられる計画を立てるべきです。表面利回りが高い物件ほど家賃下落のダメージも大きくなる点を忘れてはいけません。
初心者が見落としやすいコスト構造
実は、多くの投資家が運営コストを正確に把握できていません。固定資産税や管理委託料だけでなく、修繕費、退去時の原状回復費、仲介手数料など、多岐にわたる費用が年間収支を左右します。
日本建築学会の耐用年数データによれば、外壁や屋根の大規模修繕は15〜20年ごとに必要となり、1戸あたり50万〜100万円程度かかることがあります。また、2025年度の税制では、RC造の減価償却期間は47年、木造は22年と定められています。耐用年数を過ぎた物件は修繕費が増え、金融機関の評価も下がりやすくなるため注意が必要です。
さらに、空室対策として導入するインターネット無料設備や宅配ボックスなどは、初期費用と維持費が発生します。これらを家賃に上乗せできなければ、長期的な収益性は悪化します。コストを細部まで洗い出し、年間キャッシュフロー表に組み込むことが、安定経営のカギとなります。
収益性を高める運営のコツ
まず押さえておきたいのは、家賃以外の収入源を確保する発想です。近年は付帯サービス収入が注目されており、月額駐車場料、トランクルーム、太陽光売電などが代表例です。小さな積み上げでも年間ベースでは大きな差となります。
また、入居者ターゲットを明確に設定し、それに合わせたリフォームを行うことで、家賃と入居期間の両方を伸ばせます。たとえば駅近物件で単身者を狙うなら、Wi-Fi完備と宅配ボックスの導入が効果的です。一方、ファミリー層向けには収納拡充や子育て支援設備が喜ばれます。物件の特徴と需要のズレを埋める努力が、空室率を下げる最短ルートです。
金融面では、借り換えや繰上返済を活用し、金利負担を抑える方法もあります。地方銀行や信用金庫の中には、返済実績が一定期間ある投資家向けに、金利を0.2〜0.5%下げるメニューを用意するケースがあります。金利差は長期で見ると数百万円規模の効果を生むため、定期的な見直しを怠らないようにしましょう。
それでも挑戦する人へのリスク管理術
ポイントは、最悪のシナリオを想定したうえで資金と時間の余裕を確保することです。キャッシュフローが赤字になった際に、自己資金で半年以上のローン返済を賄える準備金を持つと精神的な負担が大幅に軽減されます。
保険活用も効果的です。2025年度の火災保険は、保険料が築年数と構造によって細分化され、築20年超の木造は値上がり傾向です。それでも、家賃の2〜3%で水災や設備故障までカバーできるプランを選べば、突発的な支出を抑えられます。
最後に、出口戦略を意識しましょう。売却時の価格は立地と築年数で大きく変動します。都市部であれば築20年超でも一定の需要がありますが、地方の高築年物件は買い手が付きにくくなります。将来の売却価格をシビアに見積もり、運営期間中のキャッシュフローと合わせて総合的に採算を判断する姿勢が求められます。
まとめ
本記事では、市場環境、家賃下落、コスト構造、運営の工夫、リスク管理の五つの観点から、アパート経営の収益性を検証しました。やめとけと言われる背景には、人口減少と高空室率、そして想定外のコストが潜んでいます。一方で、需要のある立地を選び、家賃以外の収入源を育て、金利と修繕を適切にコントロールすれば、堅実なキャッシュフローを生み出せる余地は残っています。重要なのは、楽観的な数字ではなく、厳しい前提でシミュレーションを行うことです。もし挑戦するなら、十分な自己資金と情報を備え、長期的な視点で計画を立てることを強くおすすめします。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 人口推計 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 政策金利統計 – https://www.boj.or.jp
- 国税庁 法人税基本通達 – https://www.nta.go.jp
- 一般社団法人 東日本不動産流通機構 マーケットサーベイ – https://www.reins.or.jp

