不動産投資を始めたいけれど、「北海道 アパート経営 立地選定」で何を基準に選べばいいか分からない──そんな悩みを抱える方は少なくありません。気候や人口密度、交通網など本州とは異なる条件が多く、机上の空室率データだけでは判断が難しいのが実情です。本記事では、2025年9月時点で入手できる最新データをもとに、初心者でも理解しやすい形で北海道での立地選定の考え方を整理します。読めば「どの街が自分の戦略に合うか」を具体的にイメージでき、物件探しの第一歩を踏み出せるはずです。
地域特性から見る北海道の賃貸需要
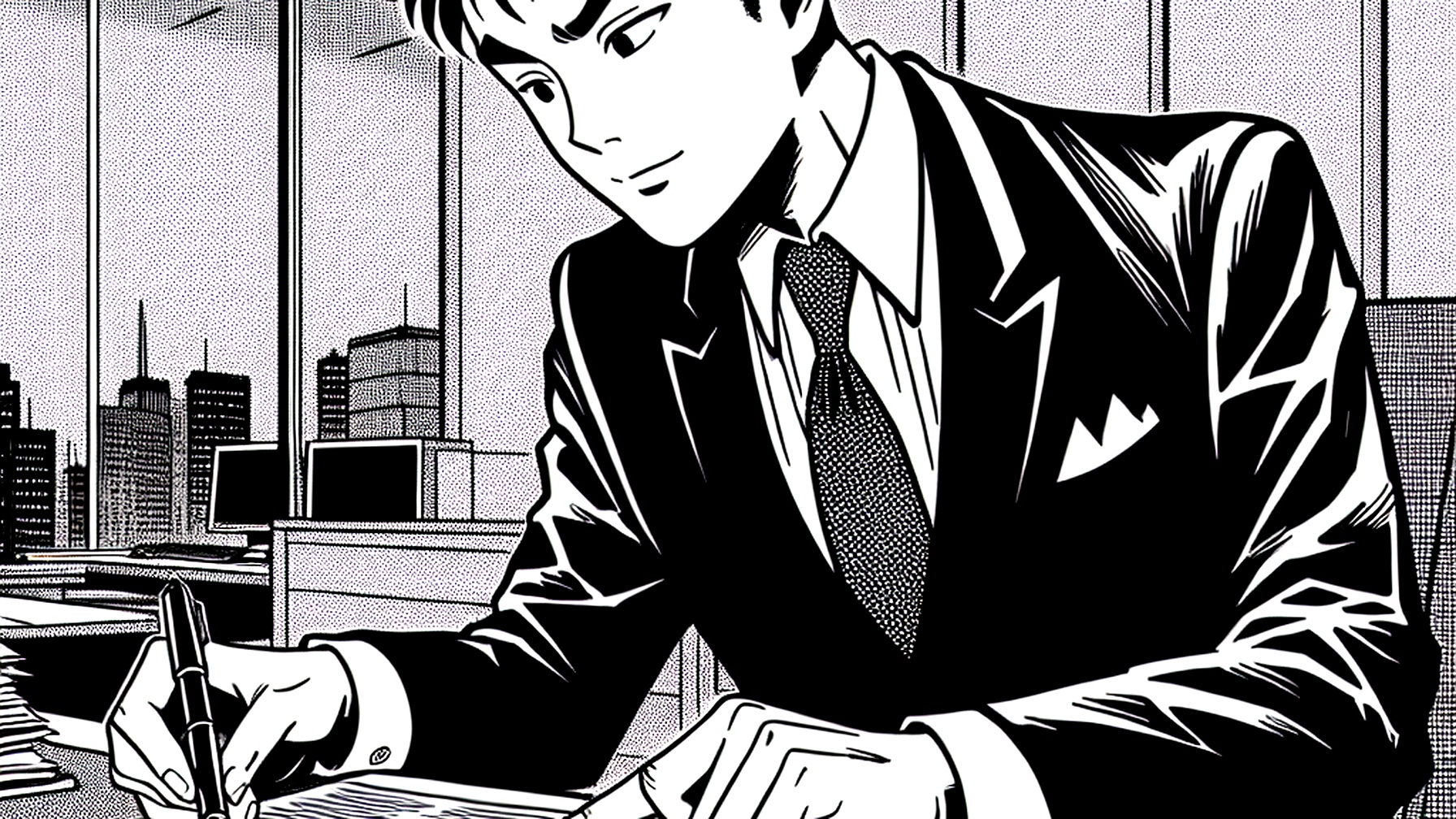
まず押さえておきたいのは、北海道の人口集中が札幌一極に近い構造だという点です。総務省の住民基本台帳によると、2025年1月時点で道内人口の37%が札幌市に住んでいます。一方、旭川市・函館市・帯広市・釧路市を合わせても17%にとどまり、地方圏では人口減少が加速しています。つまり、賃貸需要を安定的に確保したい場合、札幌市かその通勤圏を軸に検討するのがセオリーです。
しかし、地方都市でもチャンスは残っています。たとえば、苫小牧市は新千歳空港へのアクセスが良く、物流関連企業の進出が続いているため、働き盛りの単身世帯が増加傾向にあります。国土交通省住宅統計の2025年7月データでは、全国平均の空室率が21.2%なのに対し、苫小牧市中心部は18.4%にとどまっています。地方都市でも産業集積がある地域を狙えば、空室リスクを適度に抑えられるわけです。
重要なのは、「市区町村単位」で判断を止めず、町丁レベルで実際の入居者動向を確認することです。自治体の統計資料や地元不動産会社の成約データを照合し、入居率90%を超えるエリアを選定できれば、家賃設定で強気の戦略を取りやすくなります。
人口動態と交通インフラを読む
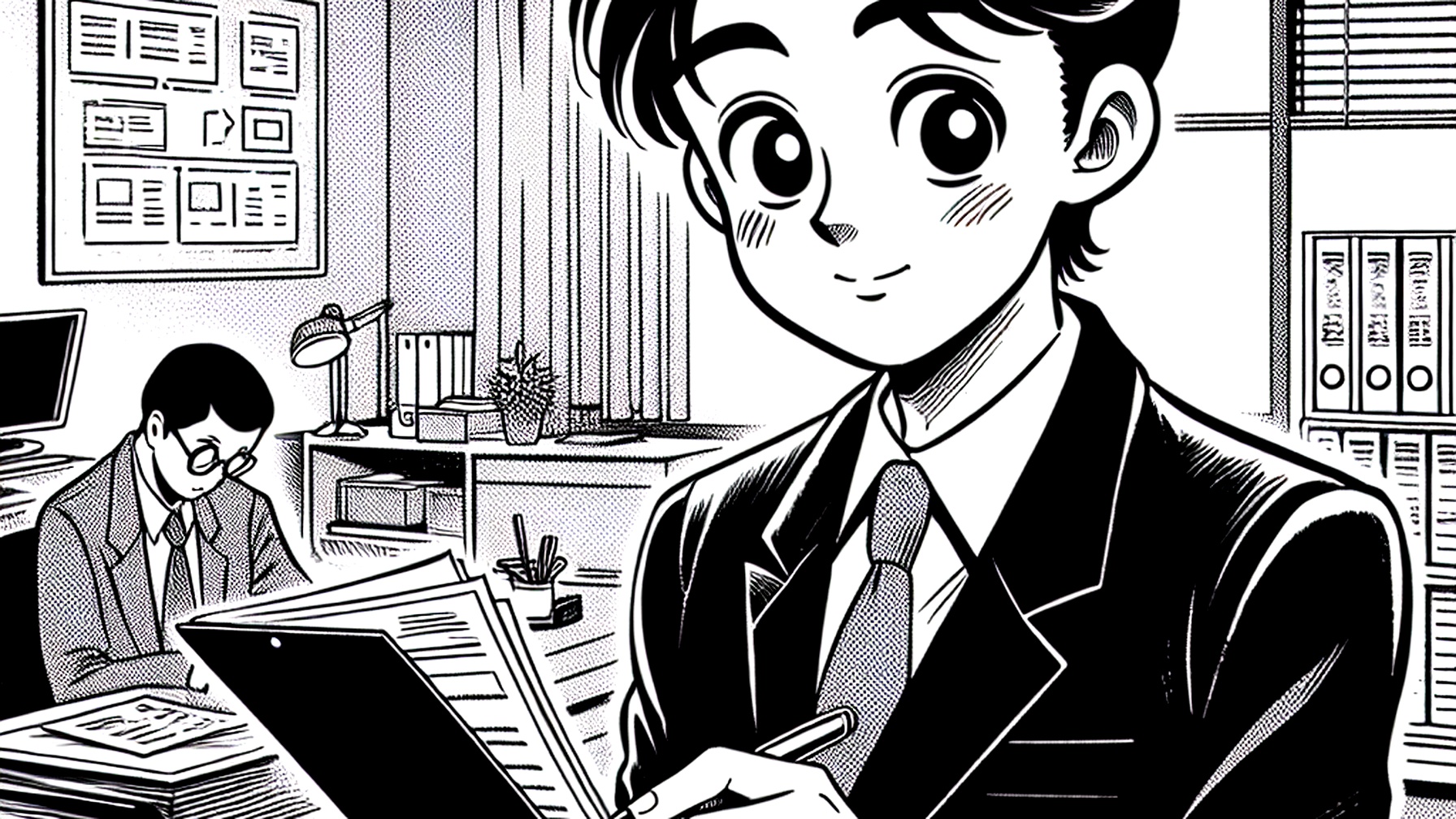
ポイントは、単純な人口増減だけでなく「通勤・通学がしやすいか」を合わせて評価することです。北海道の鉄道路線は札幌圏以外で本数が限られるため、バス路線や主要幹線道路が生活動線を左右します。たとえば、JR函館本線の駅徒歩10分よりも、地下鉄東西線の駅徒歩8分のほうが年間家賃収入が安定しやすい事例が多く見られます。
実は、2000年代に拡大した郊外団地の空洞化が、最近は都市近接のバス便地域に波及しています。北海道開発局の2024年度調査では、札幌市清田区の一部で高齢化率が45%を超え、空き家率が上昇しました。こうした地域に新築アパートを建てても、若年層の入居は期待しにくいのが現状です。
一方で、地下鉄駅から離れていても、札幌駅まで直行バスが10分間隔で運行されるエリアでは入居率が高止まりしています。交通インフラを立体的に把握し、路線の維持計画や新設計画までチェックすることで、長期的な収益安定が見込める立地を見極められます。
大学・工業団地周辺のポテンシャル
基本的に、学生や若手社員が集中する地域は単身向け需要が底堅いです。北海道大学の周辺では築20年超のワンルームでも表面利回り6%台を維持できています。大学数が少ない旭川市でも、旭川医科大学の近隣は病院勤務の研修医が多く、築年の古い物件でも入居期間が長い傾向です。
工業団地周辺は、期間従業員や独身寮の代替として賃貸ニーズが生まれます。たとえば、苫小牧東部工業地域ではEV関連企業の新設が続き、企業が法人契約で部屋をまとめて借り上げるケースが増加しています。法人契約は退去リスクが低く、同じ家賃でも経営の安定度が高い点が魅力です。
重要なのは、大学や工場だけでなく、周辺の生活利便施設まで合わせて確認することです。コンビニ・ドラッグストア・24時間ジムなどが徒歩圏にあれば、遠方出身者でも住み替えをためらいにくくなり、結果として平均入居期間が延びます。そのため、物件購入前にGoogleマップで徒歩5分圏の施設を見渡し、将来的な開発計画を役所HPで確認しておくと安心です。
冬のランニングコストを考慮した立地判断
北海道のアパート経営では、暖房費や除雪費がキャッシュフローに大きく影響します。とくに降雪量が多い日本海側では、除雪委託費が年間一戸あたり3〜5万円かかることも珍しくありません。札幌市手稲区では、2024年度の平均除雪費が1世帯3.8万円でしたが、旭川市郊外では5.2万円に達しています。
また、暖房方式によっては入居率にも差が出ます。最近は都市ガスのエコジョーズや灯油FF式より、電気ヒートポンプ式の需要が高まっています。北海道電力の「ゼロカーボン電化住宅応援プラン」は2025年度も継続予定で、深夜電力が割安になるため、電気暖房が割高という従来のイメージが薄れつつあります。
立地選定では、ガス導管の普及状況と電力契約の選択肢を確認し、光熱費の総額がどの程度かを試算します。入居者が月1万円節約できるエリアなら、家賃を1000円高めに設定しても競争力を保てることが多いからです。つまり、冬季コストを踏まえた立地判断は、賃料戦略と直結する重要な視点になります。
データで比較する札幌圏と地方都市
札幌市は人口が増え続けているものの、地価上昇で利回りが圧縮されています。日本不動産研究所の2025年4月レポートによれば、札幌市中央区の新築一棟アパート平均表面利回りは5.1%です。対して函館市では同規模物件で7.8%、帯広市では8.2%というデータが示されています。
しかし、利回りの数字だけで判断するのは危険です。2023年から2025年にかけて、函館市では年間退去率が23%に達しました。空室期間が平均3か月を超えるため、実質利回りが札幌市中央区と逆転するケースも出ています。空室損失を加味した「実効利回り」で比較することが欠かせません。
また、金融機関の融資姿勢も立地によって変わります。地方都市では評価額が低めになりやすく、自己資金3割以上を求められるケースが多いのが実態です。札幌圏であれば自己資金2割でも審査が通りやすく、レバレッジを効かせやすいというメリットがあります。資金計画とリスク許容度を考え合わせると、札幌圏の安定か、地方都市の高利回りか、投資家ごとの戦略が分かれてくるでしょう。
まとめ
本文で見てきたように、北海道でアパート経営を成功させる鍵は「地域特性」「交通インフラ」「学生・企業需要」「冬季コスト」「実効利回り」の五つをバランス良く評価することに尽きます。結論として、札幌圏を中心に通勤利便性と光熱費の優位性を確保しつつ、苫小牧など産業集積都市の成長ポテンシャルを押さえる戦略が、初心者には取り組みやすいと言えるでしょう。まずは候補エリアの空室率と除雪費を具体的に確認し、融資条件を複数行で比較するステップから始めてみてください。堅実な調査とシミュレーションこそが、北海道特有の気候リスクを乗り越え、長期安定収益を生む第一歩になります。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅統計調査 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 2025年1月 – https://www.soumu.go.jp/
- 日本不動産研究所 不動産投資家調査 2025年4月 – https://www.reinet.or.jp/
- 北海道開発局 都市圏交通調査 2024年度版 – https://www.hkd.mlit.go.jp/
- 北海道電力 ゼロカーボン電化住宅応援プラン 2025年度概要 – https://www.hepco.co.jp/

