空室や資金繰りの不安から「本当に物件を買って大丈夫だろうか」と悩む初心者の声をよく耳にします。筆者も15年前の初投資では同じ疑問を抱えました。しかし正しい情報と手順を押さえれば、収益物件は給与以外の安定収入を生み出す強力な資産になります。本記事では、物件選びの視点と融資条件を有利に進めるコツを体系的に整理します。最後まで読めば、明日から行動に移せる具体策が見えてくるはずです。
収益物件を成功に導く発想転換
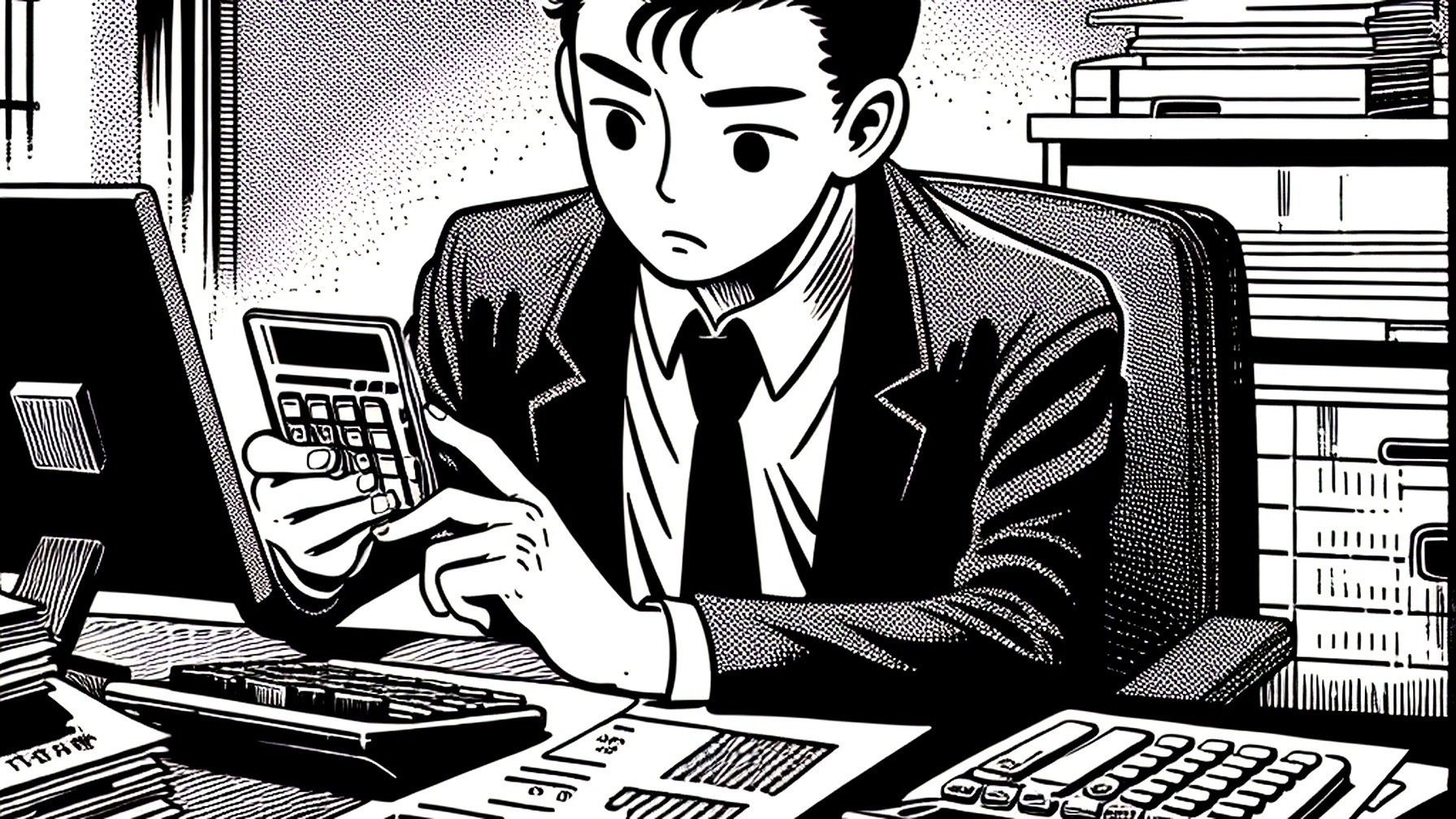
まず押さえておきたいのは、収益物件を「家賃という事業収入を生む小さな会社」と捉える発想です。この視点に立つと、立地や間取りだけでなく、需要予測や競合物件の水準まで自然とチェックする習慣が身につきます。
国土交通省の不動産価格指数(2025年4月速報)によると、東京23区の中古マンション価格は前年比3.2%上昇しました。一方で総務省の住宅・土地統計調査が示す都心部平均空室率は4.9%と、全国平均の13.3%を大きく下回っています。つまり都心は取得価格が高くても稼働率が高く、安定収入を見込みやすいのです。
しかし郊外にチャンスがないわけではありません。人口10万人以下の都市でも、駅徒歩5分以内や大学近接エリアを選べば空室率を7%台に抑えられると筆者の管理データは示します。重要なのは平均値に惑わされず、需要の源泉を具体的に特定することです。
まとめると、収益物件は「高利回り=正解」ではなく、「継続して埋まる仕組み」を持つかどうかで評価すべきだと言えます。この発想転換が、後の融資交渉でも説得力を生む土台になります。
物件選びで押さえるべき指標

実は初心者が最もつまずきやすいのが指標の読み違えです。ポイントは、表面利回り・実質利回り・キャッシュフローの三つを順番に確認することにあります。
表面利回りは「年間家賃÷購入価格」で求められ、広告でよく見かけます。ただし固定資産税や管理費、修繕費を考慮しないため、判断材料としては粗い数字にすぎません。そこで購入前に「管理費等を10%、修繕積立を5%、空室損3%」といった業界平均を差し引き、実質利回りを算出します。
さらに深掘りするにはキャッシュフロー計算が欠かせません。年間家賃から諸費用とローン返済を引くと手残り額が見えます。たとえば家賃480万円、費用90万円、ローン返済280万円なら年間110万円が自由資金になります。返済比率が家賃の60%を超えると金利上昇リスクに弱くなるため、目安として覚えておくとよいでしょう。
なお、地方都市の木造アパートで表面利回り12%と聞くと魅力的に映りますが、空室率が20%を超える市場では実質利回りが6%台まで落ち込むケースも珍しくありません。数字の裏側にある前提を必ず確認し、複数の物件を同一基準で比較する姿勢が大切です。
融資条件を有利にする信用力づくり
重要なのは、金融機関が見るのは「物件」より先に「投資家の信用力」だという点です。信用力は自己資金、年収、勤務先の安定性、既存借入の四要素で評価されます。
自己資金は物件価格の20〜25%を用意すると金融機関の信用が一気に高まります。2025年6月の日本政策金融公庫データでも、自己資金比率が20%未満と20%以上では平均金利が0.45ポイント開く結果が出ています。また、諸費用を自己資金で賄う形にすると評価がさらに上がり、フルローンよりも審査スピードが速い傾向があります。
次に年収ですが、サラリーマンの場合は年収500万円を境に融資枠が大きく変わるとされます。ただし副業収入や配偶者の収入を合算できる金融機関もあるため、確定申告書や源泉徴収票を整えて臨むと交渉がスムーズです。既存借入は住宅ローンだけでなく、車のローンやカードリボも対象に含まれるので、余計な債務は早めに整理しておきます。
最終的に融資条件は「金利」「期間」「自己資金割合」の三位一体で決まります。期間を長くすると月々の返済は軽くなりますが、総支払利息が増える点に注意が必要です。シミュレーションでは、金利2.0%、期間35年より金利1.3%、期間30年の方が総支払額は約550万円少なくなる結果が出るケースもあります。数字に基づく交渉材料を準備すると、担当者の姿勢が変わることを実感できるでしょう。
新築と中古、どちらを選ぶか
まず多くの人が悩むのが「新築か中古か」という選択です。ポイントは、減価償却と修繕リスクを天秤にかけ、自身の投資期間と照らすことにあります。
新築は初期の修繕がほぼ不要で、長期融資を組みやすいメリットがあります。ただし建築費高騰を背景に表面利回りは平均5〜6%と低めです。国土交通省の「建築着工統計」(2025年上期)によれば、賃貸マンションの建築単価は2019年比で15%上昇しており、利回り低下の一因となっています。
中古は取得価格が抑えられ、表面利回り8〜10%を狙いやすい反面、築20年以上になると大規模修繕のタイミングが早まります。また法定耐用年数の残りによっては融資期間が短くなるため、返済負担が重くなるケースもあります。しかし木造アパートなら残存耐用年数を超えても最長22年、RC造なら47年まで融資する地方銀行も存在するため、金融機関選び次第でデメリットを緩和できます。
つまり、投資期間が10年以内なら中古で減価償却を加速しつつ売却益を狙い、20年以上の長期保有なら新築で安定運用を図るといった使い分けが現実的です。自身のキャッシュフロー計画とリスク許容度に即して選択しましょう。
2025年度の制度と税制を味方にする
最後に、2025年度に実際に利用できる制度を整理します。ここを押さえることで手取りを最大化できます。
最も汎用性が高いのは「住宅ローン減税」の賃貸併用住宅枠です。2025年度は新築・取得から13年間、最大控除額455万円が維持されます。居住部分が過半であれば適用されるため、自己居住+賃貸1〜2室の物件を検討する際は有力な選択肢です。
法人化を視野に入れる方は、「中小企業経営強化税制(2027年3月期限)」の対象に賃貸住宅の設備投資が含まれる点に注目してください。高効率給湯器や太陽光発電を導入すると、即時償却または10%税額控除のどちらかを選択できます。CO₂排出抑制が評価されるため、銀行評価でもプラス材料となる傾向があります。
加えて、固定資産税の新築軽減措置が2025年度も継続します。賃貸住宅は3年間、税額が1/2になるため、築浅物件を戦略的に取得する場合はシミュレーションに必ず織り込んでおきましょう。制度には適用要件や申請期限があるため、国税庁や自治体の公式サイトで最新情報を確認し、必要書類を早めに整えることが成功の鍵です。
まとめ
ここまで、収益物件の発想転換から指標の読み解き方、融資条件を勝ち取るコツ、物件タイプの選択、そして2025年度の制度活用まで一気に整理しました。結論として、最適な物件は「高利回り」でも「最新設備」でもなく、自身の資金計画とリスク許容度に合致し、融資条件を有利に組めるものです。行動を起こす第一歩として、今日中に三つの物件を同一基準で比較し、金融機関に事前相談の予約を入れてみてください。動き出すことでしか得られない経験と数字が、次の判断を確実に後押ししてくれます。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数(2025年4月速報) – https://www.mlit.go.jp/
- 国土交通省 建築着工統計 2025年上期 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 住宅・土地統計調査 2024年 – https://www.stat.go.jp/
- 日本政策金融公庫 融資統計 2025年6月 – https://www.jfc.go.jp/
- 国税庁 中小企業経営強化税制 令和7年度版 – https://www.nta.go.jp/

