家賃収入で資産を増やしたいと考えていても、「築浅は価格が高く利回りが低いのでは?」と二の足を踏む方は多いものです。しかし実際には、適切な戦略を取れば「収益物件 築浅 高利回り」という一見相反する条件を同時に満たす投資も十分に可能です。本記事では、2025年9月時点の市場データと15年以上の実践経験をもとに、築浅物件で高利回りを実現する具体的な方法と注意点を解説します。最後まで読めば、物件選定から資金計画までの全体像がつかめ、初めての投資にも自信を持って踏み出せるはずです。
高利回りを築浅物件で得る仕組み
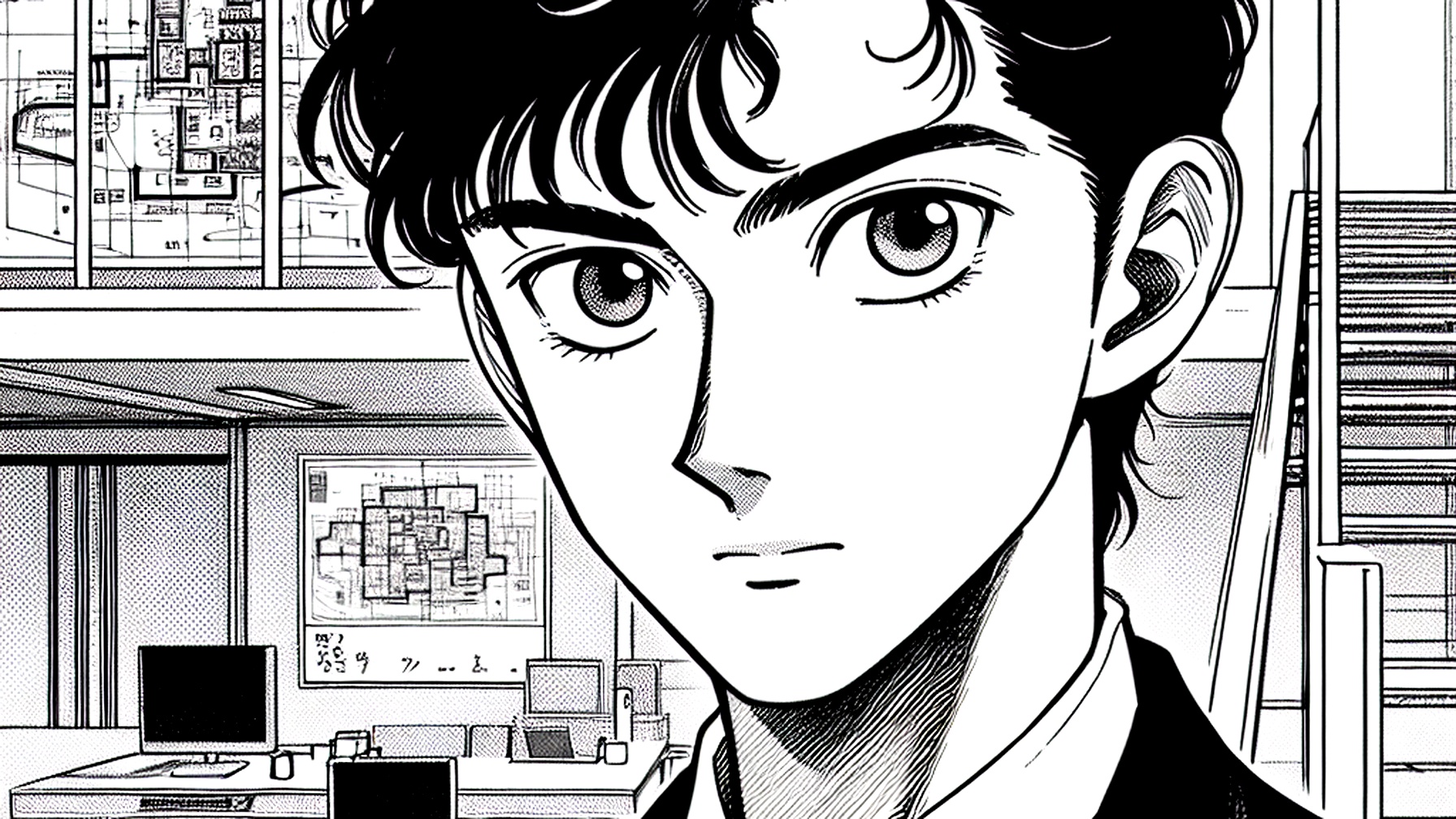
重要なのは、利回りを「家賃と購入価格のバランス」で捉え直すことです。築浅物件は確かに価格が高めですが、修繕費が少なく空室リスクも低いため、実質利回りで比較すると十分に競争力があります。日本不動産研究所のデータによると、東京23区の築5年以内アパートの平均表面利回りは5.1%で、築20年超の4.6%を上回っています。
まず家賃設定の柔軟性が大きな差を生みます。最新設備や高い省エネ性能を備えた築浅物件は、入居者から選ばれやすく、相場よりも5〜10%高い家賃を維持しやすいからです。また、減価償却期間が長いため、税引き後キャッシュフローも安定します。
さらに、初期数年間は大規模修繕が不要なケースが多い点も見逃せません。修繕積立をゆとりある金額に抑えられるため、手残りを成長投資に回せます。つまり、表面利回りだけでなく維持費まで含めた実質利回りで判断すれば、築浅でも高利回りは十分に狙えるのです。
立地選定が利回りに与える影響
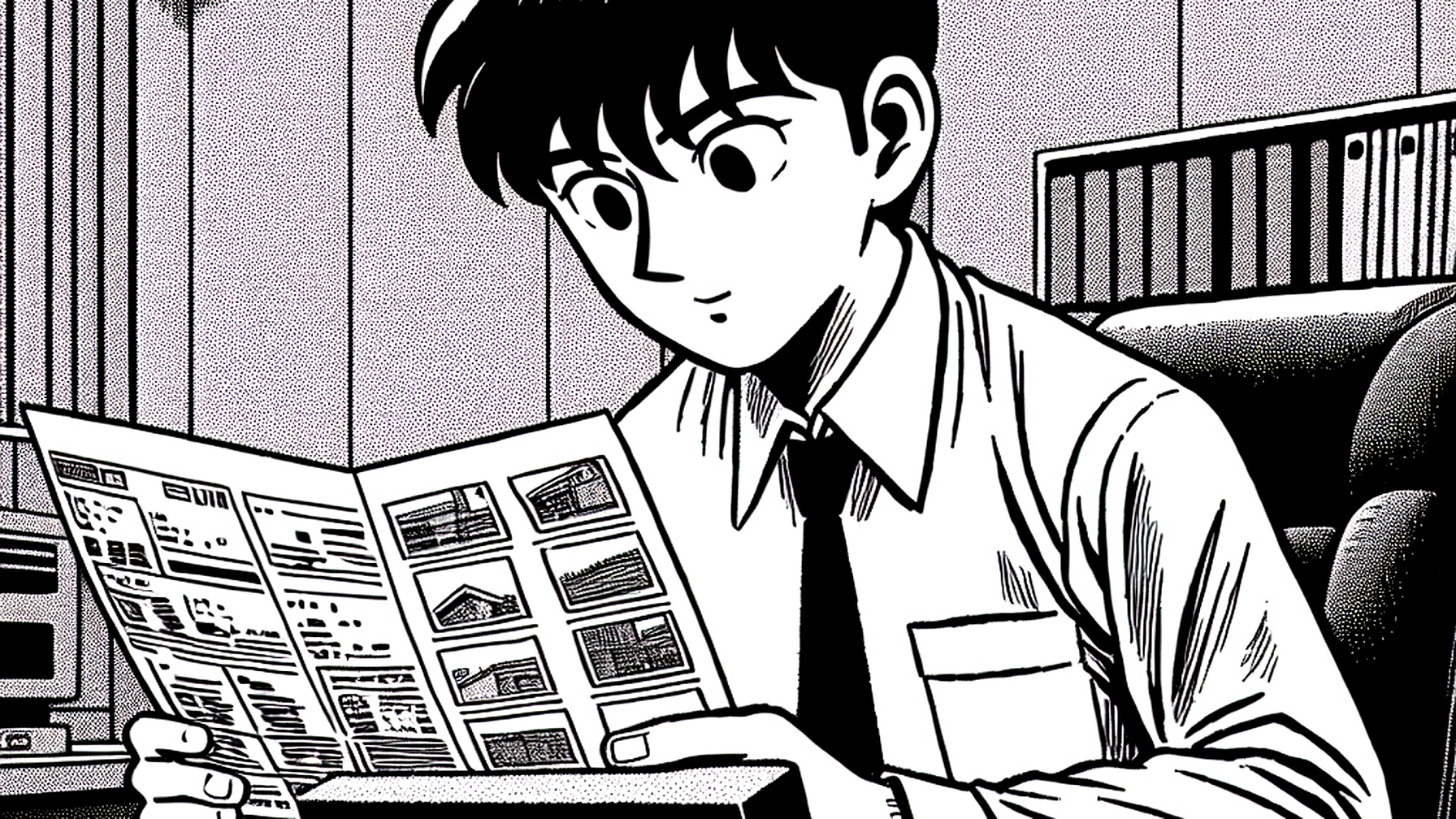
まず押さえておきたいのは、築浅でも立地が悪ければ高利回りは長続きしないという点です。立地評価では「駅距離」と「生活利便性」を掛け合わせて考えます。都心の駅近物件は価格が高騰していますが、徒歩10分圏であれば築浅プレミアムを保ちやすく、長期的な空室率は5%未満に収まる事例が多いです。
一方で、郊外でも人口が増加傾向にあるエリアなら勝算があります。例えば、再開発が進む多摩地域のターミナル駅周辺では、新築から築10年以内のワンルームでも家賃下落率が年1%以下にとどまっています。地方都市の場合は、大学や病院など「雇用の受け皿」が徒歩圏にあるかを重視するとよいでしょう。
立地を数値で確認するには、市区町村が公表する転入超過数や総務省の将来人口推計が役立ちます。空室リスクを3%刻みでシミュレーションし、最も厳しい条件でもキャッシュフローが赤字にならない場所を選ぶことが、高利回りを守る鍵となります。
築浅アパートと築浅マンションの比較
ポイントは、物件タイプによって収益構造が異なることを理解することです。築浅アパートは建物価格の比率が高いため、減価償却費を多く計上でき、税引き後の手残りが厚くなります。土地が狭い分、購入価格は抑えやすく、利回りを高めやすいのが特徴です。
一方、築浅マンションは管理会社が共用部を一括で管理してくれるため、オーナーの手間が少なく、遠隔投資とも相性が良いです。ただし、管理費・修繕積立金が毎月発生するため、表面利回りはアパートより低めに見えます。ここで重要なのは、これらの費用を「想定外コスト」として追加計算する必要がない点です。
実は、東京23区の築浅ワンルームマンションは表面利回りこそ4.2%ですが、入居期間が平均4年以上と長いため、再募集費用を年0.5ヶ月分に抑えられます。結果として、実質利回りは5%程度に上昇するケースも珍しくありません。投資目的が節税重視ならアパート、時間と手間の節約を優先するならマンションと、ライフスタイルに合わせて選択すると失敗を防げます。
資金計画とリスク管理の基本
実は、融資条件を最適化するだけで利回りは1%前後改善します。2025年現在、多くの地方銀行が築10年以内の木造アパートに対し、最長35年・金利1.3%前後の融資商品を提供しています。頭金を物件価格の20%程度入れると、返済比率が収入の50%以下となり、金利0.2%の優遇を受けられる場合もあります。
リスク管理では、空室率10%、金利上昇2%、修繕費年間家賃収入の10%という「悲観シナリオ」でシミュレーションを行います。この条件でもキャッシュフローがプラスなら、実際の運営で赤字に転落する可能性は極めて低くなります。また、入居付けに強みを持つ管理会社と早めに契約しておくことで、平均空室期間を30日以内に短縮できます。
保険の活用も忘れてはいけません。家賃保証保険は賃料の3%前後のコストで、滞納リスクを大幅に削減します。火災・地震保険については、木造アパートの場合5年一括で契約すると割引率が10%を超える場合があり、長期的な経費削減につながります。
2025年度の支援制度を上手に使う
まず、2025年度の住宅省エネ改修補助金を活用すると、築浅物件の価値をさらに高められます。対象は築5年超の物件ですが、断熱性能を国交省の定める水準へ引き上げると上限120万円の補助が受けられます。これを機に賃料を月額3000円上げても、投資家負担は実質ゼロに近づき、利回り向上に直結します。
また、地方創生テレワーク促進事業では、駅近物件の共用部にコワーキングスペースを設ける際、設備費の2/3(上限200万円)が助成されます。リモートワーカーに訴求力が高まり、競合物件との差別化にも有効です。制度は2025年12月申請分までなので、計画から工事発注までのスケジュール管理が不可欠です。
さらに、エネルギー価格高騰対策として経済産業省が継続する「省エネ家電導入補助」も見逃せません。共用部LED照明の更新や高効率給湯器の設置に対し、費用の1/3補助が受けられます。初期投資を抑えつつランニングコストを削減できるため、実質利回りが0.3〜0.5%向上するケースもあります。
まとめ
築浅物件で高利回りを実現するには、表面利回りではなく修繕費・空室率・税効果を含めた実質利回りで評価する姿勢が欠かせません。立地分析と物件タイプの特性を理解し、融資条件と補助金を組み合わせれば、築浅でも年間手残り6〜7%を狙う戦略は十分に成立します。今できる行動として、まずは候補エリアの人口動態と家賃相場を調査し、金融機関の融資条件を比較してみてください。準備を整えた投資家だけが、安定収益という果実を継続的に収穫できるのです。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省 住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 総務省 統計局 – https://www.stat.go.jp
- 経済産業省 資源エネルギー庁 – https://www.enecho.meti.go.jp
- 地方創生テレワーク交付金事務局 – https://www.chisou.go.jp/telework

