不動産投資に興味はあるものの、大きな借入や物件管理に不安を抱えている人は多いはずです。そんな悩みを解決する選択肢が、少額から参入できる上場不動産投資信託「REIT(リート)」です。本記事では、2025年9月時点の最新情報をもとに、REITの基本から始め方、銘柄選びのコツ、税制優遇まで丁寧に解説します。読み終えたとき、あなたは具体的な一歩を踏み出すイメージを描けるでしょう。
REITの仕組みと魅力を押さえる

まず押さえておきたいのは、REITが複数の投資家から資金を集め、商業ビルやマンションなど実物不動産を保有・運用し、その賃料や売却益を分配する仕組みだという点です。東京証券取引所のデータによると、2025年6月時点で上場REITの時価総額は約17兆円に達し、個人投資家の保有比率も年々高まっています。
投資家にとっての最大の魅力は、少額で複数物件に分散投資できることです。仮に一口10万円でオフィス、物流、住宅をまとめて保有するイメージなので、空室リスクが平準化されます。また、日本のREITは税制上の優遇を受け、利益の90%以上を配当すれば法人税が実質的に課されません。そのため、J-REIT平均分配利回りは3.5〜4.5%と、上場株式の平均配当利回りを上回る水準で推移しています。
一方で価格変動リスクは株式と同様に存在します。金利上昇局面では資金調達コストが増え、分配金が低下する可能性もあります。つまり、メリットだけでなく、不動産市場や金利動向をチェックする姿勢が求められるのです。
REIT投資を始める基本ステップ
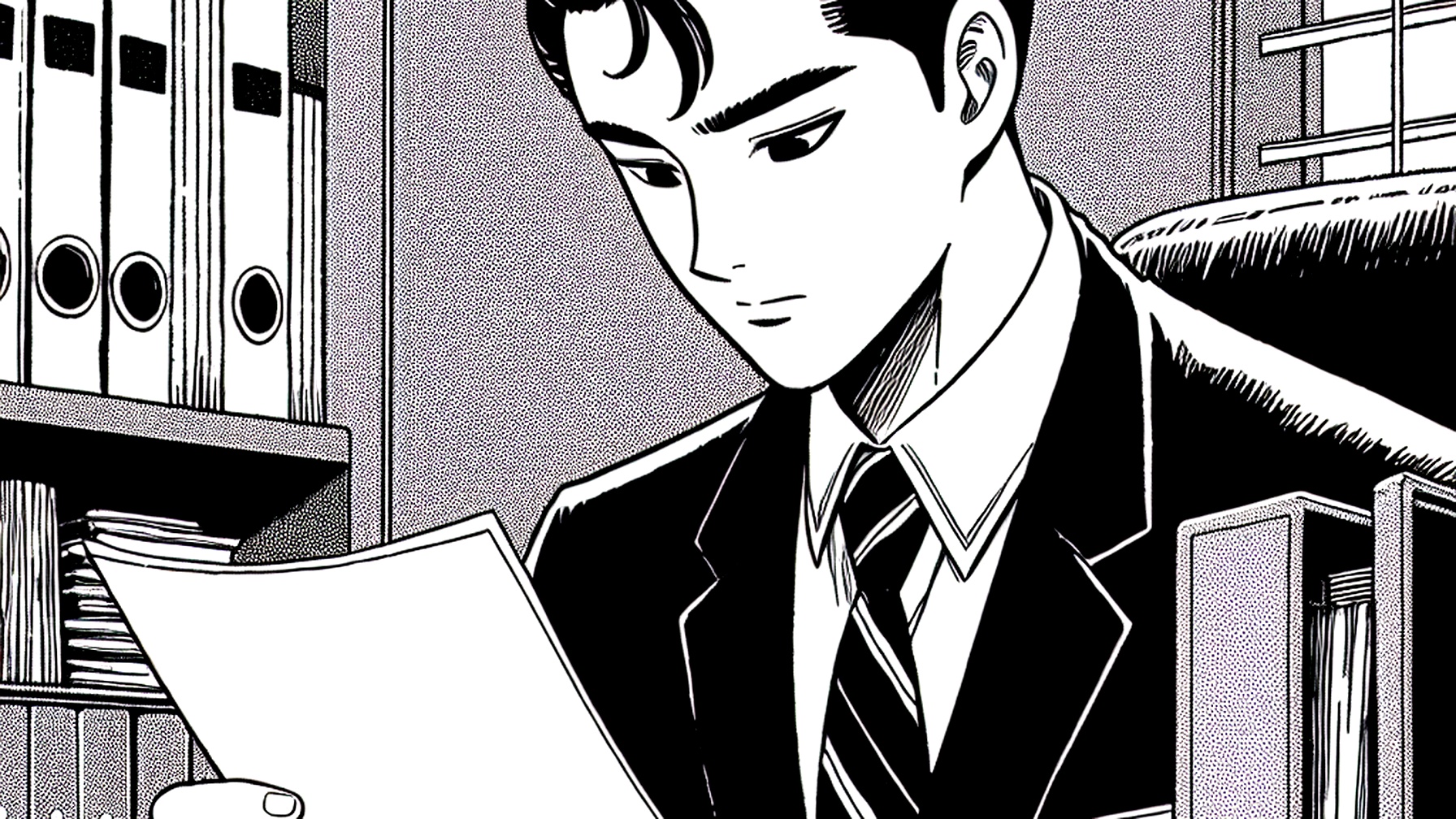
ポイントは、証券口座の開設、投資方針の策定、銘柄選定の三段階を踏むことです。まず、ネット証券や銀行窓口で一般口座またはNISA口座を開設します。2025年度の「新しいNISA」は年間投資枠360万円まで配当金が非課税のため、分配金利回りの高いREITと相性が良いです。
次に、投資目的と期間を明確にします。たとえば月々の分配金で生活費の一部を補いたいのか、長期で資産形成を目指すのかによって、利回り重視か成長性重視かが変わります。この段階で目安とする利回りや購入上限額を決めておくと、相場の上下に惑わされにくくなります。
最後に銘柄を選定しますが、上場REITは70銘柄程度と株式よりも母数が少ないぶん比較がしやすいです。証券会社のスクリーナー機能を活用し、利回り、物件用途、LTV(総資産利益剰余率)などを同時に比較すると効率的です。また、月1回開示される運用レポートを確認し、稼働率の推移や物件の立地を把握しておくと安心です。
銘柄選びで失敗しない三つの視点
重要なのは、用途分散、財務健全性、運用者の実績を同時に見ることです。まず用途分散ですが、オフィス主体の銘柄は景気変動に左右されやすい反面、安定的な賃料収入を確保しやすい物流や住宅主体の銘柄と組み合わせるとポートフォリオが安定します。
次に財務健全性を示す指標がLTVです。一般に50%未満が健全とされ、60%を超えると金利上昇時の負担増が懸念されます。例えば2025年3月期の平均LTVは約43%ですが、銘柄ごとにばらつきがあります。投資家は分配金利回りだけでなく、借入比率の水準と固定金利比率も必ず確認しましょう。
最後に運用会社の実績です。運用期間が10年以上で資産規模が拡大している銘柄は、テナント交渉力や資金調達力が高く、分配金の増配傾向が続きやすいです。一方、新規上場の銘柄は成長余地が大きいものの、分配金予想が外れるリスクもあります。言い換えると、安定と成長のバランスを見極める目が求められます。
リスク管理と出口戦略を描く
実は、REITでも保有後のフォローが成果を左右します。価格下落リスクに備えるには、購入時に投資額を段階的に分け、定期的に買い増すドル・コスト平均法が有効です。日本取引所グループによれば、過去10年間で毎月定額投資を続けた場合、単発投資よりも平均取得価格が6%低下したという試算があります。
次に分配金の再投資です。分配金を新たな口数の購入に充当すれば、複利効果で資産が伸びます。特にNISA口座内で再投資すると、非課税メリットがそのまま拡大します。ただし、自動再投資サービスは証券会社ごとに対応が異なる点に注意してください。
出口戦略としては、ライフイベントに合わせて保有比率を調整します。たとえば教育資金が必要となる5年前から徐々に売却し、価格変動リスクを抑える方法があります。また、資産全体に占めるREIT比率が高くなり過ぎた場合は、株式や投資信託へ振り分けるリバランスを行いましょう。
2025年度の税制優遇と活用術
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続される新しいNISAの恩恵です。成長投資枠240万円と積立投資枠120万円を組み合わせ、REITの分配金と譲渡益が非課税になります。期限は恒久化されたため、従来の「5年間制限」はありません。
また、確定拠出年金(iDeCo)でもREITを含む投資信託を選択できます。iDeCoは60歳まで引き出せない制約がありますが、掛金が全額所得控除となるため、高い税率の給与所得者ほど節税効果が大きくなります。つまり、NISAで流動性を確保しつつ、iDeCoで長期運用を行う二刀流が最適解の一つです。
さらに、配当控除の活用も検討できます。REITの分配金は配当所得に区分されるため、総合課税を選択し、所得税率が低い人は税額を抑えられる場合があります。ただし、所得水準や医療費控除などと合わせた総合的な計算が必要なため、確定申告前には税理士や国税庁のサイトでシミュレーションしておくと安心です。
まとめ
REITは少額で不動産ポートフォリオを構築できる便利な投資手段です。仕組みを理解し、証券口座の選択、用途分散、財務指標のチェックを怠らなければ、安定した分配金と長期的な資産成長を同時に目指せます。また、2025年度の新しいNISAやiDeCoを活用すれば、税負担を軽減しながら複利効果を高められます。今日紹介したコツを実践し、まずは少額から市場に参加することで、将来の資産形成につなげてください。
参考文献・出典
- 金融庁「令和6事務年度金融レポート」 – https://www.fsa.go.jp/
- 日本取引所グループ 統計月報2025年7月号 – https://www.jpx.co.jp/
- 不動産証券化協会「J-REIT市場データ」 – https://www.ares.or.jp/
- 国税庁「NISA・iDeCoに関する税制Q&A」 – https://www.nta.go.jp/
- 総務省統計局「家計調査報告 2025年上半期」 – https://www.stat.go.jp/

