不動産投資に興味はあるものの、「ワンルームかファミリータイプか」「都心か郊外か」など迷いが尽きない読者は多いはずです。特に検索キーワードである「収益物件 選び方 どっち」は、まさに投資家予備軍の悩みを端的に表しています。本記事では、2025年9月時点の市場データと融資環境を踏まえながら、物件タイプや立地を比較する際の判断軸を整理します。読み終えるころには、自分に合った物件像が輪郭を持ち、次の行動が具体的に描けるようになるでしょう。
まず押さえておきたい収益物件の種類
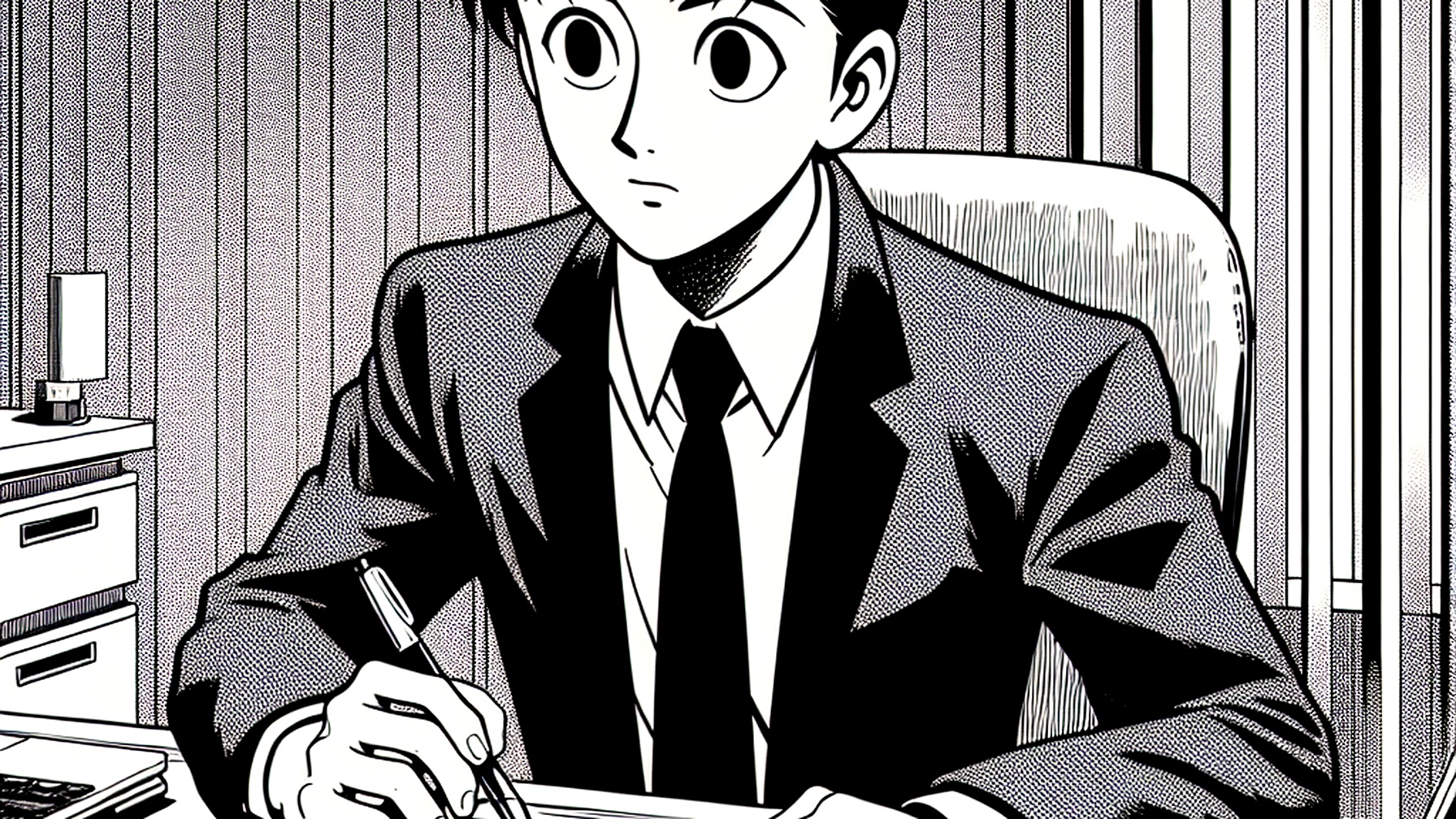
重要なのは、物件種別ごとの特徴と収益構造を理解することです。これを把握しないまま利回りだけで選ぶと、想定外の維持費や空室リスクに直面しかねません。
最も流通が多いのは都心ワンルームマンションです。単身者向けの需要が堅調で管理もシンプルですが、物件価格が高く、利回りは3〜4%台にとどまりやすいのが現状です。一方でファミリータイプは賃料単価こそ低くなるものの、平均入居年数が長く、長期安定収入を見込みやすいというメリットがあります。実際、国土交通省の「令和6年度賃貸住宅市場調査」ではファミリー物件の平均入居期間は5.9年と、ワンルームの2.8年を大きく上回りました。
郊外に多い木造アパートは初期投資を抑えられ、利回りも7%を超える事例が珍しくありません。しかし修繕周期が短く、金融機関が耐用年数をシビアに見るため融資期間が短くなる点には注意が必要です。一方、鉄筋コンクリート(RC)造の一棟マンションは長期融資が受けやすく、大規模修繕の計画を立てやすい反面、購入価格が高額で出口戦略を誤ると売却に時間がかかる恐れがあります。
シェアハウスや民泊併用物件のような特殊用途は、高利回りが期待できるものの、自治体の条例改正や消防法対応など運営コストが読みにくい点がネックです。つまり、初心者が安定運用を重視するなら、まずは需給が読みやすい王道タイプから検討するのが現実的と言えます。
立地vs利回り どちらを優先すべきか
ポイントは、長期のキャッシュフローを左右するのは「立地の需要」であり、短期の数字を際立たせるのが「表面利回り」に過ぎないことです。また、両者は必ずしも二者択一ではなく、バランスの取り方に投資家の個性が反映されます。
総務省統計局の人口移動報告によると、2024年の東京都転入超過数は7万人台を維持しましたが、5年前より約2割縮小しました。この傾向は、都心プレミアムが徐々に薄れる可能性を示唆します。それでも主要23区の空室率は5%前後で安定しており、空室期間の短さがキャッシュフローを下支えしています。したがって「空室リスクが怖い初心者ほど都心寄り」が基本線となります。
一方で利回り重視なら、人口が緩やかに減少する県庁所在地や政令市の郊外エリアが候補になります。日本政策投資銀行の収益不動産利回り調査では、地方中核市の木造アパート平均利回りは9.1%と、東京23区の約2倍です。ただし高利回り物件は入居付けと修繕費のブレが大きく、長期運営には堅固な管理体制が欠かせません。言い換えると、物件価格で得をしたつもりでも、管理会社との連携が甘いと収支は簡単に赤字化します。
さらに将来の出口を考えると、需要が落ち込むエリアでは売却価格が下がりやすく、実質利回りが目減りする恐れがあります。金融機関も立地リスクを厳しく査定するため、融資比率が低くなり、自己資金が膨らむ点も忘れてはいけません。
融資条件が変わる2025年度のポイント
まず押さえておきたいのは、2025年度の金融機関は「金利よりも自己資金比率」を重視する傾向を強めていることです。日本銀行が2024年にマイナス金利を解除したあとも短期金利は0.4%前後で推移していますが、各行は借り手審査を保守的に戻しています。
都市銀行の場合、投資用ローンの金利は変動型で年2.2〜3.0%が主流です。自己資金2割以上を用意できれば、1.6%台の優遇が得られるケースもあります。地方銀行や信用金庫では物件所在地の担保評価を軸に審査するため、築浅RC物件には35年、築古木造には15年程度と、融資期間に差がつきやすくなりました。こうした環境下では、返済比率が家賃収入の50%を超えないよう、余裕を持ったシミュレーションが肝心です。
また、2025年度の「住宅ローン減税」は自宅取得のみが対象で、賃貸用物件は適用外です。節税対策としては、減価償却費を利用した損益通算が王道ですが、耐用年数を迎えた木造物件で節税効果を狙う手法は、取得後の修繕コストがかさむ点を十分見極める必要があります。さらに、東京都と大阪府では2025年4月から「省エネ性能表示制度」が賃貸住宅にも段階的に拡大しており、断熱性能が低い物件は入居者から選ばれにくくなる恐れがあります。
実は金融機関もESG指標を重視し始めており、断熱性能を高めたリノベーション工事に対して、金利優遇を設ける地銀が増えています。改修費を含めた長期試算を行えば、表面利回りは下がっても純利益が安定するケースがあるため、単年度の数字にとらわれず全期間で比較する視点が重要です。
リスク管理と出口戦略を同時に考える
ポイントは、リスクは購入時点で八割決まり、残り二割を運営でコントロールするという発想です。つまり物件選びと同時に、売却までのシナリオを描くことがリスク管理につながります。
自然災害リスクは立地選定の段階で大きく差がつきます。国土交通省「重ねるハザードマップ」で洪水リスクが高い地域は、金融機関の担保評価が伸びにくく、売却時に買い手がつきづらい傾向があります。火災保険料も2024年の改定で築古木造が大幅に上がっており、保険料の差が利回りに直結します。保険料負担まで含めたネット利回りで比較する姿勢が欠かせません。
空室が長期化した場合に備えて、家賃を1割下げてもキャッシュフローが黒字になる水準で借入を組むと精神的負担が軽くなります。加えて、10年後の残債が想定売却価格の70%を下回るよう返済計画を調整すれば、出口の自由度が高まります。この数値は、三井住友トラスト基礎研究所の試算で、中古RCの平均価格下落率3%/年を前提として導かれた安全圏とほぼ一致します。
心理的ハードルも侮れません。長期投資では景気後退期に売却したくなる局面が訪れますが、最初に出口戦略を定義しておくことで、感情に流されにくくなります。投資期間、想定利回り、売却残債の三つをシンプルにメモしておくだけでも十分効果があります。
実例で学ぶ物件選びシミュレーション
実は、数字を具体的に並べると「収益物件 選び方 どっち」の答えは自ずと浮かび上がります。ここでは都心ワンルームと地方木造アパートを同額の自己資金で比べ、キャッシュフローと出口を検証します。
前提として、自己資金600万円を投入し、都心築10年ワンルーム(価格3,000万円、利回り4%)、地方築20年木造アパート(価格3,000万円、利回り9%)を購入するとします。ワンルームの家賃は毎月10万円、年間家賃120万円、ローン金利2.0%、期間30年、年間返済額133万円となり、当初キャッシュフローはやや赤字です。ただし空室率5%で計算しており、実質稼働率は95%です。
一方、地方アパートは年間家賃270万円、金利2.5%、期間20年、返済額191万円、空室率15%で計算すると、キャッシュフローは約38万円の黒字になります。数字だけ見れば地方アパートが有利ですが、10年後の売却価格を試算すると、都心ワンルームは2,400万円前後、残債は約2,100万円で差額300万円が手元に残る計算です。地方アパートは価格が2,000万円に下がり、残債も約1,500万円で差額500万円が出るものの、売却までの期間が延びる可能性があります。
このシミュレーションが示すのは、高利回り物件は運営期間中に資金を多く生む一方、出口で時間を要する恐れがあり、逆に低利回り物件は運営期の資金繰りが厳しくても売却しやすいという構造です。どちらが優れているかではなく、自分が重視するのが毎月のキャッシュフローか、資産の流動性かで選択肢が変わると理解しましょう。
まとめ
この記事では、物件タイプ、立地、融資環境、リスク管理、シミュレーションの五つの視点から「収益物件 選び方 どっち」という問いを整理しました。要するに、安定を求めるなら需要が読める都心ワンルームから、収益拡大を狙うなら郊外や地方の高利回り物件から始めるのが王道です。ただし金利上昇と省エネ性能の要件強化が進む2025年以降は、自己資金と修繕計画の精度が成功を左右します。次のアクションとして、居住希望エリアの賃貸市場データを確認し、融資条件を複数行で比較することから始めてみてください。着実な準備が、将来の安定収入への近道となります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局「令和6年度賃貸住宅市場調査」 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告 2024年」 – https://www.stat.go.jp/
- 日本銀行「金融政策決定会合議事要旨 2025年7月」 – https://www.boj.or.jp/
- 日本政策投資銀行「収益不動産マーケット動向 2025年版」 – https://www.dbj.jp/
- 三井住友トラスト基礎研究所「中古マンション価格と残債分析 2024」 – https://www.smtri.jp/

