不動産投資に興味はあるけれど、物件を直接購入するのは資金も手間もかかる。このような悩みを持つ人にとって、少額から参加できるREIT(不動産投資信託)は魅力的な選択肢です。しかし銘柄数が増えた今、どれを選べばいいか迷うのも事実。本記事では、2025年9月時点で人気の高い主要REITを比較しながら、利回りだけに頼らない選び方を丁寧に解説します。読めば、自分の投資目的に合う銘柄を見極めるポイントが具体的にわかります。
REITの基本と株式との違いを整理する
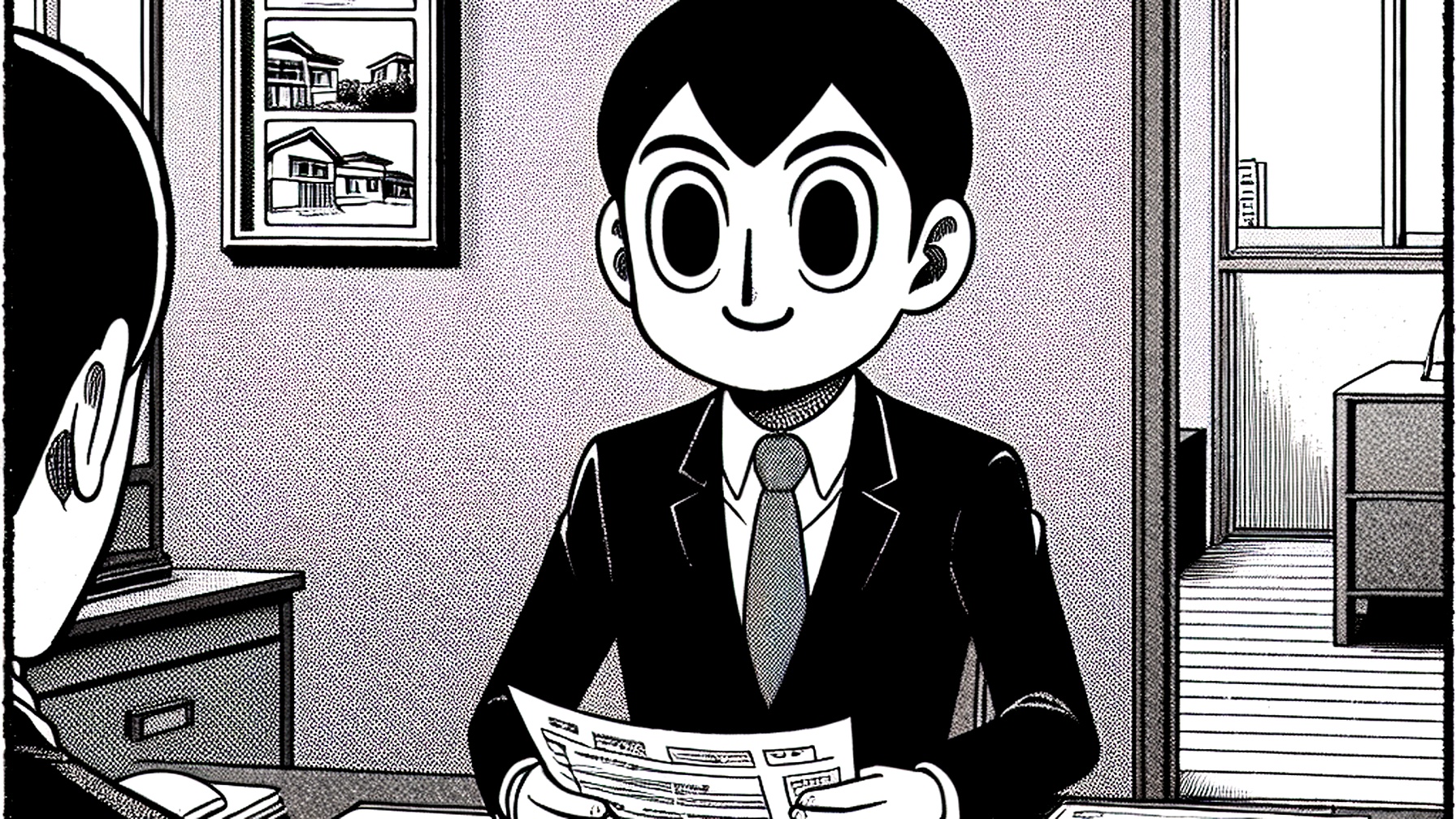
まず押さえておきたいのは、REITが株式投資とどこが異なるかという点です。REITは不動産を裏付け資産とし、賃料収入を中心に得た利益の九割超を分配金として投資家へ還元する仕組みです。そのため一般企業の配当よりも分配金利回りが高くなる傾向があります。一方で、不動産市況に強く連動するため景気悪化時は価格変動が大きくなることも頭に入れておく必要があります。
続いて流動性の面を見てみましょう。上場REITは株式と同様に証券取引所で売買できるため、現物不動産より換金しやすいのが特徴です。しかし取引量は大型株ほど多くないので、成行注文ばかりだと約定価格が想定より動くことがあります。つまり、十分な売買板を確認してから発注することが望ましいというわけです。
さらに税制上の違いにも触れておきます。2025年度も、REITの分配金に対しては株式配当と同じ20.315%の申告分離課税が適用されます。ただし特定口座を利用すれば損益通算が容易になり、株式の譲渡損と相殺できる点が資産全体の収益管理をしやすくしています。
このようにREITは高い分配金利回りと流動性を両立しつつ、税制面でも株式とほぼ同等の扱いを受ける金融商品です。基礎を理解しておくことで、次章以降の詳細比較が一段と腹落ちするはずです。
市場動向から読むセクター別人気の背景
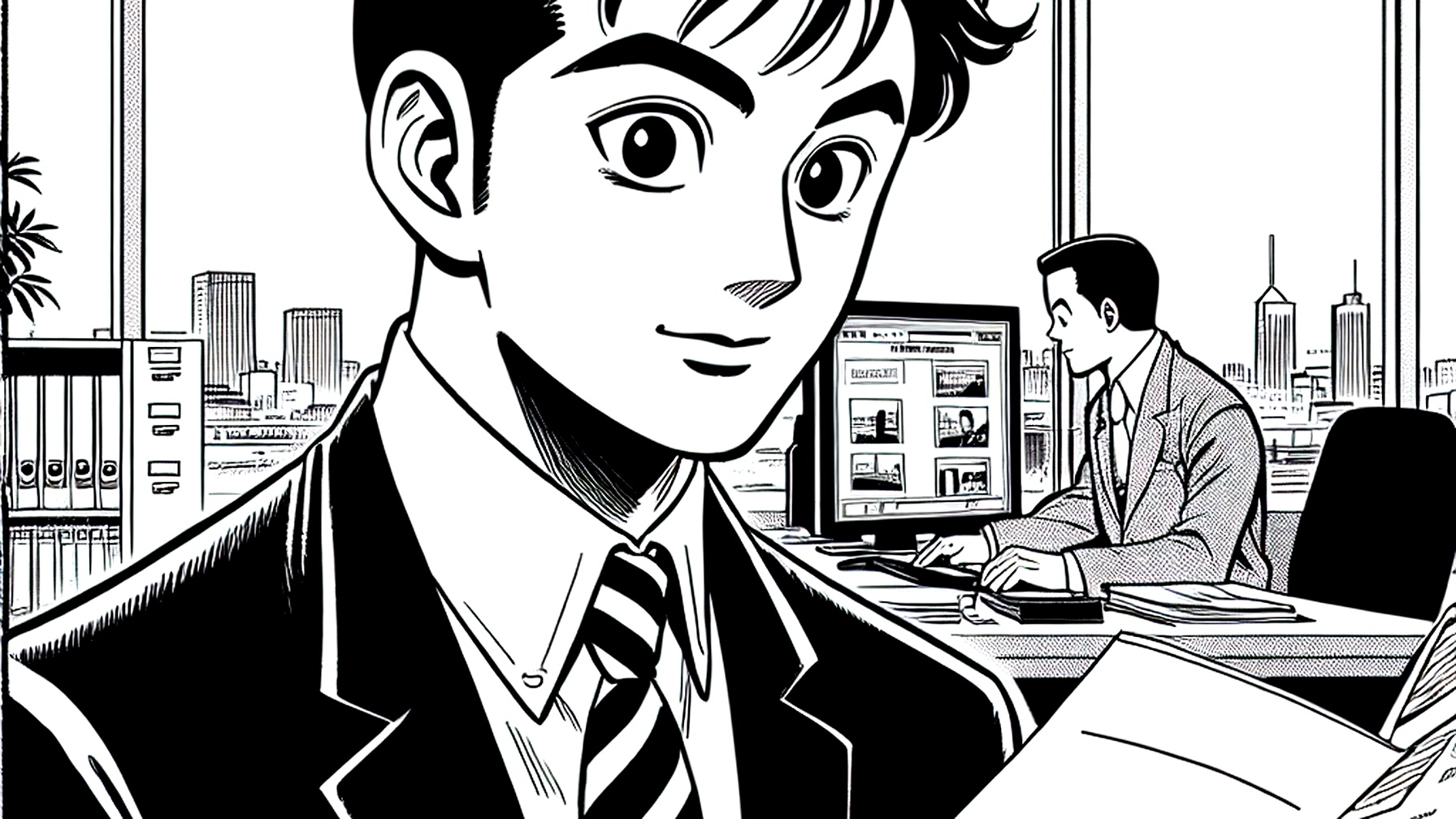
ポイントは、どの不動産セクターが今後も優位性を保てるかを見極めることです。2024年から2025年にかけて、物流施設と住居系REITへの資金流入が続いています。国土交通省「不動産投資市場動向調査」によると、物流施設の空室率は首都圏で3%を切り、賃料も前年同期比で4%上昇しました。ネット通販の成長が背景にあり、景気に左右されにくい需要が強みです。
一方、オフィス系はコロナ禍を経てリモートワークが定着したものの、2025年上期の東京グレードAオフィス空室率は4.2%と下げ止まりました。日本経済研究センターのレポートでは、ハイブリッド勤務の普及で「働く場を減らすより質を高める」企業が増え、優良物件へ需要が戻ると分析されています。つまり良質な立地と延床面積を持つ大型ビルに投資するREITは依然注目されています。
住宅系はインフレ局面でも家賃改定が比較的柔軟で、特に単身世帯向け物件を多く保有するREITの分配金は安定しています。総務省住宅・土地統計調査によれば、単身世帯数は2025年に2,135万世帯へ拡大し、全世帯の約四割を占める見込みです。人口減少局面でも世帯構造の変化が需要を支える形になっています。
商業施設系は消費回復を追い風にしていますが、ECの伸長が長期的なリスク要因です。したがって物販中心より飲食・サービス比率を高めた物件を多数持つREITの方が空室リスクに強いといえます。
代表的オフィス系REITの強みと課題
重要なのは、同じオフィス系でも保有資産の質と借入比率に大きな差がある点です。ここでは日本ビルファンド投資法人(NBF)とジャパンリアルエステイト投資法人(JRE)を取り上げます。
NBFは総資産約1.4兆円で、丸の内・大手町といったビジネスの中心地に大型ビルを多数保有しています。2025年3月期の平均稼働率は99%台を維持し、分配金は年1万300円前後です。LTV(総資産に対する有利子負債の比率)は38%と保守的で、金利上昇局面にも比較的耐性があります。ただし、好立地ゆえに物件取得競争が激しく、新規成長余地はやや限られています。
一方JREは総資産約1.3兆円、稼働率は98%前後で推移しています。特徴的なのは都心集中を維持しつつ、環境認証を取得したビルを増やしている点です。世界的なサステナビリティ投資の流れを取り込み、機関投資家の需要が厚いことが株価の安定要因になっています。LTVは40%台前半で、NBFよりやや高いものの適正水準内に収まっています。
オフィス系REITを見る際は、賃料の改定力と借入金利の固定化割合を確認することが欠かせません。固定金利比率が七割を超えていれば、長期金利上昇時でも分配金の振れ幅を抑えられます。またテナントの業種分散が進んでいるかも重要で、ITと金融に偏ると景気後退時の空室リスクが高まります。
物流・住居系REITの選び方と注目銘柄
実は、2023年以降のREIT新規資金流入の六割以上を物流・住居系が占めています。その中でも日本プロロジスリート投資法人とケネディクス・レジデンシャルネクスト投資法人は投資家から高い支持を集めています。
日本プロロジスリートは世界的な物流開発会社プロロジスの日本資産を中心に保有し、総資産は8,000億円規模です。賃料契約は平均5〜7年と長く、空室率はほぼ0%に近い水準が続きます。2025年6月期の分配金利回りはおよそ3.6%ですが、内部留保を手厚く積み上げており、将来の修繕負担に強いのが評価ポイントです。
ケネディクス・レジデンシャルネクストは、単身向け・高齢者向け住宅に特化した構成で、総資産4,500億円のうち7割が東京23区に立地しています。2025年1月期の稼働率は98.6%、分配金利回りは3.9%前後です。少子高齢化に伴うシニア住宅需要を捉えていることから、景気サイクルに左右されにくいといわれます。
選定の際は、物件ポートフォリオの新しいさと再開発余地にも目を向けてください。築浅の物流施設は高スペックかつ省エネ性能が高く、ESG資金の流入でプレミアムがつきやすい傾向があります。住宅系では学生寮やサービス付き高齢者住宅など、一般賃貸と異なるニッチ分野への展開が差別化要因になります。利回りだけを追うと地方物件比率の高い銘柄を選びがちですが、長期的な入居需要を考えれば都心アクセスと運営ノウハウの厚みが欠かせません。
分配金利回りの読み解き方とリスク管理
ポイントは「高利回り=割安」と短絡的に考えないことです。REITの分配金は内部留保の取り崩しや資産売却益を原資に上乗せできるため、一時的に好利回りになる場合があります。投資法人が発表する「1口当たり当期純利益」と「分配金のうち内部留保取り崩し額」を確認し、実力値を把握しましょう。
また、市場金利の動向はREIT価格に直結します。日銀は2025年4月、長期金利操作(YCC)を完全撤廃し、10年国債利回りは1.2%付近で推移しています。過去の統計では、長期金利とREIT分配金利回りの差(スプレッド)が3%を切ると株価が調整しやすい傾向があります。現状スプレッドは約2.6%のため、購入時は分配金再投資で平均取得単価を平準化する分散手法が有効です。
レバレッジの高さにも注意が必要です。LTVが50%を超える銘柄は金利上昇局面で分配金の減少リスクが大きくなります。金融庁の「REITモニタリング報告書」では、LTV45%以下を保守的、50〜60%を中庸、60%超を積極的と区分しています。初心者はまず保守的レンジの銘柄を中心にポートフォリオを作ると安定感が増します。
最後に、災害リスクの点検も欠かせません。国交省ハザードマップポータルで保有物件所在地を確認し、地震や水害のリスクが高い地域への集中度を把握しておきましょう。特に物流施設は湾岸エリアに立地することが多く、津波や液状化への備えが分配金の安定性を左右します。
まとめ
ここまで人気 REIT 比較を通して、セクター別の市場動向から個別銘柄の財務指標、そして利回りの裏側にあるリスクまで見てきました。高い分配金利回りに目を奪われがちですが、実際には稼働率の推移やLTV、テナント分散度といった定量データを複合的に読むことが欠かせません。オフィス系なら立地の質と借入金利の固定化割合、物流・住居系なら長期需要と再開発余地を重点的にチェックすると、自分に合った安定銘柄を絞り込めます。
今後は金利動向が最大の変数になりますが、定期的な買い増しと複数銘柄への分散でリスクを平準化すれば、REITは依然として魅力的なインカムソースです。今日紹介した視点を参考に、まずは証券会社のスクリーニング機能で候補を比較し、自分のリスク許容度に合うポートフォリオを作ってみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産投資市場動向調査 2025年上期版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 2024年速報 – https://www.stat.go.jp
- 金融庁 REITモニタリング報告書 2025年3月 – https://www.fsa.go.jp
- 日本取引所グループ REIT主要指標 2025年8月 – https://www.jpx.co.jp
- 日本経済研究センター ハイブリッド勤務とオフィス需要 2025年レポート – https://www.jcer.or.jp
- 日銀 金融政策決定会合公表資料 2025年4月 – https://www.boj.or.jp

