不動産投資に興味はあるものの、「収益物件と融資条件のどっちを優先すべきか分からない」と悩む人は多いでしょう。物件を先に決めると融資が通らない不安が残り、融資を先に確保しようとすると理想の物件を逃す恐れがあります。本記事では、15年以上の投資実務で培った経験をもとに、初心者でも迷わない判断軸を提示します。先に基礎を押さえ、次に融資条件が収支に与える影響を示し、最後に2025年現在の金融環境を踏まえた戦略を具体例とともに解説します。
収益物件選びで迷う前に知るべき基礎
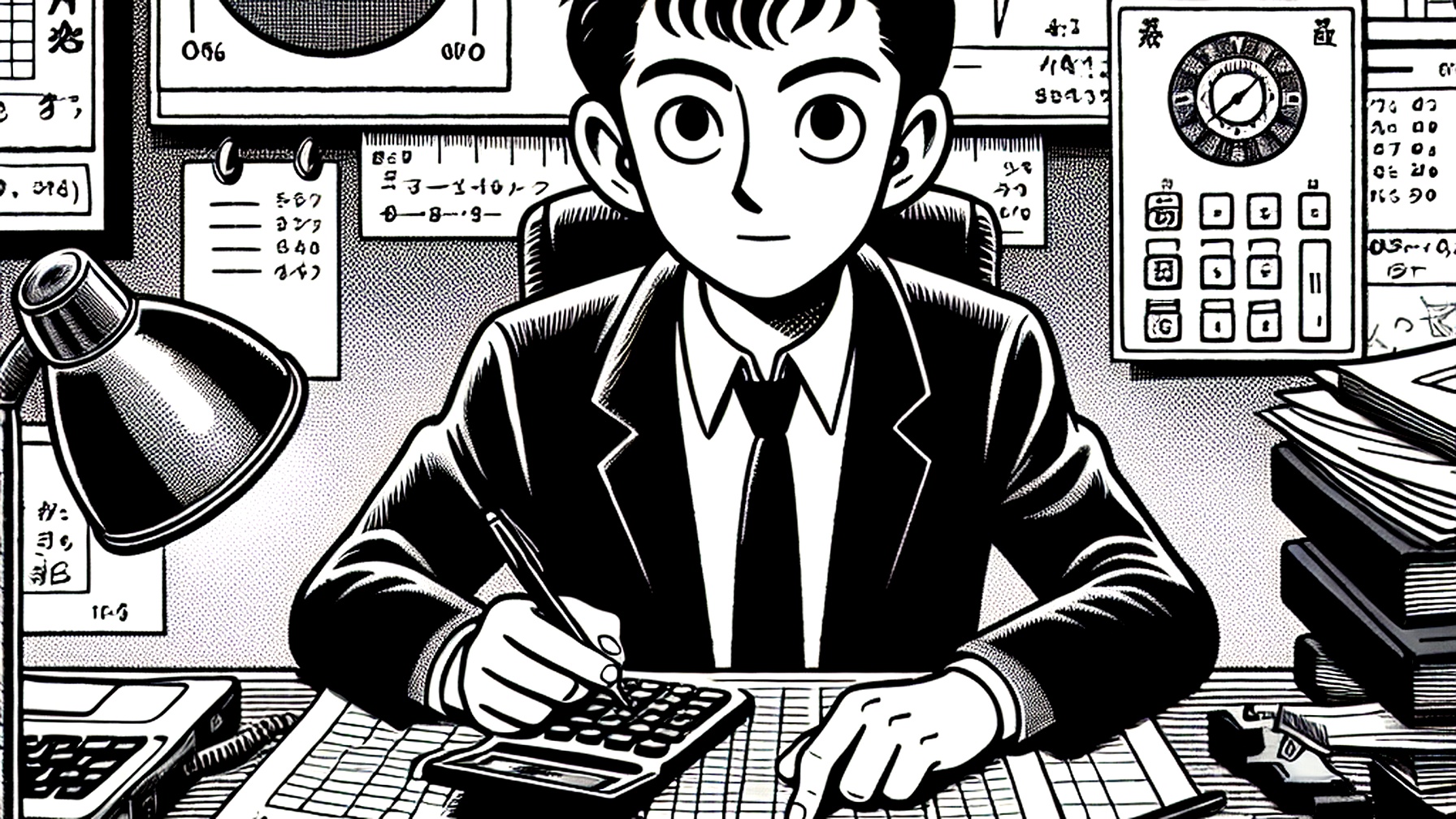
まず押さえておきたいのは、収益物件の価値が「立地」「利回り」「将来性」の三要素で決まるという事実です。立地は空室リスクを、利回りは投資効率を、将来性は資産価値の維持を左右します。国土交通省の住宅着工統計によると、2024年度の全国平均空室率は13.4%ですが、東京都心5区に限れば7%台にとどまります。この差がキャッシュフローの安定性に直結するため、立地を軽視することはできません。
一方、利回りは表面利回りと実質利回りに分かれ、初心者は手取り後の実質利回りを見落としがちです。固定資産税や管理費を差し引くと、表面利回り8%でも実質は5%程度まで下がることが珍しくありません。重要なのは、物件価格だけでなくランニングコストを含めた総投資額で評価する点です。
さらに人口動態も見逃せません。総務省「住民基本台帳人口移動報告」では、2023年から24年にかけて20代の都市部転入超過が続きました。若年層の流入が見込める地区なら、築年数が多少古い物件でも賃料維持が期待できます。つまり、物件の数字を読む際は地域の将来性を同時にチェックする習慣が不可欠です。
融資条件がキャッシュフローを左右する理由
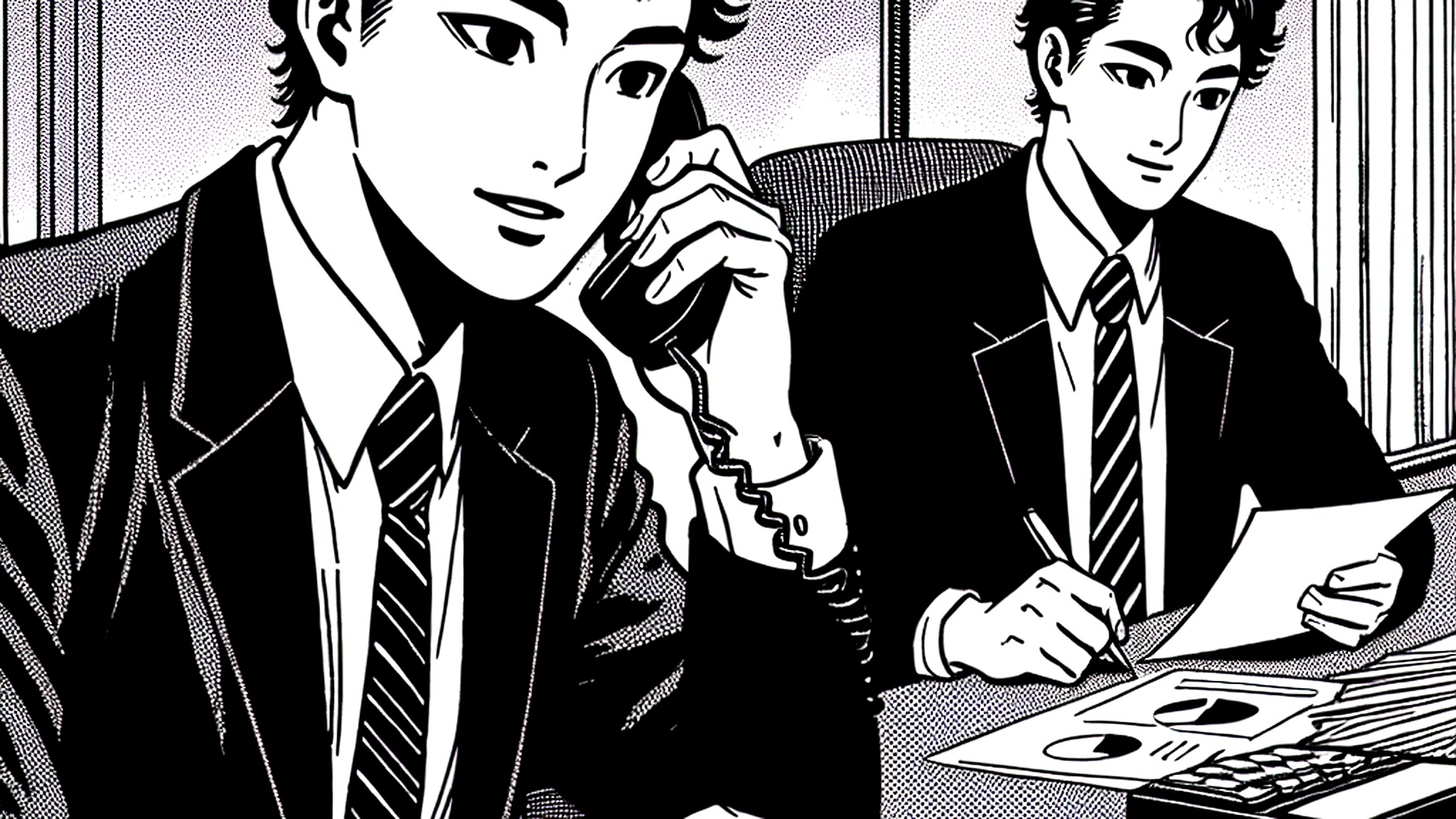
ポイントは、金利のわずかな違いが長期の収支に大きく響く点です。日本銀行の貸出約定平均金利によると、2025年4月時点で10年超の固定金利は平均1.45%ですが、金融機関によって0.8%から2.2%まで幅があります。例えば3000万円を25年返済で借りる場合、金利1%と2%では総返済額がおよそ410万円異なります。この差額はちょうどワンルーム1戸分の家賃収入に匹敵し、物件選定以上に融資条件がキャッシュフローを動かすと分かります。
また、融資期間も重要です。同じ返済比率でも期間が長いほど月々の返済負担は下がりますが、総返済額は増加します。ここで鍵になるのが「DSCR(借入返済余裕率)」です。DSCRが1.2倍以上なら金融機関は融資に前向きになりやすいと言われますが、家賃下落を織り込むなら1.4倍を目標に設定すると安全域が広がります。
保証料や団体信用生命保険(団信)の有無も忘れてはいけません。近年は金利に0.2%上乗せで「疾病保障付団信」を付けるケースが増えています。健康に自信があれば通常団信を選択し、その分金利を下げる戦略も有効です。つまり融資条件は利率だけでなく、期間と付帯費用を含めて総合的に比較する必要があります。
どっちを優先?目的別に見る判断軸
実は、「収益物件 融資条件 どっち」を優先するかは投資目的で変わります。安定収入を重視する年金代わり型なら、金利変動リスクを抑えるために融資条件を先に確定し、その枠内で物件を探す方法が適しています。具体的には複数行と事前相談し、金利1%台の承認が得られたら返済比率から逆算して物件価格を決める流れです。
一方でキャピタルゲイン(売却益)狙いの場合は、将来値上がりが見込める物件を先に押さえたほうが効果的です。都心の再開発エリアや駅直結物件は競争が激しく、融資審査中に他の投資家に買われるリスクがあります。そのため、まず買付証明を入れて売主と価格を合意し、その後に優遇金利を提示できる金融機関を比較して絞り込む戦略が現実的です。
投資経験が浅い読者なら、どちらか一方に賭けるより「同時並行」で動くことを勧めます。つまり、物件情報を収集しながら、並行して金融機関にヒアリングシートを送り、3週間以内に融資可否の目安を得る方法です。手間は増えますが、物件と融資のタイムラグを最小化でき、取り逃しを防げます。
実例で学ぶシミュレーションの作り方
重要なのは、具体的な数字で判断する習慣を身につけることです。ここでは東京都郊外のアパート一棟(価格6000万円、表面利回り8%)を例にします。自己資金1200万円(20%)を投入し、残り4800万円を金利1.3%、期間25年で借りた場合、月々の返済は約19万円です。年間家賃収入は480万円、管理費や固定資産税を差し引いた純収入はおよそ360万円となります。
この時点で年間キャッシュフローは360万円−228万円(年返済額)=132万円です。空室率15%シナリオに切り替えると純収入は306万円となり、キャッシュフローは78万円へ減少します。DSCRは1.34倍から1.14倍へ低下しますが、まだ返済負担に耐えられる範囲です。シミュレーションでは、金利2%・空室率20%の最悪ケースでもキャッシュフローが黒字かどうかを確認しておくと安心です。
次に自己資金を10%に抑えた場合を比較します。返済額は同じですが借入額が増えるため、DSCRが1.05倍に低下し、空室率が少し上がるだけで赤字に転落します。つまり、融資条件で緩い返済比率を選ぶと自己資金を減らせますが、キャッシュフローの安全余裕が縮まると分かります。これが「物件と融資はセットで検証するべき」という理由です。
2025年度の融資環境と対策
2025年度の住宅ローン減税は居住用が対象で、投資用物件には直接の恩恵がありません。その一方で、日本政策金融公庫の「中小企業投資促進融資」は、脱炭素性能を満たす賃貸住宅に対し最大7200万円、金利0.9%(5年固定)の枠を設けています。期限は2026年3月申込分までで、建築費の三分の一を自己資金で負担することが条件です。省エネ性能を高めた新築アパートを考えるなら、この制度の活用を検討する価値があります。
民間金融機関では、地銀が不動産向け融資姿勢をやや慎重に戻す傾向が見られます。しかし、ネット銀行はAI審査を導入し、賃料査定の透明性が向上したことで金利1%前後の競争が続いています。国際情勢による金利上昇リスクは残るものの、日銀は「緩和的な環境を当面維持する」と示唆しており、2025年9月時点で急激な金利上昇シナリオは主流ではありません。
これらの情勢を踏まえると、今後1〜2年で初めて投資する人は長期固定より「10年固定+その後変動」型を選び、将来の借換え余地を残す戦略が有効と考えられます。賃料上昇が見込めないエリアでは、返済期間を長めに設定しつつ繰上返済の原資をキャッシュフローから確保しておくとリスクを抑えられます。つまり、2025年度の融資環境では柔軟性と安全余裕のバランスが鍵になります。
まとめ
この記事では、収益物件と融資条件の「どっち」を優先するかという悩みの答えを、目的別に整理してきました。物件の質は空室リスクと資産価値を左右し、融資条件はキャッシュフローと安全余裕を左右します。双方を同時並行で検討し、数値シミュレーションで最悪シナリオを確認する姿勢が成功への近道です。まずは金融機関に事前相談し、同時にエリアの将来性を調べる行動を始めましょう。堅実な準備で、投資を長期の味方に変えてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅着工統計(2024年版) – https://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-jutakuchokou.html
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告(2024年) – https://www.stat.go.jp/data/idou/
- 日本銀行 貸出約定平均金利(2025年4月) – https://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/loan_rate/
- 日本政策金融公庫 中小企業投資促進融資(2025年度) – https://www.jfc.go.jp/
- 不動産流通推進センター 不動産投資分析事例集(2025年版) – https://www.retpc.jp/

