パンデミックが落ち着き、オフィスワーカーの多くが出社と在宅を組み合わせるようになった今、「一棟買い アフターコロナ」で不動産投資を始めたいと考える人が増えています。しかし、需要の変化や金利の動向を正しくつかまなければ、空室リスクや収支悪化に直面しかねません。本記事では、2025年9月時点の最新データをもとに、一棟買いの基礎、アフターコロナ特有のチャンスと落とし穴、そして資金計画から出口戦略までを丁寧に解説します。読み終える頃には、今何に注目し、どんな行動を取ればよいのかがクリアになるはずです。
アフターコロナで変わった賃貸需要
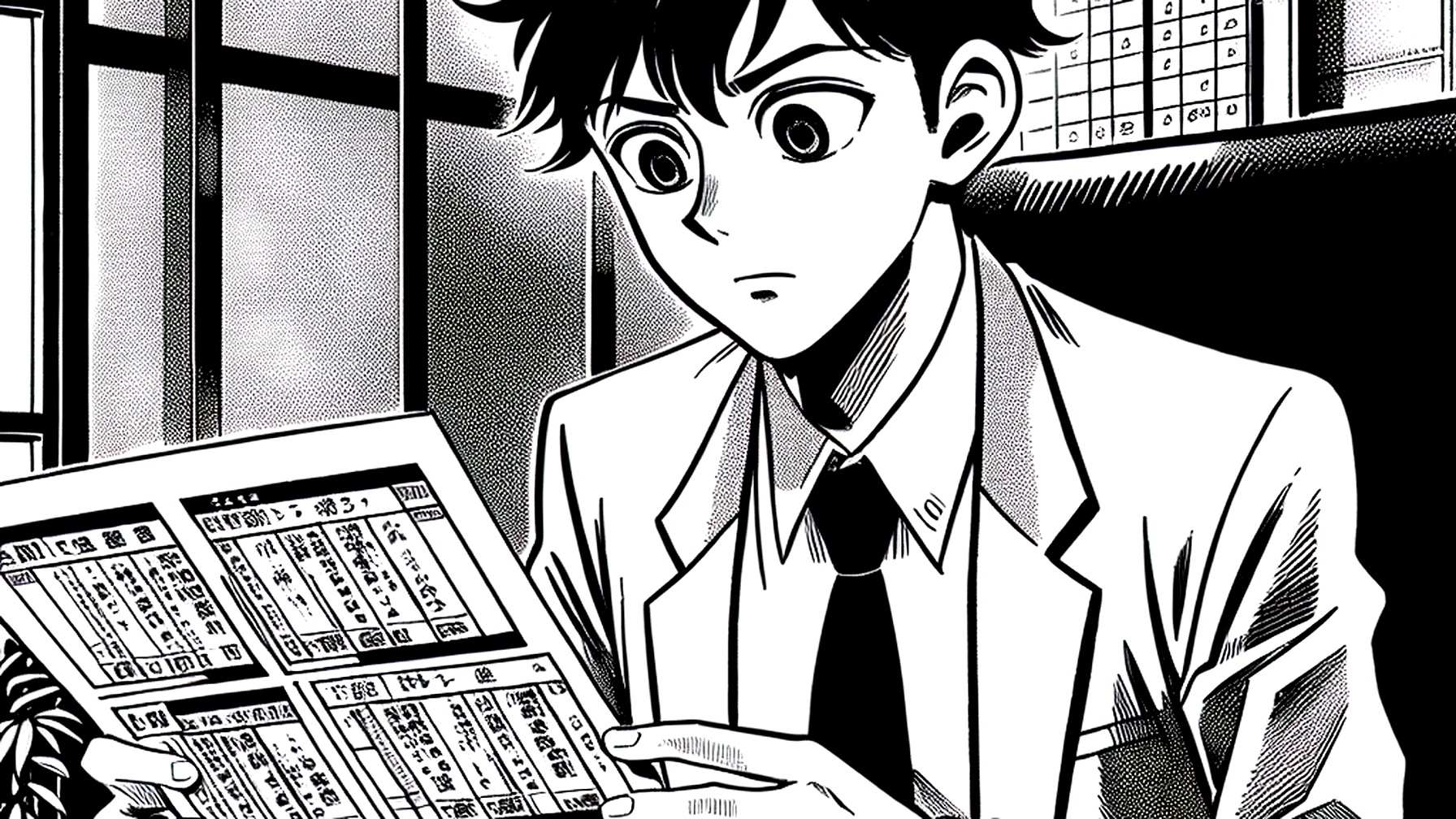
まず押さえておきたいのは、入居者ニーズがコロナ前と大きく変わった点です。総務省の労働力調査(2025年6月速報)によれば、テレワークを週に一度以上利用する層は全体の34%で、高水準を維持しています。自宅での仕事が定着した結果、入居者は「ネット回線の速度」「ワークスペースの確保」「遮音性」を重視するようになりました。
一方で、完全在宅ではなく出社も必要なハイブリッド勤務が主流となり、駅徒歩10分圏内の需要は依然として高いままです。つまり、都会離れが進むという単純な図式ではなく、「利便性」と「居住快適性」を同時に満たす物件が選ばれるようになったと言えます。実際、国土交通省の住宅着工統計では、2024年度から2025年度にかけて都市近郊の中規模賃貸マンション着工数が9%増加しました。
この流れは一棟買いにとって追い風です。区分所有よりも共用部の改修や設備投資を自在に行え、入居者の細かな要望にスピーディーに対応できるからです。しかし、立地選定を誤れば空室が長期化するリスクも大きくなるため、需要トレンドと周辺競合の両面を掘り下げて調査する姿勢が欠かせません。
一棟買いのメリットと注意点
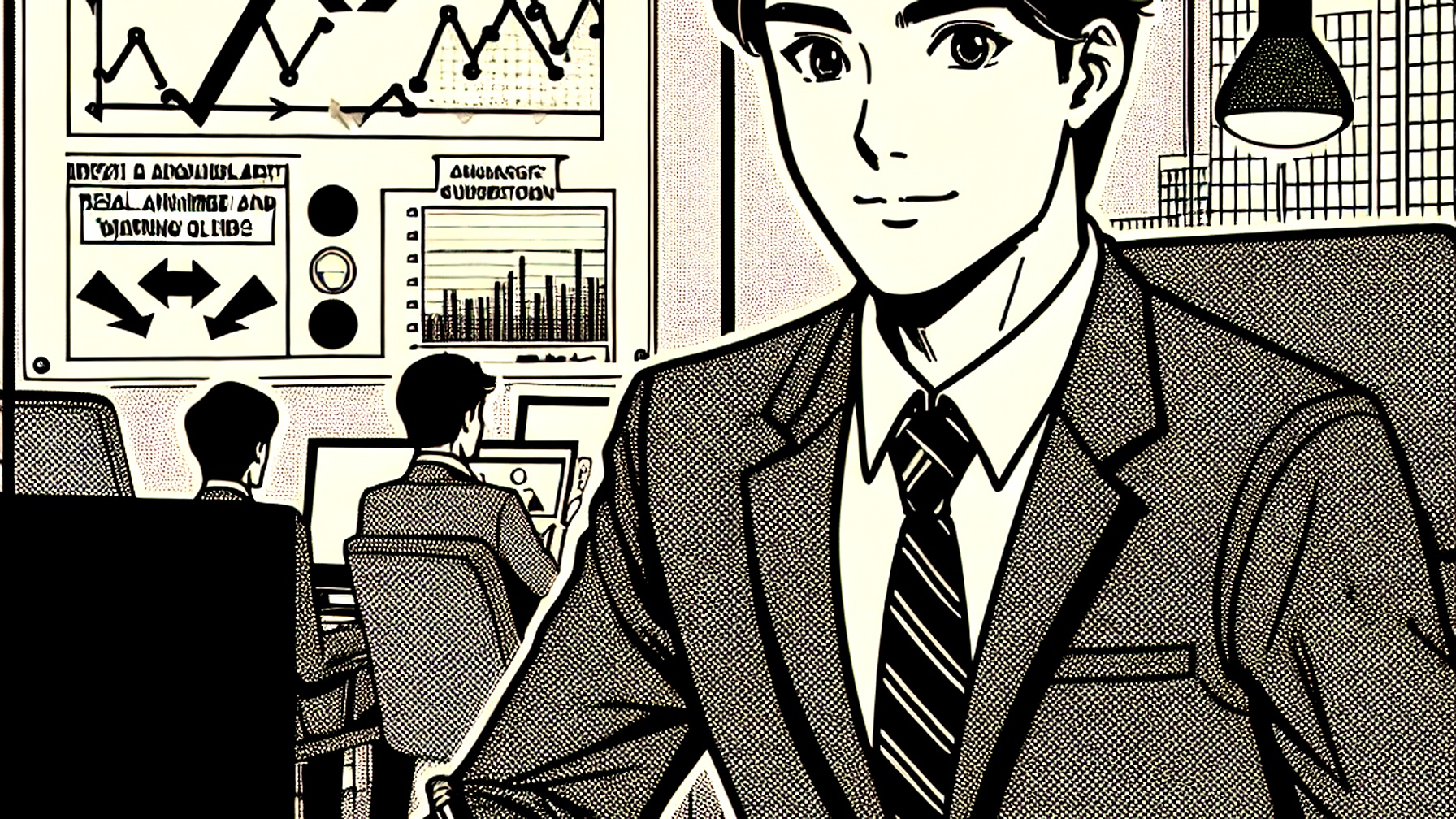
ポイントは、自ら賃貸経営をコントロールできるという一棟買い特有の強みです。共用設備のアップグレード、ペット可やワーキングスペース付きへの用途変更など、全体方針をオーナーが決められます。そのため、アフターコロナで求められる高速インターネットや屋上テラスといった付加価値を、タイムリーに導入しやすいのが魅力です。
ただし、購入金額が大きい分、資金繰りに失敗するとリカバリーが難しくなります。特に築古物件を選ぶ場合、外壁や配管の大規模修繕が発生しやすく、想定外の出費がキャッシュフローを圧迫します。国土交通省の長期修繕計画ガイドラインでは、築30年超のRC造マンションで10年ごとにおよそ建物価格の8〜12%の修繕費を見込むよう示されています。
さらに、管理の質も収益に直結します。区分所有なら管理組合が動きますが、一棟ではオーナーが全責任を負う形です。自主管理に挑戦する場合でも、入居者対応や設備点検を担当できる人材ネットワークを確保しておく必要があります。管理会社に委託する場合は、手数料だけでなく入居募集力や原状回復の品質も比較して選ぶと安心です。
2025年度の融資環境と資金計画
重要なのは、低金利が続く今をどう生かすかという視点です。日銀は2025年7月の金融政策決定会合で短期金利のマイナス解除を見送り、実質ゼロ金利を維持しました。これにより、主要地銀の投資用不動産ローン金利は固定で年1.2〜1.8%が目安となっています。ただし、審査は2010年代後半の融資過熱期と比べ厳格化しており、自己資金2割、返済比率50%以下を求めるケースが増えました。
一棟買いの平均価格は、首都圏でRC造20戸規模なら1億8,000万〜2億5,000万円が相場です。自己資金を20%入れると3,600万〜5,000万円が必要で、この時点で投資家の資金力が試されます。資金計画を立てる際は、購入時諸費用(物件価格の6〜8%)と初期修繕費、さらに家賃下落シナリオも織り込んでおくと安定します。
実は、2025年度税制改正で耐震・省エネ改修に関する投資減税が継続されました。一定の断熱性能向上工事を行うと、法人税・所得税で特別償却15%が適用される制度です(適用期限:2026年3月末)。築古物件を購入して性能向上リノベを行う場合、この減税を利用すればキャッシュフローの改善と資産価値上昇を同時に狙えます。ただし、要件を満たす設計や工事監理が欠かせないため、施工会社選びは慎重に行いましょう。
リスク管理と出口戦略
基本的に、一棟買いは長期保有を前提とする投資ですが、出口を意識したリスク管理が欠かせません。想定外の空室率上昇や金利変動に備え、三つの視点でプランBを用意しておくと安心です。第一に、資金繰りリスクには手元流動性6カ月分以上を確保すること。第二に、賃料下落に備えた段階的リフォームプランを準備し、ターゲット層の変更に機動的に対応すること。第三に、売却時期を見極めるため、周辺の成約事例や金融機関の融資姿勢を定期的にチェックすることです。
2025年上期の東日本不動産流通機構データによれば、築20年超の一棟マンション売却価格は前年同期比で4%上昇しましたが、物件のエネルギー効率評価が低い場合は価格交渉幅が広がる傾向が顕著です。つまり、今から省エネリノベを行えば、出口戦略でも優位に立ちやすいわけです。
また、空室率が想定を超えた場合は、サブリースやマンスリーマンション化など補完策を検討する選択肢もあります。ただし、サブリース契約は賃料改定条項や解除条件を慎重に読み解く必要があります。マンスリー化は稼働率を高めやすい反面、清掃コストが上がるため、周辺相場と運営体制を踏まえた収支検証が欠かせません。
サステナビリティ投資で価値を高める
実は、アフターコロナで入居者の健康意識と環境意識も大きく高まりました。経済産業省のグリーン成長戦略進捗レポート(2025年版)では、ZEB Ready(ゼブレディ)基準を満たす賃貸住宅の入居率が従来比で7ポイント高いと報告されています。環境性能が高い物件は光熱費を抑えられるため、家賃が少々高くても選ばれやすいのです。
一棟買いであれば、太陽光パネルの設置やLED共用灯への全面切替、さらには非接触型オートロックなどIoT設備を一括導入しやすい利点があります。これらの施策は、入居者満足度の向上だけでなく、ESG投資マネーの流入先として選ばれる可能性を高め、将来的な売却価格にも良い影響を与えます。
さらに、地方自治体によっては独自の省エネ改修補助を設けています。2025年度に有効な制度として、東京都環境確保条例に基づく「既存建築物省エネ改修助成」があり、補助率は工事費の最大1/3、上限1,500万円です。都内で築古物件を取得する際には、こうした制度を活用して初期負担を抑えることも検討するとよいでしょう。
まとめ
アフターコロナの賃貸市場では、利便性と居住快適性を同時に満たす物件が支持されています。一棟買いは設備や管理方針を自在にコントロールできるため、変化に強い投資手法と言えます。ただし、購入金額が大きく資金繰りリスクも増すため、自己資金2割以上、手元流動性6カ月分という保守的な計画が前提です。金利が低い今こそ融資を活用しやすいものの、入居者ニーズや省エネ性能といった付加価値を徹底的に高めなければ長期的な競争には勝てません。行動提案として、まずはターゲット立地の需要データを収集し、次に物件の修繕履歴と省エネ改修の余地を精査してください。その上で金融機関に事前相談し、複数シナリオの収支表を作成することが、アフターコロナで成功する第一歩になります。
参考文献・出典
- 総務省統計局 労働力調査(2025年6月速報) – https://www.stat.go.jp/
- 国土交通省 住宅着工統計(2025年版) – https://www.mlit.go.jp/
- 日本銀行 金融政策決定会合議事要旨(2025年7月) – https://www.boj.or.jp/
- 東日本不動産流通機構 市場動向レポート(2025年上期) – https://www.reins.or.jp/
- 経済産業省 グリーン成長戦略進捗レポート(2025年版) – https://www.meti.go.jp/

