不動産投資を始めたいものの「情報が多すぎて何を基準に物件を選べばいいのか分からない」と悩む人は少なくありません。特に初めての投資では、数字の裏付けよりも「なんとなく人気がありそう」という印象に流されがちです。本記事では、収益物件の基礎から人気エリアの見極め方、最新の融資事情までを体系的に解説します。読み終える頃には、「収益物件 選び方 人気」というキーワードに振り回されず、自分の投資目的に合った物件を自信を持って判断できるようになるでしょう。
収益物件の基礎を押さえよう
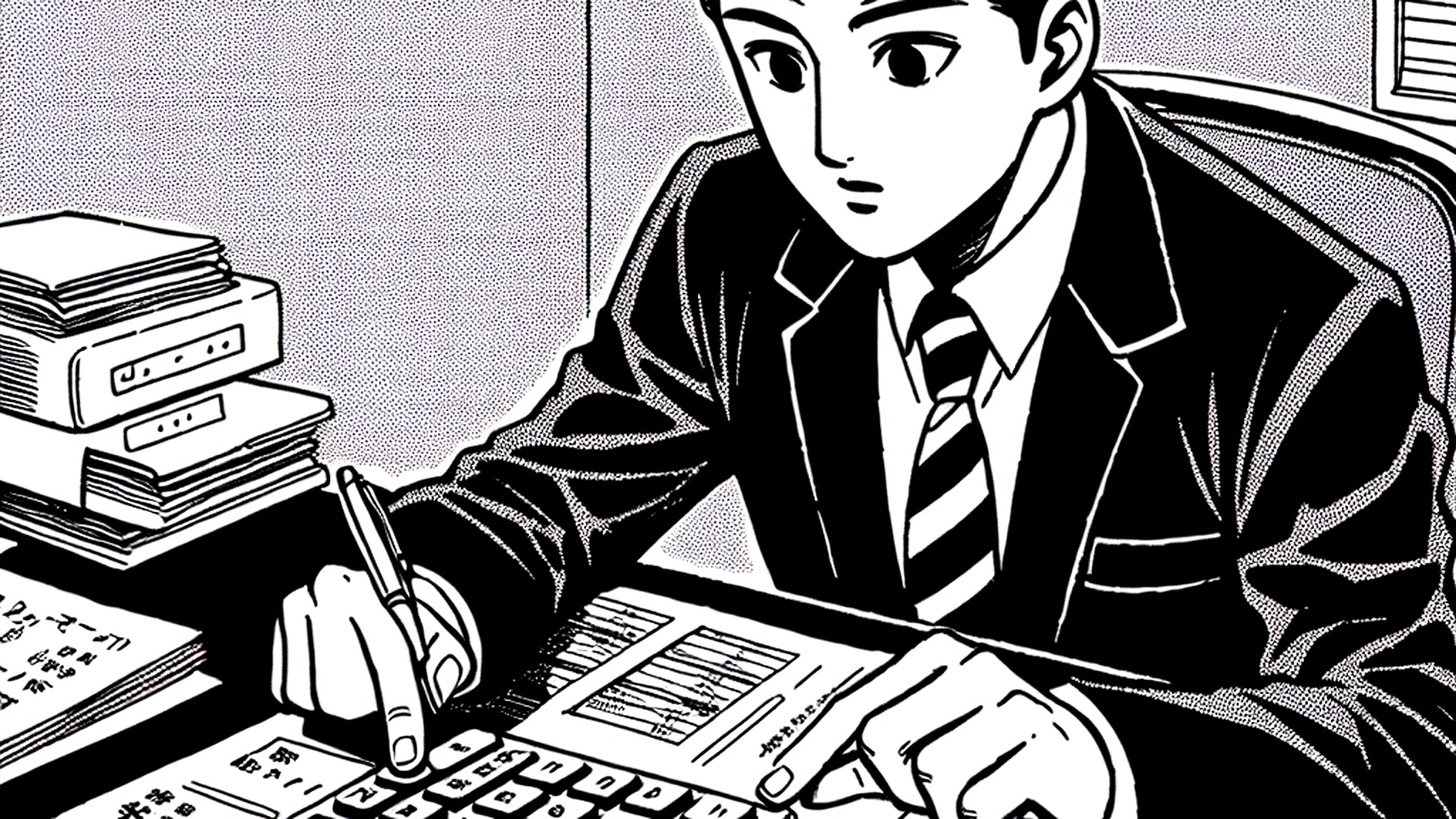
重要なのは、収益物件を「家賃収入を得るための事業用不動産」と定義し、その収支構造を理解することです。家賃という売上に対し、管理費や修繕費、固定資産税が経費として差し引かれ、残った金額がキャッシュフローとなります。この仕組みを把握しないまま立地や利回りだけを見ると、後で手残りが思ったほど残らないという事態に陥ります。
具体的には、年間家賃収入のうちおおむね15%前後が運営コストとして出ていくと考えると計算しやすくなります。また、空室期間を想定した上で利回りを算出しないと、机上の数字と実際の収入に大きな差が生じます。国土交通省の賃貸住宅市場データによると、2024年度の全国平均空室率は約17%でした。つまり、将来の家賃収入を試算する際は、この水準以上の空室を見込んでおくと保守的な資金計画になります。
初心者にありがちなのは、表面利回りだけで判断してしまうことです。表面利回りは「年間家賃÷物件価格」で示され、数字が大きいほど魅力的に見えます。しかし実際には、経費や空室を考慮した「実質利回り」が重要です。実質利回りが6〜7%を超えるかどうかが、安定的な収益ラインと言われています。
人気エリアをどう見極めるか
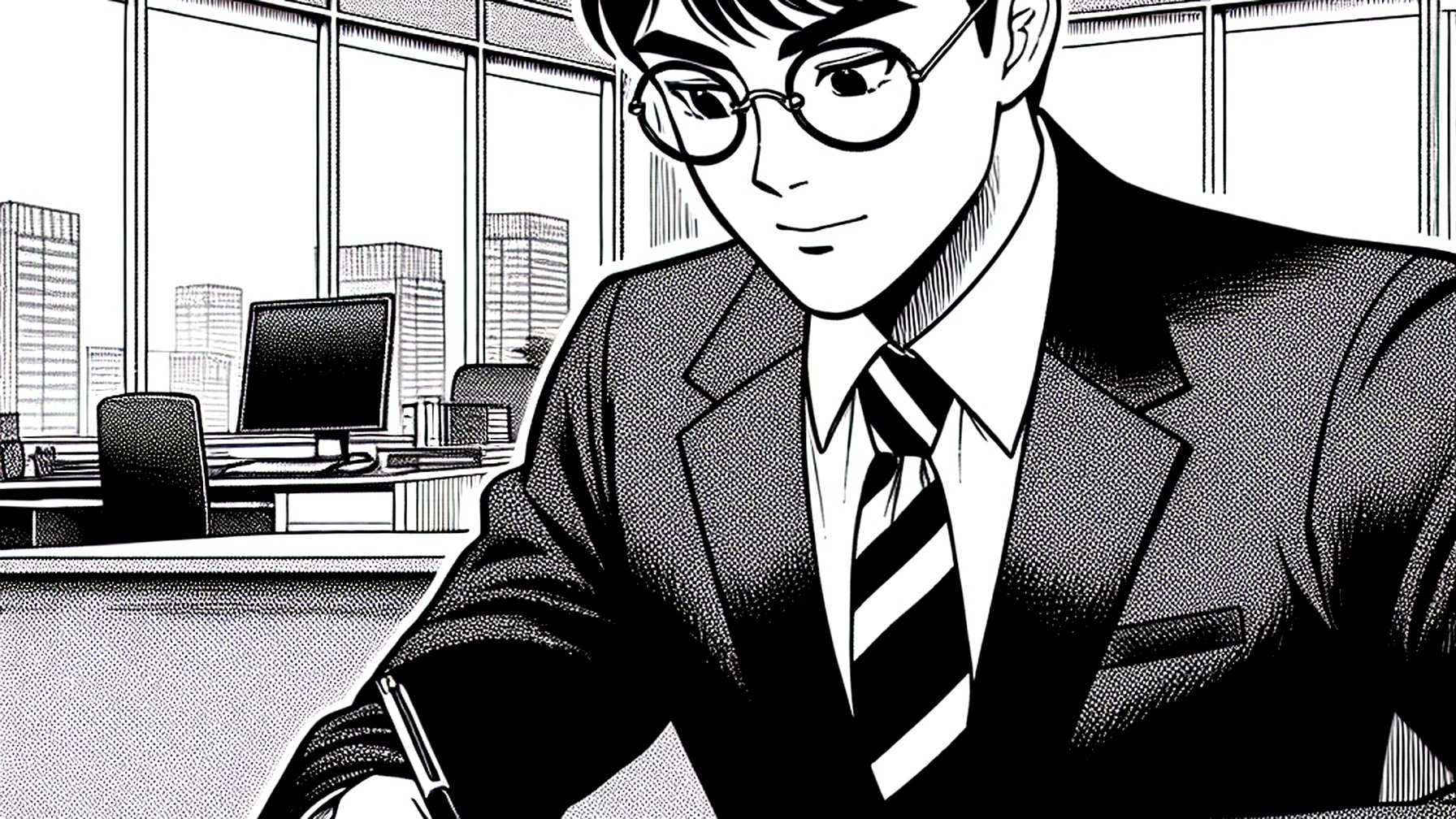
まず押さえておきたいのは、人口動態が家賃需要を左右するという事実です。総務省の「2025年人口推計」では、大都市近郊の人口は微増ないし横ばいで推移する一方、地方都市は減少傾向が続く見込みとされています。つまり、安定した入居需要を望むなら、人口流入が続くエリアに狙いを定めることが重要です。
ただし、都心部は物件価格が高く、利回りが低下しやすいという難点があります。一方で郊外や地方中核都市では、価格の割に賃料が維持されるケースもあり、利回りが確保しやすくなります。たとえば福岡市では、住宅着工件数が増えながらも賃料水準が大きく崩れていません。これは企業の拠点集約や大学進学者の増加が背景にあるためです。
エリア選定では、駅からの距離だけでなく、再開発計画や新線開業の有無にも注目してください。国交省の資料によれば、鉄道延伸が発表された沿線では発表翌年の平均地価が3〜5%上昇する傾向にあります。つまり、今はまだ評価されていない駅前であっても、将来的に需要が伸びる可能性があります。人気エリア探しは「現在の賃貸需要」と「将来の価値向上余地」をセットで考えることがポイントです。
物件タイプ別に見るメリットとリスク
実は、同じエリアでもマンションとアパートではリスクとリターンのバランスが異なります。区分マンションは少額で始められ、管理は管理組合に任せられる点が魅力です。しかし、建物全体の修繕計画に左右されるため、突然の大規模修繕費が収支を圧迫する可能性があります。
一棟アパートは家賃収入が複数戸分あるため、空室リスクを分散できます。また、自分の判断でリフォームや賃料設定を行える自由度も魅力です。反面、自己資金と融資額が大きくなり、金利上昇リスクがダイレクトに響きます。日本銀行が2024年3月に長期金利誘導目標を0.75%へ事実上上限撤廃した影響で、民間金融機関の長期固定金利はじわりと上がっています。2025年9月時点での平均は約2.1%で、わずか0.3%の上昇でも返済総額に数百万円の差が出るため注意が必要です。
また、築古物件は価格が安く利回りが高く見えますが、法定耐用年数を超えると減価償却のメリットが薄れる点に留意しましょう。修繕費が嵩む時期と家賃の下落時期が重なりやすく、資金繰りを圧迫するケースがあります。つまり、物件タイプごとのキャッシュフロー特性を理解し、リスク許容度に合わせて選択することが成功の鍵になります。
キャッシュフローと資金計画の作り方
ポイントは、家賃収入だけでなく、ローン返済や税金まで含めた毎月の手残りをシミュレーションすることです。自己資金は物件価格の20〜30%を用意すると、金融機関の評価が上がり、金利交渉が有利に進みます。さらに、突発的な修繕や退去に備えて家賃の3か月分程度を現預金として確保しておくと安心です。
収支計画を立てる際は、空室率を少なくとも20%、金利を+2%で試算する「ストレステスト」を行いましょう。国交省の家賃傾向調査では、賃料は3年平均で年0.5%程度しか上昇していません。つまり、家賃増加を前提にした楽観的な計画は危険です。家賃が変わらずとも返済負担に耐えられるかが判断基準になります。
税制面では、所得税の節税効果を過大評価しないことも大切です。減価償却による損益通算は初年度が最も大きく、年数が進むにつれて効果が薄れます。2025年度の税制では、不動産所得の赤字と給与所得の通算は継続して認められていますが、今後の議論によっては制限が加わる可能性も指摘されています。だからこそ、節税効果は「おまけ」と考え、あくまでキャッシュフローで採算を取る設計が望ましいのです。
2025年度の制度活用と融資最新情報
まず、2025年度も「住宅ローン減税」とは別に、賃貸用住宅への直接的な国の減税制度は存在しません。ただし、賃貸住宅を長期優良住宅として建築した場合に受けられる固定資産税の減免は継続しています。具体的には、2026年3月末までに新築された長期優良住宅は、固定資産税が5年間半額になります。長期保有を前提とする投資家にとっては、キャッシュフロー改善に直結するため検討する価値があります。
融資面では、地方銀行と信用金庫が中小規模の一棟アパート向け融資に積極的です。金融庁の2024年度金融レポートによると、地域金融機関の不動産向け貸出残高は前年比3.8%増となりました。また、日本政策金融公庫の「新規創業融資制度」は2025年度も継続され、自己資金1割での借入が可能です。新米投資家が小規模からスタートする際に活用できます。
一方で、都市銀行は融資審査をより厳格にしています。賃料下落リスクの説明責任や自己資金比率の引き上げを求める傾向が強まっており、事業計画書の完成度が以前より重視されています。つまり、最新の金利動向だけでなく、金融機関ごとのスタンスを把握した上で交渉する力が、2025年以降の投資家に求められます。
まとめ
ここまで、収益物件の基礎から人気エリアの見分け方、物件タイプごとの特性、資金計画、そして2025年度の制度や融資動向までを解説しました。物件選びで失敗しないためには、表面利回りより実質利回り、現在の需要だけでなく将来の人口動態、そして金利上昇も織り込んだ資金計画が欠かせません。今後は情報に振り回されるのではなく、自分の投資目的とリスク許容度を軸に判断していきましょう。今日得た視点をもとに、まずは気になるエリアの空室率を調べ、一件でも多く物件を実地で見学することから行動を始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 人口推計(2025年) – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp
- 金融庁 2024年度金融レポート – https://www.fsa.go.jp
- 日本政策金融公庫 新規創業融資制度 – https://www.jfc.go.jp

