個人や法人で小規模オフィスビルに投資したいものの、「いったい自分はいくらまで借りられるのか」と悩む人は多いでしょう。居住用アパートと異なり、事務所物件は空室リスクや景気変動の影響が大きいため、金融機関の審査基準も一段厳しくなります。そこで本記事では、事務所 不動産投資ローン 借入限度額をテーマに、最新の金融動向と計算方法、そして限度額を引き上げる実践的なコツまで丁寧に解説します。読み終える頃には、自分の投資計画に合わせた安全な融資枠がイメージできるはずです。
事務所用物件への融資は何が違うのか

まず押さえておきたいのは、事務所物件の融資では「収益安定性」が住宅系より重視される点です。テナント契約は通常3年更新で、景気悪化時に一気に退去が重なる可能性があります。そのため金融機関は、想定賃料の下落リスクを割り引いて評価し、結果として借入限度額が低めに設定されがちです。
一方、耐用年数の長さはプラスに働きます。鉄筋コンクリート造のオフィスビルは法定耐用年数47年で、木造アパートの22年より長い分、返済期間を伸ばしやすくなります。ただし築古の場合は残存耐用年数を超える返済期間を認めない銀行もあるため、購入前に建築年と併せて確認が欠かせません。
加えて、事務所では共益費や電気料金の預かりが収入に含まれない点に注意が必要です。家賃部分だけで返済比率を計算されるため、見かけの利回りほど借入余地が伸びないことがあります。つまり、ファミリー向けマンションと同じ感覚でシミュレーションすると、いざ審査で減額されるケースが少なくありません。
借入限度額を左右する三つの視点
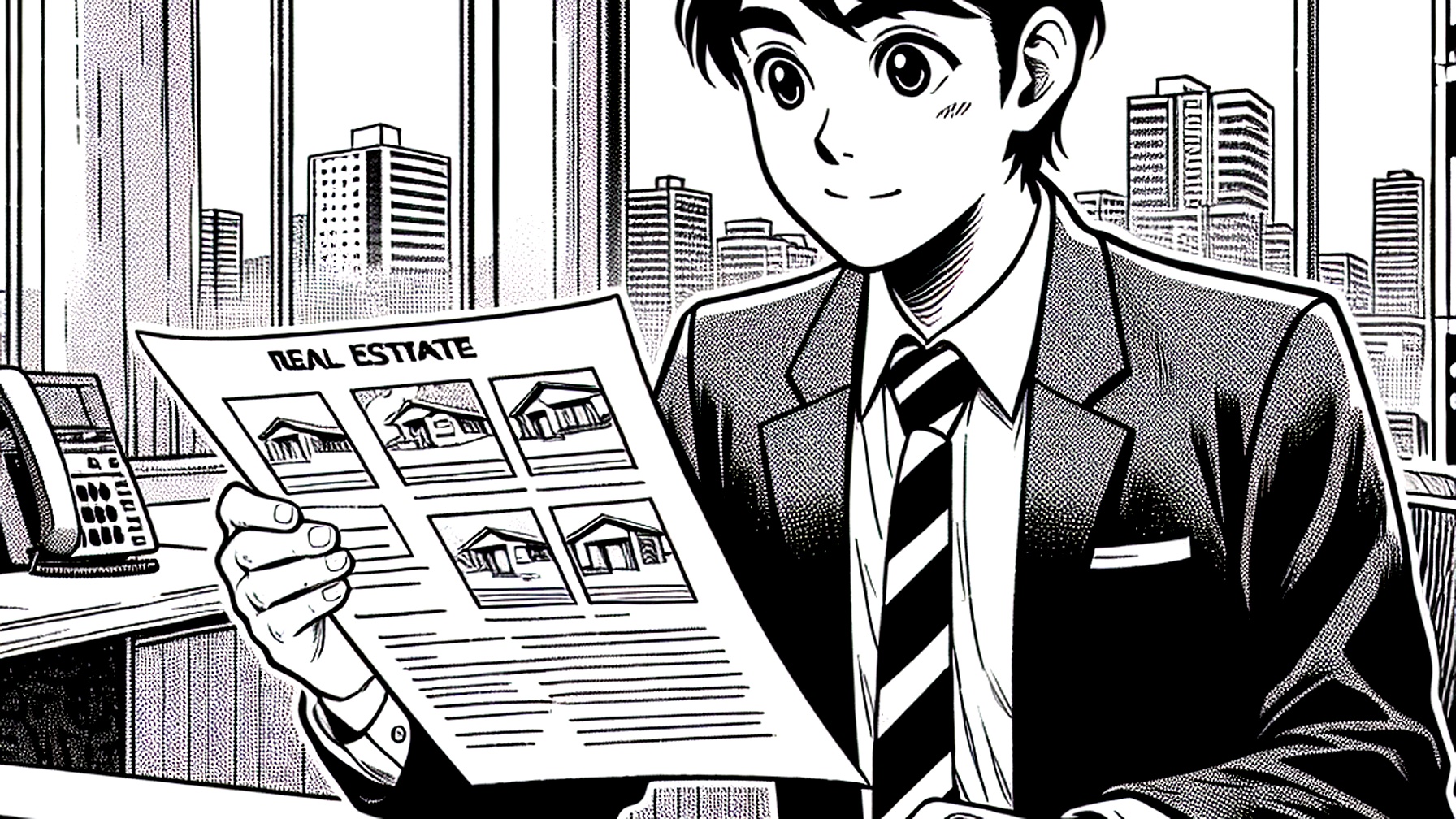
ポイントは「物件収益力」「担保評価」「個人・法人属性」の三層チェックです。金融機関はまず、満室想定賃料から空室率10〜20%を控除し、そこから経費20%前後を差し引いて純収益を算出します。この純収益が返済額の1.2〜1.3倍をカバーするかどうかが一つ目のハードルとなります。
次に担保評価では、国土交通省の不動産価格指数や近隣成約事例をもとに「積算法」と「取引事例比較法」を併用し、通常は低い方の評価額を採用します。評価額の70〜80%が融資上限となるため、表面利回りが高くても路線価が低いエリアでは限度額が縮む点を覚えておきましょう。
最後に個人あるいは法人の信用力です。金融庁の「2025年度金融モニタリング基本方針」では、不動産業向け融資の健全性を確保するため、自己資本比率や返済原資を重視するよう銀行に求めています。そのため年収や自己資金が厚いほど、あるいは法人決算で安定黒字を示せるほど、同じ物件でも借入余地が広がります。
2025年度の金利水準と金融機関の最新スタンス
実は、金利動向は借入限度額の試算にも影響します。全国銀行協会の2025年9月レポートによると、オフィス投資向け変動金利は年1.7%前後、固定10年は2.7%前後で推移しています。金利が0.3%上がると、同じ返済額で借入可能額は約5%減少するため、金利トレンドを見逃せません。
また、メガバンクは大型案件を主に扱い、自己資金30%以上を求める傾向が強まっています。一方で地方銀行や信用金庫は、地域活性化の観点から小規模オフィスへの融資に積極的です。特に店舗兼事務所など地元企業が需要を支える物件では、自己資金20%でもフルに評価する事例が増えています。複数行に同時打診して、金利・期間・最大融資額を比較する姿勢が重要です。
政府系金融機関である日本政策金融公庫は、コワーキングスペースなど新事業創出に資する投資に対し、2025年度も通常より0.2%低い特例利率を継続中です。ただし運営実績や利用者見込みを綿密に聞かれるため、事業計画を数値裏付け付きで示す必要があります。
借入限度額を引き上げる具体策
まず、自己資金を増やすのが王道です。頭金を物件価格の10%から20%に上げるだけで、返済比率が改善し、最大融資額が15〜20%伸びるケースは少なくありません。また、同物件内に自社オフィスを一部入居させる「オーナー使用」形態にすると、事業性と自家使用を兼ねたローン商品が利用でき、金利が0.1〜0.2%下がることもあります。
保証協会付き融資を活用する方法もあります。東京都や大阪府など一部自治体では、2025年度も中小企業向け「建物取得資金特別保証」を実施しており、保証料の一部補助が受けられます。期間は最長20年、保証割合80%が上限ですが、金融機関にとってはリスクが軽減されるため、融資枠を広げやすい制度です。期限付きのため、利用を検討するなら早めの相談が欠かせません。
さらに、物件のエネルギー効率を高めると評価額がアップします。国交省の調査では、BELS(建築物省エネルギー性能表示)星3以上を取得した中小規模オフィスは、周辺同等物件より賃料が平均7%高い結果が出ています。金融機関は将来キャッシュフロー改善を見込める物件を好むため、設備更新費用を含めて一体融資を依頼すると、総額が増えても返済年数を延ばせる可能性があります。
シミュレーションで見る安全な借入ライン
ここでは、築15年・延べ床500㎡の地方中核都市オフィスを例に、借入限度額を算出してみます。想定賃料は月額270万円、平均空室率15%、運営経費25%とすると、年間純収益は約2,070万円です。返済余力判定で元利金がこの80%以内に収まるよう設定し、変動金利1.8%・期間25年で試算すると、借入限度額はおよそ2億8,000万円となります。
しかし、担保評価が取引事例比較法で2億5,000万円しか出なければ、融資上限は評価額の80%である2億円となり、前述の返済余力は満たすものの、最終的な限度額は2億円に制限されます。ここに自己資金5,000万円を加えて総額2億5,000万円の物件取得が成立するイメージです。
一方で、低金利局面を狙って固定10年2.6%を確定させ、返済期間を30年に伸ばすと、同じ年間返済額で最大2億2,000万円まで借入枠が拡大します。ただし金利上昇期の再固定時に月々負担が跳ね上がらないか、複数シナリオで予測しておくことが欠かせません。言い換えると、限度額の上限イコール安全ラインではなく、長期キャッシュフローの余裕を優先すべきです。
まとめ
事務所物件の不動産投資ローンでは、収益力・担保評価・信用力という三つの視点が重なり合って借入限度額が決まります。2025年時点の平均金利はまだ低水準ですが、評価額の天井や自己資金割合によっては、想定より枠が縮む場面も珍しくありません。だからこそ、複数行比較と制度活用で条件を引き上げつつ、保守的なキャッシュフロー計算を行う姿勢が成功の鍵となります。まずは簡易シミュレーションを作成し、最低でも年間純収益の20%は余裕資金として残す計画を立てることをおすすめします。安全な借入ラインを見極め、将来の拡大戦略への布石を打っていきましょう。
参考文献・出典
- 全国銀行協会 – https://www.zenginkyo.or.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 2025年度金融モニタリング基本方針 – https://www.fsa.go.jp
- 日本政策金融公庫 融資情報 – https://www.jfc.go.jp
- 東京都産業労働局 中小企業向け保証制度 – https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp

