不動産投資に興味はあるものの、「何から始めればいいのか分からない」「失敗したら怖い」と感じていませんか。特に収益物件は価格も大きく、購入後の管理まで視野に入れる必要があります。本記事では、15年以上の投資経験を踏まえつつ、初心者でも迷わず実践できる購入手順を整理し、2025年9月時点で考えるべきメリット・デメリットを丁寧に解説します。読み終えるころには、自分に合った物件を選び、リスクを抑えながら収益を最大化する具体策がイメージできるでしょう。
収益物件とは何かと市場動向
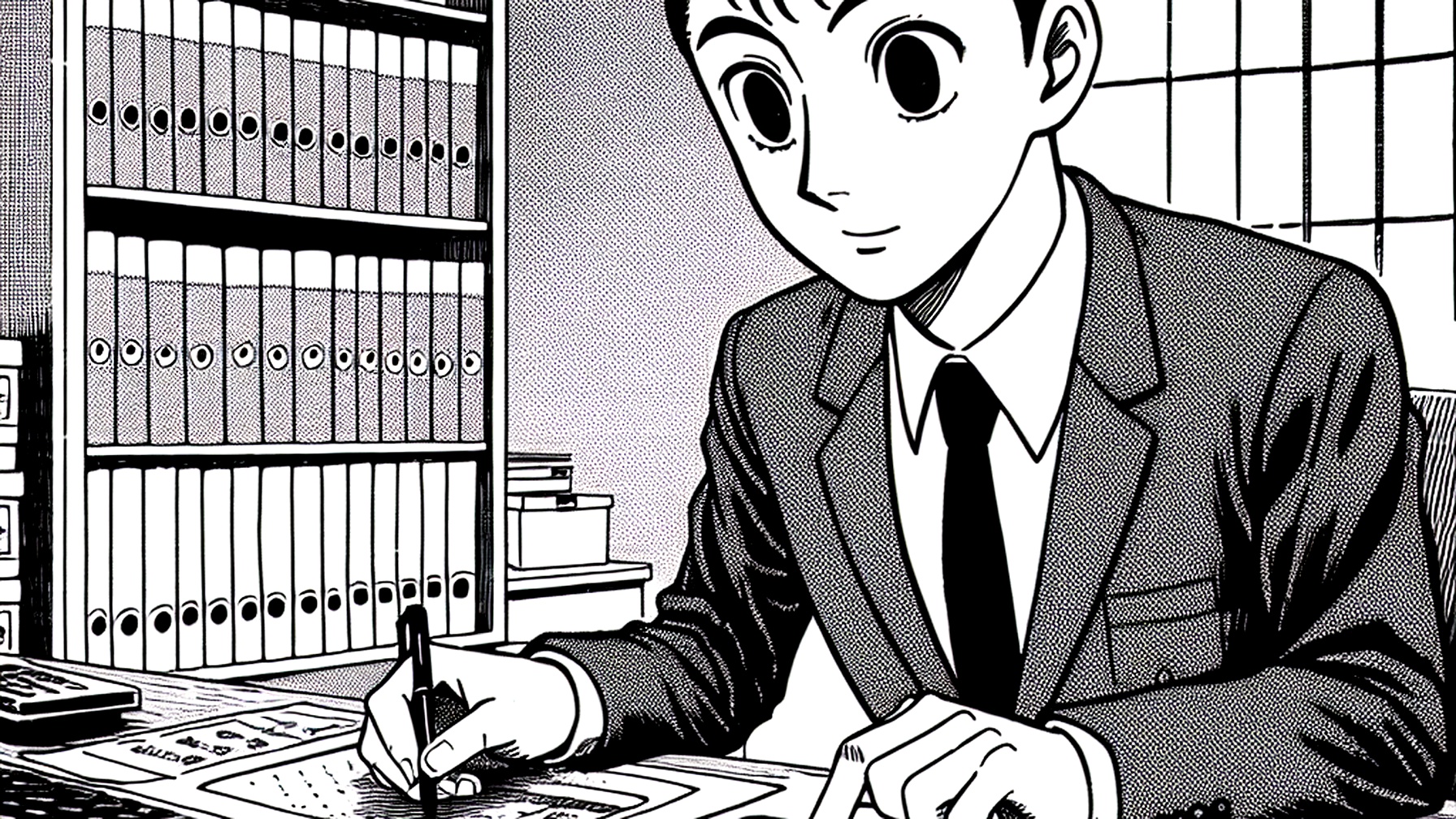
まず押さえておきたいのは、収益物件が家賃収入や転売益を目的として購入される不動産である点です。国土交通省が2025年6月に発表した不動産価格指数によると、全国の住宅系物件は前年同月比で4.2%上昇し、特に大阪・福岡など中規模都市の伸びが顕著でした。つまり地方中枢都市も視野に入れた戦略が必要になります。
一方で、人口減少が進むエリアでは空室率が高止まりしています。総務省「住宅・土地統計調査」2023年速報値を基に推計すると、2025年時点の全国平均空室率は13.8%ですが、郊外の一部では20%を超えます。ここから分かるのは、単に表面利回りが高いだけで飛びつくと、入居者が集まらずキャッシュフローが崩れる危険があるという事実です。
投資家にとって重要なのは、こうしたデータを踏まえつつ将来の賃貸需要を見極めることに尽きます。市場動向の読み取りは難しく感じるかもしれませんが、後述する購入手順に沿って情報を整理すれば、根拠のある判断が可能になります。
購入手順を押さえる
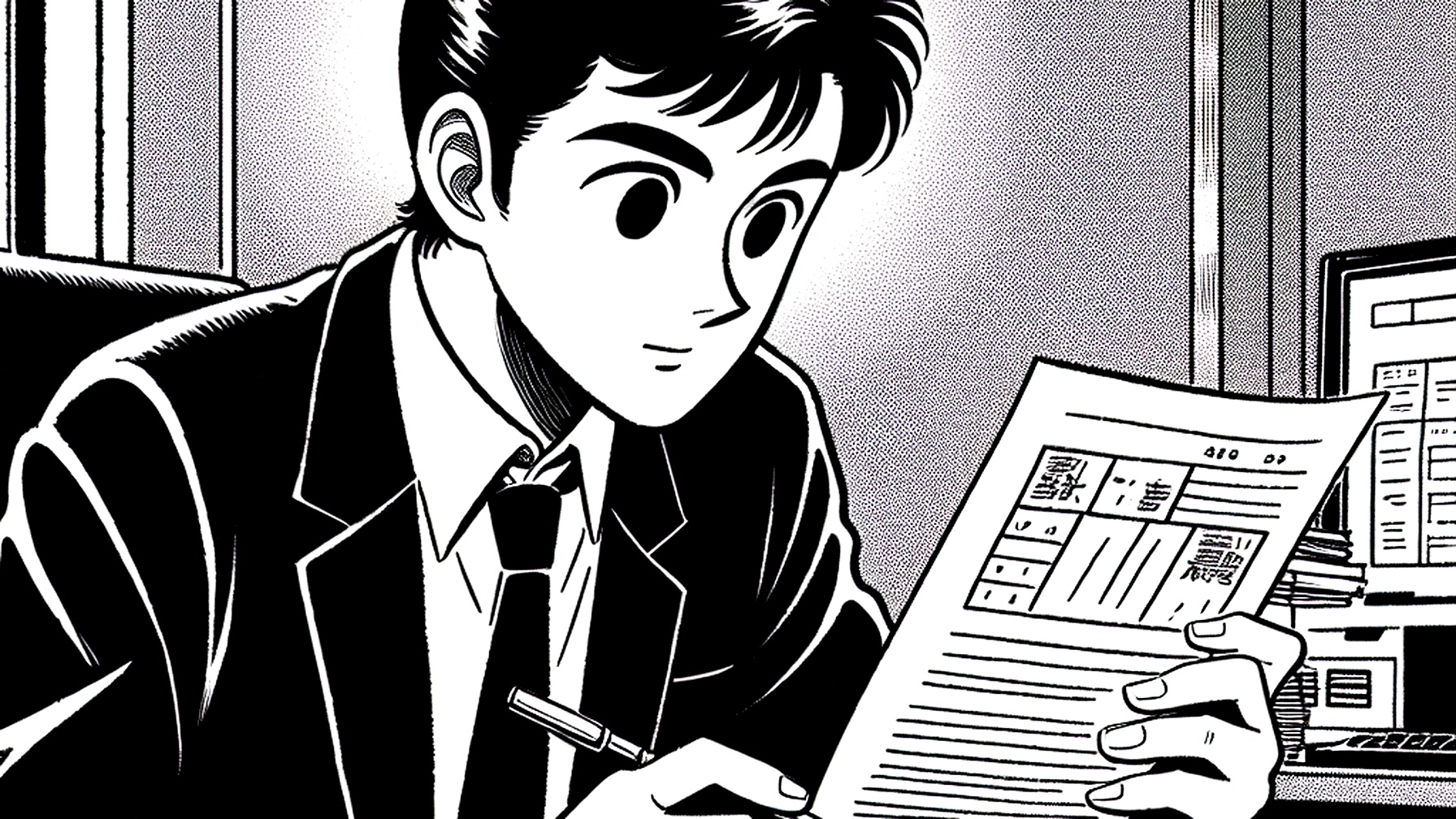
ポイントは、物件探しより前に資金計画と目的設定を固めることです。金融機関は、自己資金の20〜30%を投入し、年間家賃収入の30〜40%を返済原資にする計画を好みます。したがって資金繰りの目安を把握してから、エリアや物件タイプを絞り込む流れが王道です。
次に物件調査では、レントロール(入居状況表)と過去2年分の修繕履歴を必ず確認します。ここで家賃の滞納率や修繕費の推移が分かれば、利回りの実質感がつかめます。また固定資産税評価額と実勢価格の差を調べておくと、将来の売却益を試算しやすくなります。
買付申込書を提出した後は、金融機関に事前審査を申し込みます。2025年時点では、ネット銀行であっても面談を求めるケースが増えており、事業計画書の提出が事実上必須です。計画書には、空室率20%・金利上昇1.5ポイントのシナリオでも黒字化する試算を盛り込むと説得力が高まります。
最後に重要なのは、売買契約と同時に管理体制を決めることです。自主管理を選ぶ場合でも、退去立会いと緊急対応だけは外部委託すると、時間的な負担が大幅に減ります。この一手間が、購入後のストレスを軽減し、長期保有のモチベーションにつながります。
投資メリットを具体的に理解する
実は収益物件の魅力は、「毎月の家賃収入」だけにとどまりません。第一に、ローン返済を入居者が肩代わりしてくれる仕組みになりやすい点が挙げられます。元本が減るたびに純資産が増えるため、10年後に売却益が期待できるのは大きな利点です。
第二に、減価償却費を経費計上できるため、実際のキャッシュアウトよりも小さい所得で税金が計算されます。国税庁の所得税基本通達によれば、木造アパートなら22年、RC造マンションなら47年という法定耐用年数が目安になり、短期的な節税効果が得られます。言い換えると、自己資金を温存しつつ手元資金を次の投資へ回せるわけです。
さらに、インフレ対策としての側面も見逃せません。物価が上昇した場合、家賃も連動して上がる可能性があります。過去10年間の消費者物価指数(CPI)は年平均1.2%の上昇ですが、同期間の都心部ファミリー物件の平均募集家賃は1.6%上がりました。物価を上回る賃料アップが実現すれば、実質資産価値の目減りを防げます。
最後にレバレッジ効果があります。仮に自己資金500万円で3000万円の物件を購入し、表面利回り8%を確保できれば、自己資金ベースの利回りは約48%になります。高い利回りを維持できれば、複利的に資産を拡大できる点が他の金融商品にはない醍醐味です。
覚えておきたいデメリットと対策
一方で、収益物件にはリスクも存在します。まず空室リスクですが、地方の築古アパートで顕著です。対策として、駅から徒歩10分以内、築20年以内など明確な基準を設けると、募集期間が短くなりやすいです。また入居者属性を分散させることで、景気変動の影響を受けにくくできます。
次に修繕リスクがあります。屋上防水や給水管交換など大型修繕は一度に数百万円かかります。購入前に長期修繕計画を作成し、月々の家賃から1戸あたり3000円程度を修繕積立に回す習慣を付けておくと安心です。
金利上昇リスクも忘れられません。日本銀行は2024年3月にマイナス金利政策を解除し、2025年は長期金利が1.2%前後で推移しています。変動金利の借入比率を50%以下に抑え、返済比率を家賃収入の40%以内に収めると、金利上昇2ポイント程度まで耐えるシミュレーションが立ちやすいです。
最後に流動性リスクがあります。株式と違い、売却まで数か月かかるのが一般的です。しかし、物件情報を整理したレポートを事前に作成し、仲介会社とのネットワークを広げておけば、急な売却でも価格交渉を優位に進めやすくなります。
2025年時点で活用できる支援策と税制
重要なのは、制度を味方につけて投資効率を高めることです。2025年度の住宅ローン控除は、自ら居住する住宅が対象ですが、併用住宅(1階店舗2階住居など)で居住部分が延床面積の50%以上なら一部控除が可能です。投資と自宅を兼ねるケースでは検討する価値があります。
2025年度も継続する中小企業経営強化税制では、法人が一定の耐用年数が残る中古物件を取得し、省エネ改修を行えば特別償却や税額控除が受けられます。法人化を視野に入れる投資家にとって、キャッシュフローを押し上げる有効な手段になります。
さらに、自治体独自の空き家活用補助金も見逃せません。例えば福岡市は2025年度、賃貸用リノベーション費用の3分の1(上限100万円)を支援しています。各自治体で条件が異なるため、購入前に必ず公式サイトで最新情報を確認しましょう。
税制面では、青色申告特別控除65万円が不動産所得にも適用されます。複式簿記で帳簿を付けるだけで大きな節税になるため、会計ソフトを導入して手続きを簡素化すると負担が軽減されます。
まとめ
本記事では、収益物件の購入手順からメリット・デメリット、2025年時点で利用できる支援策までを網羅的に整理しました。資金計画を先に固め、エリア選定と物件調査を徹底すれば、リスクを抑えながら安定収入を目指せます。さらに、減価償却や青色申告などの制度を活用することで手元資金を守り、次の投資につなげる好循環が生まれます。まずは、自己資金と返済比率のシミュレーションを行い、現地調査へ一歩踏み出してみてください。その行動が、将来の堅実な資産形成への第一歩となります。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 2025年6月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 2023年速報 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 2025年7月 – https://www.boj.or.jp
- 国税庁 所得税基本通達 第7章 不動産所得 – https://www.nta.go.jp
- 福岡市 空き家活用補助金 2025年度要綱 – https://www.city.fukuoka.lg.jp

