高い利回りを求めてREIT(不動産投資信託)へ資金を振り向けたものの、「分配金が思ったほど伸びない」「市場全体の利回りが低下している」と感じている経験者は少なくありません。2025年9月時点でJ-REIT平均分配金利回りはおよそ3.6%と、10年前よりも約0.8ポイント低下しています。それでも個別銘柄を精査し、税制やコストを最適化すれば、ネット利回り4%台を維持することは十分に可能です。本記事では、市場環境の読み解き方からポートフォリオの組み替え、税金と手数料の見直しまで、経験者が直面しやすい課題を解決しながら利回りを高める実践的手法を解説します。
REITの利回りを再確認しよう
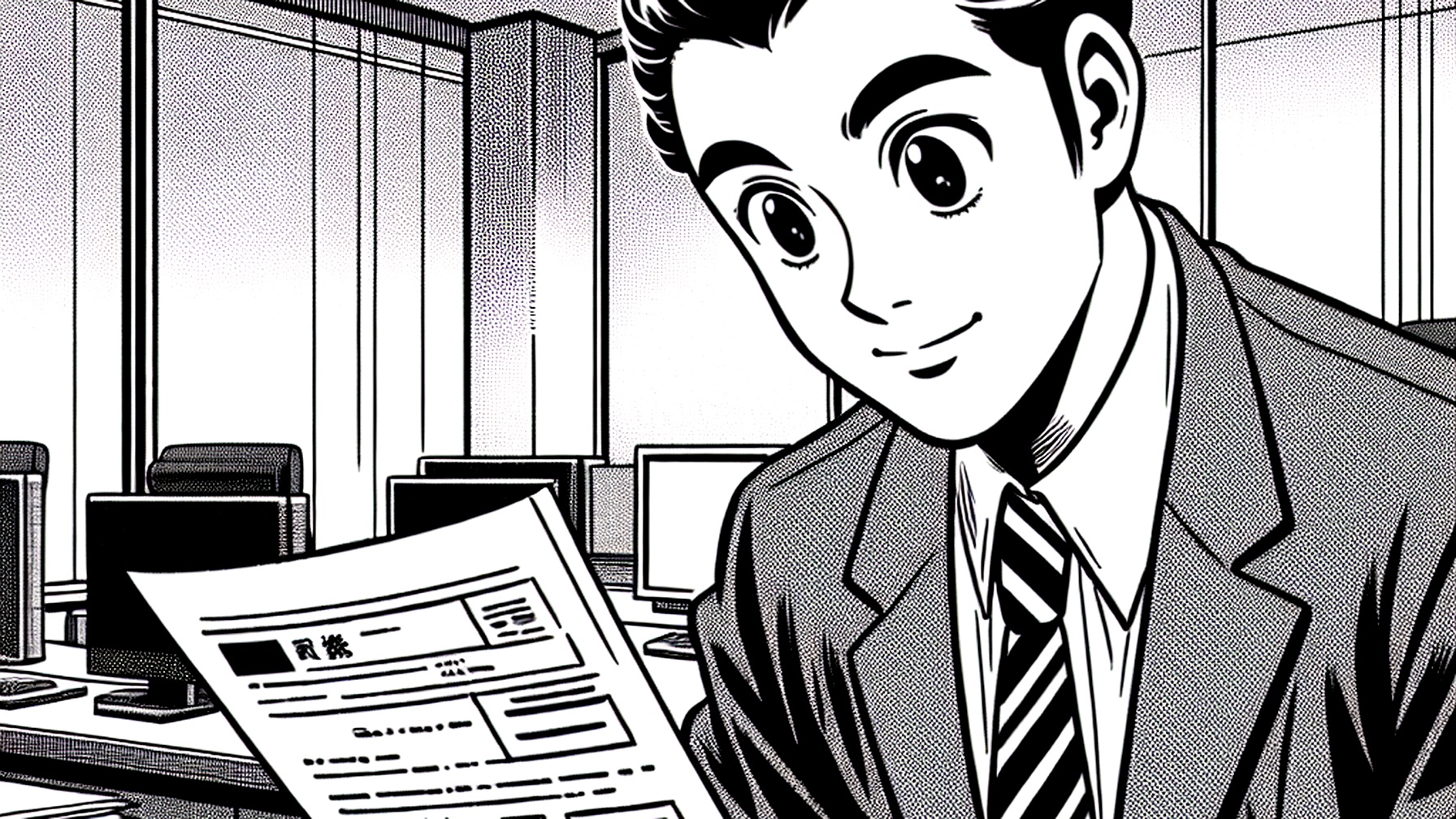
重要なのは、表面利回りとネット利回りを区別して評価することです。表面利回りは株価に対する年間分配金の割合を示す単純指標ですが、実際の手取りを測るには税金や諸経費を差し引いたネット利回りを用いる必要があります。
まず総合課税口座でREITを保有すると、分配金には約20%の源泉徴収がかかります。新しいNISA口座を活用できる場合、年間360万円の成長投資枠で買い付けた分については非課税となり、単純にネット利回りが2割向上します。また証券会社の口座管理料はゼロ化が進んでいますが、信託報酬(運用手数料)は年0.1〜0.5%程度と銘柄で差が大きい点に注意が必要です。
具体例として、表面利回り3.8%、信託報酬0.3%の銘柄を課税口座で保有すると、ネット利回りは3.8%×0.8−0.3%=2.74%に下がります。一方、NISA口座で同じ銘柄を保有すれば、3.8%−0.3%=3.5%まで改善します。つまり非課税枠の活用だけで、実質利回りが0.76ポイント跳ね上がる計算になります。
市場環境と分配金利回りの関係
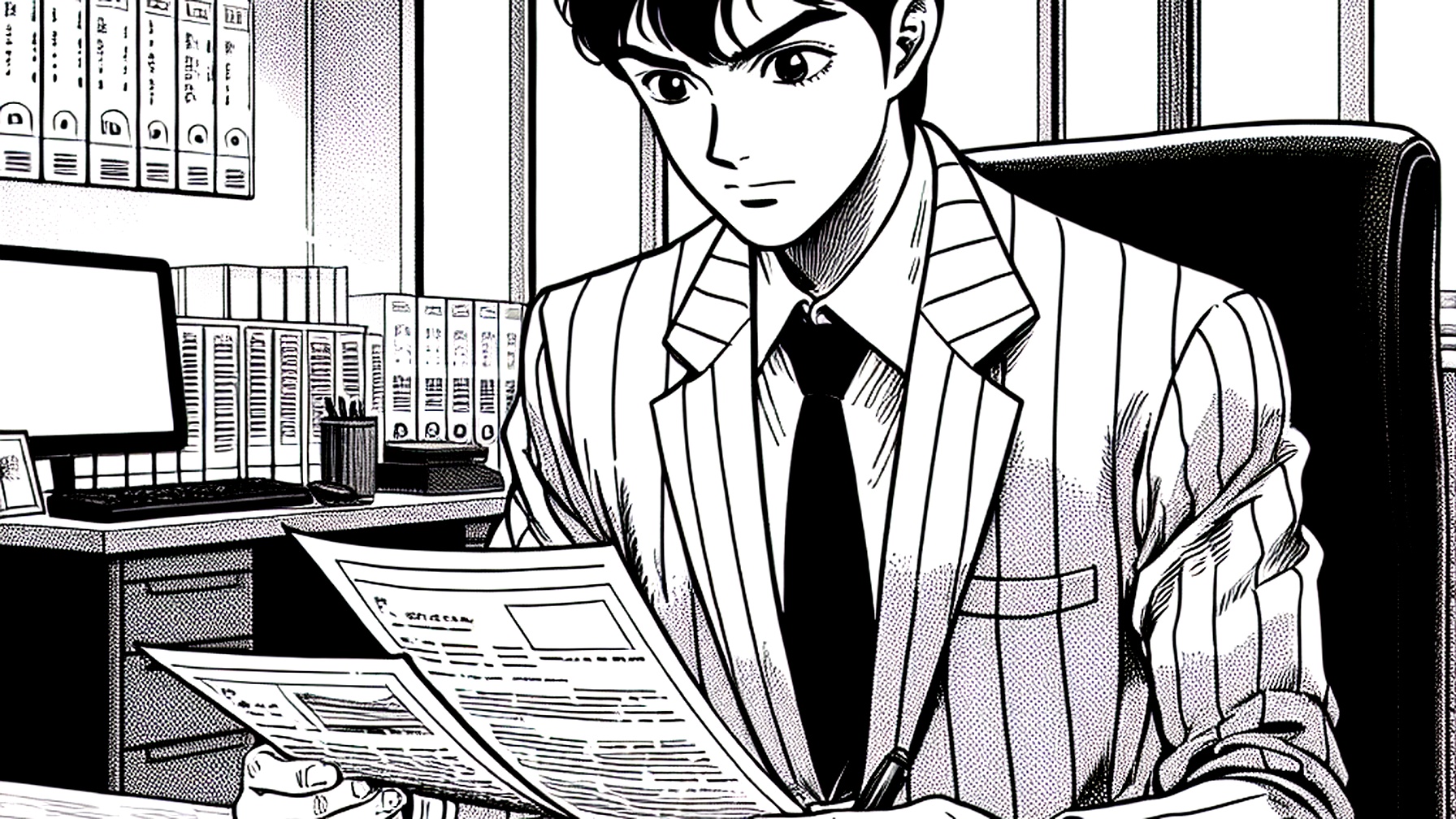
まず押さえておきたいのは、分配金利回りが長期金利と逆相関する点です。日本銀行がYCC(イールドカーブコントロール)を柔軟化した2024年以降、10年国債利回りは1%前後で推移しています。過去のデータを見ると、国債利回りが0.5%上昇するとJ-REIT価格は平均7%程度下落し、その結果表面利回りは約0.3ポイント上昇する傾向にあります。
しかし、金利上昇局面ではオフィス系REITよりも物流・住居系REITの分配金が相対的に安定する傾向が強いです。国土交通省の2025年地価LOOKレポートによると、東京湾岸の物流施設賃料は前年同期比で4.5%上昇し、賃料収入の増加が分配金を下支えしています。また住居系は賃料改定周期が短いため、インフレを転嫁しやすい点も強みです。
このように、ファンダメンタルズに強いアセットタイプへ資金を寄せることで、分配金の減少リスクを抑えつつ利回りを底上げできます。つまり金利動向とアセット特性を組み合わせて読むことが、経験者にとっては欠かせない視点になります。
利回り向上に効く物件ポートフォリオ分析
実は、銘柄分散よりも「物件タイプと地域」の分散が利回りに与えるインパクトは大きいです。たとえば物流特化型REIT AとBを組み合わせても、賃料下落リスクは根本的に減りませんが、物流とヘルスケアを組み合わせれば景気変動への耐性が向上します。
日本不動産研究所が2025年9月に公表したデータでは、東京23区のオフィス空室率は5.9%、一方で高齢者施設の空室率は2.3%にとどまりました。オフィス系REITの分配金が横ばいで推移する中、ヘルスケア系REITは前年同期比で平均4%の分配金成長を記録しています。こうした数字を踏まえ、キャッシュフローの伸長が期待できるアセットを厚めに組み入れると、ポートフォリオ全体のネット利回りが底上げされます。
また地域分散も重要です。大阪市中心部のオフィス賃料は2025年上期に2.1%下落しましたが、福岡市天神地区は1.8%上昇しました。単一都市に集中しているREITを複数保有している場合は、地域分散の観点から組み換えを検討する余地があるでしょう。
税制とコスト最適化でネット利回りを守る
ポイントは、制度を理解して手取りを減らさないことです。2025年度も適用される「投資法人課税特例」により、J-REITは利益の90%以上を分配すると法人税が実質免除されます。しかし投資家側では所得税・住民税が課されるため、前述のNISAやiDeCoの活用が効果的です。
さらに、信用取引でREITを買い建てる場合の金利・貸株料は年2%前後に達します。単純に配当取りを狙うと逆ザヤになりやすいので、長期保有なら現物に絞った方が無難です。加えて、分配金再投資時の売買手数料が何度も発生すると、年0.2%程度ネット利回りを削ります。証券会社によっては「DRIP(分配金自動再投資)」機能が無料で提供されており、手数料を抑えつつ複利効果を享受できます。
最後に、為替ヘッジコストにも注目しましょう。外貨建てREIT ETFを組み入れる際、2025年9月のヘッジコストは米ドルで年1.4%前後です。表面利回りが5%でも、ヘッジ後に3.6%へ低下するので、国内REITと比較した場合の実質利回りを必ず確認してください。
2025年度の注目テーマ型REITとリスク管理
まず押さえておきたいのは、テーマ型REITの利回りが高いからといってリスクが低いわけではない点です。再生可能エネルギー施設に投資するインフラファンド型REITは表面利回り6%超が目立ちますが、売電価格やFIT(固定価格買取制度)期間終了後の収益不確実性が潜在リスクです。
一方で、データセンター特化型REITは分配金成長率が年5%前後と高く、総務省の通信量統計でもデータトラフィックは毎年20%以上増加しています。ただし土地取得コストが高騰しており、LTV(負債比率)が60%を超える銘柄も散見されます。過度なレバレッジは金利上昇局面で分配金を圧迫するので、財務指標のチェックが欠かせません。
リスク管理のためには、①テーマ型を全体の3割以内に抑える、②LTV50%以下の銘柄を中心に組む、③金利スワップや借換え期限をIR資料で確認する、といった手順が有効です。これらを徹底すれば、景気後退や金利ショックが起きてもネット利回りを大きく毀損せずに済みます。
まとめ
ここまで、経験者がREIT投資でネット利回りを高めるための視点を解説しました。表面利回りだけでなく税金・手数料を差し引いた実質利回りを基準にし、市場金利とアセットタイプの相関を読み解きながらポートフォリオを最適化することが鍵となります。さらに、2025年度も有効なNISA非課税枠や投資法人課税特例を活用し、テーマ型REITを適切な割合で組み込めば、金利上昇局面でも4%台のネット利回りは十分狙えます。まずは保有銘柄の信託報酬とLTVを洗い出し、非課税口座への移行や銘柄組み替えを実行してみてください。行動を一歩進めることで、REIT投資の収益力は着実に向上します。
参考文献・出典
- 一般社団法人不動産証券化協会(ARES) – https://www.ares.or.jp
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省 地価LOOKレポート – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 通信利用動向調査 – https://www.soumu.go.jp

