マンション投資に興味はあるものの、「本当に儲かるのか」「失敗したら怖い」と迷っている方は多いでしょう。私も数年前までは同じ悩みを抱えていました。しかし実際に一歩を踏み出し、購入から運用、売却まで経験したことで見えてきた現実があります。本記事では、その生々しい体験を基に、資金計画や空室対策、税務処理までを初心者にも分かりやすく解説します。読むことで、メリットとリスクの両方を理解し、自分に合った投資判断ができるようになるはずです。
マンション投資を始めたきっかけと物件選びの軸
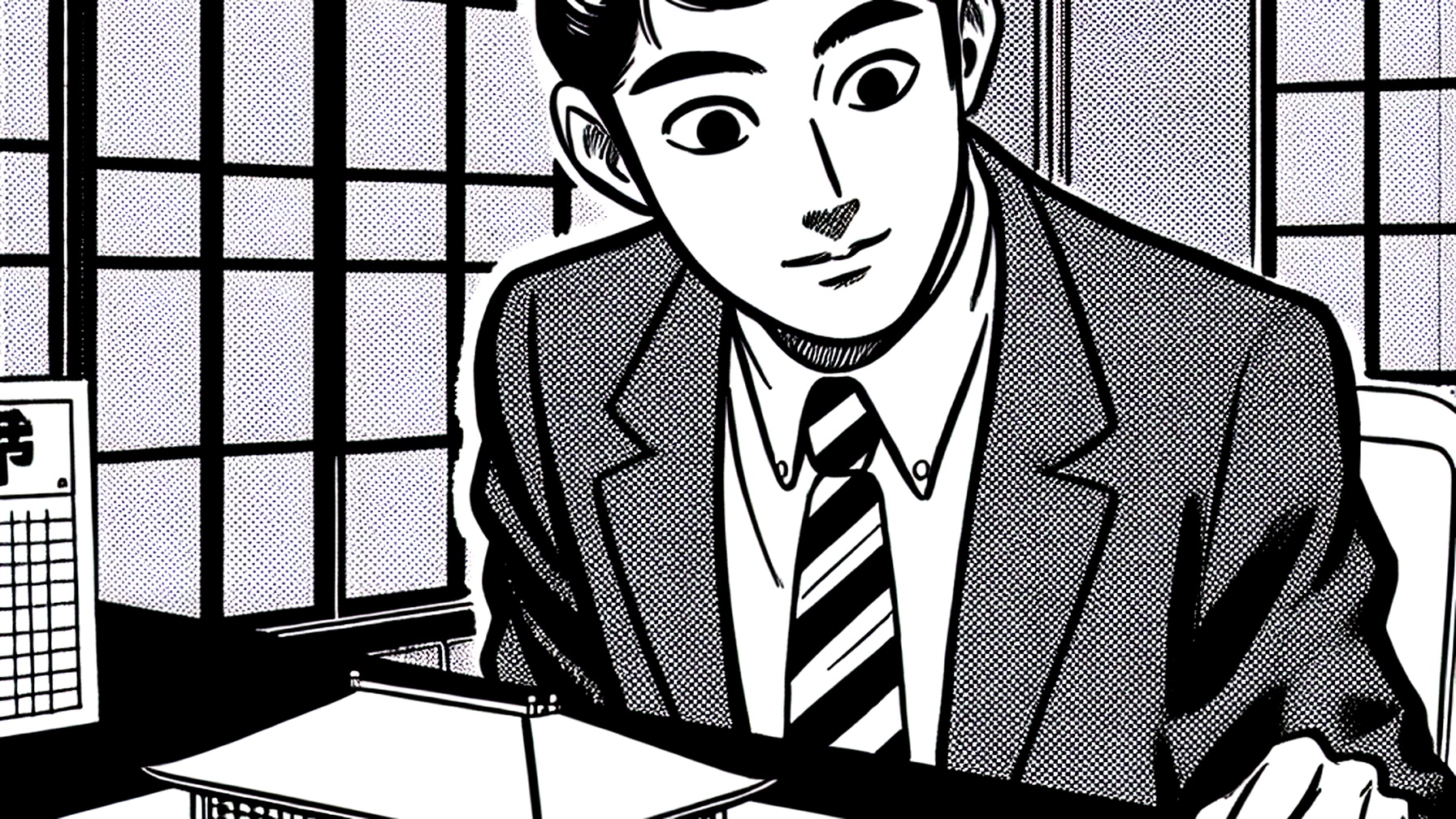
ポイントは、最初に「なぜ始めるのか」を明確にし、目的に沿った物件を選ぶことです。私は会社の先輩から「給与以外の収入源を持とう」と助言され、老後の年金補完を目的に投資を検討しました。
まず、都心か郊外かで迷いました。東京23区の新築マンション平均価格は2025年9月時点で7,580万円と高額です(不動産経済研究所調べ)。一方、郊外なら4,000万円前後でもファミリータイプが狙えます。私は初期投資を抑えつつ、賃貸需要が底堅い「駅徒歩5分・築10年以内・30㎡以上」という条件を重視しました。結果として、世田谷区の中古ワンルーム(2,980万円)をフルローンで取得しました。
選定の決め手は、周辺人口の増減と賃料相場です。国勢調査の小地域データを確認すると、対象エリアの20〜40代人口が緩やかに増加しており、家賃下落リスクが低いと判断できました。つまり、購入前に公的データで需給を確認する作業が、後悔しないための第一歩になります。
初購入で痛感した資金計画と融資条件
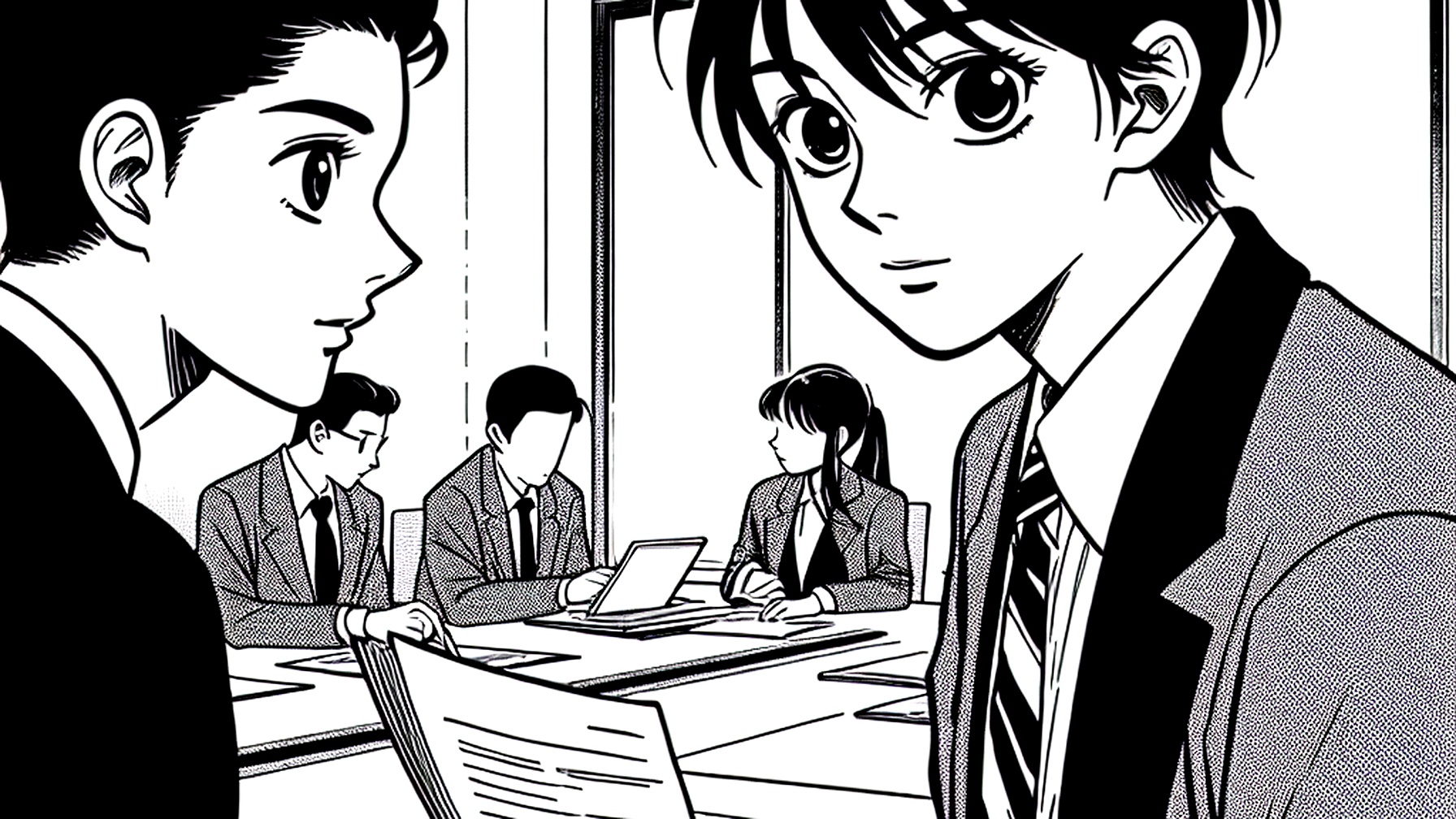
まず押さえておきたいのは、物件価格だけでなく諸費用を含めた総額に目を向けることです。私の場合、購入諸費用として登記費用や仲介手数料、火災保険などで約200万円が追加で発生しました。
融資は都市銀行を中心に3社を比較しました。最終的に金利1.9%、期間35年、フルローンで契約できたのは、自己資金として購入総額の10%を普通預金に残していたことが評価されたからです。金融機関は返済能力と同時に手元流動性を重視します。そこで、生活防衛費とは別に100万円の予備資金を確保し、万一の修繕や空室時に備えました。
キャッシュフローシミュレーションは、空室率15%、金利上昇1%を想定し、最悪でも年間収支がプラス5万円になるよう計算しました。実は、この慎重な試算こそが精神的な安定につながります。楽観シナリオだけで突き進むと、突発的な出費に耐えられず資金繰りが破綻する危険があります。
空室と家賃下落にどう向き合ったか
重要なのは、空室をゼロにするのではなく、「早期に次の入居者を決める仕組み」を持つことです。購入後2年目、退去が発生し、家賃68,000円の部屋が1か月空きました。管理会社任せにせず、自らポータルサイトの募集ページをチェックし、近隣競合物件の写真やコメントを比較しました。
すると、浴室乾燥機とWi-Fi無料設備がある物件ほど、成約が早い傾向が分かりました。そこで、設備導入費30万円を投じて物件の魅力を底上げし、家賃は据え置きのまま再募集を行いました。結果として、空室期間は前回の半分で済み、設備費は1年で回収できました。つまり、収益を守るには小まめな市場調査と差別化投資が必須です。
家賃下落については、長期契約割引を提案しました。3年契約なら月1,000円値引きという条件により、平均居住期間が1.8年から2.6年へ伸び、退去に伴う原状回復費の抑制につながりました。一方で、値下げ幅を大きくし過ぎると利回りが崩れるため、近隣相場の95%を下限と設定しています。
税務処理と2025年度に使える制度
実は、手取り収益を最大化するには税務知識が欠かせません。私が最も効果を感じたのは「青色申告特別控除65万円」です。複式簿記で帳簿を作成し、期限内に電子申告することで適用され、給与所得と損益通算できます。2025年度も制度は継続しており、賃貸経営者の基本戦略として有効です。
減価償却も重要です。築10年のRC造マンションは法定耐用年数47年のうち残存37年があり、定額法で年あたり約70万円を経費化できました。この費用計上により、課税所得を圧縮し、実効税率20%の私なら年間14万円の節税効果がありました。
なお、補助金やポイント制度は自宅向けが中心で、投資用物件は対象外のものがほとんどです。現行制度の中で投資家が確実に利用できるのは、耐震や省エネ改修に伴う固定資産税の軽減(一部自治体)ですが、期限や条件が細かく異なります。利用を検討する際は、必ず自治体の最新要綱を確認しましょう。
売却で感じた出口戦略の大切さ
ポイントは、購入時から出口をイメージしておくことです。私は5年目に市場価格が上昇したタイミングで売却を検討しました。不動産流通推進センターの取引事例を分析すると、同条件の部屋が3,300万円で成約していると判明しました。
売却益を最大化するため、仲介手数料が2%のネット系仲介会社を選び、内装リフォームは最低限のクロス張替えにとどめました。その結果、購入価格2,980万円に対し売却額3,280万円、手残りは仲介手数料や税金を差し引いて約210万円となりました。ここで重要なのは、「いつ売るか」を自分で決められるよう、ローン残高を常に把握し、市況に応じて柔軟に動くことです。
一方で、売却を急ぐと希望価格を下げざるを得ません。事前に複数社へ査定依頼し、交渉材料を持つと有利に進められます。逆に、市場全体が下落局面に入った場合は、賃貸として持ち続ける「貸すか売るか」の選択肢を残しておくと損失を回避できます。
まとめ
今回のマンション投資 体験談を通じ、物件選びから資金計画、運用、売却までの一連の流れをお伝えしました。要点は、①目的とデータに基づく立地選定、②余裕を持ったキャッシュフロー設計、③空室対策と税務知識の習得、④出口戦略の準備です。これらを押さえれば、投資はギャンブルではなく再現性のあるビジネスになります。まずは公的データを参照し、自分のリスク許容度を数値で把握するところから始めてみてください。行動すれば、未来の選択肢は確実に増えていきます。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国勢調査(総務省統計局) – https://www.stat.go.jp/data/kokusei
- 国土交通省 不動産取引価格情報 – https://www.land.mlit.go.jp
- 不動産流通推進センター – https://www.retpc.jp
- 国税庁 タックスアンサー – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer

