マンション投資に興味はあるものの、「京都で本当に利益が出るのか」「表面利回りと実質利回りの違いが分からない」と悩む方は多いものです。京都は観光都市として有名ですが、単身者やファミリーの流入も続き、賃貸需要は堅調に推移しています。本記事では、マンション投資で重要な実質利回りの計算方法から、京都ならではの市場動向、2025年度時点で活用できる制度までを網羅的に解説します。読み終えるころには、物件選びや資金計画の具体的なイメージが描けるはずです。
実質利回りとは何か
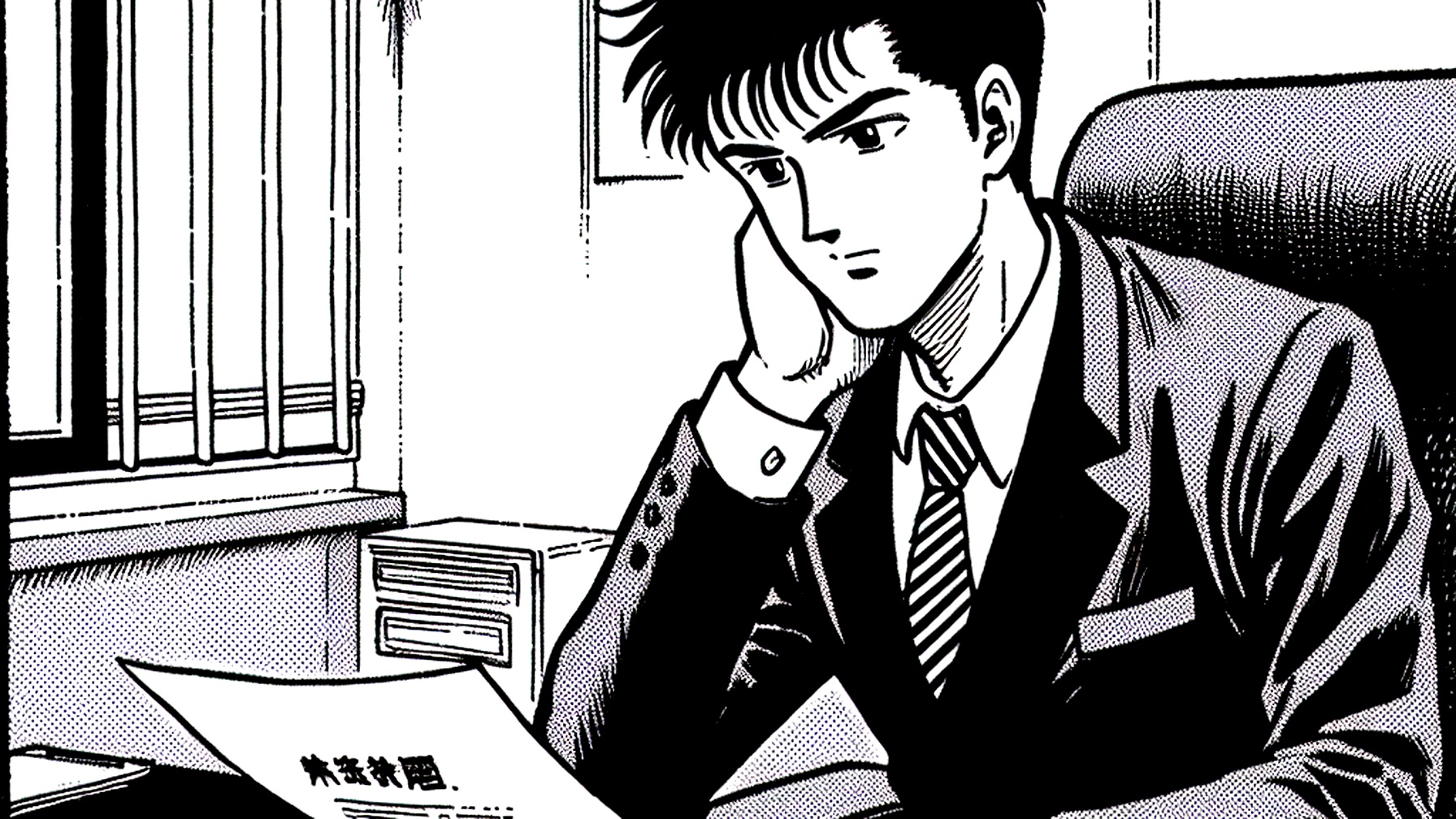
まず押さえておきたいのは、実質利回りが「手取りベースの収益性」を示す指標だという点です。表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割った単純な数字ですが、実質利回りでは固定資産税、管理費、修繕積立金、空室リスクなどを差し引きます。つまり、投資家が実際に受け取れるキャッシュフローを測定できるため、購入判断に欠かせません。
たとえば、価格3,500万円のワンルームを月8万円で貸す場合、表面利回りは約2.7%です。しかし管理費・修繕積立金で月1.5万円、年間固定資産税が9万円、入退去による空室が年間1カ月あると仮定すると、手取り家賃は年間75万円程度にまで減少します。その結果、実質利回りは約2.1%に下がります。この差を理解しておくと、ローン金利や将来の修繕計画を見落とす危険を回避できます。
日本不動産研究所が公表する2025年9月の東京23区ワンルーム平均表面利回りは4.2%ですが、同時期の京都中心部では4.5%前後という調査結果が見られます。数字だけを見ると魅力的ですが、管理費が高めの物件や築古の修繕リスクを考慮しないと、実質利回りが急落するケースもあります。
京都の賃貸市場の特徴
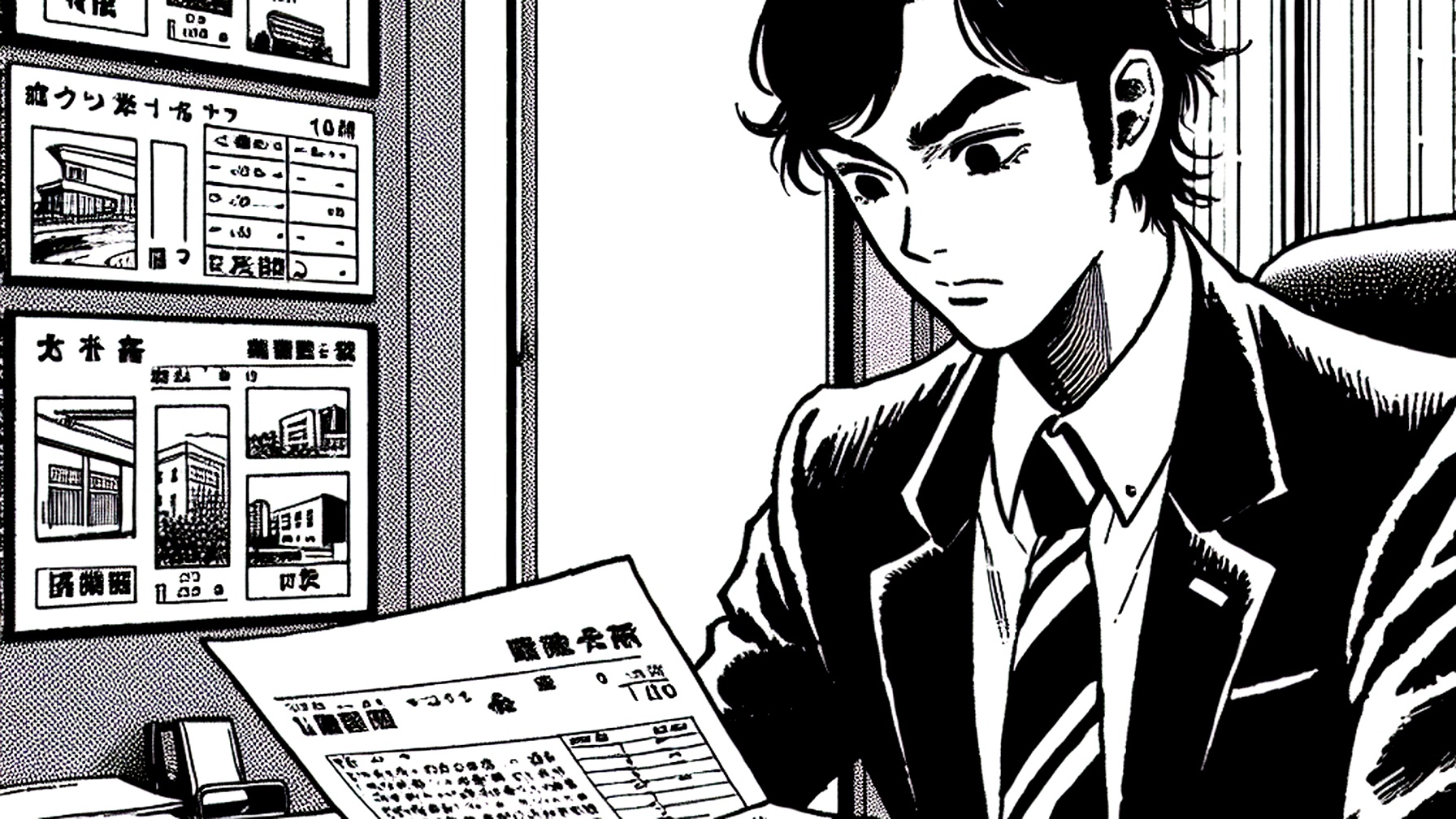
ポイントは、京都の賃貸需要が「学生」「観光関連従事者」「IT系転勤族」に分かれていることです。京都市統計ポータルによると、2025年4月時点で市内大学の学生数は約15万人で、うち7割が府外出身者です。この層は駅近ワンルームを好む一方、賃料には上限があり、実質利回りを押し下げる場合があります。
一方で、JR京都駅から徒歩圏の再開発エリアや四条烏丸のオフィスゾーンでは、IT企業のサテライトオフィスが増え、30〜40㎡の1LDKを探す単身ビジネス層が拡大しています。家賃は月10万〜13万円が相場で、表面利回りはやや低くても回転率が低く、実質利回りが安定しやすい特徴があります。
さらに、観光産業の回復に伴い、短期賃貸から長期賃貸へニーズを切り替える動きも見えます。2025年の京都市民泊規制強化により、合法的に運営される長期賃貸物件の価値が相対的に高まりました。つまり法規制が強化されるほど、適法に運用できるマンションの希少性が高まるため、家賃維持力が増しやすいのです。
実質利回りを高める物件選び
重要なのは、購入時点で「将来の支出を読み切る」ことです。築20年超のマンションは価格が抑えられますが、大規模修繕の積立不足があると、あと数年で一時金を求められるリスクがあります。京都市内では築浅プレミアムが大きく、築5〜10年の物件は価格が高止まりしていますが、修繕負担の見通しが立ちやすく、実質利回りのブレが小さくなります。
また、管理組合の議事録をチェックし、修繕積立金の引き上げ計画がないか確認することが欠かせません。特に学生向けマンションでは管理費が月額1.8万円を超えるケースが散見され、表面利回りが良くても実質では1%台に落ち込む危険があります。言い換えると、低めの管理費と長期修繕計画が明確な物件こそ、実質利回りが高まりやすいのです。
さらに、京都では町家風の外観を持つデザインマンションが人気です。家賃単価は一般的なRC造と比べ月1万円ほど上乗せできる例もあり、出口戦略としての売却価格も維持しやすい傾向があります。初期投資が大きくても、家賃上乗せで実質利回りを補えるため、総合的にメリットが出る可能性があります。
資金計画と税効果を押さえる
実は、ローン金利だけでなく「減価償却」の扱いがキャッシュフローに直結します。中古RCマンションの法定耐用年数は47年で、残存年数の計算を誤ると急激に減価償却費が減り、所得税負担が増える恐れがあります。税務上の耐用年数と実際の使用可能年数は一致しないため、税理士にシミュレーションを依頼すると安心です。
また、不動産所得は給与所得と損益通算が可能です。初年度の取得費用やローン利息が大きい間は赤字計上となりやすく、その分所得税と住民税が軽減されます。国税庁のモデルケースでは、年収700万円のサラリーマンが不動産所得で100万円の赤字を計上すると、税負担が約20万円減少する試算があります。これを実質利回りに加味すると、見かけの数字以上に手取りが増える場合があります。
融資面では2025年時点で、地元信用金庫のワンルーム向け投資ローンが固定金利2.1%台、都市銀行のアパートローンが変動1.6%台といった水準です。金利が0.5%違えば月々の返済額が数千円変わるため、実質利回りも大きく動きます。複数行の事前審査を取り、金利と融資期間のバランスを比較することが重要です。
2025年度に活用できる制度とリスク管理
まず押さえておきたいのは、「賃貸住宅耐震・省エネ改修促進事業」(2025年度〜2026年3月末予定)が投資用マンションにも適用される点です。耐震補強や高効率給湯器の設置費用について、国交省から上限150万円の補助が受けられます。補助対象になると、改修後の賃料上昇が期待できるだけでなく、自己負担を抑えられるため実質利回りの向上に直結します。
一方で、京都市では2025年7月に施行された「住宅宿泊事業法上乗せ条例」により、住居専用地域での短期貸しがさらに制限されました。投資家は長期賃貸を前提にシミュレーションを組み、途中で用途変更が難しいことを理解しておく必要があります。条例の改正は収益計画に影響するため、行政情報を定期的に確認する習慣が欠かせません。
自然災害リスクにも注意が必要です。京都市防災マップによると、鴨川沿いの一部地域は洪水想定区域に入り、マンションでも機械式駐車場の浸水被害が過去に報告されています。火災保険だけでなく、水災補償を付帯すると年間保険料が約1.5万円増えますが、実質利回り低下は0.05%程度で済み、長期的には安心材料になります。
まとめ
京都でのマンション投資を成功させるカギは、実質利回りを軸に物件と資金計画を組み立てることです。学生需要やビジネス需要が共存するエリアを選び、管理コストと修繕計画を徹底的に調べれば、安定したキャッシュフローが期待できます。さらに、減価償却や損益通算の税効果、2025年度の改修補助を取り込むことで、数字以上のリターンを得ることが可能です。まずは気になるエリアで複数の物件を比較し、実質利回りを試算するところから行動を始めてみてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 京都市統計ポータル – https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000183582.html
- 国土交通省 賃貸住宅耐震・省エネ改修促進事業概要 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 タックスアンサー 不動産所得 – https://www.nta.go.jp

