突然の空室や修繕費の高騰を聞くたびに、「マンション投資は本当に安全なのだろうか」と不安になる方は多いはずです。実際、利回りが高そうに見えても、諸費用を差し引くと手元に残るお金が想像より少ない例は珍しくありません。本記事では、表面利回りではなく実質利回りに着目し、初心者が陥りやすい危険を洗い出したうえで、2025年時点で通用する具体的な攻略法を解説します。読み終える頃には、数字の裏側を読み解き、リスクを管理しながら着実に収益を伸ばす道筋が見えてくるでしょう。
実質利回りとは何か
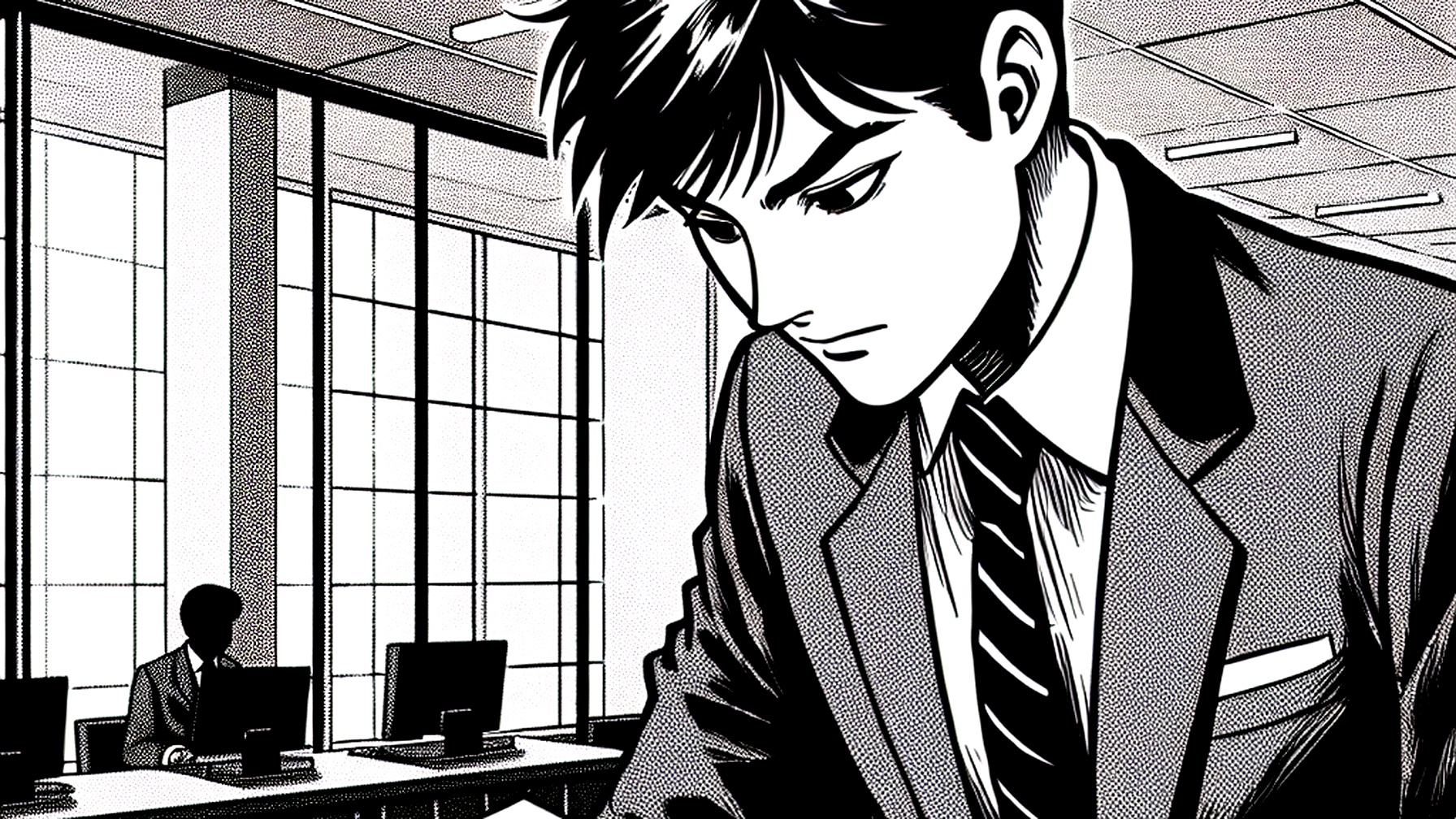
まず押さえておきたいのは、実質利回りが投資判断の軸になる点です。これは家賃収入から管理費や固定資産税などの経費を差し引き、購入総費用で割ったものを指します。表面利回りより厳しい数値ですが、手取りに近いため現実的な判断材料になります。
多くの広告は表面利回りばかり強調し、管理費や修繕積立金の上昇リスクに触れません。例えば東京23区のワンルーム平均表面利回りは4.2%ですが、管理費と固定資産税で年額60万円を支払うと、実質利回りは3%台前半に下がるケースが一般的です。言い換えると、経費を正しく見積もらなければ計画はすぐに崩れます。
さらに、実質利回りを計算する際は購入時の仲介手数料や登記費用を忘れがちです。物件価格の6〜8%に相当するこれらの費用を含めることで、より厳密なシミュレーションが可能になります。重要なのは、初年度だけでなく長期の維持費まで視野に入れることです。
最後に、空室期間を前提に加えると数字はさらに変わります。日本不動産研究所によると、2025年の東京23区平均空室率は5%前後で推移していますが、物件やエリアによっては10%を超える場合もあります。実質利回りを語る上で、空室リスクを加味した収入減少を織り込む発想が欠かせません。
マンション投資に潜む主な危険

ポイントは、数字以外の要素にも危険が潜んでいる事実を認識することです。法律改正や地域の需給バランスの変化は、家賃収入に直接影響を与えます。
まず、建物の築年数と修繕履歴は見逃せません。築25年を超えると、給排水管や屋上防水などの大規模修繕が必要になるタイミングが近づきます。修繕積立金が不足していれば一括徴収され、想定外の大きな出費となります。また、防火・耐震基準を満たしていない物件は、将来的な賃貸需要低下や売却価格の下落リスクが高まります。
次に、賃料下落は緩やかに進むため、危険を実感しにくい特徴があります。不動産経済研究所のデータによれば、2025年上期の新築マンション価格は前年比3.2%上昇しましたが、中古賃料は横ばいです。つまり、購入価格だけが上がる一方で賃料が伸びなければ、実質利回りは目減りします。
一方で、金融機関の融資姿勢が変わるリスクも見逃せません。金利が1%上昇すると、3,000万円を25年返済で借りた場合、総返済額は約400万円増えます。この差額は実質利回りを大きく削ります。
最後に、管理会社選びの失敗も危険要因です。入居者対応が悪いと退去が増え、空室期間が長期化します。レポートや収支報告が遅い会社では、問題発見が遅れ、損失が拡大する恐れがあります。したがって、管理レベルの把握も投資判断の一部として位置付けることが大切です。
実質利回りを高める攻略法
重要なのは、経費を抑えながら収入を底上げする具体策を組み合わせることです。ここでは費用削減と収入向上の両面から攻略法を解説します。
まず費用面では、金利交渉が効果的です。2025年9月時点で地方銀行の投資向け変動金利は年1.8%前後ですが、自己資金を3割以上入れると1.4%まで下げられた事例があります。金利0.4%の差は25年返済で総返済額が約250万円変わるため、実質利回りに直結します。
次に、適切なリフォームで賃料を維持する方法があります。築20年を超える物件でも、キッチン交換やアクセントクロスを採用すると賃料が7〜10%向上した事例が報告されています。投資額を賃料アップで3年以内に回収できれば、以降の実質利回りは向上します。
さらに、サブリース契約を活用する場合は、賃料改定条項を細かく確認してください。保証賃料が毎年2%ずつ下がる契約では、安定どころか収益が減少し続ける危険があります。誤った契約を回避すること自体が、攻略法の一つといえます。
最後に、保険の見直しも効果的です。火災保険は補償範囲を合理化するだけで年数万円の削減が可能ですし、家賃保証保険を導入しても空室時の損害を限定できます。このように支出とリスクを同時にコントロールすることで、実質利回りを底上げできます。
物件選定と立地戦略のコツ
実は、物件選定で八割が決まると言われるほど立地は重要です。人口動態や開発計画を読み解くことで、長期的な空室リスクを大幅に減らせます。
まず、駅から徒歩10分以内は依然として強い需要がありますが、単に距離だけでは判断できません。乗降客数が減少しているローカル線の駅前よりも、複数路線が交差する駅から12分の立地の方が将来的な競争力は高い場合があります。国土交通省の「都市計画現況調査」によると、複合的な交通利便性を持つ地区は人口の流入が続いており、賃貸需要の維持に寄与しています。
次に、エリアの世帯属性を確認します。ファミリー層が多い地域でワンルームを供給すると空室が長期化する恐れがあります。逆に、大学や専門学校が集まるエリアでは家具付きのマンスリープランが高稼働する傾向があり、差別化によって実質利回りを高められます。
さらに、周辺の新築供給量にも注目する必要があります。不動産研究所のレポートでは、2024年度に供給が集中した湾岸エリアで2025年に賃料が微減した事例が紹介されています。大量の新築が一斉に募集を開始すると、築浅・中古の賃料が下押しされるため、中長期の需給バランスを読むことが攻略法の一部と言えます。
最後に、将来の出口戦略も含めて立地を検討します。インバウンド需要が高まる地域では、民泊転用による売却プレミアが期待できます。一方で、高齢化が進み公共交通が先細る地域では、想定以上に売却価格が下がる危険があります。投資開始時点で出口を意識することが、長期的な実質利回り向上につながります。
2025年度の制度・融資活用術
まず知っておきたいのは、2025年度に継続している減税・補助制度を上手く使うことで、手残りを増やせる点です。個人投資家に直接関係する代表例が「住宅ローン控除の投資用併用部分」です。居住面積の半分以上を自宅とし、残りを賃貸として貸し出す場合、住宅ローン控除を最大20万円/年(2025年度上限)まで利用できます。併用住宅という形ですが、実質利回りを向上させる手段として注目されています。
一方、賃貸住宅の耐震・省エネ改修に対する「既存賃貸住宅ストック活用支援事業」は2025年度も継続しており、上限120万円の補助が受けられます。条件を満たすとリフォーム費用の1/3が補助されるため、実質利回りを押し上げる効果があります。期限は2026年3月末の完了工事分までと発表されていますので、スケジュール管理が攻略法の鍵になります。
また、金融機関の「エコリノベ融資」は、省エネ改修を行うことで金利を最大0.3%引き下げる優遇策があり、2025年度も申し込みを受け付けています。金利差による総返済額削減は先述の通り実質利回りに直結します。
最後に、地方自治体の独自助成も忘れず確認しましょう。東京都では2025年度も「空き家活用スタートアップ支援事業」を継続しており、賃貸住宅へのコンバージョンに最大200万円を補助します。助成額が大きいため、リノベ費用を抑えつつ賃料を底上げできる点が大きな魅力です。制度は予算枠到達次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。
まとめ
ここまで、マンション投資に潜む危険を具体的に示し、実質利回りを高める攻略法を解説しました。実質利回りの正確な計算、立地選定の緻密な分析、費用と収入を同時に改善する施策、そして2025年度の制度や融資を活用する姿勢が、長期的な成功のカギとなります。まずは自分の投資計画を実質利回りベースで再計算し、リスクを洗い出すところから始めてみてください。数字がクリアになれば、不安は次第に戦略へと変わり、安定収益への一歩を踏み出せるはずです。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 都市計画現況調査 – https://www.mlit.go.jp
- 住宅金融支援機構 金利情報 – https://www.jhf.go.jp
- 東京都 空き家活用スタートアップ支援事業 – https://www.metro.tokyo.lg.jp
- 国土交通省 既存賃貸住宅ストック活用支援事業 – https://www.mlit.go.jp/housing_stock2025

