後悔のないセミリタイアを目指しても、収益物件の収支計算が難しくて一歩を踏み出せない、と感じていませんか。金利上昇や人口減少のニュースが流れるたびに、不動産投資は本当に安定した資産形成になるのか不安が募ります。この記事では、初心者がつまずきやすい収支計算の基本を整理し、2025年時点で活用できる実践的なポイントを示します。読み終えたころには、自分に合った物件を見極め、セミリタイアへの道筋を数字で描けるようになるはずです。
セミリタイアに必要なキャッシュフローの考え方
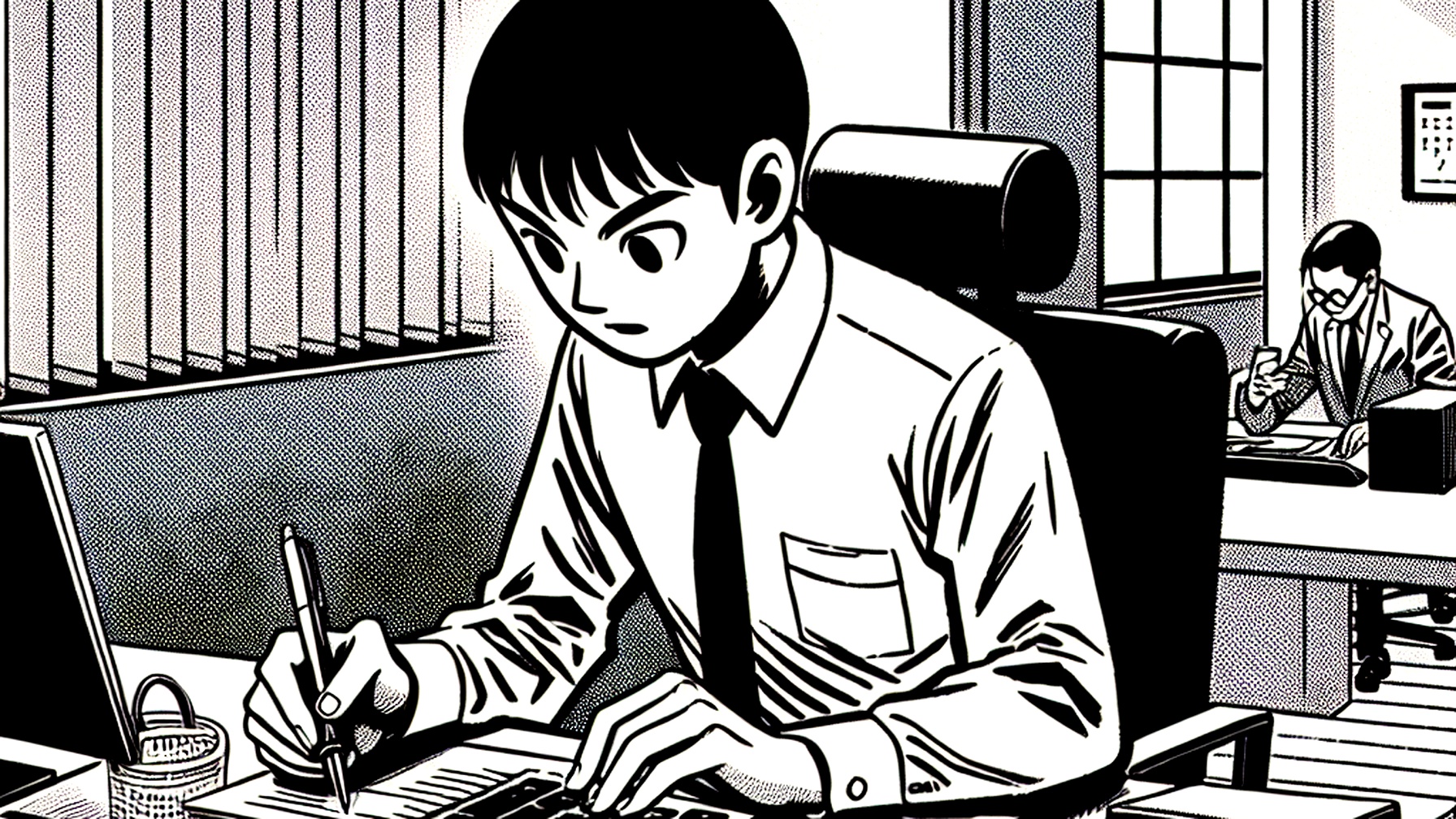
重要なのは、毎月の手取りキャッシュフローを生活費と照らし合わせ、安定して不足を補えるかを確認することです。家賃収入だけに目を奪われず、支出の全体像を把握する姿勢が欠かせません。
まず、生活費を可処分所得ベースで把握します。総務省家計調査によると、50代夫婦の平均消費支出は月約29万円です。セミリタイア後は通勤関連費が減る一方、健康維持や趣味の費用が増える傾向もあるため、自分のライフスタイルに合わせて35万円前後を目安に設定すると現実的です。
次に、物件単体のキャッシュフローを見積もります。収入は賃料、支出はローン返済、管理費、修繕積立、固定資産税、空室損、保険料が主要項目です。例えば月賃料7万円のワンルームで、ローン返済が4万円、諸経費が1.5万円なら、手取りは1.5万円にとどまります。この数字が生活費の不足分を埋められるかが判断基準です。
複数物件を保有する場合、物件間の収支を合算して考えます。しかし、全物件が同時に空室となるリスクは小さいもののゼロではありません。つまり、生活費をまかなうには、最悪のケースでもキャッシュが残る保守的なシミュレーションが欠かせないのです。
収益物件の収支計算を構成する七つの数字
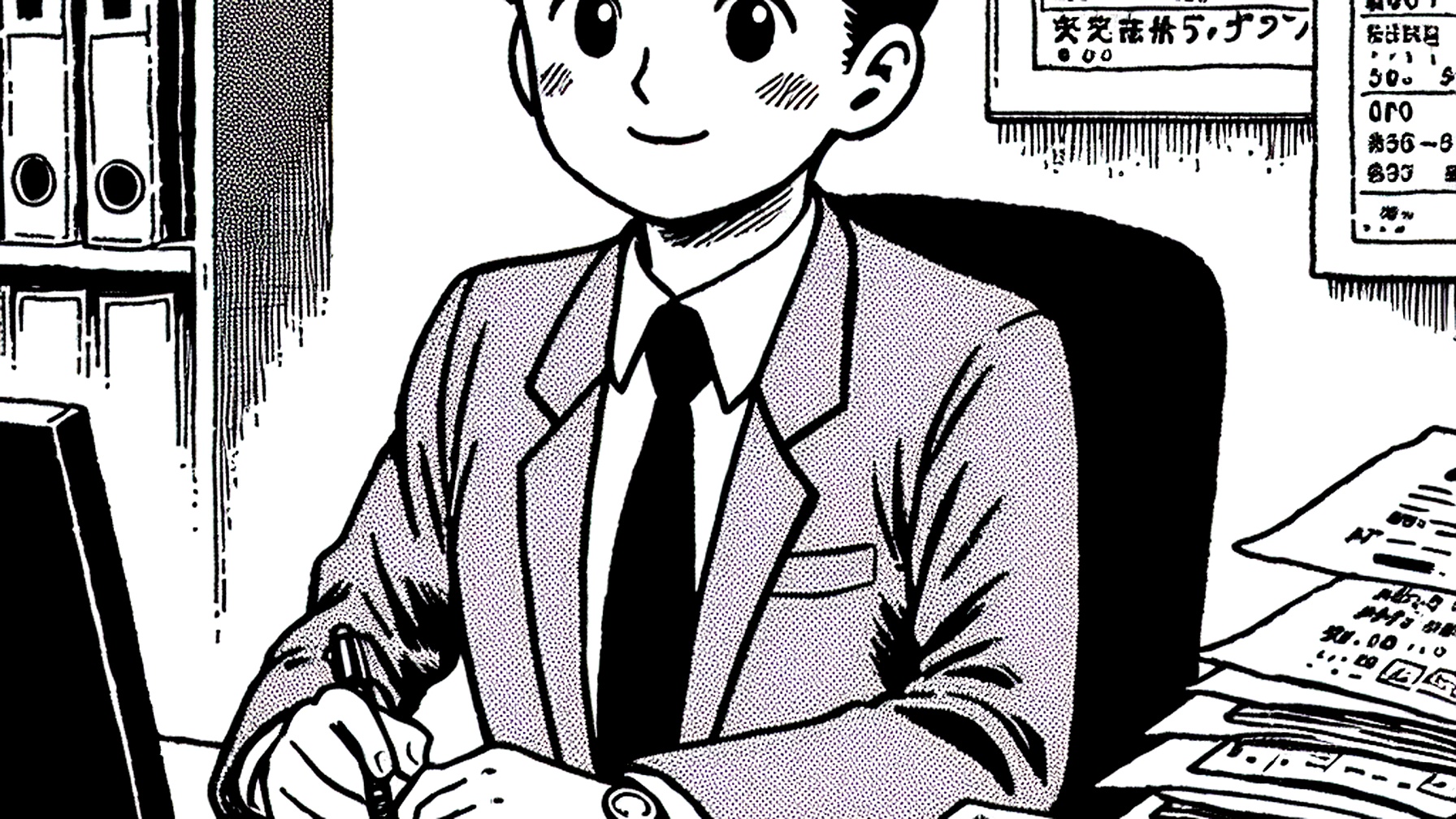
ポイントは、七つの数字を押さえるだけで精度の高い収支計算が可能になることです。家賃、空室率、運営費率、金利、返済期間、自己資金、税率を順に整理すると、ブレが少なくなります。
最初に家賃と空室率を決定します。レインズマーケットインフォメーションでは、2025年上期の東京23区平均空室率は約9%です。家賃7万円の物件なら、年間家賃収入は7万円×12ヶ月×0.91で約76万円と計算できます。
運営費率は物件の種別で異なります。マンションは15%前後、アパートは20%が一般的と言われます。ここには管理会社への手数料や共用部電気料のほか、原状回復費の積立も含めて考えましょう。
金利と返済期間は金融機関の融資方針で大きく変わります。2025年9月時点で投資用ローンの固定金利は2.5%前後が目安です。返済期間を30年に設定すると、元利均等返済で月々の支払いはおおむね融資額1000万円につき約4万円となります。
最後に自己資金と税率です。頭金2割を入れると、ローンの借入額と毎月返済額が減り、収支は安定します。税率は所得税、住民税に加え、個人事業として青色申告特別控除65万円を活用すると、課税所得を圧縮できます。
金融機関の評価と融資条件を読み解く
実は、金融機関が見るのは物件の魅力だけではありません。投資家個人の属性とポートフォリオ全体の安全性も審査対象になります。適切な情報開示と交渉が、金利や融資期間を有利にする鍵です。
まず、金融機関は「積算評価」と「収益還元評価」を併用します。積算評価は土地と建物の再調達価格をベースに算定し、都心の築古区分マンションでは融資額が限られる場合があります。一方、収益還元評価は家賃から純収益を導き、利回りで割り戻す手法です。キャッシュフローが安定していれば、築年数が進んでも評価が出やすいのが特徴です。
次に、個人の年収や金融資産も審査対象です。金融庁のガイドラインでは、返済負担率を年収の35%以下に抑えることが推奨されています。セミリタイアを視野に入れていても、直近の給与所得が高いほど好条件を引き出しやすいのが現実です。そのため、退職前に融資審査を通しておく戦略が効果的です。
さらに、金融機関はポートフォリオの偏りを嫌います。区分マンションだけに集中すると、家賃下落リスクが高いと判断されることがあります。戸建てや小規模アパートを組み合わせ、エリアも分散することで、与信枠が広がる可能性が高まります。
2025年度の税制と経費計上で手取りを増やす
まず押さえておきたいのは、税引き後キャッシュフローを最大化するには、経費を適正に計上し、減価償却をフル活用することです。2025年度もこの基本は変わりません。
減価償却は建物価格を法定耐用年数で割り、毎年経費化できる制度です。鉄筋コンクリート造の中古マンションなら、法定耐用年数47年のうち残存年数を基に計算します。例えば築20年で購入した場合、残存年数は27年となり、建物価格2000万円なら年間約74万円を経費計上できます。
さらに、青色申告特別控除65万円を使うには、不動産所得で複式簿記と貸借対照表を提出する必要があります。クラウド会計ソフトを導入すると、レシートの画像取り込みや自動仕訳が可能になり、月2時間程度で帳簿が完成します。
また、個人で購入した収益物件を法人へ移す「資産管理会社スキーム」は、所得が900万円を超えると効果が出やすくなります。法人税率が23.2%で頭打ちになるため、個人の累進税率を抑えられるからです。ただし移転コストや登録免許税が発生するため、税理士に試算を依頼し、総合判断することが重要です。
シミュレーション事例:都内中古ワンルームと地方築浅アパート
ポイントは、具体的な数字で比較するとリスクとリターンの性質が見えやすいことです。ここでは、都内中古ワンルームと地方築浅アパートを取り上げます。
【都内中古ワンルーム】 購入価格1800万円、自己資金360万円、金利2.5%、期間30年。家賃7.5万円、空室率8%、運営費15%で計算すると、年間手取りは約27万円、月3.2万円です。耐用年数残存27年で減価償却額は60万円強となり、所得が圧縮されるため、税引き後キャッシュフローはさらに向上します。
【地方築浅アパート】 購入価格6000万円、自己資金1200万円、金利2.7%、期間25年。満室家賃46万円、空室率12%、運営費20%とすると、年間手取りは約162万円、月13.5万円です。木造耐用年数22年のうち残存20年で減価償却は年270万円となり、初期数年は赤字決算で還付が発生するケースもあります。
このように、ワンルームは小口で始めやすく、都心の流動性が高い点が魅力です。一方、アパートは一棟で管理効率が良く、家賃総額が大きいためキャッシュフローの伸びしろがあります。しかし修繕費や退去のタイミングが重なると、一時的に手取りが大きく落ち込むリスクもあるので注意が必要です。
結論として、セミリタイアまでの期間と必要キャッシュフローを軸に、物件タイプと融資戦略を組み合わせることが成功への近道と言えます。
まとめ
ここまで、セミリタイアを実現するための収益物件の収支計算を、キャッシュフローの基礎から税制、シミュレーション事例まで体系的に整理しました。重要なのは、生活費と物件収支を同じ土俵で比較し、最悪のケースでも資金ショートしない設計図を描くことです。そのうえで、金融機関との交渉や税務戦略を駆使すれば、計算上の利益を実際の手残りに変換できます。今日紹介した七つの数字を使い、自分の目標に合った物件を選定し、早期のセミリタイアへ一歩踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- レインズマーケットインフォメーション – https://www.reins.or.jp
- 総務省 家計調査報告 – https://www.stat.go.jp
- 金融庁 令和6事務年度金融行政方針 – https://www.fsa.go.jp
- 国税庁 青色申告の手引き2025 – https://www.nta.go.jp

