相続で突然物件を受け継いだものの、「売却か賃貸か」「ローンを組んで買い増すか」など判断に迷う人は少なくありません。また近年は低金利が続き、レバレッジを利かせて資産規模を拡大する選択肢も現実的になっています。本記事では相続物件を活用してレバレッジ効果を引き出す方法を、初心者にも分かりやすく解説します。読むことで、金融機関との交渉ポイントから税務・法務の注意点、将来の出口戦略までを体系的に把握できるでしょう。
レバレッジとは何か、なぜ相続物件で注目されるのか
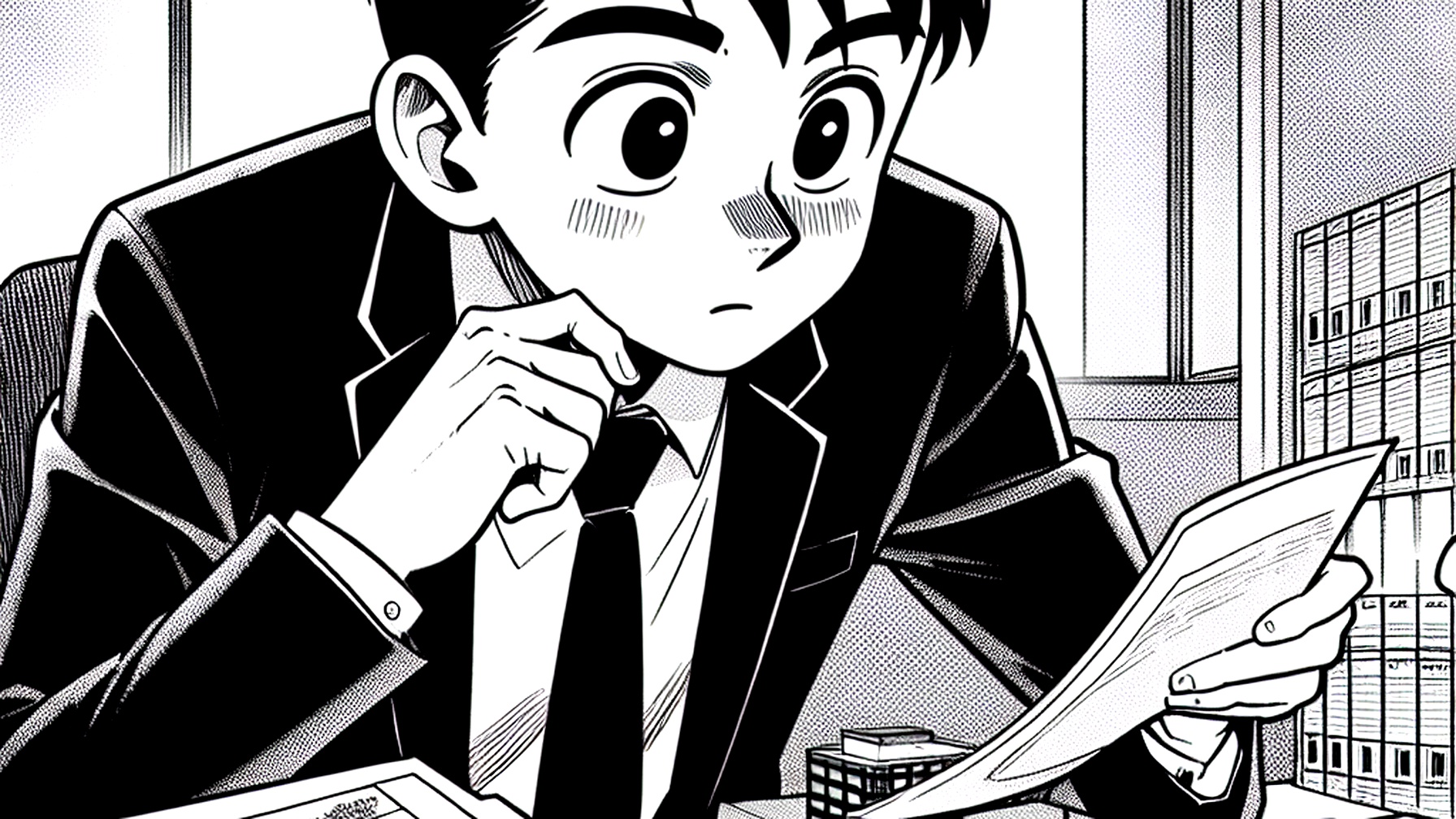
まず押さえておきたいのは、レバレッジが「てこ」を意味し、自己資金より大きな取引を実現する金融技術である点です。保有資産を担保に融資を受け、利回りが借入金利を上回るかぎり、手元資金以上のリターンを得られます。相続物件は担保評価が立ちやすく、追加の自己資金を抑えて投資拡大を図れるため、レバレッジとの相性が良いと言えます。
一方で、借入が膨らめば返済負担や金利上昇リスクも増大します。相続時点ではローンが残っていないケースも多いため、「無借金だから安全」という思い込みが返って危険を招きます。つまり、レバレッジの可否は物件価値だけでなく、キャッシュフローや長期的な資金計画まで総合的に判断することが必須です。
相続物件の現状と市場動向
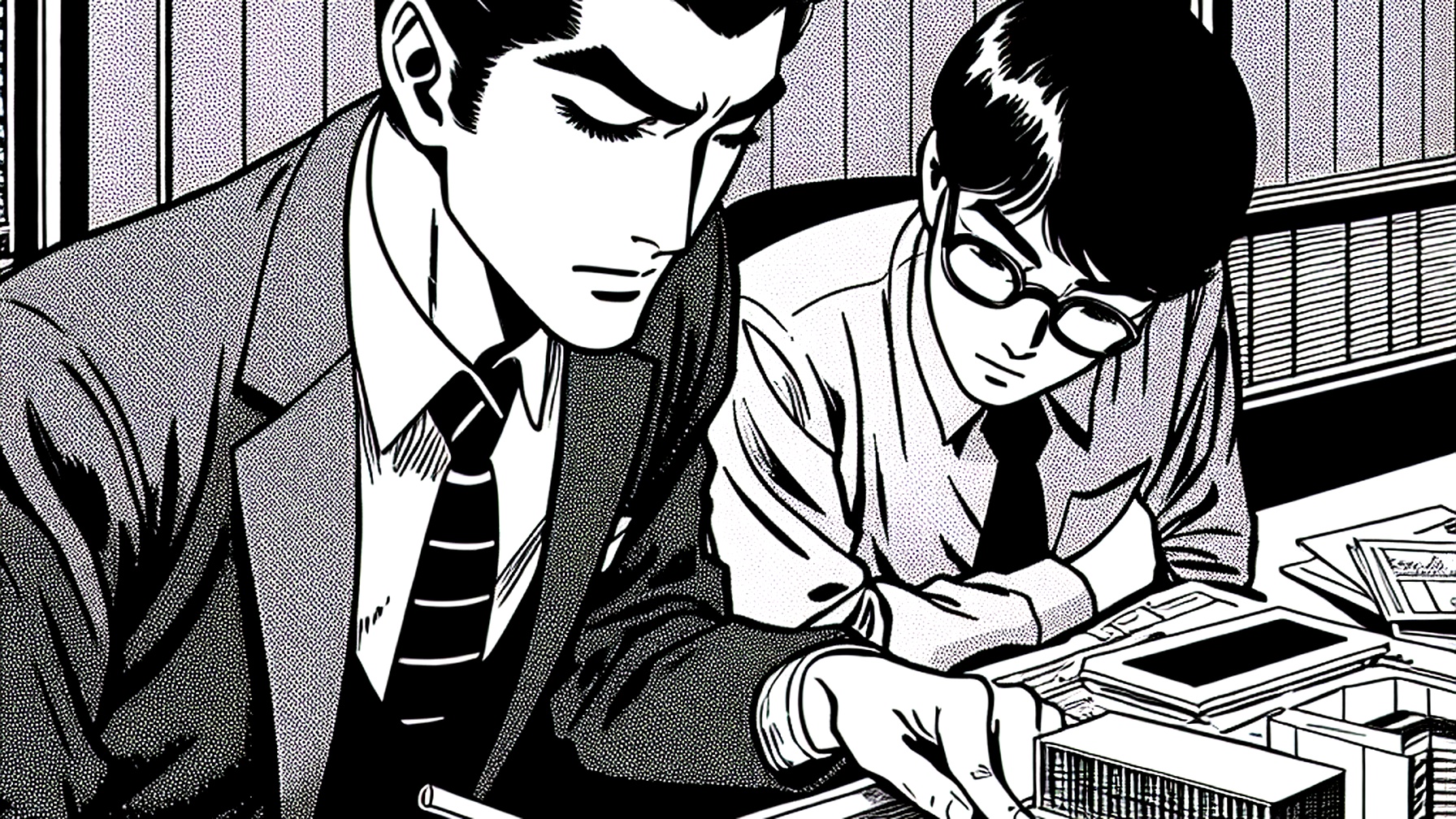
実は、相続をきっかけに不動産が市場へ供給される流れが強まっています。国土交通省の「不動産価格指数(2025年7月公表分)」によると、地方の中古住宅価格は前年同期比で1.8%下落した一方、東京23区の中古マンションは3.4%上昇しました。人口移動の二極化が続き、都市部と地方で賃貸需要に差が拡大していることが読み取れます。
総務省の住民基本台帳ベースのデータでは、2024年に地方圏の人口が前年比で約0.7%減少しました。空室率が上がりやすい地域の相続物件は、レバレッジ以前にポートフォリオから除外すべきかもしれません。一方、都市部の築古マンションを相続した場合、低金利でリフォーム資金を借り入れ、賃料を高めてリターンを狙う戦略が現実味を帯びます。
こうした動向を踏まえると、相続物件の所在地や築年数によって「売却して資金を確保する」「運用益を維持しつつ追加で買い増す」など、レバレッジ活用のシナリオは大きく変わります。
融資戦略で差がつくレバレッジ活用術
ポイントは、自分の信用力だけでなく相続物件の担保余力を見極めることにあります。金融機関は「物件評価額の70〜80%まで融資可」とするケースが多いものの、2025年度も続く金融庁の「地域金融円滑化方針」により、収益物件向け融資はやや慎重です。そのため、複数行を回って比較する姿勢が欠かせません。
まず、住居系より事務所系や店舗系の方が評価が下がりやすい点を意識しましょう。管理状態を示す修繕履歴や入居率のデータを提示できると、金利や融資枠で優遇を受けやすくなります。また、自己資金を1割でも入れると、金利が0.2%下がる例も少なくありません。わずかな差に見えても、30年返済では数百万円の節約となるため、短期でのキャッシュフロー改善につながります。
さらに、相続時に取得した土地を分筆して戸建を新築し、建築資金を新たに借り入れる手法もあります。建物部分で減価償却費を計上できるうえ、2025年度の「住宅省エネ基準適合住宅向け融資」で金利が年0.3%引き下げられる場合があり、収益性を高めやすいです。ただし、適用には断熱性能や設備仕様など技術基準を満たす証明が必要なので、早めに設計士と連携しましょう。
税務と法務の基礎知識を押さえる
重要なのは、レバレッジを活用しても税負担を抑えなければ手取りが増えない点です。相続で取得した物件の取得費は、被相続人が当初購入した金額に設備費や改良費を加算して算出します。売却を検討する場合、この取得費が低いと譲渡所得が大きくなり、所得税・住民税が合計で最大55%課税される恐れがあります。
一方で、賃貸運用を続けるなら、減価償却費や借入利息を経費計上できるため、所得税の節税効果があります。国税庁の「令和6年分所得税取扱い通達」によれば、木造の法定耐用年数は22年ですが、中古取得時は残存年数で再計算できます。築古で耐用年数を超えていれば、「22-経過年数+経過年数×20%」の簡便法が適用でき、償却期間を短縮して早期に経費化が可能です。
法務面では、相続登記が未了だと融資を受けられません。2024年4月に施行された相続登記義務化により、相続開始から3年以内の登記が法的に求められ、怠ると10万円以下の過料が科されます。実務では金融機関が登記完了を確認してから担保設定するため、時間的余裕を持って司法書士へ依頼しましょう。
失敗を防ぐリスク管理と出口戦略
まず押さえておきたいのは、レバレッジは利益を増幅する一方で損失も拡大させる仕組みである点です。最長35年のローンを想定するなら、空室率15%でも回る収支計画を組み、金利上昇2%までは返済比率が40%を超えない水準に抑えたいところです。
また、建物の老朽化に備えて修繕積立を毎月賃料の10%程度確保しておくと、大規模修繕時の追加借入を避けられます。日本銀行の「マクロプルーデータ(2025年7月)」によると、平均金利は1.2%で安定していますが、インフレ率が継続して2%を超える場合、長期金利の上昇余地は十分にあります。リスクシナリオを前提にプランを練る姿勢が安全弁となります。
出口戦略としては、①築20年時点で売却してキャピタルゲインを確定、②築30年超でも賃貸を維持し、減価償却が尽きたら相続人へ継承、③建替えやコンバージョンで再投資、の三つが代表的です。どの道を選ぶにしても、金融機関とのリレーションを維持しながら、将来必要な返済額と資産価値のバランスを定期的に見直してください。
まとめ
結論として、相続物件にレバレッジを掛けるかどうかは、物件の立地、融資条件、税務コスト、そして家族を含めた長期の資産設計を総合的に見極める作業です。低金利と都市部の賃貸需要が味方すれば、少ない自己資金で資産を雪だるま式に増やすことも可能です。一方で、法改正や金利上昇といった外部要因は常に変動します。この記事で紹介した市場動向や税務・法務の基礎を押さえ、定期的なシミュレーションと専門家への相談を通じて、堅実かつ戦略的な不動産投資を実践してください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp
- 金融庁 地域金融円滑化方針(2025年度版) – https://www.fsa.go.jp
- 国税庁 令和6年分所得税取扱い通達 – https://www.nta.go.jp
- 日本銀行 マクロプルーデータ – https://www.boj.or.jp

