不動産投資に興味はあるものの、「ネットでは収益性 やめとけと書かれていて不安だ」という声をよく耳にします。高額なローンを背負った後で失敗に気づいても、簡単には引き返せません。本記事では、なぜ「やめとけ」と警告されるのかを丁寧に紐解き、具体的な回避策まで解説します。読み終えれば、数字の裏側に潜むリスクを見抜き、安心して第一歩を踏み出す判断軸が手に入るはずです。
収益性 やめとけと言われる背景
重要なのは、警告の根拠を感情ではなくデータで確認する姿勢です。国土交通省によると、2024年度の全国平均空室率は住宅で13%、地方都市では20%前後に達しました。この数字自体は一見小さく見えますが、家賃下落と組み合わさると利回りを大きく削ります。
まず、初心者が陥りやすいのは「表面利回り」だけで判断することです。表面利回りは家賃収入を購入価格で割った単純な指標で、管理費や税金、修繕積立金を含めません。言い換えると、実際の手取りとはかけ離れた幻想の数字になりがちです。
一方でローン金利は2025年9月時点で変動型が年0.7%前後と低水準ですが、将来の上昇余地は残ります。家賃が下がり、金利が上がる局面が重なると、キャッシュフローは一気に赤字へ傾く可能性があります。
つまり、「収益性 やめとけ」という警句は、甘い利回り表示と将来リスクを同時に考えない姿勢を戒めるサインだと理解すべきです。
キャッシュフローの落とし穴
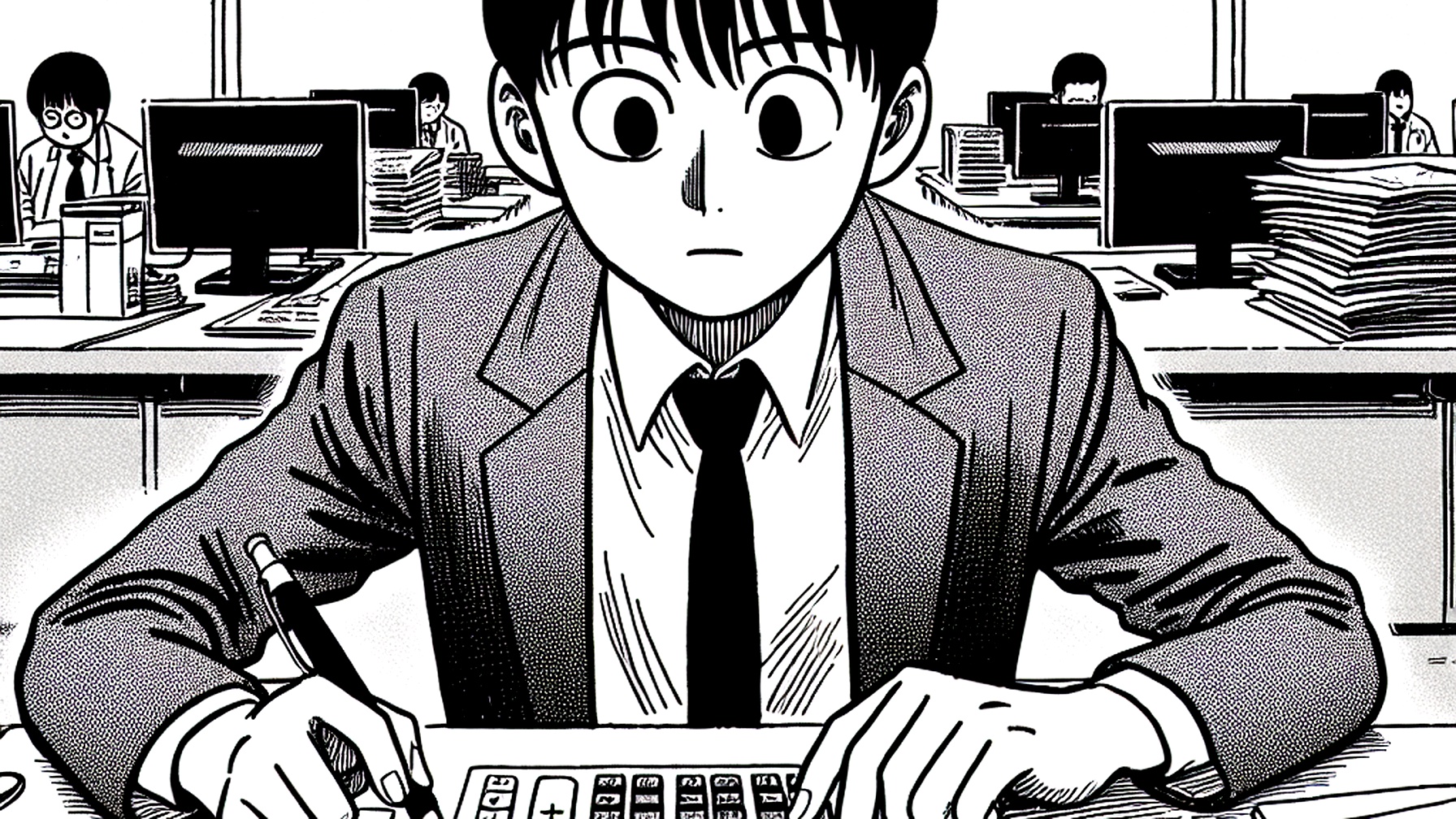
ポイントは、手元に残るお金を正しく計算することです。たとえば家賃月8万円のワンルームを2,000万円で購入した場合、表面利回りは4.8%となります。しかし管理委託料は家賃の5%、固定資産税は年7万円、共用部修繕積立金は月1万円といった費用が継続的に発生します。
さらに、エアコン交換や給湯器故障のような小規模修繕は3〜5年おきに平均15万円かかります。これらを織り込むと、実質の手取り利回りは3%台まで下落します。ここに1カ月の空室が発生すると、年利回りはさらに0.4ポイントほど低下し、ローン返済後に残る現金は月数千円にしかなりません。
加えて、日本政策金融公庫が公表する「小規模企業共済加入者の家計調査」では、修繕費の実績が家賃収入の15%前後に達するケースが珍しくないと示されています。数字の上では黒字でも、突発的な支出によって預金残高が減り続ける状態を「赤字倒産」と呼びますが、個人投資家でも十分起こり得ます。
実は、このキャッシュフローの読み違いこそが「収益性 やめとけ」の核心です。表面利回りが高くても、実質の手取りが低ければ投資として成立しません。
利回り表示のトリックを見抜く
まず押さえておきたいのは、利回り計算に使われる「家賃想定額」が現実と乖離していないか確認する手順です。SUUMOやアットホームなどのポータルで周辺家賃を調べると、広告で示された想定賃料より5〜10%高めに設定されている例が頻出します。
一方、利回りの分母となる購入価格も注意が必要です。不動産会社が提示する「税抜き価格」で計算した利回りは高く見えますが、実際には消費税や登録免許税、不動産取得税が上乗せされます。これらの諸費用は物件価格の6〜8%に達し、利回りを0.3〜0.5ポイント押し下げる要因になります。
さらに、利回り計算において空室率をゼロと仮定しているケースもあります。総務省「住宅・土地統計調査」の地区別空室率を参考に、最低でも5%を織り込むのが実務的です。もし空室率を全く考慮しないシミュレーションを提示されたなら、その物件は「収益性 やめとけ」と判断するほうが賢明でしょう。
このように、利回り表示には複数のトリックが潜んでいます。言い換えると、自分自身で前提を検証できる投資家だけが、本当の収益性を把握できるのです。
長期保有で差がつく運営コスト
基本的に、木造アパートの法定耐用年数は22年ですが、実際の使用期間は30年を超えることも珍しくありません。その間に屋根や外壁の大規模修繕が発生し、費用は1戸あたり50〜80万円に上ることがあります。大規模修繕積立を怠ると、いざという時に追加融資が必要となり、金利コストが増大します。
一方でRC造(鉄筋コンクリート造)の物件は耐用年数47年と長く、長期保有に向きますが、修繕費も高額です。国土交通省の「マンション維持修繕ガイドライン」によれば、大規模修繕費は延床1㎡あたり平均1万2千円が目安です。20戸規模なら数千万円単位の支出となり、事前準備が不可欠です。
ここで注目したいのが、2025年度も継続している「省エネ改修促進税制」です。一定の断熱改修を行うと固定資産税が最大1/3減額されるため、修繕コストの一部を抑えられます。つまり、制度活用が運営コスト圧縮の鍵となります。
以上を踏まえると、長期視点で運営できる余裕資金と制度知識が不足している場合は、「収益性 やめとけ」と自制するのが合理的です。
2025年度制度を活用してリスクを減らす
実は、制度を利用するだけでキャッシュフローが大きく改善するケースがあります。まず、「住宅ローン控除」は自宅用だけでなく、賃貸併用住宅であれば賃貸部分を除いた面積に対して適用され、最大13年の所得税控除が得られます。収益の一部を税金で補填できる形になるため、実質利回り向上につながります。
また、2025年度税制改正では、耐震基準を満たさない住宅を除却して新築賃貸を建てた場合、登録免許税の軽減措置が延長されました。具体的には所有権移転登記の税率が0.1%に抑えられ、3,000万円の物件なら通常の3分の1以下で済みます。取得時コストを下げることで、初年度からのキャッシュフロー改善が期待できます。
さらに、住宅金融支援機構の「フラット35アパートローン」は2025年度も継続しており、金利は全期間固定で年1.4%台です。金利上昇リスクを完全に遮断できるため、長期の収支計画が立てやすくなります。これにより、キャッシュフローの変動幅を最小限に抑えられます。
以上の制度を組み合わせると、同じ物件でも実質利回りが1ポイント以上改善するケースがあり、「収益性 やめとけ」と感じた物件が一転して有望になることもあります。ただし、制度の適用条件や期限を満たさない場合は余計なコストが発生するため、必ず専門家に確認してください。
まとめ
結論として、「収益性 やめとけ」という警告は、表面利回りだけを見て判断する危険性を示しています。家賃下落、修繕費、税金、金利上昇を織り込んだ実質キャッシュフローを試算し、公的データで前提を検証することが第一歩です。そのうえで、2025年度に有効な控除や税制優遇を活用すれば、手取り利回りを底上げしリスクを抑えられます。読み終えた今こそ、数字と制度を武器に物件の真の価値を見極め、後悔のない投資判断を下してください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査 2024年度版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 2023年結果 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 マンション維持修繕ガイドライン 2023改訂版 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫 家計調査レポート 2024年 – https://www.jfc.go.jp
- 住宅金融支援機構 フラット35商品概要 2025年度 – https://www.flat35.com

