会社勤めを続けながら不動産投資を始めたいものの、「忙しくて時間がない」「本当に自分にもできるのか」と不安を抱える方は多いでしょう。実は、限られた時間と資金でも計画的に進めれば、給与に頼りきらない収入源を築くことは十分可能です。本記事では、成功事例 サラリーマン の実態をひもときながら、初心者が押さえるべきポイントと2025年9月時点で使える最新制度を解説します。読み終えたころには、具体的な行動イメージが描けるはずです。
サラリーマン投資家が増える背景
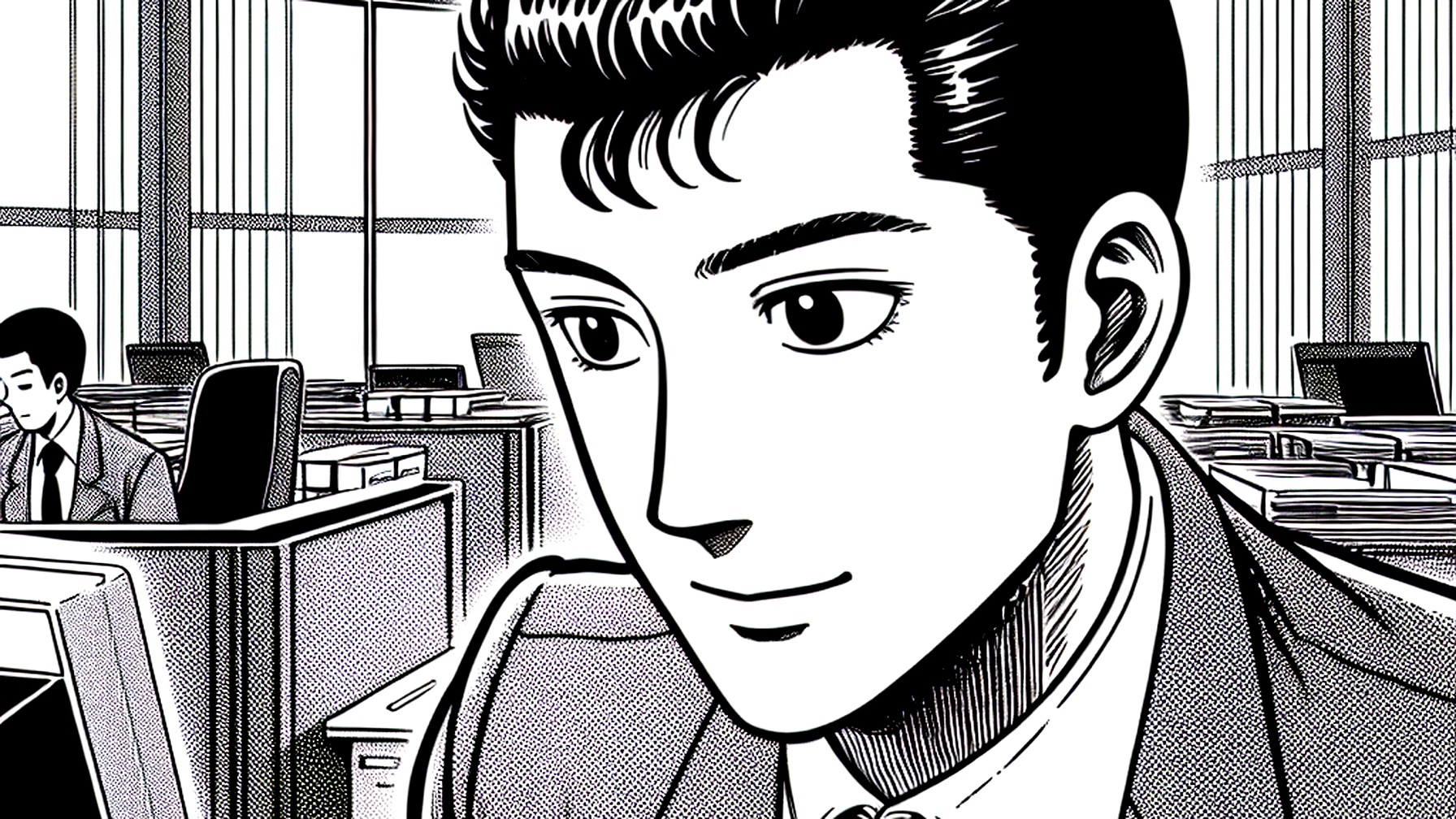
まず押さえておきたいのは、サラリーマンが不動産投資に参入する環境が以前より整っている点です。総務省「就業構造基本調査」によると、副業や兼業を認める企業は2019年から2024年にかけて約1.5倍に増加しました。勤務先が投資そのものを禁止していないケースも多く、勤務外の時間で運営できる不動産は選択肢に挙がりやすいのです。
一方、日本銀行の低金利政策が続くなか、銀行預金だけで資産を守るのは難しくなりました。資産形成の必要性を感じる現役世代が、安定的なキャッシュフローを期待できる賃貸経営へ関心を寄せるのは自然な流れといえます。住宅ローンより高い金利ながら、アパートローンでも固定1.5〜2.5%台を維持できるため、長期の返済計画を立てやすいのも追い風です。
国土交通省「住宅市場動向調査2024」では、投資用区分マンションの平均購入年齢が38.6歳と報告されました。子育てや住宅ローンの真っただ中でも、管理会社を活用することで運営負担を軽減し、投資を開始する人が増えています。この流れを受け、金融機関も給与所得を安定収入として評価しやすいサラリーマン向け商品を強化しています。
重要なのは、こうした追い風があっても自己判断に頼りきればリスクは高まるという点です。次のセクションでは、安定したキャッシュフローを得るための基本指標を整理します。
キャッシュフローの基礎を数字で理解する
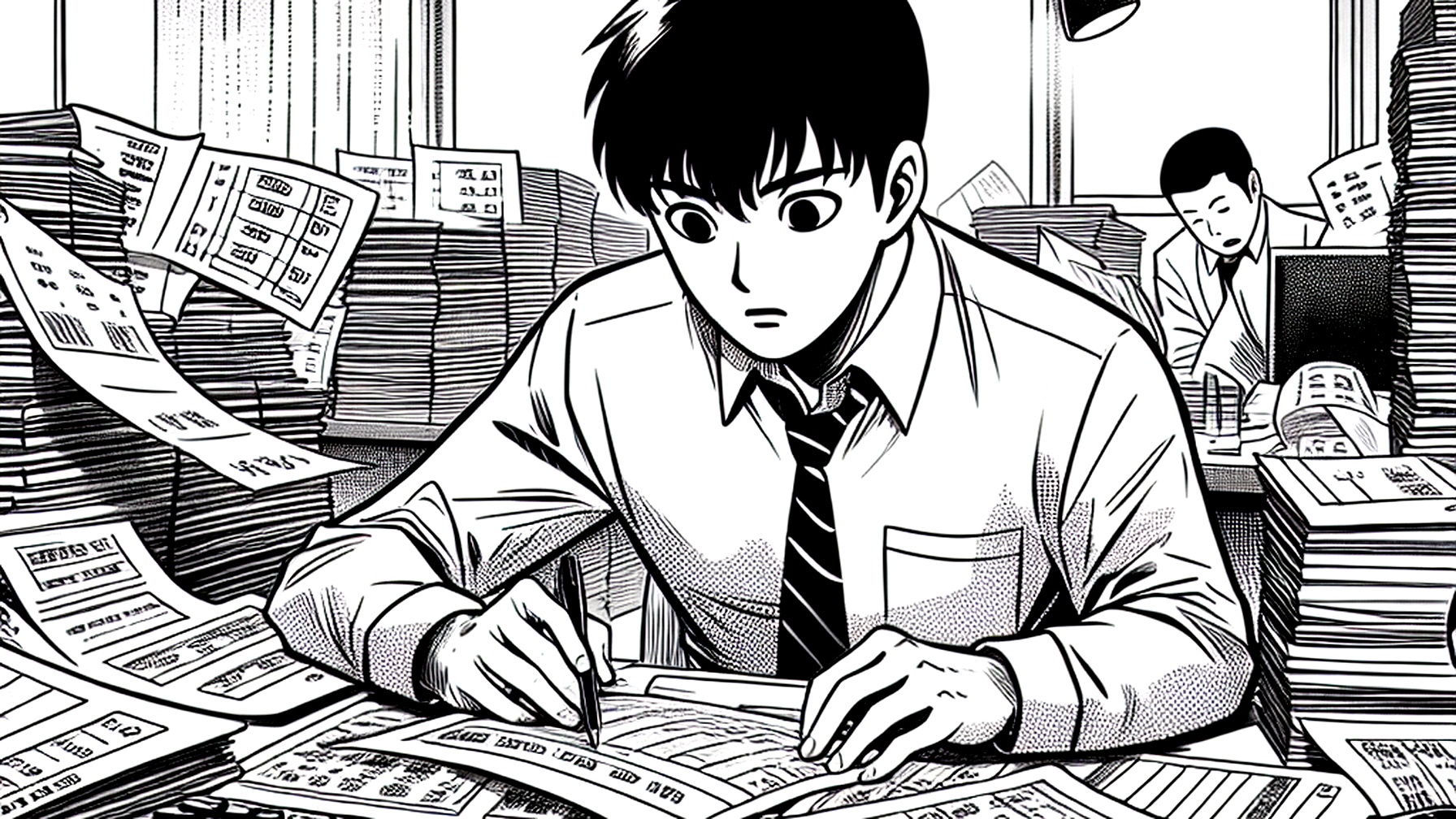
ポイントは、表面利回りとネット利回りを混同しないことです。表面利回りは家賃収入を物件価格で割っただけの単純指標ですが、実際の手残りを示すのは税金・ローン返済・管理費を差し引いたネットキャッシュフローです。
たとえば、価格2,500万円の区分マンションで年間家賃収入が150万円の場合、表面利回りは6%になります。ここから管理費・修繕積立金で年24万円、固定資産税で7万円、ローン返済で90万円が発生すると、手元に残るのは29万円です。つまりネット利回りは約1.2%に過ぎません。数字で検証することで、利回りだけに踊らされず健全な投資判断ができます。
さらに、長期的には空室と修繕が収支を左右します。日本賃貸住宅管理協会によれば、首都圏ワンルームの平均空室期間は1.5か月前後です。この期間を家賃に換算して織り込むと、年間家賃収入は実質約12%減少します。加えて築20年を超えると給排水管更新など大規模修繕が必要になるため、毎月家賃の10%程度を積立金として確保する姿勢が欠かせません。
これらを反映したシミュレーションを作成し、家賃が1割下落したケースや金利が2%上昇したケースでもキャッシュフローが黒字になるか検証することが、サラリーマン投資家にとって実務的な安全装置になります。
成功事例から学ぶ物件選びの着眼点
実は、成功事例 サラリーマン の多くが「都心駅近の中古区分」と「郊外ファミリー向け戸建て」のいずれかに集中しています。都心の中古区分では、賃貸需要の強さと流動性の高さが評価されます。たとえば、東京都品川区の築25年ワンルームを購入したAさんは、購入から8年で2度の家賃改定を行いましたが、募集開始から平均25日で入居が決まり、空室リスクを最小限に抑えています。
一方、郊外の戸建てに取り組んだBさんは、埼玉県川越市の築30年木造を1,100万円で取得し、100万円のリフォームを実施しました。ファミリー層の需要が安定しており、家賃は月9万円。購入から5年で総家賃収入は540万円となり、改修費用を含めた自己資金400万円を早々に回収しています。戸建て投資は管理組合費が不要で、土地値が下支えになる点がメリットです。
成功者に共通するのは、投資目的に合った出口戦略を描いていることです。Aさんは将来の売却益を見込み、物件をフルローンで取得してインカムゲイン(賃料収入)よりキャピタルゲイン(売却益)を重視しました。Bさんは長期保有を前提に固定金利を選択し、家賃を年金代わりに受け取る計画です。つまり、自分のライフプランに沿った物件を選ぶことで、投資効率は大きく変わります。
融資戦略と資金計画を立てる手順
重要なのは、融資条件が投資成否を大きく左右する点です。サラリーマンの場合、勤続年数3年以上・年収500万円以上であれば、地銀や信金で物件価格の80〜90%まで融資を受けられるケースが多く見られます。住宅ローンと違い、頭金ゼロでも組める商品はありますが、毎月のキャッシュフローが薄くなるため注意が必要です。
資金計画では、自己資金の20%を頭金、10%を予備費として確保する方法が堅実です。たとえば、3,000万円のアパートを購入するなら、頭金600万円、予備費300万円を用意するイメージです。日本政策金融公庫の「生活衛生改善貸付」を利用すると、リフォーム費用を低金利で賄える場合もあり、自己資金を温存する選択肢が増えます。
返済比率(年間返済額 ÷ 年収)は30%以内に抑えると、住宅ローンや教育費と重なっても家計が圧迫されにくくなります。加えて、退職金を前倒しで担保に取られることがないか、団体信用生命保険の適用範囲は十分か、といった細部を見逃さないことが結果としてリスク低減につながります。
2025年度に利用できる税制・補助制度の活用ポイント
まず押さえておきたいのは、「租税特別措置法第26条の不動産所得損益通算」が2025年度も継続している点です。所得が900万円以下の場合、減価償却や修繕費で発生した赤字を給与所得と通算できるので、キャッシュフロー以上に手取りが増えるケースがあります。
また、2025年度の「住宅省エネ改修促進税制」では、賃貸物件でも断熱改修や高効率給湯器設置にかかった費用の10%(最大25万円)が所得税額から控除されます。郊外の中古戸建てをリノベーションする際、この制度を適用すれば実質コストを抑えつつ賃料アップと入居促進が期待できます。
さらに、地方自治体によっては「空き家再生補助金」を2027年3月まで延長している地域があります。補助率や上限額は自治体ごとに異なりますが、リフォーム費用の2分の1、上限100万円前後が目安です。制度利用には事前申請が必須なので、購入前に必ず確認しておきましょう。
最後に、配偶者と共有名義で購入する場合には、2025年度も配偶者控除の適用が可能です。共有割合に応じて所得を分散できるため、課税所得を抑えられる点は見逃せません。制度は地域・年度で変更されることがあるため、国税庁の最新情報をこまめにチェックする姿勢が求められます。
まとめ
本記事では、サラリーマンが不動産投資で成功するために必要な視点を、キャッシュフロー計算から融資・制度活用まで体系的に整理しました。成功事例 サラリーマン に共通するのは、自分のライフプランを軸に物件タイプと融資条件を選び、数字で収支を管理している点です。まずは手元の資金と家計を洗い出し、小規模でも実践可能な物件を選ぶところから一歩を踏み出してください。行動と検証を繰り返すことが、将来の安定収入への最短ルートになります。
参考文献・出典
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 日本銀行 金融システムレポート – https://www.boj.or.jp
- 日本賃貸住宅管理協会 – https://www.jpm.jp
- 国税庁 タックスアンサー – https://www.nta.go.jp

