投資用マンションを調べていると、「一棟買いは利回りが高いらしい」「でも区分所有よりリスクが大きいのでは」と迷う方は少なくありません。自己資金も融資額も大きくなるため、不安を抱くのは当然です。本記事では、一棟マンション投資の仕組みから物件選び、資金計画、最新の税制情報まで網羅的に解説します。仕組みを正しく理解すれば、初心者でもリスクを抑えながら安定収益を狙える手法です。読み終える頃には、ご自身が次に取るべき具体的なアクションをイメージできるはずです。
一棟買いと区分所有の違い
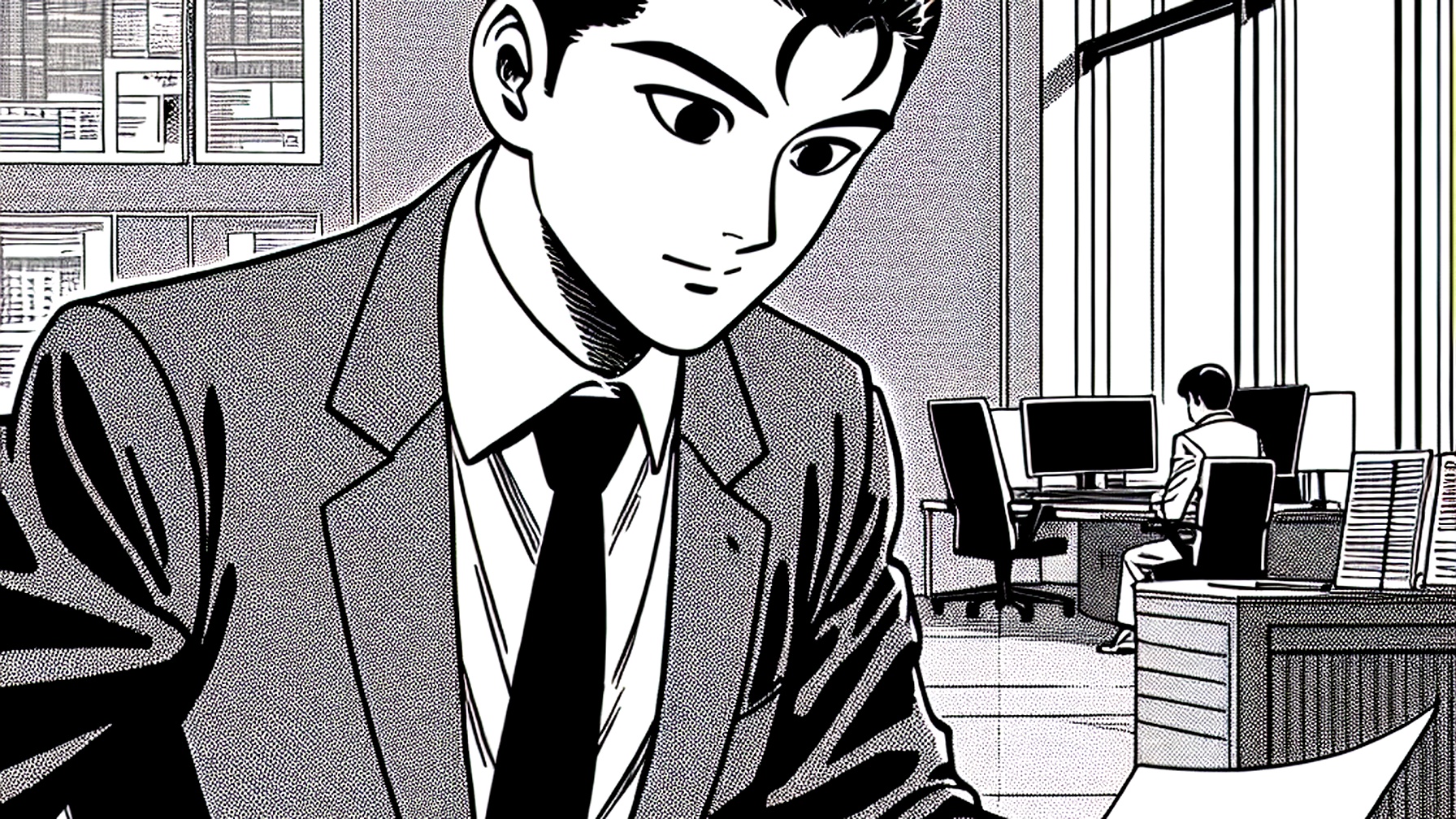
重要なのは、収益構造と管理責任の差を把握することです。一棟買いでは建物全体を所有するため、家賃収入の総額がそのままキャッシュフローの源泉になります。また、共用部の修繕計画やテナント構成を自分で決められる自由度の高さも魅力です。
一方で、区分所有は管理組合が存在し、修繕の意思決定に時間がかかることがあります。これに対し、一棟所有者は全責任を負う代わりに意思決定が迅速です。入居募集やリフォームを即時に実行できるため、市場変化に柔軟に対応できます。
ただし、負債も一括で背負う点は覚悟が必要です。例えば、築20年・総戸数20戸の中規模マンションを2億円で購入する場合、自己資金2,000万円、残りを金利1.8%、期間25年で借り入れると、年間元利返済は約970万円になります。空室率10%なら年間家賃収入は約1,800万円ですから、返済後の手残りより修繕費を差し引くと、実質利回りは表面利回りの半分程度に下がることもあります。つまり、家賃収入の総額が大きい点に安心せず、細かな費用まで試算する姿勢が欠かせません。
資金計画と融資の基本
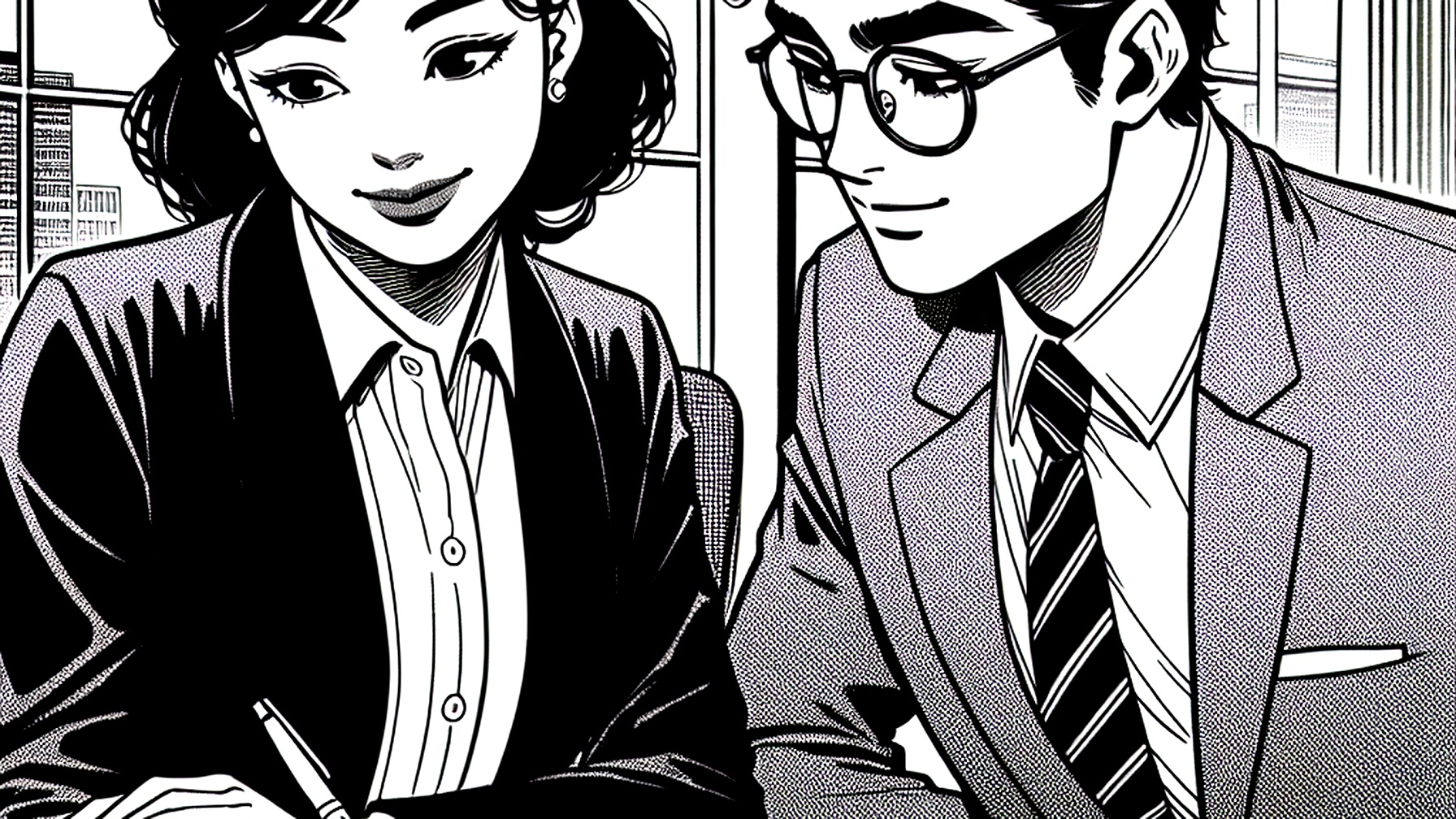
まず押さえておきたいのは、金融機関が一棟買いに対して重視する「担保力」と「事業性」です。土地値が高い都心立地や、築浅RC(鉄筋コンクリート)造は評価が出やすく、自己資金10〜20%でも融資が通る可能性があります。
日本政策金融公庫の2025年度不動産投資向け融資統計によると、自己資金比率の中央値は22%でした。健全な資金計画としては、物件価格の2割に加え、購入時諸費用(おおむね物件価格の8%)と突発修繕費を合わせた3割程度を現金で確保すると安心です。修繕積立金を毎月家賃収入の5%ほど積み立てると、10年後の大規模修繕に備えやすくなります。
また、金利タイプの選択も長期収益を左右します。変動金利は1%台前半から組めますが、将来の金利上昇リスクがあります。固定金利は当面2%台後半が目安で、返済額が読める安心感が強みです。金融機関ごとに審査基準が異なるため、同行に固執せず複数社へ事業計画書を提示し、見積もりを比較することが成果につながります。
物件選びで押さえる立地と構造
ポイントは、人口動態と賃貸需要の継続性です。総務省「住民基本台帳人口移動報告」では、東京23区への転入超過は2024年度に6万人を超え、2025年も同程度で推移しています。したがって23区内の駅徒歩10分圏は、空室リスクが相対的に低いことがデータから裏付けられます。
構造面では、RC造は耐用年数47年と長く、金融機関の評価が高い点が強みです。木造は表面利回りが高く自己資金を抑えられますが、法定耐用年数が22年と短いため、築古の融資期間は厳しく設定される傾向があります。
実は、築年と立地の組み合わせで収益パターンは大きく変わります。たとえば、築30年のRC造をリノベーションして家賃を1万円上げられれば、年間240万円の増収です。利回り改善だけでなく、将来の出口戦略として売却価格も底上げしやすくなります。逆に、郊外で築浅でも周辺に競合の建売が増えているエリアでは、将来の賃料下落リスクが高まります。現地の人口構成や開発計画を細かくチェックすることが必須です。
収支シミュレーションの作り方
実務で大切なのは、最悪ケースでもキャッシュフローが赤字にならない計画です。不動産経済研究所の2025年新築マンション平均価格によれば、東京23区の平均は7,580万円で前年比3.2%上昇しました。価格上昇局面では取得コストが増えるため、家賃設定の上限と空室期間を厳しめに見積もります。
シミュレーションでは、①家賃下落2%、②空室率15%、③金利上昇1%という保守的条件を盛り込みます。これらは国土交通省「賃貸住宅市場の将来見通し調査」で示された平均的な変動幅を参考にしています。運営費は家賃収入の20〜25%を想定し、固定資産税や火災保険を含めると、手取りは表面利回りの半分程度に落ち着くのが一般的です。
また、出口戦略の想定価格を入れて内部収益率(IRR)を計算すると、長期的な比較がしやすくなります。例えば10年後に物件価格が10%下落しても、年間手残り400万円を確保できれば、自己資金2,500万円に対してIRRは7〜8%に到達します。株式配当やREITと比較しても遜色ない水準であり、リスクに見合うリターンかどうか判断しやすくなるでしょう。
2025年度の税制・補助金の注意点
まず、投資用マンションは原則として住宅ローン減税の対象外です。借入金利を経費算入できる代わりに、個人の所得税控除は受けられません。
一方で、新築または一定要件を満たす大規模リフォームを行った賃貸住宅には、固定資産税が3年間1/2になる措置(地方税法第349条の3)が2025年度も継続しています。適用には、①居住用であること、②床面積が40〜280㎡、③工事完了後6カ月以内の申告、という条件を満たす必要があります。
さらに、中小企業経営強化税制の「建物附属設備の即時償却」も2025年度まで延長されています。耐用年数が10年以上残る設備を省エネ型へ更新した場合、取得価額の全額を初年度に経費計上でき、キャッシュフローの改善効果が高い制度です。いずれも期限があるため、購入計画と改修時期を逆算してスケジュールを組むと良いでしょう。
まとめ
一棟マンション投資は、区分所有よりも裁量の幅が広く、資産拡大のスピードを高められる手法です。しかし、購入金額もリスクも比例して大きくなるため、保守的な収支シミュレーションと長期の資金計画が欠かせません。立地選定では人口動態と賃貸需要をデータで裏付け、構造の違いによる融資条件の変化にも注目しましょう。さらに、2025年度に有効な固定資産税の軽減や設備投資減税を活用すれば、キャッシュフローを安定させやすくなります。次のステップとして、気になるエリアの金融機関へ事前相談を行い、具体的な返済条件と評価額を確認してみてください。行動を起こすことで、数字と肌感覚の両面から投資判断の精度が高まります。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp/
- 国土交通省 賃貸住宅市場の将来見通し調査 – https://www.mlit.go.jp/
- 日本政策金融公庫 2025年度中小企業向け融資実績 – https://www.jfc.go.jp/
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.stat.go.jp/
- 地方税法第349条の3(固定資産税の軽減措置) – https://elaws.e-gov.go.jp/

