不動産投資に興味はあるものの、「高齢の親から資産を受け継ぐ時期が近づいてきた」「相続税がどのくらいかかるのか不安だ」と感じていませんか。築浅アパート経営はキャッシュフローを生みながら相続税評価額を抑えやすく、家族への資産承継に適した手法です。本記事では、初心者が押さえるべき基礎から2025年度に利用できる具体的な制度、物件選びの注意点までを丁寧に解説します。読み終える頃には、自分に合った相続対策の方向性が見え、最初の一歩を踏み出す勇気が得られるはずです。
相続とアパート経営が相性の良い理由

まず押さえておきたいのは、賃貸用不動産の相続税評価額が実勢価格より低く算定される点です。国税庁の路線価方式では、自用地と比べて借地権や借家権の控除が入るため、評価額がおおむね70%前後に下がります。さらに建物は固定資産税評価で計算されるので、築浅でも新築価格より大幅に圧縮される仕組みです。つまり、保有中は家賃収入を得ながら、相続時には現金より低い税負担で承継できる可能性があります。
一方で空室リスクが高い物件を選ぶと、税金は減っても収支が赤字になり本末転倒です。国土交通省住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で前年から0.3ポイント改善しましたが、地域差は依然大きいと報告されています。相続対策として取り組む場合でも、安定運営を前提にエリア分析を行うことが欠かせません。
築浅アパートのメリットと潜在的リスク
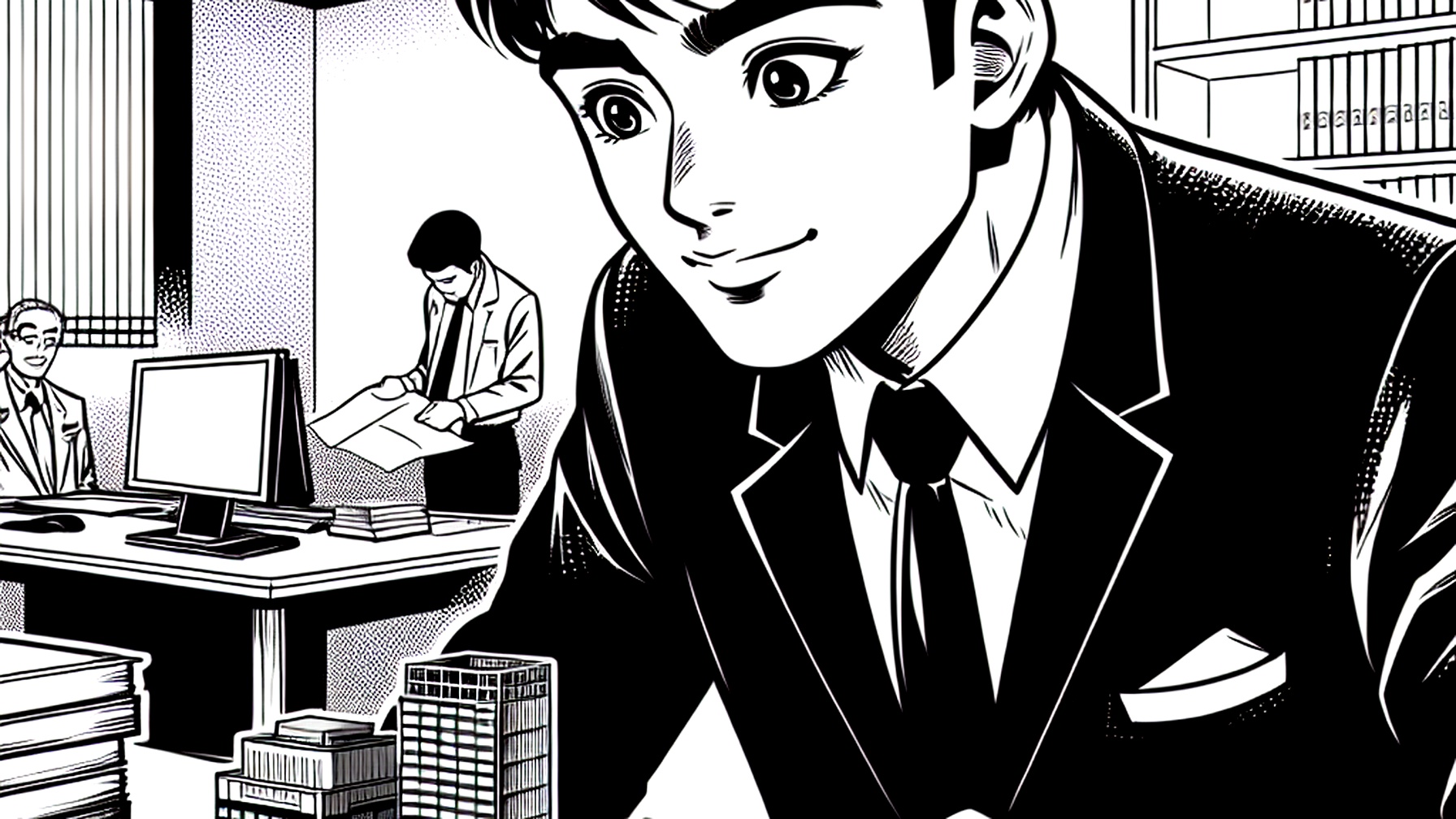
ポイントは、築浅アパートが「見栄えの良さ」と「修繕費の読みやすさ」を兼ね備えている点です。築5年以内なら外観や設備が現代的で、入居者募集の際も写真映えします。加えて主要構造部分の大規模修繕は10年超を見込めるため、当面のキャッシュフローが読みやすいです。
ただし購入価格が高めに設定されやすいのが難点です。想定利回りが都心部で4〜6%、地方都市で6〜8%にとどまるケースも珍しくなく、ローン金利がわずかに上がるだけで手残りが減る恐れがあります。また、築浅物件でも管理コストを軽視すると入居者満足度が下がり、結果的に空室期間が延びます。長期運営を視野に、建物管理会社の体制や修繕計画の透明性を確認しておきましょう。
キャッシュフローと税負担のバランスを読む
実は、相続対策とキャッシュフロー改善は両立できます。家賃収入がローン返済と運営費を上回り、年間手残りが物件価格の2〜3%程度確保できれば資金繰りは安定しやすいです。そのうえで、減価償却費を利用して所得税を圧縮すると、手元キャッシュをさらに厚くできます。築浅木造アパートの法定耐用年数は22年ですが、中古扱いになると残存耐用年数が短くなり、償却幅が広がることがあります。この仕組みを理解すると、実質利回りの計算精度が上がります。
一方で過度な赤字計上は税務調査の対象になりやすいので注意が必要です。特に親子間売買の場合は、適正価格か、融資条件は常識的かなどを専門家と確認しましょう。税理士や不動産鑑定士に早めに相談し、シミュレーションを毎年更新しておくと安心です。
2025年度に活用できる主な相続対策制度
基本的に、築浅 アパート経営 相続対策を組み合わせる場合、以下の制度が軸になります。
1. 小規模宅地等の特例(2025年度) 2. 相続時精算課税制度(2025年度) 3. 住宅取得等資金の贈与非課税特例(2025年12月31日契約分まで)
小規模宅地等の特例では、貸付事業用宅地は200㎡まで50%評価減が認められます。土地値が高い都心では減税効果が大きく、築浅アパートとの相性が良好です。相続時精算課税制度を使えば、生前に建築資金を子へ贈与する際、2,500万円まで贈与税が非課税となり、将来の相続税計算に組み込めます。贈与時点で評価額を確定できるため、将来土地値が上がると予想される場合は有効です。
一方で利用条件や手続きは複雑で、例えば相続時精算課税は一度選択すると暦年贈与へ戻れません。制度名と期限、適用範囲を把握し、税理士と二重三重に確認してから動くことが肝心です。
物件選びと運営で失敗しないための視点
まず、需要が読める立地を選ぶことが最重要です。周辺人口が減少していない、駅徒歩10分以内、大学や商業施設へ自転車圏内など、入居ターゲット像が明確な場所を探します。次に、築浅アパートはサブリース契約が提示されることが多いですが、賃料改定条項や中途解約条件を必ずチェックしてください。固定家賃保証に安心しても、10年後の減額が大きいケースがあります。
さらに融資条件は金利だけでなく、返済期間も重要です。35年フルローンが組める場合でも、利息総額が増えすぎないよう20〜25年で試算し直すとリスクに気づけます。入居付けの実績を持つ管理会社を選定し、家賃査定に根拠があるか、オンライン募集の対応状況はどうかなどを具体的に質問しましょう。
結論として、相続対策を成功させるには税務・融資・管理の三側面を同時に最適化する姿勢が欠かせません。相談先をワンストップでまとめると、手続きの抜け漏れを防ぎやすくなります。
まとめ
相続税評価を抑えつつ家賃収入を得られる築浅アパート経営は、現金や株式だけでは実現しにくい資産承継の選択肢です。土地評価減、減価償却、2025年度の各種特例を組み合わせれば、税負担とキャッシュフローの両立が期待できます。ただし空室リスクやローン条件を見誤ると、節税効果を帳消しにしかねません。物件選びと制度活用は早い段階から専門家と緻密に計画し、家族全員が納得できる形で進めることが成功への近道です。今日から情報収集を始め、まずは気になるエリアを歩いてみましょう。そこで得た肌感覚こそ、長期運営を支える最初の一歩になります。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅統計調査 2025年7月速報値 – https://www.mlit.go.jp/statistics
- 国税庁 相続税評価基準書 2025年度版 – https://www.nta.go.jp
- 財務省 税制改正の解説 2025年度 – https://www.mof.go.jp
- 総務省 人口推計 2025年4月公表 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート 2025年6月 – https://www.boj.or.jp

