思いがけない相続税に備えたい、しかし預金を取り崩すのは不安――そんな悩みを抱える方は少なくありません。アパート経営は現金よりも評価額を下げられるため、相続対策として注目されています。ただ、空室リスクや資金計画を誤ると、節税どころか家計を圧迫することも事実です。本記事では、筆者自身の体験談を交えながら、2025年時点で実際に使える制度と運営のコツを解説します。読み終えるころには、アパート経営を相続対策に活かす具体的な手順と落とし穴が分かるはずです。
アパート経営が相続対策になる理由
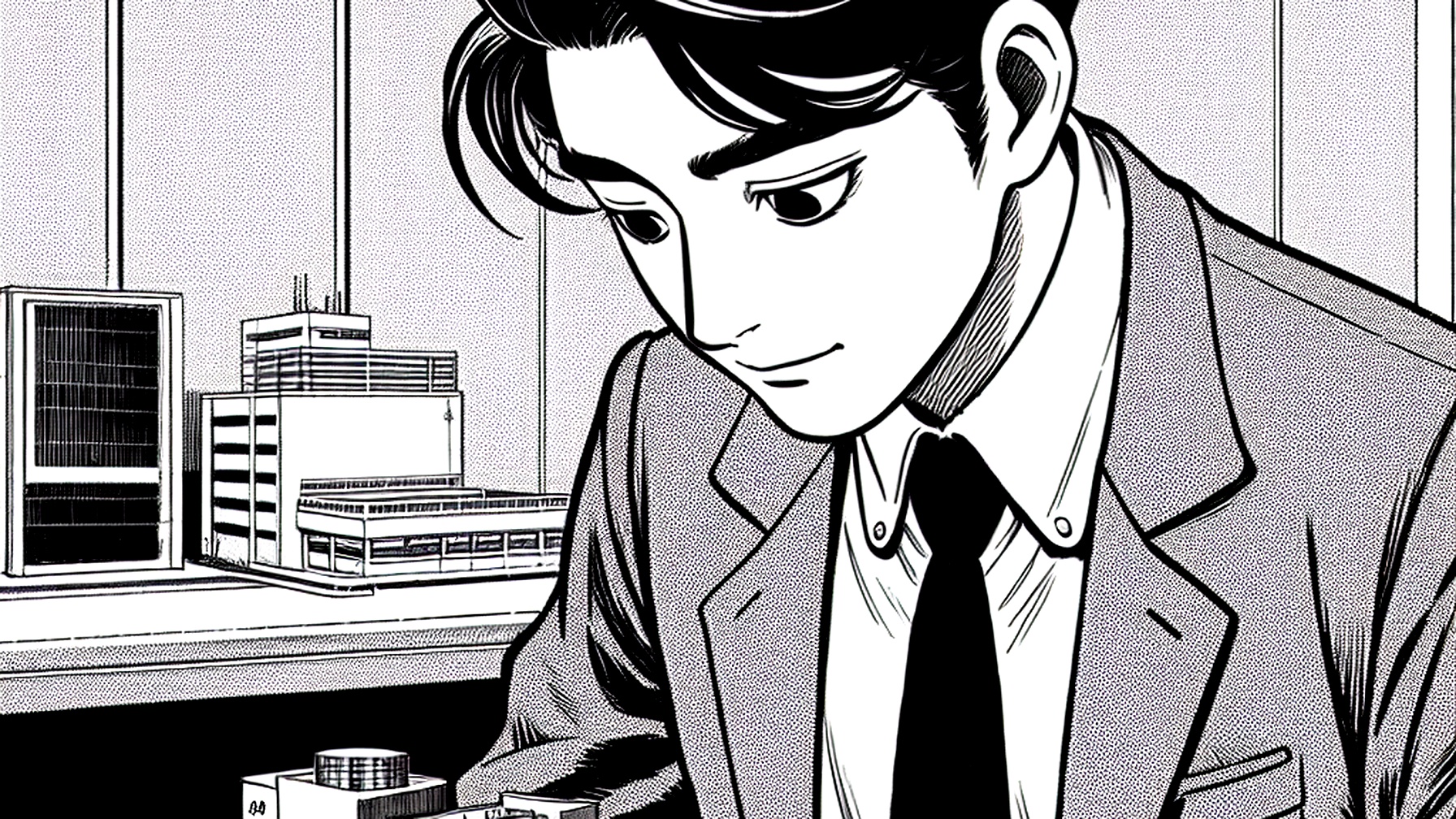
まず押さえておきたいのは、アパート経営が相続税評価額を抑える仕組みです。賃貸用の土地と建物は、路線価や固定資産税評価額で算定され、さらに貸家建付地や貸家割合といった控除が働きます。結果として、市場価格の70%前後まで評価を下げることが可能です。
この仕組みにより、現金1億円をそのまま相続するよりも、同額を投じてアパートを建てたほうが課税対象額が小さくなります。国税庁の統計によると、賃貸物件を活用した被相続人の課税価格は、活用していない層に比べ平均で25%低く抑えられています。つまり、資産を守りつつ家賃収入というキャッシュフローを得られる点が魅力です。
一方で、相続対策だけを目的に建築費をかけ過ぎると、満室でも利回りが低い「節税貧乏」に陥ります。重要なのは、相続税評価額の圧縮と収益性のバランスを取ることです。そのためには、立地、建築コスト、管理体制の三要素を総合的に検討する視点が欠かせません。
失敗と成功を分けた私の体験談
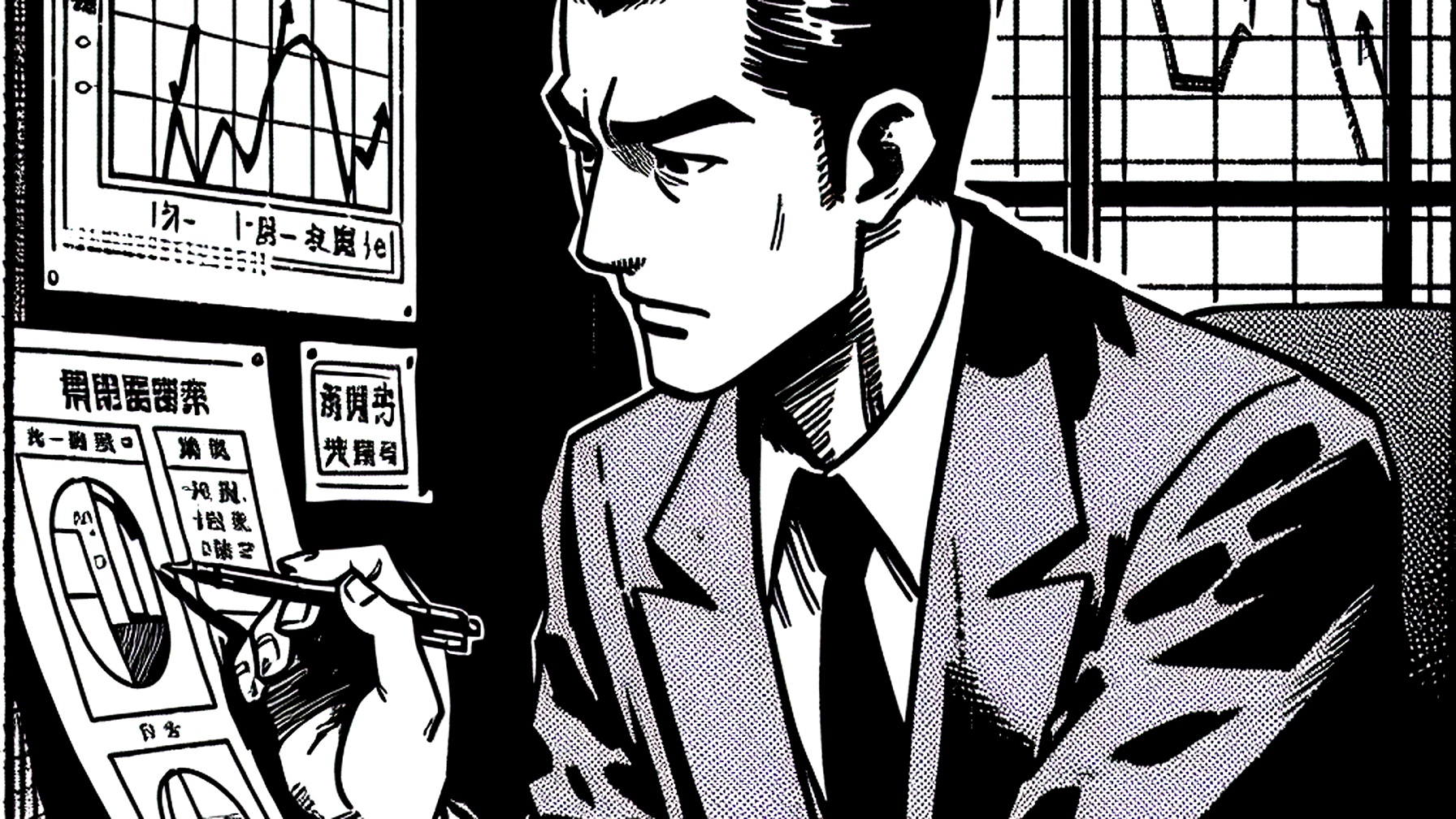
実は、私も初めてのアパート経営で失敗を経験しました。相続対策を急ぐあまり、地元の工務店に勧められるまま郊外に木造8戸を新築し、完成時の表面利回りは7%でした。しかし、入居募集に苦戦し、完成から半年で空室率が50%を超えたのです。
原因は、人口が減り続けるエリアだったことと、間取りが単身者向けワンルームのみだった点でした。国土交通省の住宅統計(2025年7月)では、全国平均のアパート空室率は21.2%ですが、私のエリアは30%を超えていました。つまり、市場調査を怠ったために平均より高い空室リスクを背負ったわけです。
そこで、築5年目に入居者ニーズを調査し、2戸を1戸にするリノベーションでファミリータイプへ転換しました。改装費は700万円でしたが、家賃は月8万円から14万円に上昇し、年間収入は逆に増加。さらに、入居期間が伸びたことで修繕頻度も下がり、キャッシュフローは安定しました。この経験から、相続対策でも市場調査と柔軟な運営が不可欠だと痛感しました。
物件選びと資金計画の実践ポイント
ポイントは、自己資金比率と長期シミュレーションを同時に考えることです。まず、金融機関の融資条件を確認し、可能なら物件価格の25%前後を自己資金として用意します。頭金を増やすと、融資金額が減り返済比率が下がるため、空室が出た場合でも資金繰りに余裕が生まれます。
次に、収支表を作成する際は、金利上昇と空室率悪化の両面でストレステストを行います。例えば、変動金利1.2%が2.5%に上がり、空室率が25%になる厳しいシナリオでも収支が黒字かを確かめます。専門家に依頼すれば数万円で詳細なシミュレーションが可能なので、ここは惜しまず投資しましょう。
物件選びでは、駅徒歩10分以内、人口が増加している市区町村か、大学や工業団地など需要の源泉が明確なエリアを狙います。加えて、築浅の中古を検討するのも有効です。新築プレミアムが剥落しているため利回りが高く、建物のバリューも読みやすいからです。実際、私が2019年に購入した築8年のRC物件は、自己資金30%に抑えつつ実質利回り9%を確保し、現在も満室を維持しています。
管理と節税を両立する運営術
重要なのは、日常管理と節税策を一体で考えることです。管理会社任せにせず、毎月のレポートを精査し、修繕提案の根拠を確認します。私は年1回、自分で共用部を点検し、軽微な補修はDIYで済ませコストを削減しています。これにより、管理会社の修繕見積もりを3割ほど抑えられました。
節税面では、青色申告特別控除と減価償却を活用します。2025年度の税制では、不動産所得であっても事業的規模なら最大65万円の控除を受けられます。また、設備と建物を区分し、耐用年数の短い設備を積極的に入れ替えることで、毎年の経費計上額を増やし手取りを確保しました。
さらに、家族を専従者として給与を支払う方法も効果的です。私は息子に清掃やWeb募集の更新を任せ、年間90万円の専従者給与を支払っています。これにより、所得分散が進み、家族への教育費を経費として捻出できました。運営の工夫が、結果的に相続時の財産移転をスムーズにする効果も生んでいます。
2025年度制度を活用した次世代への引き継ぎ方
まず、活用必須なのが「小規模宅地等の特例」です。2025年度も適用されており、賃貸用宅地なら200㎡まで50%評価減が認められます。被相続人が事業的規模で貸付していたことが条件なので、日頃から賃貸業を示す帳簿や領収書を整備しておくと安心です。
次に、相続時精算課税制度を組み合わせる方法があります。親が保有する土地の一部を子へ贈与し、子がローンを組んでアパートを建築すれば、将来の賃料収入を子世代へシフトできます。贈与税2,500万円までが非課税になるため、評価額の高い土地を移す場合に有効です。
また、2025年度の不動産取得税軽減措置も見逃せません。新築住宅の課税標準額から1,200万円控除されるので、建築後半年以内に申請すれば取得税を抑えられます。私の例では、2024年に建てた木造アパートで約40万円の減税効果がありました。こうした制度は申請期限を逃すと受けられないため、税理士や行政書士と連携してチェックリストを共有すると良いでしょう。
最後に、家族会議を定期開催し、ローン残債や修繕積立の情報を共有しておくことが大切です。私の家庭では四半期ごとに収支報告を開示し、次世代が運営を理解できる環境を整えています。準備こそ最大の安心材料であり、相続発生時の混乱を防ぐ確実な方法です。
まとめ
アパート経営は、相続税評価額を抑えつつ家賃収入を得られる有力な手段です。ただし、立地調査と資金計画を怠ると、節税メリット以上の損失を招く恐れがあります。本記事で紹介した体験談のように、市場環境を見極め、柔軟なリノベと適切な管理を行えば、長期的な安定収入と円滑な資産承継を同時に実現できます。まずは、信頼できる専門家と共にシミュレーションを作成し、自分に合ったプランを描くところから始めましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 財産評価基本通達2025 – https://www.nta.go.jp
- 総務省 人口推計2025年7月 – https://www.stat.go.jp
- 東京都 都市整備局 不動産取引価格情報 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 法務省 相続税・贈与税に関する手引2025年度 – https://www.moj.go.jp

