アパート経営を検討するとき、多くの人が「建物を建てるお金は結局誰が払うのだろう」と戸惑います。自己資金だけでは足りないのではと心配になり、ハウスメーカーに相談しても説明が専門的で分かりにくい場合があります。本記事ではこの疑問に正面から向き合い、アパート経営 建築費 誰がというキーワードを軸に、資金の流れや負担者の違いを整理します。読めば、資金調達の仕組みと費用削減のヒントが分かり、安心して次の一歩を踏み出せるはずです。
建築費の基本構造を押さえよう
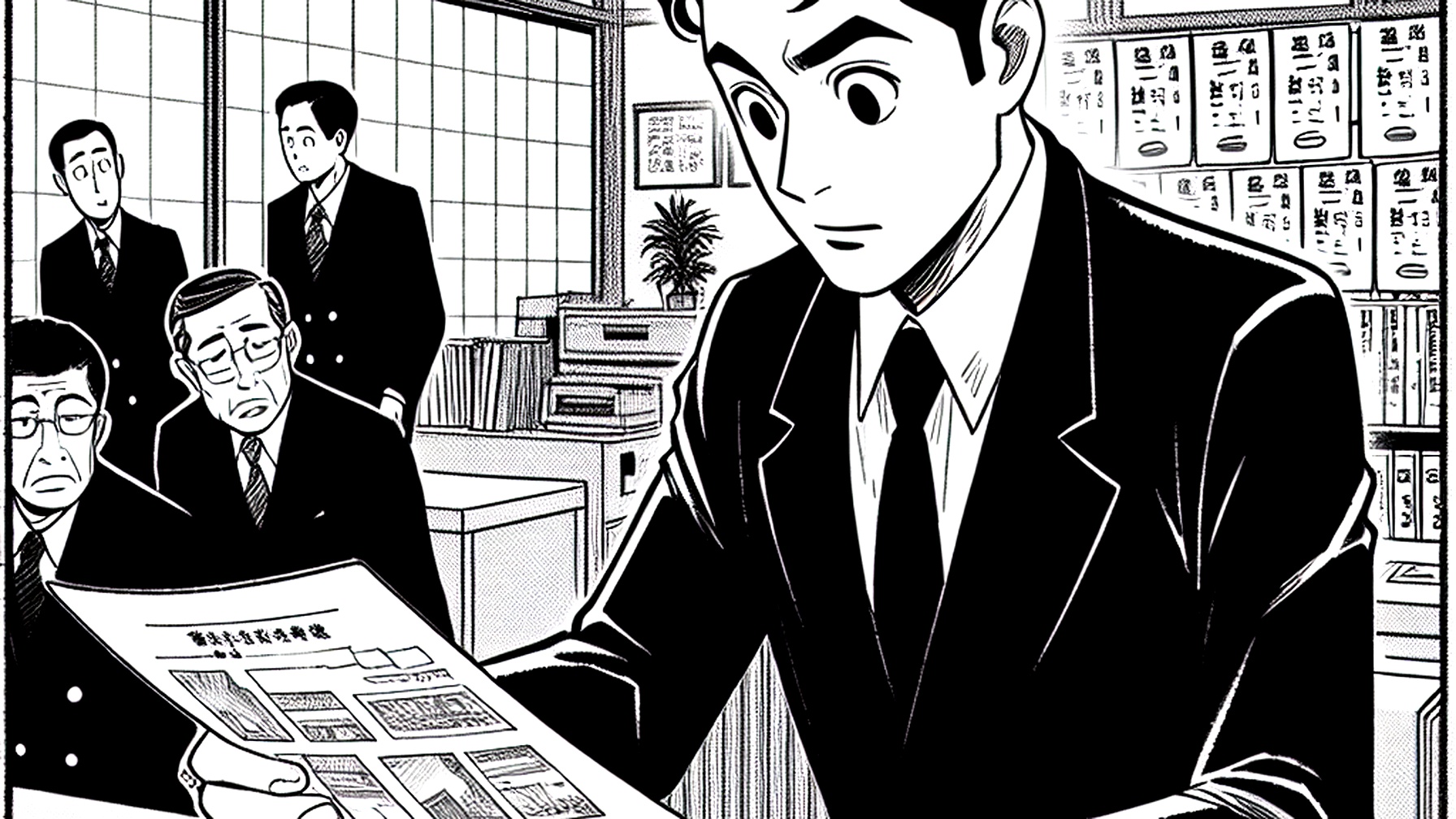
まず押さえておきたいのは、建築費が本体工事費だけでは完結しない点です。設計料、地盤改良費、外構工事費、さらには消費税まで含めた総額が必要になります。
本体工事費は建物本体を造るための費用で、おおむね総コストの七〇%前後を占めます。残りの三〇%が付帯工事や諸経費で、地盤が弱い土地では改良費が数百万円単位で増えることもあります。つまり、見積書を見るときは「本体価格が安いから安心」と短絡的に判断しないことが重要です。
さらに、二五年七月の国土交通省住宅統計では全国の平均建築単価が木造三階建てで一坪六十万円前後と示されています。しかし土地条件や仕様によって二割以上の差が生じるため、地域の相場情報と自分の土地状況を照合しながら予算を組む必要があります。
土地オーナーが負担するケース
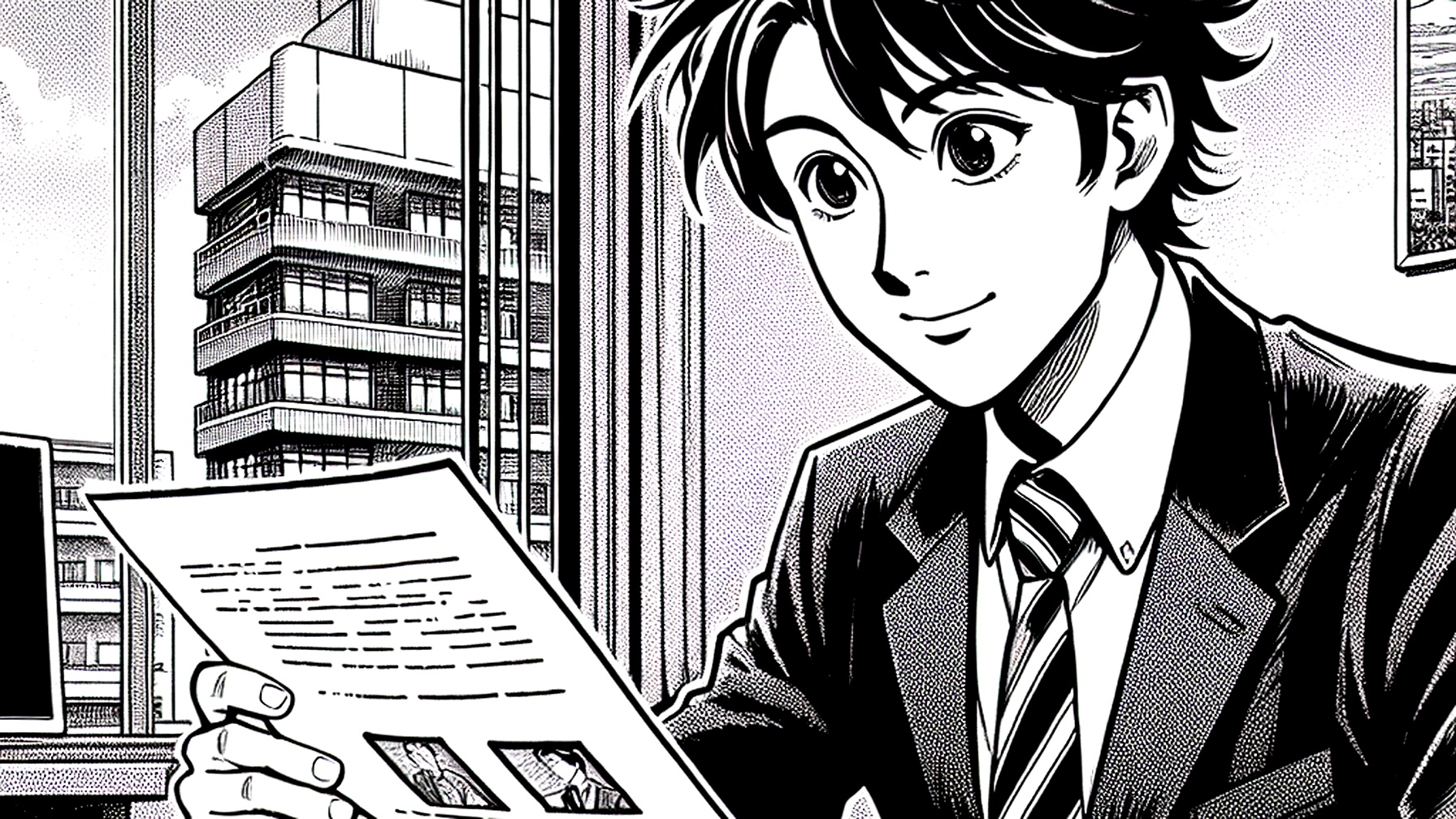
基本的に、自分の土地に自分の名義でアパートを建てる場合、建築費を負担するのは土地オーナー本人です。金融機関からの融資を受ける際も、建物と土地を一体で担保提供する形が一般的です。
ここでポイントになるのが自己資金の割合です。二〇二五年時点で都市銀行のアパートローンは、自己資金一割から二割を求める傾向が続いています。自己資金が少ないほど金利が上がりやすく、返済負担が膨らむため、頭金を厚くするのが安全策です。
また、所有土地を活用する場合は贈与税や相続税の圧縮効果も期待できますが、建物分の借入が増えると債務控除が複雑になるため、税理士にシミュレーションを依頼しておくと後悔を防げます。つまり、建築費を自ら負担するときは、税務と資金繰りの二面から準備を進めることが成功への近道です。
ハウスメーカー提案型の費用配分
実は、ハウスメーカーが土地探しから建築まで一括提案するプランでは、費用を「建物価格」と「土地付き販売価格」に分けて提示することが多いです。この場合、建築費は最終的に買主が負担しますが、契約形態によって資金の流れが変わります。
一つは売買契約で土地建物をまとめて購入する方式で、このときは建築会社が販売会社を兼ねるため、着工前に多額の手付金を要求されることがあります。もう一つは土地はオーナーが取得し、建物を請負契約で建てる方式で、こちらは出来高払いが一般的です。
後者では中間金を二回から三回に分けて支払い、完成時に残額を払うため、融資実行のタイミングを金融機関と綿密に調整する必要があります。スケジュールを誤ると、工事の進捗に合わせて自己資金を一時的に多く投入する羽目になりかねません。したがって契約前に支払い条件と融資実行日をひとつひとつ確認しておくことが不可欠です。
金融機関と補助金の関わり方
金融機関は二〇二五年度も、アパート建築資金に対し長期固定型と変動型の両方を用意しています。固定金利は二%台後半、変動金利は一%台半ばが目安ですが、自己資金割合や返済比率で上下します。重要なのは、長期経営を見据えた場合、空室率の変動を加味して毎月キャッシュフローを把握することです。
補助金に関しては、国土交通省が推進する「サステナブル建築物等先導事業(木造共同住宅部門)」が二〇二五年度も継続中です。省エネ性能を高めた木造アパートに対し、上限三五〇万円の補助が受けられる可能性があります。期限は二〇二六年三月交付申請分までと発表されていますので、活用するなら設計初期で要件を満たす必要があります。
なお、補助金は融資とは別枠で交付されるため、金融機関の審査には直接影響しません。ただし、補助金を自己資金の一部に充当すると見なされるケースもあり、融資計画に好影響を及ぼす場合があります。申請手続きには建築士の協力が欠かせないため、対応実績のある設計事務所を選ぶとスムーズです。
コスト削減の現実的なアプローチ
ポイントは、建築費を削るというより、将来の修繕費を抑える視点で仕様を選ぶことです。例えば外壁をサイディングからタイル貼りに変えると初期費用は一五%ほど上がりますが、再塗装周期が長くなり、二〇年トータルでは支出が逆転することも珍しくありません。
また、室内設備は入居者ニーズに直結します。二〇二五年の全国賃貸住宅新聞の調査では、インターネット無料対応の物件が空室期間を平均で一〇日短縮しています。初期投資五万円程度のインターネット設備を設置するだけで家賃維持に寄与するなら、長期収益を考えればむしろプラスです。
最後に、複数の施工会社から同一仕様で見積もりを取り、価格差の根拠を突き合わせる手間を惜しまないでください。同じ木造二階建てでも、構造計算の有無や保証内容が異なれば金額は簡単に数百万円開きます。比較材料がそろえば、値引き交渉も理論的に進められ、不要なオプションを削るだけでなく、必要な品質を守りながら総コストを下げることが可能になります。
まとめ
ここまで、建築費の内訳、負担者のパターン、融資と補助金の関係、そして賢いコスト削減策を順に見てきました。重要なのは、誰が建築費を負担するかは契約形態で決まり、最終的に返済責任を負うのはオーナー自身だという現実です。そのうえで、融資条件と補助金を組み合わせ、省エネ仕様や長寿命素材を選ぶことで、長期的な収支を安定させられます。この記事を参考に、まずは複数の見積もりと資金計画を並べ、数字とスケジュールを可視化するところから始めてください。堅実な準備こそ、将来の空室リスクを跳ね返す最大の武器になります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp/statistics/
- 国土交通省 サステナブル建築物等先導事業概要 – https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/
- 日本政策金融公庫 融資のご案内2025 – https://www.jfc.go.jp/
- 全国賃貸住宅新聞 2025年版空室率レポート – https://www.zenchin.com/
- 東京都都市整備局 住宅市場動向調査2025 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/

