不動産投資で店舗物件を検討するとき、「変動金利だと返済額が増えそうで不安」「固定金利は金利が高いと聞くが本当に得なのか」といった悩みを抱く方が少なくありません。特に初めての投資では、収益性に目を奪われて資金計画が後回しになりがちです。しかし、ローンの選び方を誤ると想定利回りが一気に崩れ、キャッシュフローが赤字に転落するリスクがあります。本記事では、不動産投資ローン 店舗 固定金利を軸に、店舗物件の特性、審査の着眼点、収益シミュレーションの作り方、2025年度の支援制度まで順を追って解説します。読み終えるころには、自分に合ったローン戦略を描けるようになるでしょう。
店舗物件を選ぶ前に押さえたい資金計画
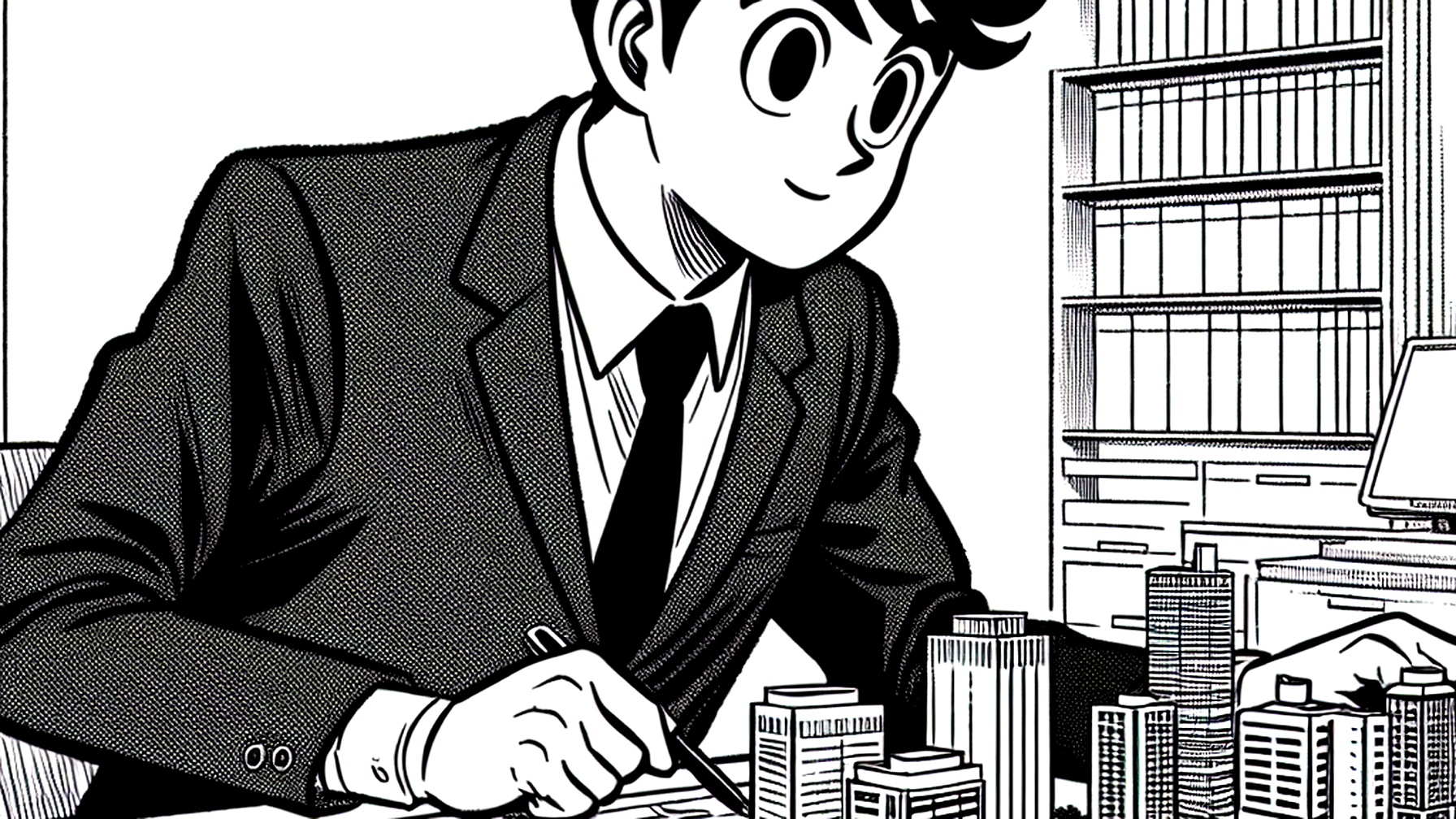
重要なのは、物件価格だけでなく開業までの総コストを把握することです。店舗物件は住居用より工事費がかさみ、保証金や内装設備に追加の資金が必要になります。たとえば、家賃20万円のテナントでは保証金に6か月分、内装に300万円前後かかるケースが一般的です。自己資金が不足するとローンで賄う額が増え、返済額もふくらみます。また、店舗は入居者によって賃料が変動しやすいため、空室期間を長めに見積もる姿勢が欠かせません。
一方で、立地が良ければ住居用より高い賃料を設定できる利点があります。国土交通省の2024年都市調査では、主要駅から徒歩5分圏の路面店は住居用と比べ平均賃料が約1.4倍でした。つまり、初期費用の増加を高賃料で取り戻せる可能性があるわけです。ただし、飲食店や美容室など業種によって収益変動が大きいため、想定収入を複数パターンで計算し、利回りが下振れしても黒字を保てるかを確認してください。
固定金利型ローンのメリットと注意点
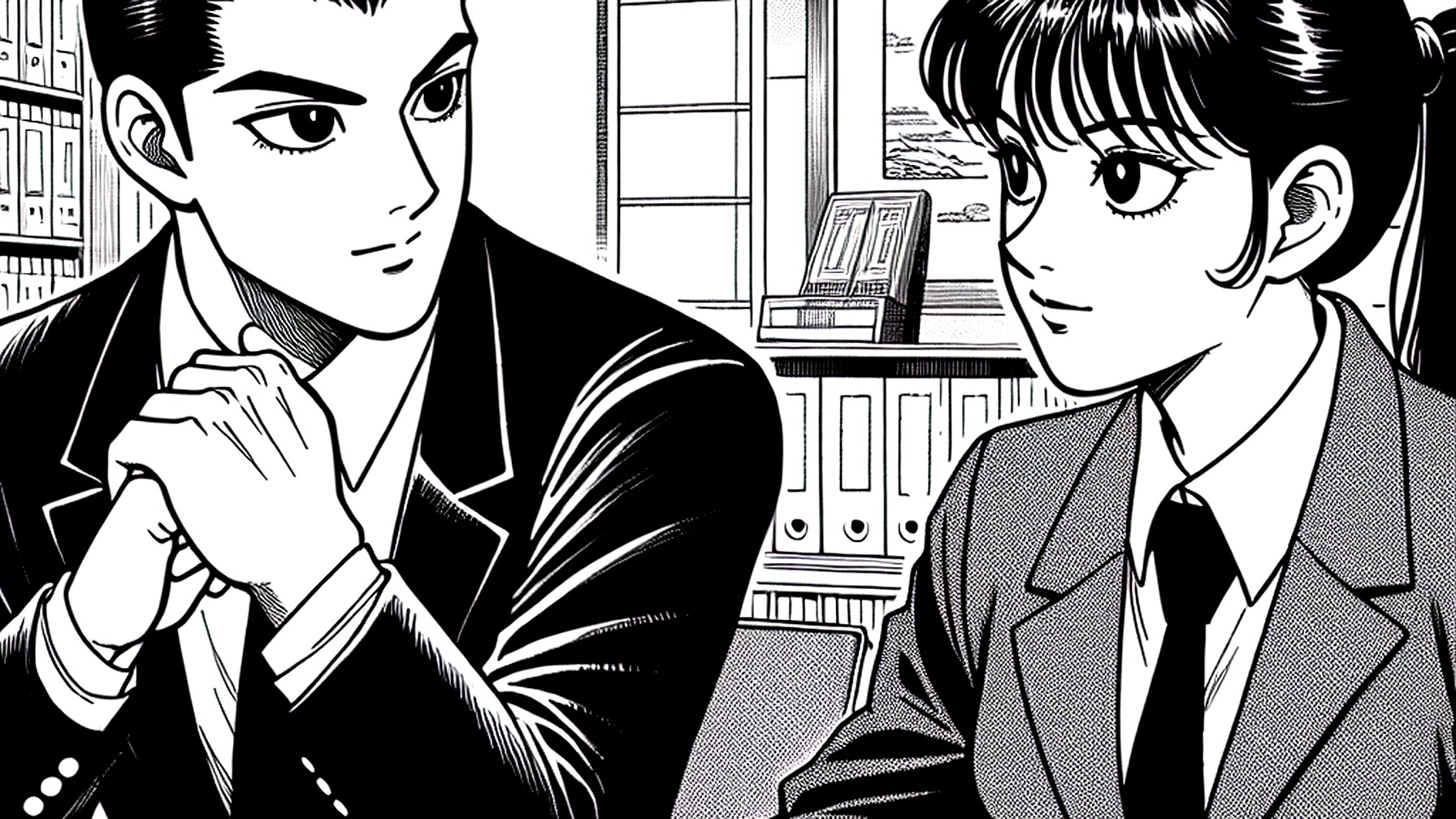
まず押さえておきたいのは、固定金利がもたらす返済額の安定です。全国銀行協会の2025年9月調査では、10年固定型の平均金利が2.5〜3.0%と示されており、変動型の1.5〜2.0%に比べて1%前後高い水準になっています。この差をデメリットと捉えがちですが、返済額が30年間一定なら、店舗の賃料を長期契約で結べた場合に予想キャッシュフローを固めやすくなります。
たとえば3,000万円を35年返済、固定金利2.7%で借りると月々の返済は約10万円です。一方、変動金利1.7%で借りた場合は約8.8万円ですが、金利が1%上昇すると返済額は約10万円に達し、固定型と差がなくなります。つまり、金利上昇局面では固定型のほうが精神的にも有利です。また、店舗物件は賃料が住居用より高く変動幅も大きいので、オーナー自身が変動リスクを背負うより、ローン返済を固定化して収益変動に集中する戦略が合理的といえます。
一方で早期繰上返済を計画する場合、固定型は違約金が発生することがあります。金融機関によっては3年以内に返済すると元本の1〜2%の手数料がかかるため、売却益でローンを一括返済したい投資家には不向きです。さらに、固定期間終了後の金利が再び変動になる商品もあるため、契約前に「全期間固定」か「期間選択型」かを必ず確認しましょう。
店舗向け不動産投資ローンの審査で見られるポイント
ポイントは、事業性評価が住宅ローンより重視される点です。審査では物件の立地・賃料相場に加え、入居テナントの業種や契約内容まで詳細にチェックされます。特に重視される「デッドカバー率(DCR)」は、年間純収益を年間返済額で割った指標で、1.2以上が目安とされています。たとえば年間家賃収入300万円、経費60万円、返済額200万円の場合、DCRは1.2でぎりぎり承認ラインというわけです。
また、金融機関は投資家の事業計画も確認します。テナント募集の方法、長期修繕計画、退去時の原状回復負担など、運営体制が明確になっているかをチェックされるため、想定空室期間や賃料下落率を盛り込んだ計画書を用意しましょう。自己資金比率も重要で、2025年時点では物件価格の20%程度を求める銀行が多い状況です。自己資金を増やせば、金利優遇や融資期間の延長を引き出しやすくなります。
さらに、店舗向けローンは個人信用情報よりも法人格やSPC(特定目的会社)を利用したスキームが好まれる傾向にあります。法人で借り入れると節税や資金調達の幅が広がりますが、決算書の内容が重視されるため、収益が安定するまでは個人名義で実績を作る方法も選択肢です。どの形態が自分の与信力や長期戦略に合うか、税理士や金融機関と十分に相談することが欠かせません。
収益シミュレーションで確認すべき数字
実は、シミュレーションの精度が投資成果を左右します。まず家賃収入は保守的に設定し、近隣の募集賃料ではなく実際の成約賃料を参考にしてください。国土交通省が提供する「賃貸住宅実態調査」には店舗賃料も掲載されており、エリア平均を把握できます。そこから5%下げた金額を想定賃料にすると、空室リスクへの備えが強化できます。
次に経費割合ですが、店舗物件は原状回復費が高額になりやすく、年間収入の25〜30%を見込むと安心です。たとえば年収入360万円に対し108万円を経費とした場合、手取りは252万円です。ここからローン返済120万円を差し引くと、年間キャッシュフローは132万円となります。なお、固定資産税や減価償却費を加味し、課税所得を抑えるシミュレーションも同時に行うと、手取り額のイメージがより具体的になります。
金利上昇シナリオは必ず複数設定しましょう。固定金利でも期間終了後に金利が上がる場合に備え、2%上昇時の返済額を計算し、それでもキャッシュフローがプラスかを確認します。最後に出口戦略として10年後の売却価格を推計し、IRR(内部収益率)を算出すれば、複数案件を定量比較できるようになります。
2025年度の支援制度と税制優遇を活用する
まず押さえておきたいのは、「中小企業経営強化税制」の即時償却措置です。2025年度は店舗用の省エネ設備を導入すると、最大即時償却または10%税額控除が受けられます。空調や照明を更新するタイミングで活用すれば、初年度のキャッシュフロー改善に直結します。
さらに、日本政策金融公庫の「事業用不動産投資支援融資」は、店舗物件にも利用可能で、固定金利は10年2.3〜2.8%と民間より低めに設定されています。融資限度額は7,200万円までですが、担保評価が高い物件なら自己資金10%でも承認されるケースがあります。また、地方自治体によっては空き店舗活用補助金が設けられており、改装費の3分の1を補助する例も存在します。補助率や締切は自治体ごとに異なるため、必ず公式サイトを確認しましょう。
最後に、法人化による「減価償却の自由度」も見逃せません。建物部分を短い耐用年数で償却すれば、課税所得を圧縮できるため、固定金利で返済額が一定でも手取りは増える結果になります。ただし、償却費が減る数年後の課税負担増を見越し、長期的な資金繰り計画を立てておくことが大切です。
まとめ
固定金利を選択した店舗向け不動産投資ローンは、金利上昇局面で安定した返済を実現し、キャッシュフロー計画を立てやすくする利点があります。店舗物件は初期費用が大きいものの、高賃料と税制優遇を活用すれば収益機会も広がります。重要なのは、自己資金比率を高めて審査条件を有利にし、複数シナリオで収益シミュレーションを行うことです。記事で紹介した支援制度や公的データを活用し、自分に合ったローン戦略を具体化してください。準備を丁寧に進めれば、店舗投資でも安定した資産形成が十分に可能です。
参考文献・出典
- 全国銀行協会 – https://www.zenginkyo.or.jp
- 国土交通省 都市局「賃貸住宅実態調査」 – https://www.mlit.go.jp
- 中小企業庁「中小企業経営強化税制の手引き(2025年度版)」 – https://www.chusho.meti.go.jp
- 日本政策金融公庫「事業用不動産投資支援融資」 – https://www.jfc.go.jp
- 東京都産業労働局「空き店舗活用補助金」 – https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp

