アパートを所有しているのに部屋が埋まらず、家賃収入が安定しない――この悩みは地方だけでなく都市圏のオーナーにも広がっています。「アパート経営 なぜ 空室対策」が欠かせないのか、それは空室が生む損失が想像以上に大きいからです。さらに、人口減少や新築供給の増加といったマクロ要因も絡み合い、待っているだけでは入居が決まらない時代になりました。本記事では2025年9月現在の最新データを参照しながら、空室率上昇の背景、家賃設定の考え方、リノベーションや管理体制の改善方法、公的支援までを具体的に解説します。読み終えた頃には、自分の物件に合った対策を選択し実行できるようになるはずです。
空室対策が注目される背景
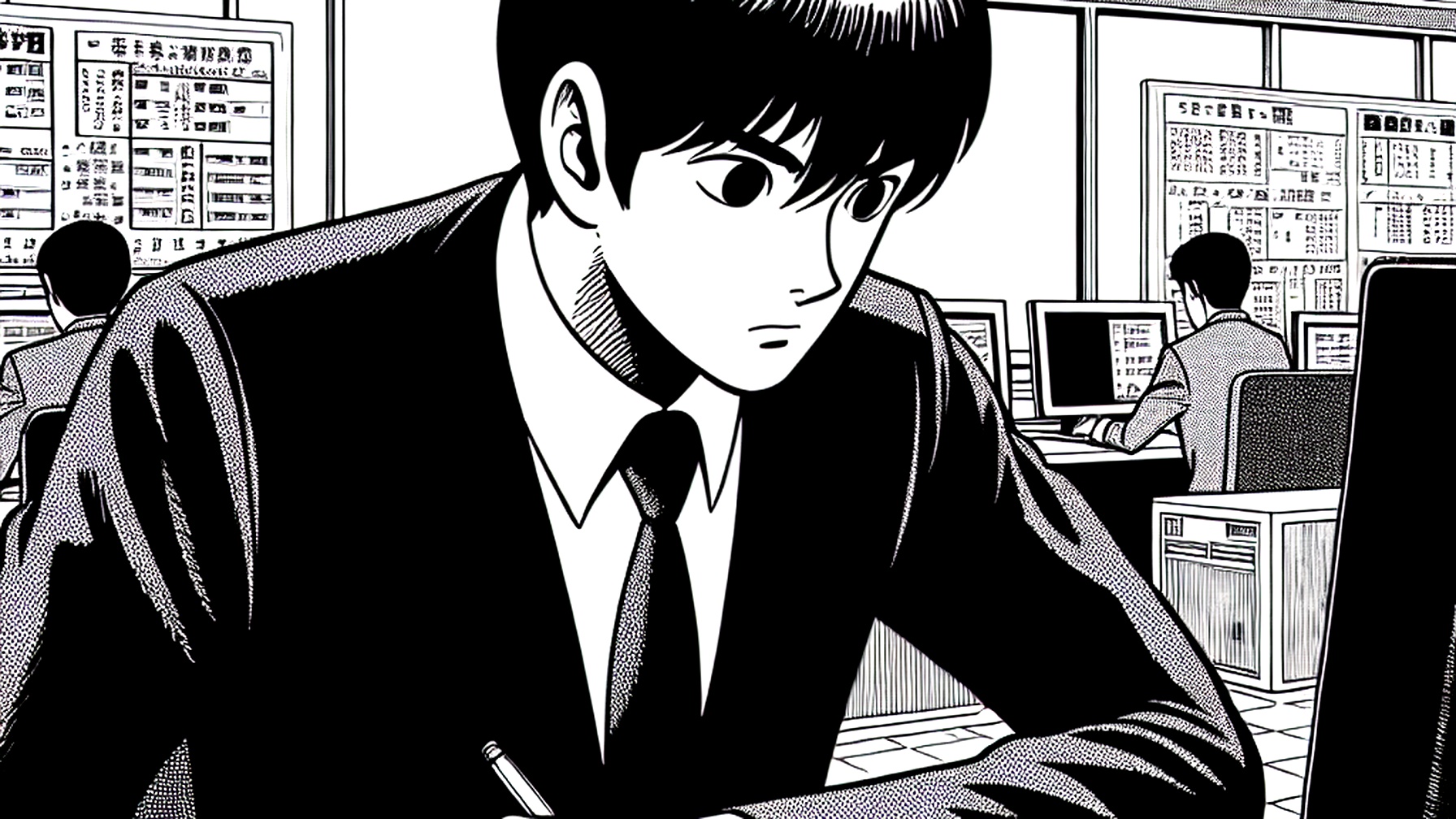
まず押さえておきたいのは、市場全体の空室率が依然として高水準にある事実です。国土交通省住宅統計によると、2025年7月時点の全国アパート空室率は21.2%で、前年より0.3ポイントしか改善していません。この数字は物件の5戸に1戸以上が空いている計算で、空室に対する危機感が高まるのも当然と言えます。
しかし、単に空室率が高いから対策が必要というわけではありません。空室期間が1か月延びるごとに家賃1か月分の純利益がそのまま失われ、年間利回りが大きく低下します。自己資金を厚めに入れていても、修繕費や管理費が固定的に発生するため、収支は赤字へ傾きやすくなるのです。つまり、満室経営を目指すことは安定収益のための前提条件と言えます。
一方で、空室率はエリアによって大きく異なります。都市部でも駅徒歩15分以上の築古物件は競争力を失いやすく、逆に地方でも大学や工業団地が近いエリアでは低く抑えられるケースがあります。自分の物件が置かれたマーケットを把握し、競合物件と比較しながら対策を講じる姿勢が求められます。
家賃設定の最適化と市場分析
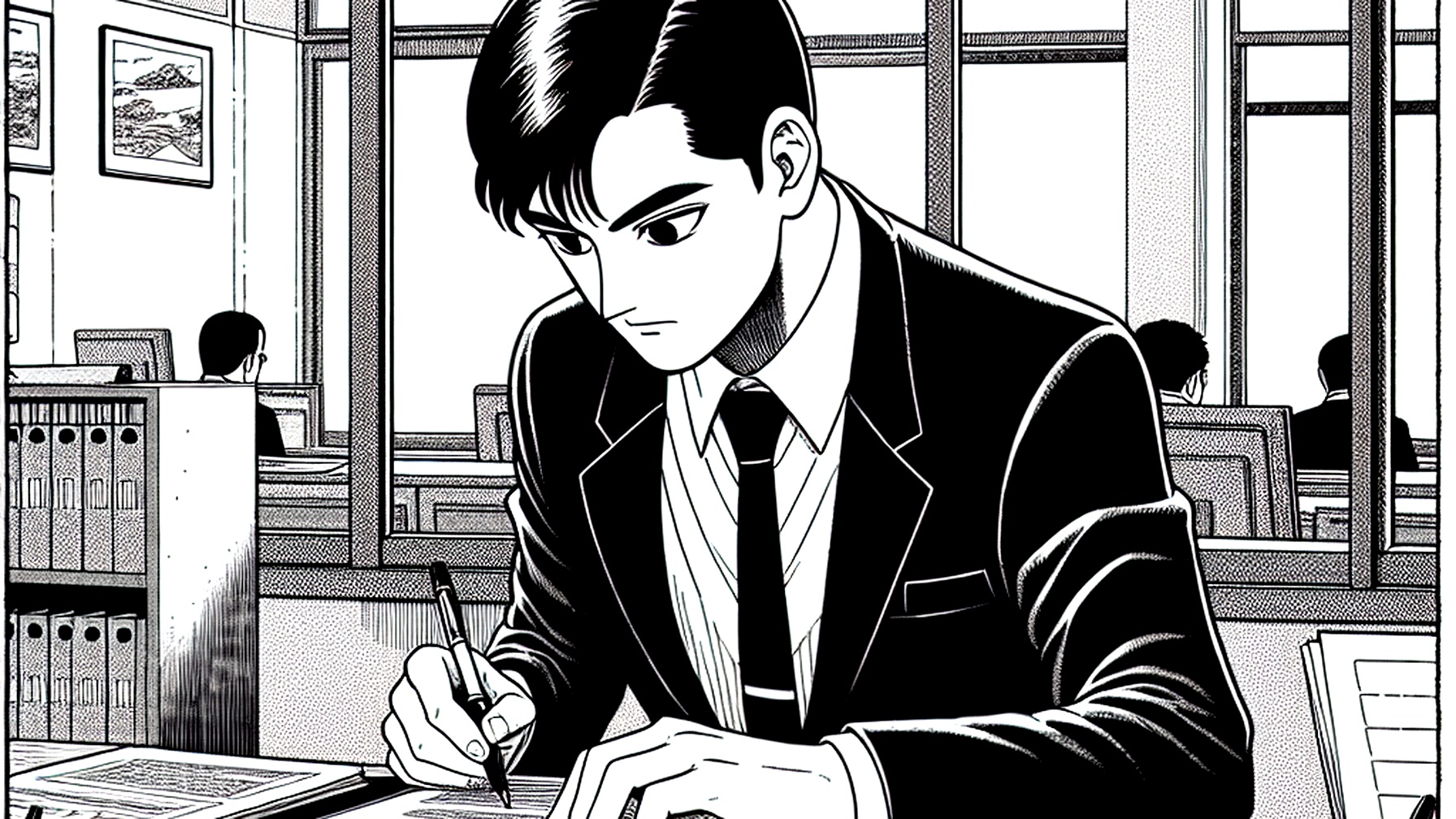
重要なのは、家賃を下げれば必ず入居が決まるという単純な発想から脱却することです。家賃を10%下げれば利回りも10%下がりますから、価格戦略は慎重に決めなければなりません。実際には、周辺家賃の中央値より2〜3%低い水準を提示するだけで反響が増えるケースが多く、過度な値下げは不要です。
家賃設定の前提となる市場分析には、民間ポータルサイトの掲載家賃と成約家賃を分けて見る視点が役立ちます。掲載家賃は売り手の希望価格であるため割高に出ている場合が多く、過去3か月の成約事例まで追うことで実勢価格を把握できます。さらに、競合物件の築年数や設備を一覧化し、自分の物件が見劣りする点を洗い出すと、有効な賃料帯のヒントが得られます。
また、家賃と同時に「初期費用の総額」を最適化することも見逃せません。礼金ゼロや仲介手数料半額といった施策は、オーナーの負担を比較的抑えながら入居ハードルを下げられます。若年層の入居者は初期費用に敏感なため、数万円の差でも意思決定が変わるのが現実です。
物件価値を高めるリノベーションの考え方
ポイントは、リノベーションに投じた資金が何年で回収できるかという投資視点を持つことです。ただ流行色のクロスに張り替えるだけでは、資金を回収できずに終わる危険があります。たとえば、20万円をかけて宅配ボックスを導入し、月額2000円の家賃アップと平均空室期間の1か月短縮を同時に達成できれば、約3年で投資額を回収できます。
一方で、水回り設備の総入れ替えは費用対効果が分かれます。50万円以上かかるケースが多いですが、築30年以上の物件では入居決定の要因になるため、長期保有を前提に検討する価値があります。日本政策金融公庫の設備投資ローンを活用すれば、年1.5%前後の固定金利で7年程度の融資を受けられる可能性があり、自己資金の圧縮も可能です。
さらに、2025年度も継続している国土交通省「長期優良住宅化リフォーム推進事業」を活用すれば、工事規模に応じて最大250万円の補助金を受けられます。断熱性能の向上や耐震補強を同時に行うことで、入居者の光熱費を抑えられる点を訴求しやすく、家賃を維持しながら競争力を確保できるのがメリットです。
入居者満足を左右する管理体制
実は、物件の第一印象を決めるのは建物そのものより「管理状態」であることが多いです。エントランスに郵便物が散乱している、共用灯が切れている、雑草が伸び放題――こうした要素は写真にも写り込むため、ネット閲覧段階で候補から外される恐れがあります。週1回の定期清掃を実施するだけで、内見率が2割向上したという管理会社の報告もあります。
入居後のトラブル対応も空室対策に直結します。騒音やゴミ出しマナーのクレームが放置されれば、既存入居者の退去につながり、新たな空室を生む悪循環が始まります。管理会社との委託契約書に「24時間クレーム受付」と「48時間以内の一次対応」を明記しておくと、サービスレベルを維持しやすくなります。
加えて、デジタル化による効率化も進んでいます。2025年時点で普及が拡大しているスマートロックは、内見時の案内キー手配を不要にし、仲介会社の案内件数を実質的に増やす効果があります。年間1戸あたり5000円程度のシステム利用料で済む場合が多く、入居者にも利便性をアピールできるため費用対効果は高いと言えるでしょう。
公的支援と2025年度の税制優遇
まず、住宅用地の固定資産税軽減措置は2025年度も継続しており、敷地200㎡以下の部分は課税標準が6分の1に抑えられます。空室があっても住宅用地と見なされるため、土地税負担は大幅に下げられます。ただし、長期の空室が続き居住実態が疑われると、特例が適用外になるケースが報告されているため、物件稼働率の維持は税務面でも重要です。
次に、所得税・住民税を抑える手段として「減価償却費」の適切な計上があります。築古アパートを取得した場合、法定耐用年数の短さを活かして早期に費用計上でき、実効税率30%のオーナーなら年間50万円の節税が可能となるケースもあります。ただし、税務調査で否認されないよう、構造別耐用年数と取得価額の内訳を記録・保存しておくことが欠かせません。
最後に、2025年度創設の「省エネ賃貸住宅支援税制」に触れておきます。この制度は、賃貸住宅の断熱性能を一定基準まで高めた場合、改修費用の10%(上限60万円)が所得税額から控除されるものです。期限は2026年3月末の工事完了分までとされているため、計画から着工までのスケジュール管理が成功の鍵となります。
まとめ
本記事では、全国空室率21.2%という現実を出発点に、家賃設定の根拠、投資回収を意識したリノベーション、管理体制の改善、公的支援の活用までを順に見てきました。大切なのは、マーケットを数字で把握し、費用対効果を検証しながら複数の施策を組み合わせる姿勢です。空室は放置すると資金繰りと税負担を同時に悪化させますが、適切な対策を講じれば利回りは回復し、物件価値も高まります。まずは自分の物件の競合状況を調査し、入居者目線で改善点を洗い出すことから始めましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局住宅政策統計調査 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 統計局 住民基本台帳人口移動報告 2025年版 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫 融資制度ガイド 2025年度 – https://www.jfc.go.jp
- 国土交通省 長期優良住宅化リフォーム推進事業 2025年度概要 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 財務省 税制改正の解説 2025年度 – https://www.mof.go.jp

