相続はいつ訪れるか分からないものです。そのため、早めの準備が将来の安心につながります。とはいえ、税制や制度は複雑で、何から始めればよいか迷う方も少なくありません。
本記事では、不動産投資歴15年以上の視点から、相続対策と資産形成を同時に進める具体策を分かりやすく解説します。制度を味方につけながら、次世代への資産継承と自分自身の老後資金確保を両立させる方法が見えてくるはずです。
相続対策が資産形成につながる理由
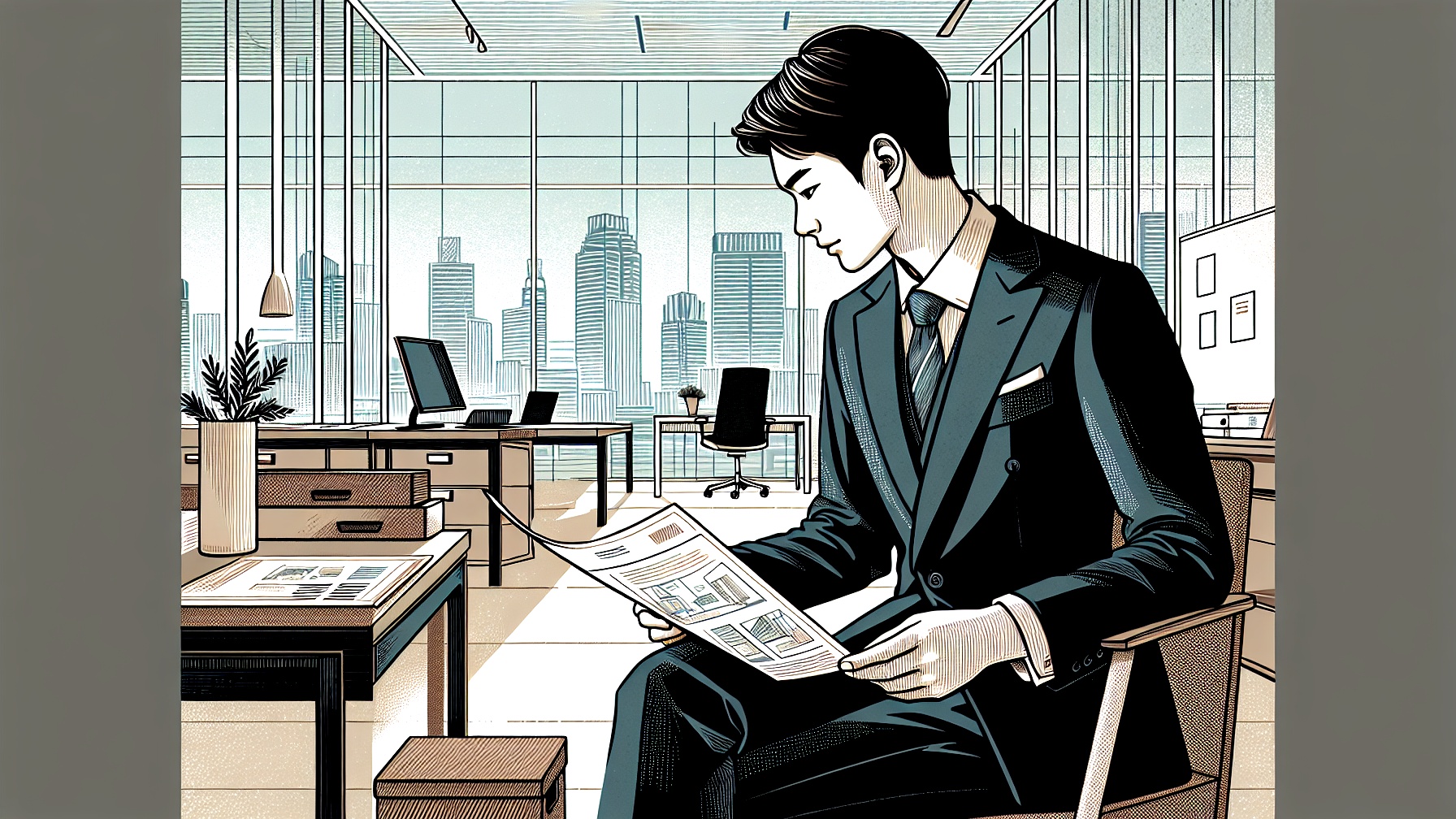
相続対策というと、多くの方が節税テクニックをイメージするかもしれません。しかし、本質的に重要なのは、資産を次世代へ円滑に渡す仕組みを構築することです。この仕組みづくりが、結果として自身の老後資金を増やす道筋にもなります。
総務省の家計調査によると、60代以降の金融資産は年々増加傾向にあります。一方で、相続発生時に現金が偏っていると税負担も増える傾向があります。現役世代のうちに資産を分散し、評価額を抑える工夫を始めることが、将来の負担軽減につながるわけです。
また、不動産などの実物資産はインフレ局面で価値が目減りしにくい特徴を持っています。日本銀行が発表する消費者物価指数は2024年から緩やかな上昇が続いており、現金のみを保有するリスクが顕在化しています。相続視点を取り入れた資産形成は、インフレ対策としても有効に機能するのです。
さらに、家族構成やライフスタイルが多様化する現代では、相続対策は早めにプランニングするほど選択肢が広がります。たとえば、持ち家を賃貸化するか売却するかによって、老後のキャッシュフローは大きく変わってきます。早期に試算しておけば、認知症リスクや不測の事態にも柔軟に対応できるでしょう。
不動産活用がもたらす二重のメリット

不動産を相続対策に活用する最大の利点は、評価額を圧縮しながら収益を生み出せる点にあります。国税庁の路線価方式に基づくと、建物は固定資産評価額で、土地は路線価で評価されます。この評価方法により、市場価格より2割から3割程度低く算定されるケースが一般的です。
具体的に言えば、同じ3,000万円でも現金より不動産のほうが相続税負担を抑えやすくなります。これは評価方法の違いから生まれるメリットであり、合法的な節税手段として広く活用されています。
家賃収入が老後を支える
賃貸経営から得られる家賃収入は、老後の生活資金として大きな役割を果たします。年金だけでは生活費が不足すると言われる中、毎月安定したキャッシュフローがあることは心強い支えとなります。
国土交通省の賃貸住宅市場データによると、家賃が多少下落しても、ローン完済後の実質利回りは4%から5%を維持しやすい傾向にあります。長期的な視点で見れば、不動産投資は安定した収益源になり得るのです。
リスク管理も忘れずに
一方で、空室リスクや修繕費用を見落とすと収支が崩れかねません。建物診断を定期的に行い、長期修繕計画を設定することで、突然の出費を平準化できます。購入前には同じエリアで空室率が低い物件を複数調査し、平均入居期間を把握することが重要です。
つまり、評価圧縮とインカムゲインの二重取りを実現するには、数字に基づく慎重な選定と運用が欠かせません。感覚的な「立地が良さそう」で終わらせず、将来の相続分割まで想定したシナリオ作成が成功のカギとなります。
2025年度も活用できる税制優遇のポイント
2025年度においても、相続対策に有効な税制優遇がいくつか存在します。これらの制度を理解し、適切に組み合わせることで、節税効果を最大化できます。
小規模宅地等の特例
代表的な制度が「小規模宅地等の特例」です。この特例を使えば、被相続人の自宅や事業用地について最大330平方メートルまで評価額を80%減額できます。自宅の土地評価額が5,000万円であれば、1,000万円まで圧縮される計算になります。
ただし、相続開始前3年以上の保有など一定の要件があるため、適用を受けるには早期の計画が必須です。要件を満たさないまま相続が発生すると、この大きな節税メリットを受けられなくなってしまいます。
相続時精算課税制度の活用
「相続時精算課税制度」は、2,500万円まで贈与時に非課税となり、超過分も一律20%の税率で済む仕組みです。2024年の税制改正で適用年齢が18歳に引き下げられ、2025年10月現在も有効に活用できます。
この制度を使い、将来値上がりが見込める不動産を子に移転すれば、評価益を次世代にシフトできます。贈与時点の評価額で相続財産に加算されるため、その後の値上がり分は課税対象から外れるメリットがあります。
暦年贈与の非課税枠
年間110万円の「暦年贈与」の非課税枠は2025年度も存続しています。相続発生前7年以内の贈与加算対象額が調整されたため、計画的な少額贈与がより活用しやすくなりました。毎年コツコツと贈与を続けることで、長期的には大きな資産移転が可能になります。
贈与税の申告はオンライン化が進み、マイナポータル経由で手続きできる点も見逃せません。手続きの手間が軽減されたことで、制度を活用するハードルは以前より下がっています。
制度を組み合わせる設計力
重要なのは、複数の制度を組み合わせる設計力です。たとえば、自宅は小規模宅地等特例で評価減を図り、賃貸用区分マンションは相続時精算課税で子に移転します。残余の金融資産は暦年贈与で分散する、といった具合に組み合わせることで効果が高まります。
制度ごとの適用条件は複雑なため、税理士と確認しながら3年から5年単位のロードマップを描くことをおすすめします。専門家の助言を得ながら計画を立てることで、制度の恩恵を最大限に受けられるでしょう。
実践的な資産形成シミュレーション
ここでは、夫婦と子ども2人の世帯を例にシミュレーションしてみます。現預金3,000万円を保有し、都内中古区分マンションを1戸購入するケースを考えてみましょう。物件の評価額は2,000万円、表面利回りは5%と想定します。
購入から運用までの流れ
頭金500万円を投入し、残り1,500万円を年利1.8%、20年ローンで組むと、月々の返済は約7万4,000円となります。一方、家賃収入は月10万円を見込めます。管理費・修繕積立金1万5,000円と空室率5%を考慮しても、年間約75万円のキャッシュフローが残る計算です。
この収益を全額ローンの繰上げ返済に充てれば、完済期間を17年程度に短縮できます。子が30代半ばで相続する時点にはローンが完済されており、純資産として引き継げる状態になります。
相続税評価額の圧縮効果
相続税評価額を試算すると、建物部分は固定資産評価額で約700万円、土地は路線価で約500万円となり、合計1,200万円と算出されます。市場価格2,000万円との差額800万円が圧縮されるわけです。
同額の現金を相続する場合と比べて、税額は数十万円から百万円単位で軽減できる可能性があります。評価圧縮と家賃収入、両面のメリットが具体的な数字で見えてきます。
ストレスシナリオの重要性
もちろん、このシミュレーションは一つのモデルにすぎません。空室率10%への上昇や金利2.5%への引き上げなど、厳しい条件でも損益分岐点を確認することが大切です。楽観的なシナリオだけでなく、悲観的なケースも想定しておくことでリスク管理が強化されます。
金融機関が提供する無料の返済計算ツールや、国土交通省の賃料統計を活用すると、シミュレーションの精度が上がります。複数のパターンを試算し、自分にとって許容できるリスク範囲を把握しておきましょう。
失敗を防ぐための実践チェックポイント
相続対策と資産形成を両立させるには、計画的な準備が欠かせません。ここでは、失敗を防ぐために押さえておきたい重要なポイントを解説します。
資産の棚卸しから始める
まず取り組むべきは「情報の棚卸し」です。所有資産、負債、保険契約を一覧化し、家族で共有するだけでも問題点が見えてきます。特に複数の金融機関に分散している預金は、相続手続きの負担を増やす要因になるため、可能な範囲で整理しておくとよいでしょう。
資産一覧を作成する際は、不動産の登記情報や金融資産の口座番号など、具体的な情報も併せて記録しておくことをおすすめします。いざという時に家族が困らないよう、情報を整理しておくことが大切です。
専門家チームの構築
次に重要なのが、専門家チームの構築です。税理士のほか、司法書士、ファイナンシャルプランナー、不動産管理会社を早めに選定しておくと、相続発生時の手間とコストを抑えられます。
専門家を選ぶ際は、費用だけでなく相続発生後のサポート体制や実績を細かく質問することをおすすめします。相続は長期にわたる手続きが必要になることも多いため、信頼できるパートナーを見つけておくことが安心につながります。
定期的な家族会議の開催
家族会議を定期的に開くことで、認識のズレを防げます。近年は「終活ノート」や「エンディングノート」を使い、資産状況や終末期の希望を共有する家庭が増えています。書面に残すことで、感情的な対立が生じにくくなる効果が期待できます。
家族間でお金の話をするのは気が引けるかもしれません。しかし、事前に共有しておくことで、相続発生時のトラブルを大幅に減らせます。年に1回程度は家族で集まり、資産状況や将来の希望について話し合う機会を設けてみてください。
制度改正への対応
最後に忘れてはならないのが、制度改正のチェックです。2025年度の制度が将来も同じ形で続く保証はありません。税制は毎年のように見直しが行われるため、最新情報を把握しておく必要があります。
国税庁や金融庁のウェブサイトを年に1回は確認し、必要に応じてプランを更新しましょう。このような地道なプロセスこそが、長期的な資産形成と円滑な相続の両方を守る基盤となります。
まとめ
本記事では、相続対策と資産形成を一体で考えるメリットと具体的な進め方を紹介しました。不動産を活用すれば、評価額を抑えつつ家賃収入で老後資金を補うことができます。
2025年度も利用できる税制優遇を組み合わせることで、節税効果を高めながら家族間トラブルも防げます。小規模宅地等の特例や相続時精算課税制度、暦年贈与など、それぞれの制度を理解し、自分の状況に合った活用法を検討してみてください。
行動の第一歩は、資産一覧の作成と専門家への相談です。今日から情報を整理し、将来の安心と資産拡大を同時に実現する準備を始めましょう。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp/
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp/
- 日本銀行「消費者物価指数」 – https://www.boj.or.jp/
- 国土交通省「住宅市場動向調査」 – https://www.mlit.go.jp/
- 金融庁「家計の安定的な資産形成に関する報告」 – https://www.fsa.go.jp/

