初心者の方は「少額から始められると聞くけれど、本当に利益は出るのか」「株と何が違うのか」が気になるはずです。実はREITは不動産の専門知識がなくても分散投資ができる便利な商品ですが、仕組みを理解しないと価格変動に振り回されてしまいます。本記事では、REIT市場の現状を踏まえつつ、具体的な始め方と運用のコツを丁寧に解説します。読み終える頃には、自分に合った銘柄の選び方から購入後の管理まで、一連の流れがイメージできるようになるでしょう。
REITの基本と株式投資との違い
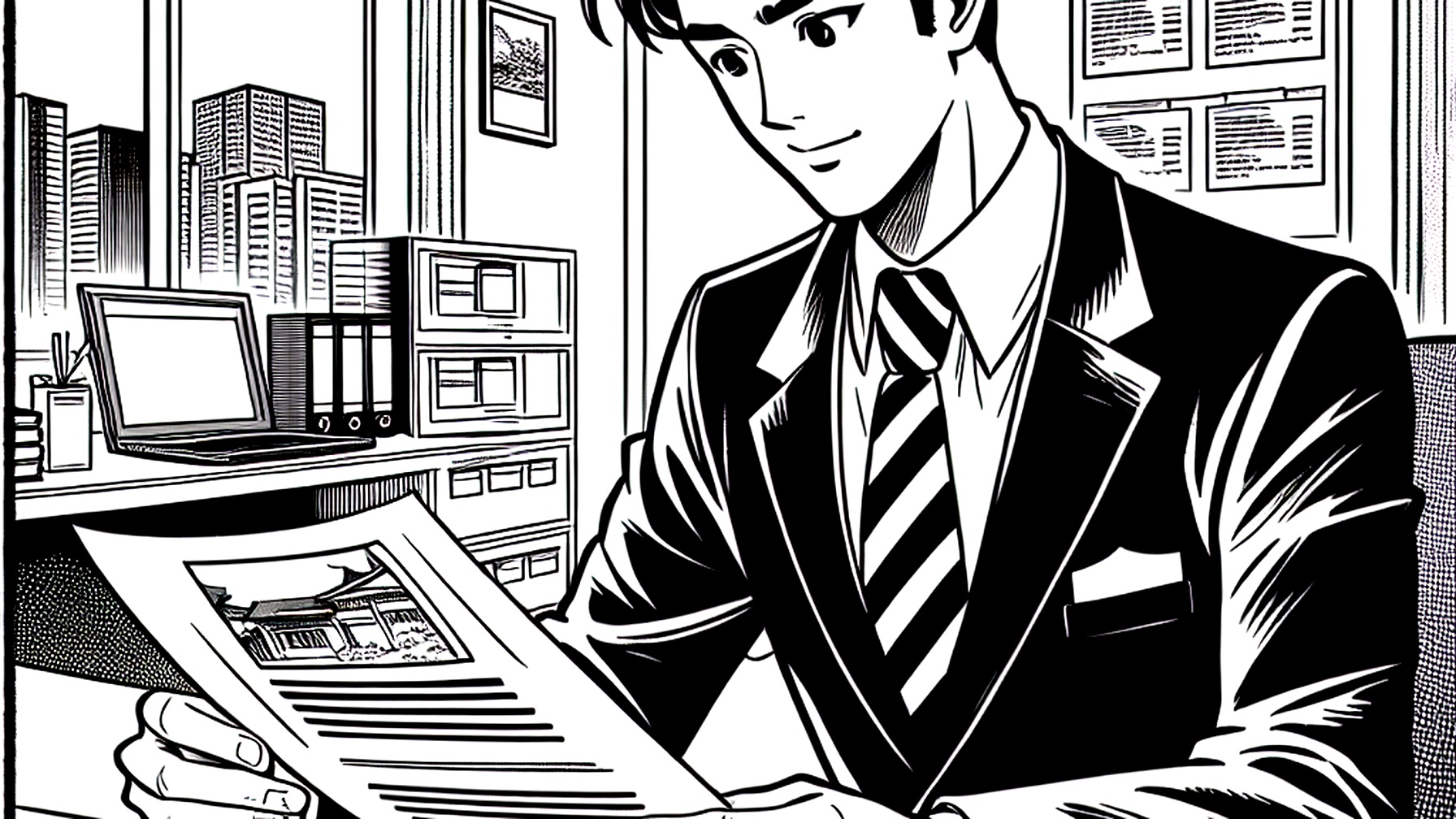
まず押さえておきたいのは、REITが不動産を証券化した金融商品だという点です。不動産会社がビルや商業施設を保有し、その賃料収入を投資家に分配する仕組みで、東京証券取引所に上場しているため株と同じように売買できます。一方で、法律上は「投資信託」の一種に分類され、利益の九割以上を配当に回すよう義務づけられているので、比較的高い分配利回りが期待できます。
日本取引所グループのデータによると、2025年6月時点のJ-REIT市場時価総額は約18兆円で、上場銘柄は64本に増えました。流動性が高まり、1口あたり十万円前後から購入できる銘柄も多いため、少額ではじめる投資として注目を集めています。つまり、物件を丸ごと買う現物不動産よりも手軽で、株式よりインカムゲイン(配当)を重視できるのがREITの特徴です。
ただし、株価要因と不動産市況の両方の影響を受けるため、上昇局面と下落局面で値動きの幅が大きくなることがあります。そのため、日経平均やTOPIXと相関が高まる場面を想定し、分散投資の一角として組み込む姿勢が大切です。
リスクとリターンを見極める視点
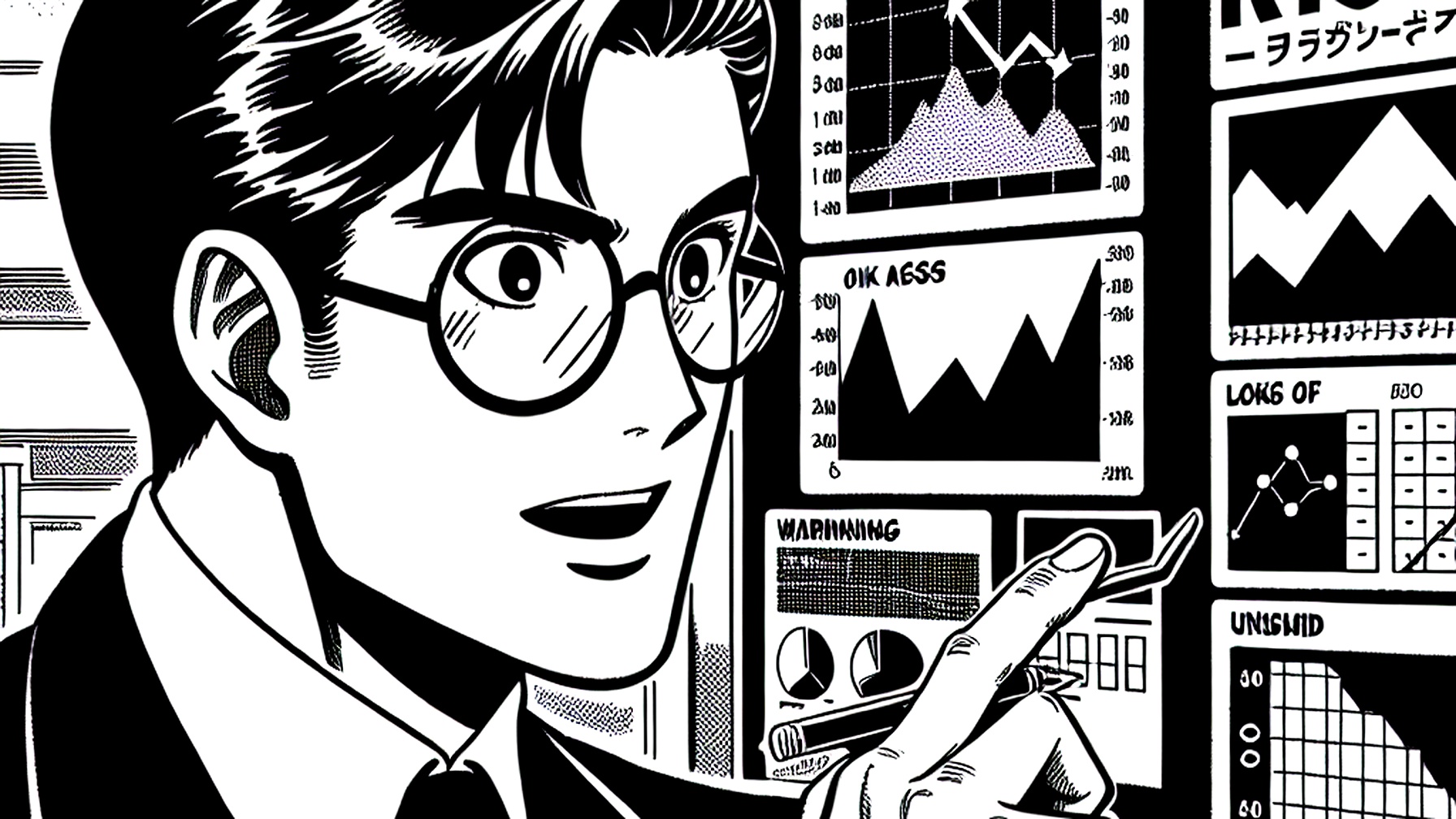
ポイントは、REIT特有の三つのリスクを把握することです。第一に価格変動リスクがあります。たとえば東証REIT指数は2020年3月の急落時に前月比で四割下落しましたが、2023年末までにほぼ回復しています。つまり、長期保有できる資金で運用すれば、短期の乱高下に耐えやすくなります。
第二に財務リスクが挙げられます。REITは資金を借り入れて物件を取得するため、金利上昇局面では利払い負担が増えます。2025年10月現在、日銀の長期金利誘導目標は1.0%上限で推移していますが、仮に1.5%まで上昇すると、借入比率が高い銘柄は分配金を減らす可能性があります。固定金利比率やLTV(総資産に対する借入金比率)が50%前後で抑えられているか確認しましょう。
第三に物件集中リスクがあります。オフィス主体のREITは都心の空室率に左右され、住宅主体のREITは人口動態の影響を受けます。国土交通省の調査によれば、2025年4月の東京都心五区オフィス空室率は4.5%で前月比0.2ポイント上昇しました。複数用途に分散している総合型REITを混ぜることで、ポートフォリオ全体の安定性が高まります。
証券口座開設から購入までの流れ
実は、REITの購入手順は株式とほぼ同じですが、いくつか確認すべきポイントがあります。まず、NISA口座か特定口座を選択します。2024年に制度が抜本改正され、2025年度も年間360万円、通算1800万円までの非課税投資枠が利用可能です。長期で分配金を受け取るREITとNISAの相性は良好なので、非課税枠を優先的に活用すると効率的です。
次に、証券会社を比較します。手数料の上限や取扱銘柄数、自動再投資サービスの有無が違いになります。分配金を現金で受け取り再投資するか、自動で再投資するかによって、長期の複利効果が変わるからです。SBI証券や楽天証券では1口未満の端株買付サービスが拡充され、毎月一万円程度から積立できる仕組みも整っています。
最後に発注方法を決めます。指値注文は希望価格で約定しやすく、成行注文はすぐに約定しますが価格が読めません。REITは出来高が株式より少ない銘柄もあるため、板の薄い時間帯を避けると有利です。注文後は約定通知が届くので、購入単価と口数を記録し、目標利回りに対する進捗を定期的に確認しましょう。
銘柄選定のコツとチェックポイント
重要なのは、分配金利回りだけで飛びつかないことです。表面利回りが高く見える銘柄ほど、将来的な賃料下落や追加修繕費のリスクを抱えている可能性があります。投資口価格が急落したタイミングで利回りが跳ね上がるケースもあるため、バックグラウンドを調べてから判断します。
具体的には、IR資料に掲載されている「1口当たりNAV(純資産価値)」と投資口価格を比較するNAV倍率を確認します。倍率が1倍を下回る場合は割安とされますが、物件の含み損リスクも潜んでいるため、資産評価額の妥当性をチェックしましょう。また、運用会社の実績も重要です。運用開始から10年以上で増資を重ねながら安定的に分配金を増やしているREITは、内部成長戦略が成功していると判断できます。
分散投資を図るには、用途とエリアを意識します。オフィス、住宅、物流、ホテル、商業施設、それぞれ景気敏感度が異なります。たとえば2024年以降のインバウンド需要回復でホテル系REITの稼働率は九割近くに達していますが、外的要因に左右されるためポートフォリオ全体では二割程度に抑えるなど、バランスを取る姿勢が求められます。
2025年度の税制優遇と最新トレンド
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続して適用されるNISA制度と、上場REIT配当にかかる二重課税調整です。REITの分配金は投資信託同様に税率20.315%が源泉徴収されますが、法人段階で支払った法人税が差し引かれるため、実効税率は株式配当より低くなります。NISA口座で受け取れば、さらに税負担がゼロになるため、長期的な手取り利回りが向上します。
さらに、環境配慮型物件への投資を進めるグリーンREITが増えています。環境省の「サステナブルファイナンスロードマップ2025」によると、GRESB(不動産版ESG指標)の高評価銘柄は運用資産のエネルギー消費量を年1%以上削減しています。投資家からの需要が高まり、金利優遇を受けるケースもあるため、中長期で価格にプレミアムが乗る可能性があります。
一方で、日銀の金融政策転換による長期金利上昇リスクは無視できません。日本銀行は2025年10月の金融政策決定会合でもYCC(イールドカーブ・コントロール)の柔軟運用を継続していますが、市場金利の変動幅は拡大しています。金利動向と分配金の感応度を定期的にチェックし、借入期間の長い銘柄を中心に選定するなどの対応策を取ると安心です。
まとめ
本記事では、REITの仕組みからリスク管理、銘柄選定の着眼点までを一気通貫で解説しました。高利回りに目を奪われず、LTVやNAV倍率を確認しながら用途とエリアを分散することで、安定したインカムゲインを確保できます。また、2025年度のNISA改正を活用すれば、分配金をまるごと受け取れるメリットが広がります。まずは少額で始め、四半期ごとに分配金と金利環境を見直す習慣をつけると、中長期でブレない投資判断ができるでしょう。今日ご紹介した「REIT 始め方 コツ」を参考に、一歩踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 – https://www.boj.or.jp
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 環境省 – https://www.env.go.jp

