不動産投資に興味はあるけれど、「本当に安定収入になるのか」「借金だけが残らないか」と不安を抱える人は少なくありません。華やかな成功談が多い一方で、損失リスクや手間の大きさが語られることは意外と少ないです。本記事では、15年以上の実務経験を踏まえ、あえて「不動産投資 デメリット」に焦点を当てて解説します。読み終えたとき、リスクを正しく理解し、自分に合った投資戦略を選ぶための判断軸が身につくはずです。
キャッシュフロー悪化の落とし穴
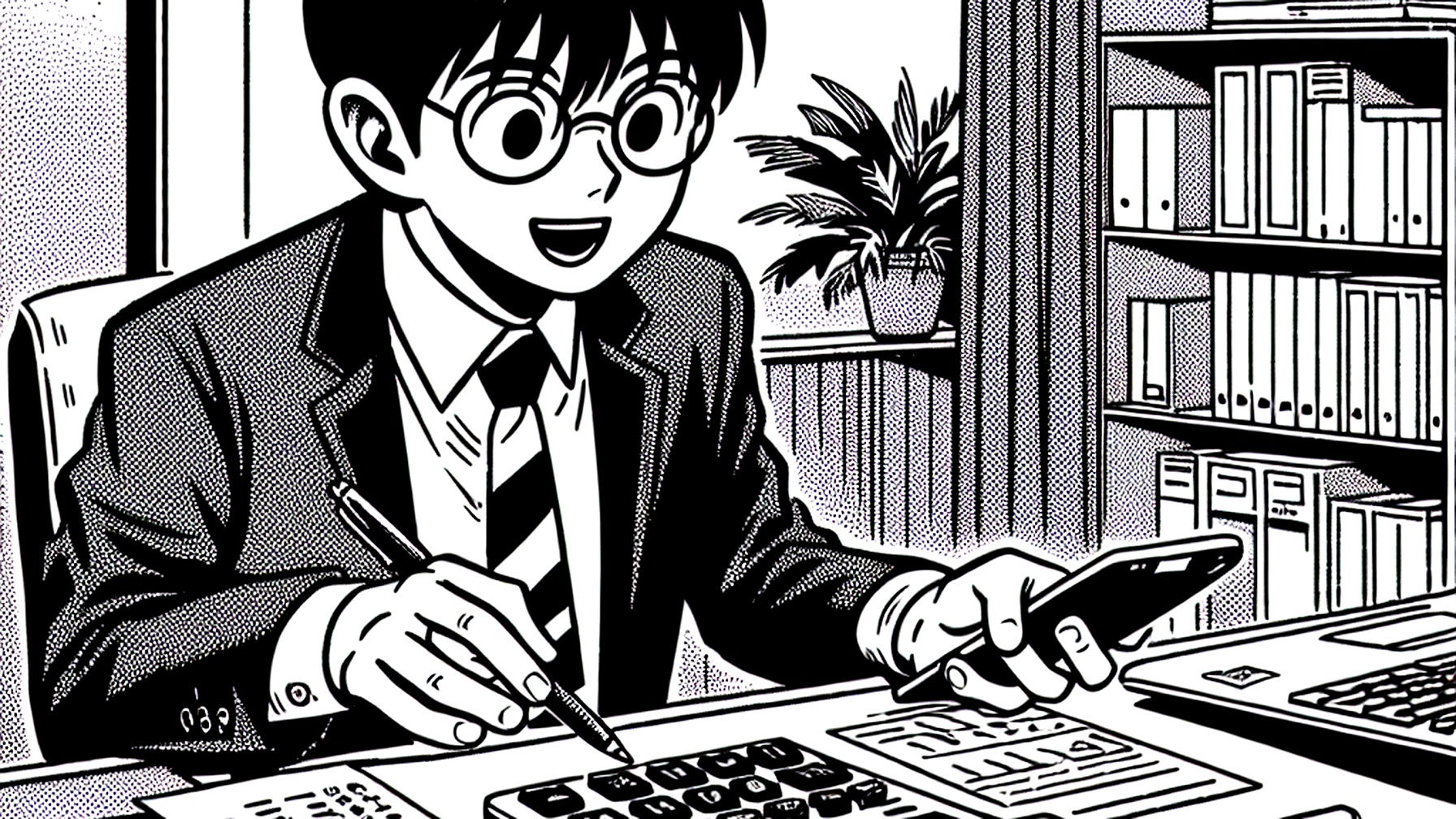
まず押さえておきたいのは、家賃収入からローン返済や諸経費を引いた残りを示すキャッシュフローが、予想より簡単に悪化するという事実です。国土交通省の「住宅市場動向調査(2024年度)」によると、投資用マンションの年間空室率は平均11.6%に達しています。
実際の現場では、入居者の退去が続くと次の入居募集に広告費がかかり、原状回復費も発生します。さらに、ローンは毎月必ず返済しなければならないため、家賃が入らない月が続くと自己資金で穴埋めする場面が増えます。つまり、満室想定のシミュレーションだけでは危険で、空室期間を保守的に見積もった計画が必要です。
さらに金利上昇も無視できません。日本銀行のマイナス金利政策は2025年に解除され、メガバンクの変動金利は平均0.3ポイント上昇しました。借入額3,000万円・残期25年の場合、月々の返済は約4,100円増えます。一見小さく感じますが、年間では約5万円、複利を考慮すると長期的な収支に響きます。
重要なのは、賃料下落と金利上昇を同時にシミュレーションし、手元資金の余裕を確保することです。最低でも家賃収入6か月分の現金を用意しておくと、突発的なキャッシュフロー悪化に耐えやすくなります。
空室と家賃下落の現実
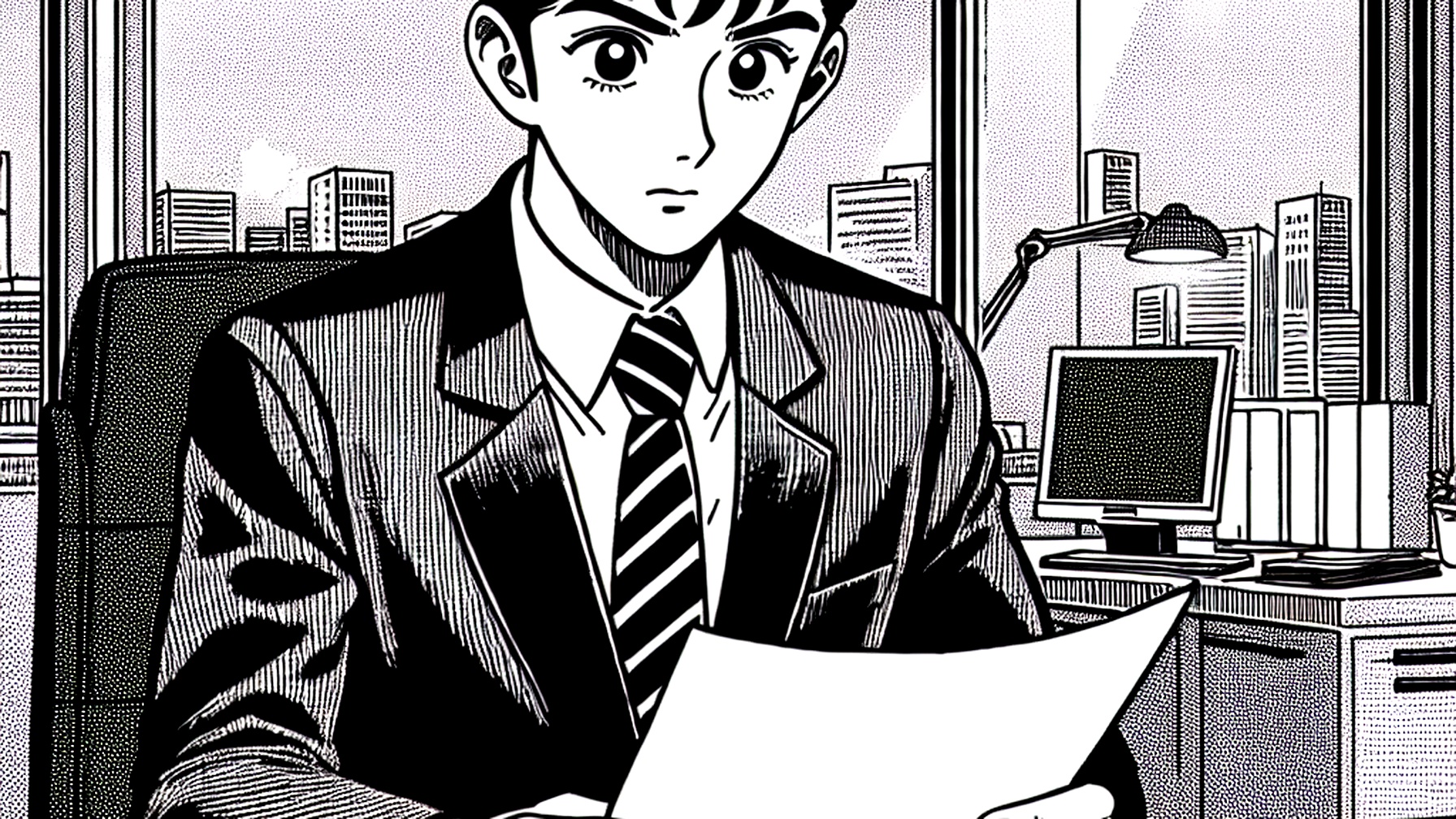
実は、空室は単なる一時的な収入ゼロでは終わりません。総務省の「2025年国勢調査・中間解析」では、地方中核都市で単身世帯が減少局面に入り、賃貸住戸の需給バランスが逆転しつつあります。その影響で築20年以上のワンルームマンションの平均家賃は、過去5年で7.3%下落しています。
一方で、首都圏のような人口流入エリアでも競合物件のグレードが年々向上し、築古物件は家賃を維持しにくい状況が続きます。たとえば同じ駅徒歩10分でも、共用部にオートロックや宅配ボックスが無いだけで募集賃料を5,000円下げないと決まらないケースが増えています。
空室対策としては、設備投資による魅力度向上とターゲット入居者の絞り込みが効果的です。ただし投資額が大きいと回収期間が延びるため、利回りの再計算を忘れないでください。家賃下落幅を年1%とみなしても、10年後には実質利回りが約0.9ポイント下がる計算になります。
ポイントは、購入前に周辺エリアの人口動態と競合物件の築年数・設備を丹念に調査し、家賃維持に必要な追加投資を織り込んだ収支計画を立てることです。物件価格が安くても、想定家賃が維持できなければ意味がありません。
修繕費と老朽化への備え
基本的に、不動産は時間とともに劣化します。国立研究開発法人建築研究所の試算では、鉄筋コンクリート造でも共用部の大規模修繕サイクルは12〜15年が目安とされています。築30年を超えた物件では、外壁補修と給排水管更新で1戸あたり約80万円かかるケースが珍しくありません。
表面利回り8%で購入した物件でも、修繕積立金の不足が判明すると収支は一気に悪化します。また、区分所有の場合は管理組合の合意形成が難しく、修繕計画が先送りになると資産価値が下落します。一棟物件ではオーナー判断で修繕時期を決められますが、その分資金繰りの責任はすべて自分に返ってきます。
言い換えると、購入前に長期修繕計画書を精査し、積立不足があれば購入価格に反映させる交渉が欠かせません。さらに、自己資金とは別に「修繕専用口座」を作り、毎月家賃の10〜15%を自動積み立てすると、突発的な支出にも慌てずに済みます。
売却時の価格変動リスク
不動産投資はインカムゲイン(賃料収入)とともにキャピタルゲイン(売却益)を期待する面があります。しかし、経済情勢や地域の再開発計画の遅れなどにより、売却価格が購入時を下回る可能性は常に存在します。2025年上期の東日本不動産流通機構データでは、築25年以上の区分マンション成約価格は前年同期比で3.1%下落しました。
特に融資残債より低い値でしか売れない「オーバーローン」状態になると、手出しで差額を返済しなければなりません。出口戦略を誤ると、せっかく積み上げた家賃収入が一瞬で消える危険があります。
ポイントは、物件購入時から出口を考える「逆算思考」です。周辺の取引事例を収集し、将来の売却シナリオを最低3パターン描いてください。例えば、賃料下落2%、利回り上昇0.5ポイントという厳しめの前提で価格を試算し、その価格でもローン残債を上回るか確認する手順が有効です。
また、資産組み換えのタイミングを逃さないよう、年1回は簡易査定を取り、マーケットの変化を定点観測する習慣をつけましょう。価格下落が小さいうちに売却を検討できれば、傷口を最小限に抑えられます。
税金と法改正がもたらす不確実性
重要なのは、税制と法律が投資収益を大きく左右する点です。所得税の最高税率は2025年度も45%で据え置かれましたが、ふるさと納税の控除限度額見直しや、住宅ローン減税の適用範囲の縮小が議論されています。これらは、物件を個人名義で保有する場合の手取りを変動させる要因になります。
一方で、固定資産税の評価替えは3年に1度行われ、2026年度が次回の基準年です。築古物件ほど評価額が下がりにくい例もあり、想定より税負担が軽くならないケースがあります。また、民法改正により2024年から敷金精算ルールが明確化され、退去時の原状回復費用を貸主が負担する範囲が拡大しました。これに伴い、実質的な運営コストが上昇しています。
対策としては、法人設立による節税余地を検討しつつ、顧問税理士と年1回のレビューを行い、最新の法改正を収支シミュレーションに反映させることが欠かせません。税務知識をアップデートし続ける姿勢こそ、不確実性をコントロールする鍵になります。
まとめ
ここまで「不動産投資 デメリット」に絞って解説してきました。キャッシュフローの悪化、空室と家賃下落、修繕費の膨張、売却時の価格変動、さらに税法改正の影響など、リスクは多岐にわたります。ただし、リスクを正しく認識し、保守的な収支計画と十分な資金クッションを用意すれば、多くはコントロール可能です。まずは自分のリスク許容度を明確にし、購入検討中の物件ごとに厳しいシナリオを試算してみてください。地に足の着いた準備こそが、長期的に安定した収益への最短ルートになります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査(2024年度) – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 2025年国勢調査 中間解析 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合 議事要旨(2025年7月) – https://www.boj.or.jp
- 東日本不動産流通機構 2025年上期マーケットレポート – https://www.reins.or.jp
- 建築研究所 建築物の長寿命化に関する研究報告書 2024 – https://www.kenken.go.jp

