収益物件に興味はあるものの、購入手順が複雑で二の足を踏んでいませんか。とくにネット上には「いらない物件をつかまされた」という失敗談が溢れ、恐怖心が先に立ちます。しかし、重要なのは正しい順序で情報を集め、数字で判断し、制度を活用することです。本記事では十五年の実務経験と2025年10月時点の最新データを基に、いらない物件を避ける具体的な購入手順と、購入後に安定収益を得るコツをわかりやすく解説します。
収益物件が「いらない」と感じる瞬間とは
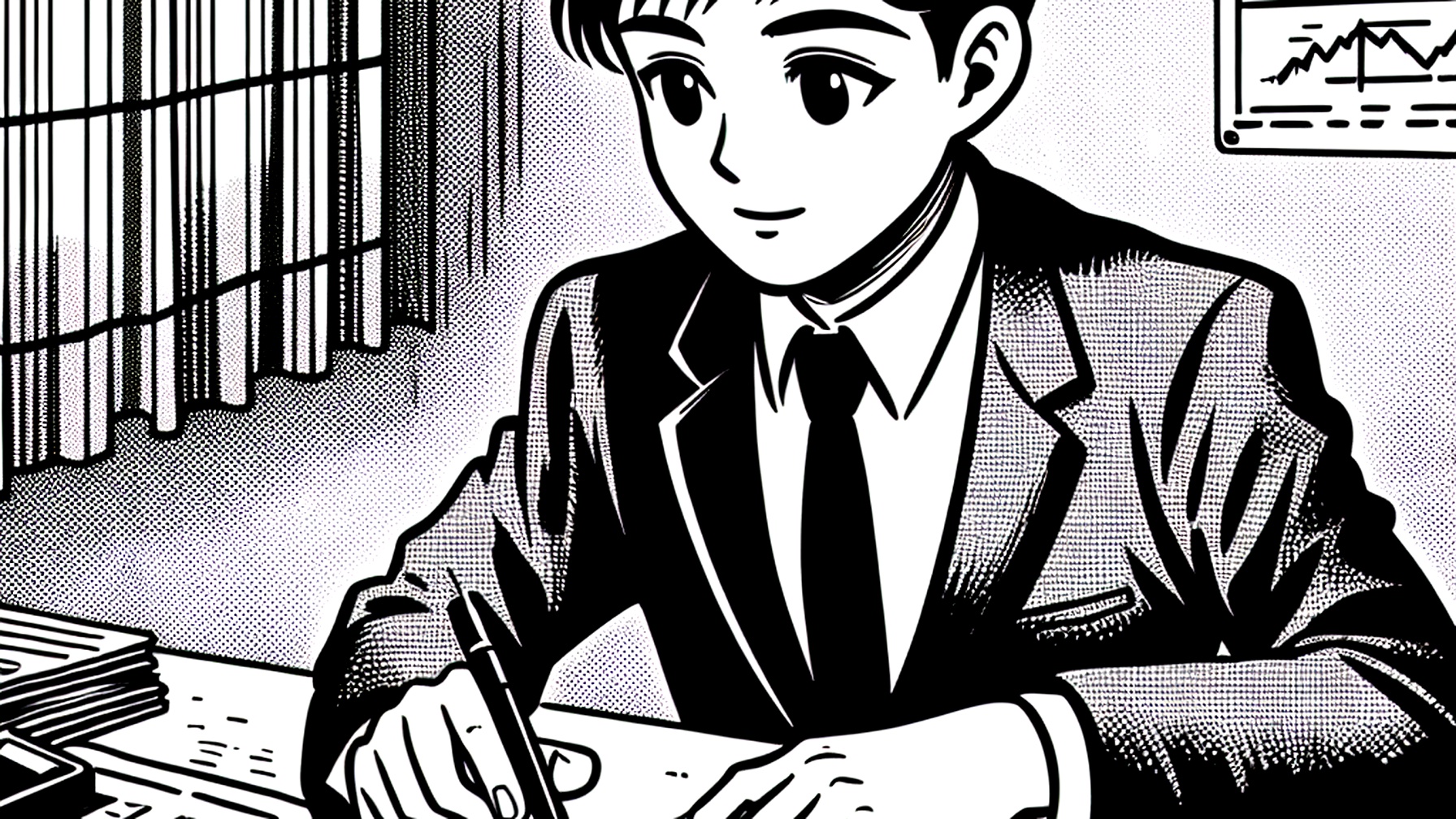
まず押さえておきたいのは、どのような場面で投資家が「この物件はいらない」と判断するかです。理由を理解すれば、同じ落とし穴を避けやすくなります。
家賃が下落してもローン返済が追いつかないケースが典型例です。国土交通省が公表する「不動産価格指数」によると、2025年はマンション価格が高止まりする一方、築二十年以上の中古アパート家賃は横ばいが続きます。このギャップを読めないまま利回りだけで購入すると、想定キャッシュフローが崩れやすいのです。
また、修繕費の見積もり不足も大きな原因です。築古物件は利回りが高く見えますが、大規模修繕が重なると内部留保が一気に吹き飛びます。日本建築学会の平均修繕サイクルによれば、屋上防水は十五〜二十年ごと、外壁塗装は十〜十五年ごとに実施が推奨され、費用は延床面積一平方メートル当たり一万五千円が目安です。
さらに、運営体制の不備が重なると「いらない物件化」が加速します。管理会社まかせで入居者属性をチェックしないまま募集を続けると、トラブル対応に追われ、賃料滞納率も上がります。つまり、購入前に収支だけでなく管理体制までシミュレーションし、想定外の支出を洗い出すことが何より重要になります。
基本的に押さえておきたい購入手順の全体像
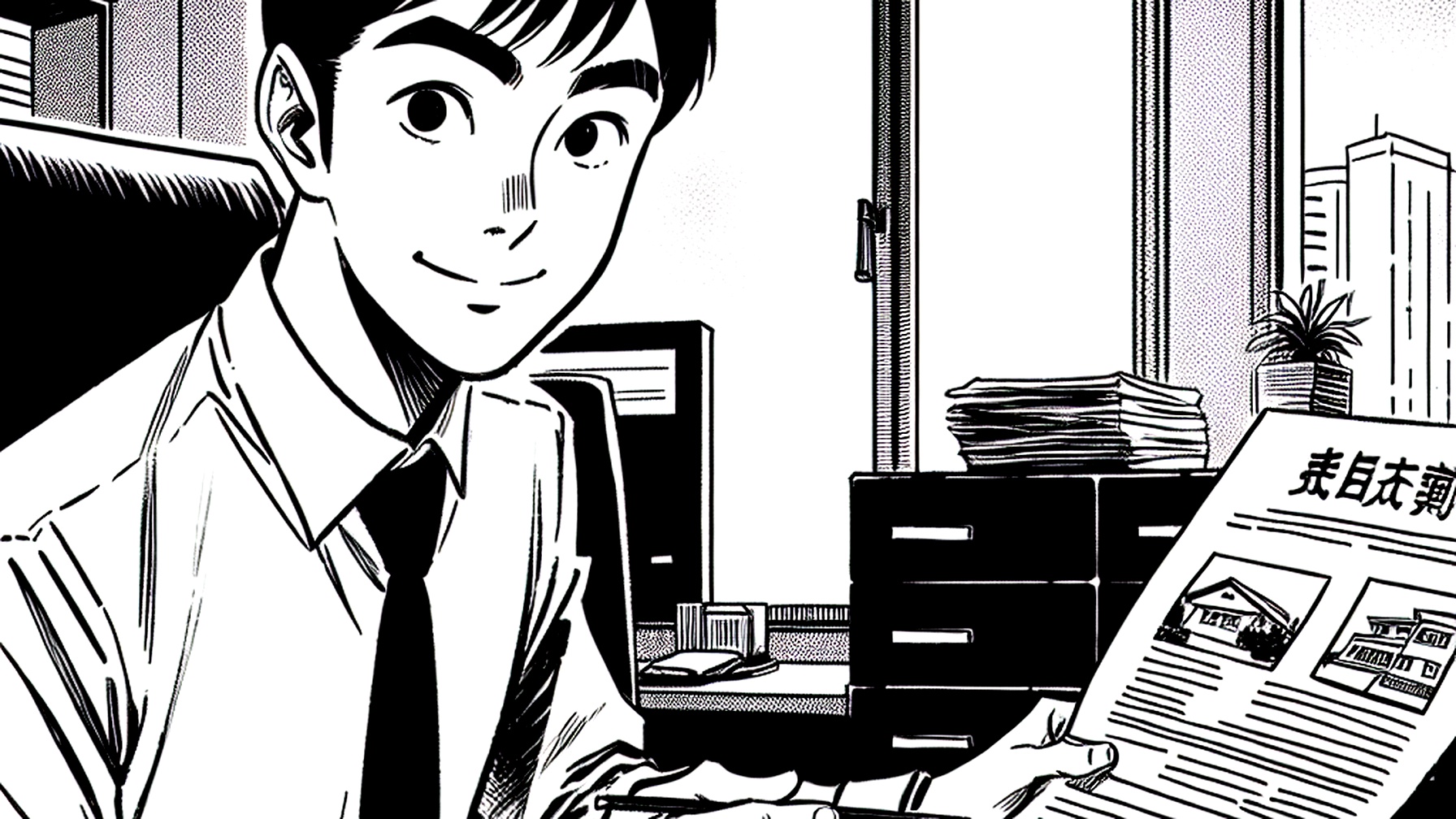
実は「いらない 収益物件 購入手順」という検索キーワードが語るとおり、手順のどこかを飛ばすと失敗リスクが跳ね上がります。ここでは、最低限踏むべきステップを整理します。
以下の五つを順守すれば、致命的なミスは大幅に減らせます。
- 目的設定と資金計画
- 立地と市場調査
- 物件調査と価格交渉
- 融資条件の最適化
- 売買契約と決済後の管理計画
まず、目的設定と資金計画が土台になります。例えば「十年後に売却益を得たい」のか「年金代わりに二十年以上保有したい」のかで選ぶエリアも融資期間も変わります。金融機関は自己資金比率二割を推奨しており、融資期間を短くすると金利が下がる一方で月々の返済が増えるため、キャッシュフローとのバランスを確認してください。
次に、市場調査では人口動向と新築供給量を重視します。総務省の「住民基本台帳人口移動報告」では、2025年も政令指定都市近郊で転入超過が続き、三大都市圏外は微減です。このデータを踏まえ、長期保有の場合は人口流入が続く周辺駅徒歩圏を中心に探すと空室リスクを抑えられます。
物件調査では、レントロール(入居者一覧)と修繕履歴を取得し、収支シミュレーションに反映させます。国税庁の「路線価」を用いれば、土地価格の下限をつかめるので、価格交渉の目安としても有効です。そして、融資条件は三行以上から見積もりを取り、表面金利だけでなく保証料や団信保険料を含めた実質金利で比較しましょう。
実は融資戦略で成否が決まる
ポイントは、金利だけでなく融資期間と返済比率を最適化することです。日本銀行の「短観」によると、2025年は地銀の投資用不動産向け平均金利が2.1%まで下がりましたが、期間は最長十五年に短縮する傾向があります。
利回り八%の中古アパートを例に取ると、金利2.1%で十五年返済の場合、返済比率(年間返済額÷年間家賃収入)は約60%です。一方、同じ金利で二十年返済に延ばせば比率は約48%に下がり、手残りキャッシュが増えます。ただし、期間が延びるほど総返済額は増えるため、出口戦略を明確にしたうえで選択する必要があります。
保証料の扱いにも注意が必要です。保証料を融資額に上乗せする「一括前払い型」を選ぶと、初期費用は抑えられますが、金利計算の元本が増えるため総返済額は高くなります。分割型は毎月の支払いに含まれるためキャッシュフローを圧迫しやすいものの、途中で繰上返済する場合は支払う保証料が少なくて済むというメリットがあります。
また、2025年度は住宅ローン減税の適用外となる投資用ローンでも、地方銀行の「長期固定1%台キャンペーン」が一部継続中です。ただし、自己資金三割と綿密な事業計画が条件なので、選択できる投資家は限られます。逆に言えば、このハードルをクリアできるなら固定金利でリスクを低減できるため、競争優位が得られるでしょう。
空室リスクを抑える物件選定のコツ
重要なのは、家賃需要の裏付けをデータと現場感覚の両方で確認することです。SUUMOやホームズといったポータルで募集戸数をチェックし、同じエリアの築年数・間取り・賃料帯を比較すると需給バランスが見えてきます。
内覧時は共用部の清掃状態と郵便受けのチラシ量にも目を向けてください。チラシが溜まっていない物件は居住者の定着率が高い傾向があります。反対に、廊下に私物が放置されている場合、管理が行き届いておらず、今後のトラブルリスクが高まります。
間取り選定も収益安定に直結します。国土交通省「住宅市場動向調査」によると、単身者向け需要は駅徒歩十分以内の20〜25平米に集中しています。これより狭いワンルームは賃料単価こそ高めですが、募集期間が長引きやすいため、新規投資なら25平米前後を狙うほうが無難です。
さらに、家賃を下げずに入居を促せる付加価値を検討しましょう。Wi-Fi無料化やスマートロック設置は一戸当たり年間三万円前後の追加投資で済み、入居率改善効果が高いと報告されています。こうした小規模投資は大規模修繕に比べて回収期間が短く、キャッシュフロー改善に直結します。
2025年度制度を活用した出口戦略
まず押さえておきたいのは、出口戦略を購入前に決めておくと融資期間や修繕計画が明確になり、投資判断がブレにくくなる点です。売却を前提にするなら、耐用年数の残存期間と金融機関評価を意識する必要があります。
2025年度も「不動産投資法人への譲渡特例」は引き続き有効です。長期譲渡所得の税率が個人と法人で異なるため、個人投資家でも売却時に法人化を検討する価値があります。また、建物を減価償却しきった後に土地値で売却する「土地値投資」戦略は、相続税評価額を下げたい世帯にも有効です。
一方、保有を前提とする場合は、再投資のタイミングに合わせたリファイナンス(借り換え)を計画しましょう。日本政策金融公庫は2025年度も事業拡大目的の借り換えを認めており、金利1.9%前後で最長二十年の融資が可能です。キャッシュアウトを抑えつつ次の物件取得に備えられるため、中長期のポートフォリオ構築に役立ちます。
最後に、インボイス制度への対応も忘れてはいけません。課税売上高が一千万円を超えると消費税申告が必要になり、課税事業者としての会計処理コストが増えます。売却益が大きい年度は、修繕や設備更新を前倒しで実施し、課税所得を圧縮するなど、税負担を平準化する工夫が求められます。
まとめ
結論として、収益物件を「いらない」と後悔しないためには、目的設定から出口戦略まで一貫した購入手順を守ることが欠かせません。資金計画と市場調査を丁寧に行い、融資条件を最適化し、空室を抑える物件選定を徹底すれば、長期的なキャッシュフローは安定します。今日紹介したデータと制度を活用し、まずは一件の物件で収支シミュレーションを作成してみてください。行動に移すことで、数字の裏付けと自信が生まれ、次の投資判断がより正確になります。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp
- 日本銀行 短観(全国企業短期経済観測調査) – https://www.boj.or.jp
- 国税庁 路線価図 – https://www.nta.go.jp
- 日本政策金融公庫 融資制度概要 – https://www.jfc.go.jp

