小学校から大学までの学費は年々上昇し、私立大学に自宅外通学となれば1,000万円を超えるケースも珍しくありません。預金だけで備えるのは心許なく、かといってハイリスクな投資に踏み出すのも不安だという声を多く聞きます。そんな悩みを持つ保護者の方にこそ、家賃収入が長期的に見込めるマンション投資は有力な選択肢になります。本記事では、教育費を目標にした場合の資金計画や物件選びのポイント、2025年時点の市場データまでをわかりやすく解説します。読み終えたとき、具体的な第一歩を踏み出せる道筋が見えるはずです。
教育費はいくら必要か、まず現実を把握する
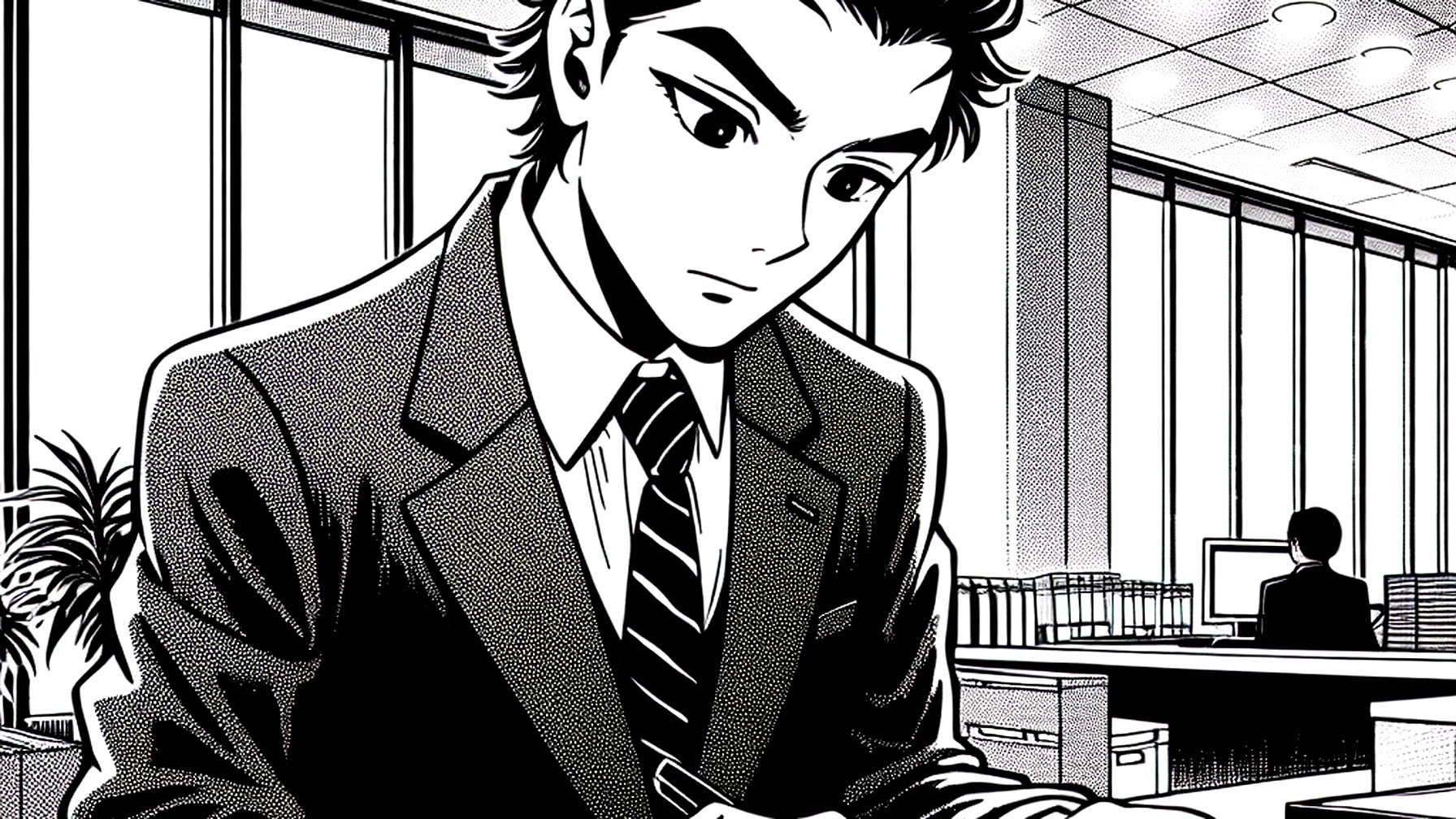
重要なのは、具体的な金額を知り、投資目標を数値化することです。文部科学省の最新調査によると、幼稚園から大学までオール公立でも平均740万円、すべて私立なら約2,200万円が必要とされています。また、都心部で自宅外通学が加わると家賃や仕送りが年間150万円前後上乗せされるため、総額は3,000万円規模になる計算です。言い換えると、月5万円程度の家賃収入を20年間確保できれば学費の大半をまかなえる試算になります。
こうした数字を出発点にすれば、投資額・物件タイプ・融資期間を逆算しやすくなります。例えば利回り4%の区分マンションで手取り月5万円を得るには、概算で1,800万円ほどの自己資金か、低金利融資を活用した2,500万円前後の物件が目安となります。結論として、教育資金づくりは「月いくら必要か」を先に定義し、そこから投資プランを組み立てる姿勢が欠かせません。
都心と郊外、どちらを選ぶべきか
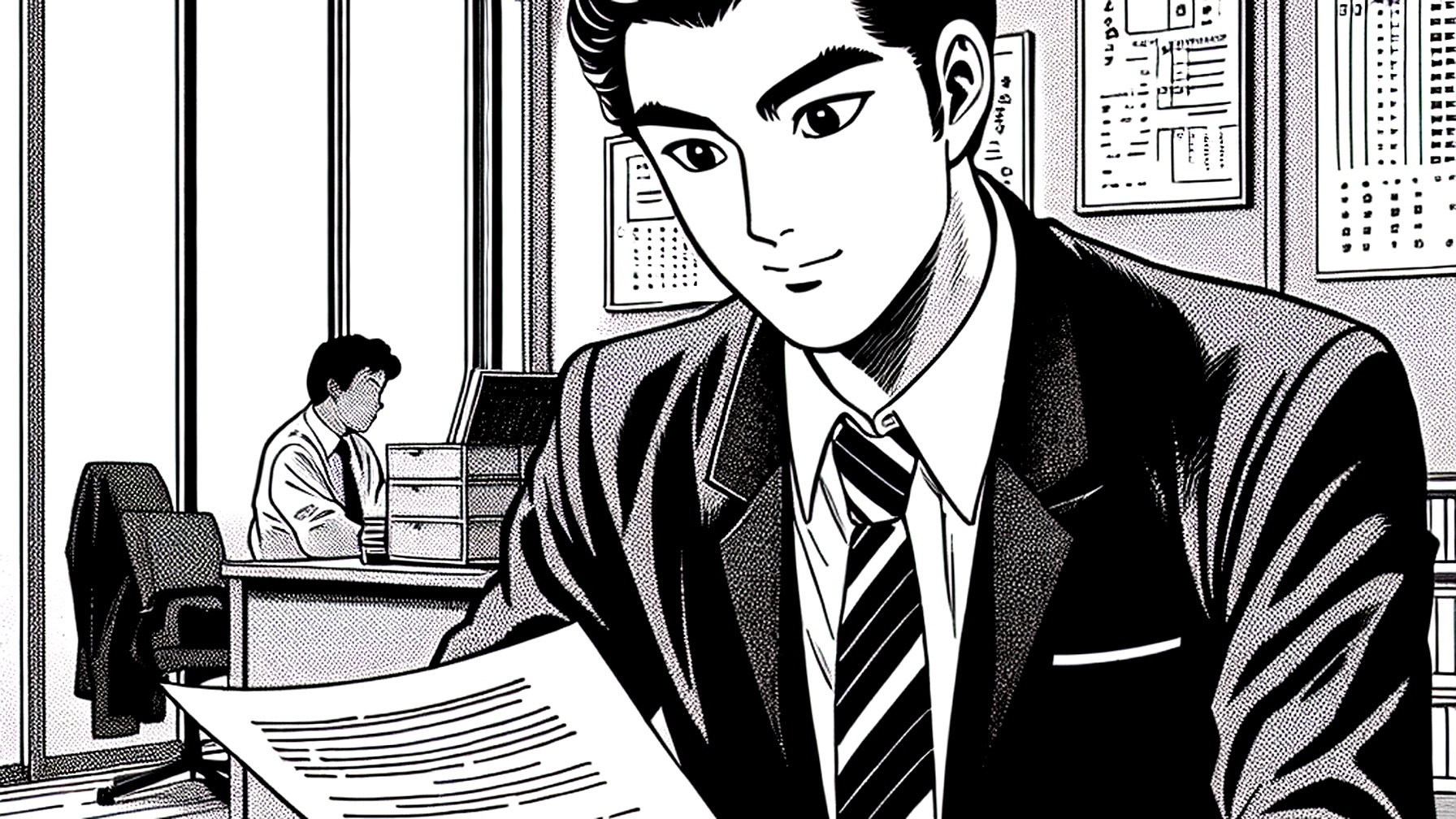
ポイントは、収益の安定性と資産価値をどうバランスさせるかにあります。2025年10月のデータでは、東京23区の新築マンション平均価格が7,580万円と依然高水準を維持しています。一方で空室率は5%未満に抑えられており、賃料下落も小さいためキャッシュフローが読みやすい状況です。つまり、高価格でも融資比率を調整すれば、長期的な家賃収入で教育費を積み立てられるメリットがあります。
郊外物件は初期費用を抑えやすく、利回りも都心より1〜2ポイント高く出る場合があります。しかし、人口減少が進むエリアでは10年後の賃料維持が難しく、空室リスクも相対的に高まります。教育資金のように「使う時期が決まっている目的資金」では、利回りよりも入居継続性を重視するほうが安全です。実は、「駅近」「築浅」「ワンルーム」という王道スペックを守るだけで、都心でも表面利回り3.5〜4%を確保できる物件は見つかります。結果として、郊外で5%を狙うより、都心で4%の確実性を選ぶ投資家が増えているのが現状です。
キャッシュフローと税効果を味方に付ける
まず押さえておきたいのは、家賃収入からローン返済、管理費、固定資産税を差し引いた「手取り」が教育資金の原資になる点です。ここで節税効果を活用すれば、実質的な手取りをさらに底上げできます。賃貸用マンションの減価償却費は、建物価格を22年(鉄筋コンクリート造)で経費化できるため、初期数年間は課税所得を圧縮できます。また、借入金利も経費に算入できるので、高年収の会社員ほど所得税・住民税の還付メリットが大きくなります。
例えば年収800万円の会社員が2,500万円の区分マンションを購入し、年間120万円の家賃収入を得るケースを考えます。諸経費と減価償却で年間経費を90万円計上すれば、課税対象は30万円に抑えられます。税率20%とすると6万円の税負担で済み、手取りは約24万円です。月換算2万円ながら、ローン元本返済分も将来の資産形成につながるため、実質利回りはさらに高くなります。こうしてキャッシュフローと税メリットを重ねることで、教育資金を計画的に積み上げられるわけです。
なお、2025年度税制では賃貸住宅に対する新たな補助や減税は公表されていませんが、所得税の総合課税方式と減価償却の取り扱いは従来通り維持されています。基本的な税優遇だけでも十分に効果的なので、まずは確定申告を正しく行い、控除を漏れなく受け取る体制を整えましょう。
融資戦略と返済計画の立て方
実は、教育資金目的のマンション投資では借入期間の設定が成否を分けます。子どもが18歳になるまでにローン残債を減らし、学費支出が本格化する時期にキャッシュフローを厚くする計画が理想です。例えば子どもが3歳のときに投資を始めた場合、15年返済に設定すれば高校入学時にはローンが完済し、家賃の大半を使途自由にできます。金利負担は増しますが、目的資金のタイムラインに合致するため、総返済額を上回るメリットが期待できます。
一方で、返済期間を30年にして月々の負担を軽くし、繰り上げ返済で調整する方法もあります。長期固定金利が年1.5%前後で推移する2025年時点では、繰り上げ返済の柔軟性を重視する投資家も多いです。ポイントは、ボーナス併用返済や一部繰り上げにより、教育費ピーク前に残債を2割以下にできるかを定期的にチェックすることです。金融機関によっては、「教育資金準備プラン」として団体信用生命保険に学資保険を組み合わせる提案もあるので、比較検討するとよいでしょう。
さらに、同一金融機関で教育ローンを併用すると金利優遇が受けられるケースもあります。つまり、マンション投資と教育ローンを縦断的にプランニングすれば、総支払利息を抑えながら必要資金を確保できる可能性が高まります。
失敗を防ぐための運用・出口戦略
まず押さえておきたいのは、出口を意識した運用が教育資金づくりには不可欠だという点です。大学進学時にまとまった資金が必要なら、物件売却でキャピタルゲイン(売却益)を得る選択肢も視野に入ります。東京23区の中古マンション価格は過去10年で平均25%上昇しており、築15年以内の駅近物件なら購入価格以上で売れる事例も珍しくありません。
しかし、売却益に頼りすぎると市場調整局面で計画が狂う恐れがあります。そこで、安全策として家賃収入だけで学費をまかなえるプランをベースとし、売却益はあくまで上振れ要素と位置づけると安心です。また、学費支出が終わった後も物件を保有すれば、老後資金の柱として活用できます。賃料が下がっても元手ゼロで得られる不労所得は大きな安心材料になるでしょう。
出口戦略を柔軟にするためには、管理状態を良好に保ち、入居者募集を途切れさせない運用が大切です。管理会社のレポートを毎月確認し、原状回復や設備更新を先送りにしない姿勢が、結果的に高値売却や再融資の成功率を高めます。
まとめ
マンション投資を活用した教育資金づくりでは、必要額を明確にし、安定的な家賃収入が得られる物件を選ぶことが第一歩です。都心部の築浅ワンルームは購入価格が高めでも空室リスクが低く、長期的なキャッシュフローを見込みやすい特徴があります。さらに、減価償却や金利控除を活用すれば手取りを押し上げることが可能です。ローン期間を教育費のタイミングに合わせ、繰り上げ返済や売却を組み合わせることで、計画通りの資金確保が現実味を帯びてきます。今日から家計と投資プランを見直し、一歩踏み出すことで、子どもの夢を経済面で支える準備を始めてみてはいかがでしょうか。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 文部科学省「子どもの学習費調査」 – https://www.mext.go.jp
- 東京都都市整備局 住宅市場動向報告 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 国税庁 「所得税法」関連資料 – https://www.nta.go.jp
- 日本銀行「貸出金利動向」 – https://www.boj.or.jp

