不動産による相続対策に興味はあるものの、「高齢の親名義で土地はあるが何から始めればいいのか分からない」「空室が増えていると聞くが、本当に収益になるのか」と不安を抱える人は多いはずです。実は築浅アパートを活用すれば、相続税評価額を抑えつつ安定収益も狙えるため、資産を残したい家族にとって有力な選択肢になります。本記事では最新の空室率データと2025年度の制度を踏まえながら、資金計画、税制優遇、物件選び、管理体制まで丁寧に解説します。読了後には「アパート経営 築浅 相続対策」を実践する具体的な手順が見えるでしょう。
築浅アパートが相続対策に向く理由
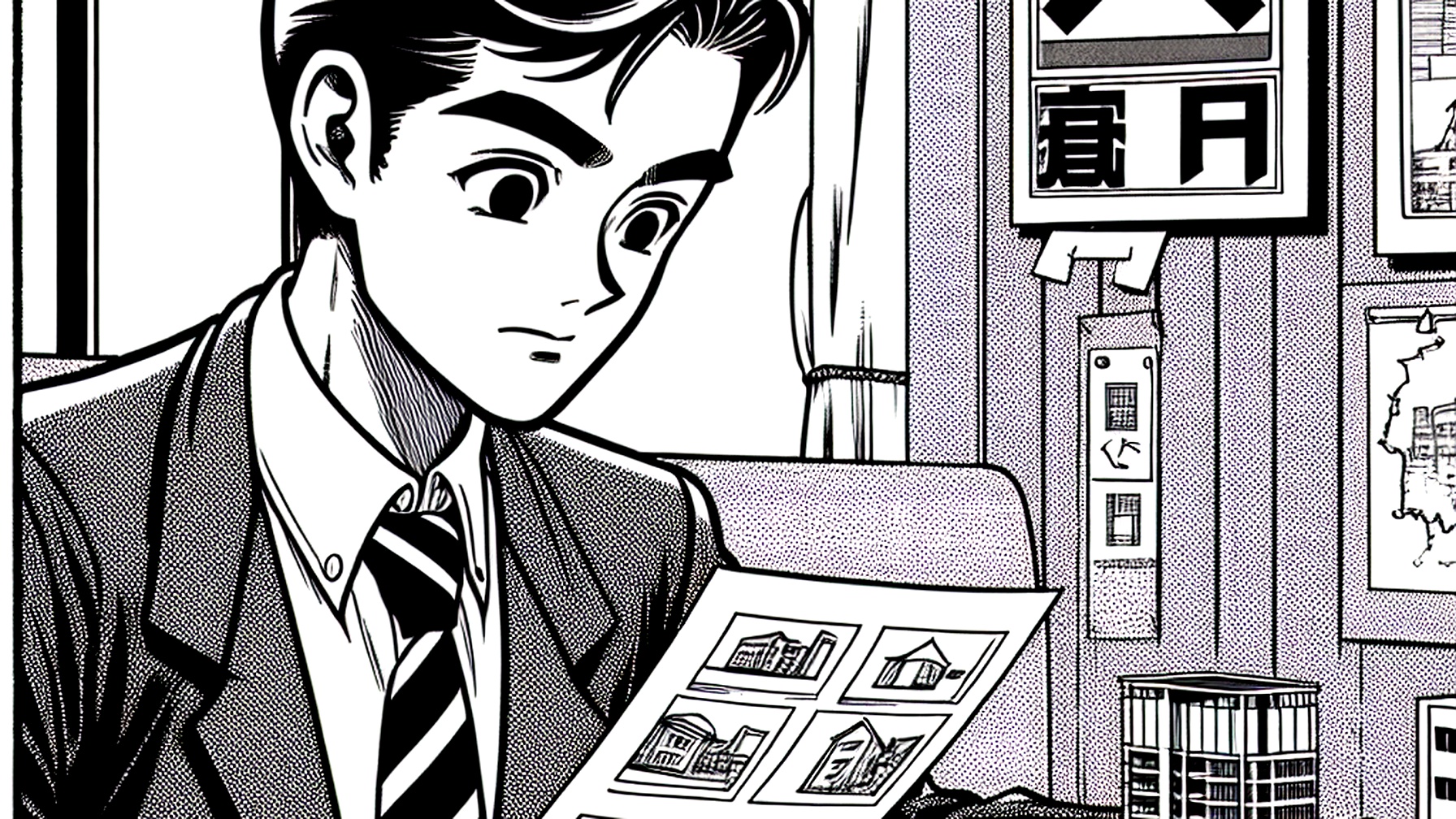
重要なのは、築浅アパートが現金よりも相続税評価額を下げやすい点です。土地を所有している場合、建物を新築または築浅で建てることで「貸家建付地(かしやたてつけち)」評価となり、土地価格が約20%減額されます。さらに建物自体も「固定資産税評価額」で評価されるため、建築費の約50〜70%まで圧縮されるのが一般的です。
続いて収益面を見てみると、国土交通省住宅統計によると2025年8月時点の全国アパート空室率は21.2%で、前年より0.3ポイント改善しています。築年数が浅い物件では設備が最新であるため広告効果が高く、同じエリアの築古物件より入居決定が平均2週間早いという仲介大手の社内データもあります。つまり相続対策と収益安定を同時に満たしやすいのが築浅アパートなのです。
一方で、建築費が高くなりがちな点や、立地が悪ければ空室リスクが急増する点には注意が必要です。相続税を減らせてもキャッシュフローが赤字では本末転倒ですから、後述する資金計画と物件選びが成功の分かれ道になります。
資金計画とキャッシュフローの見極め方
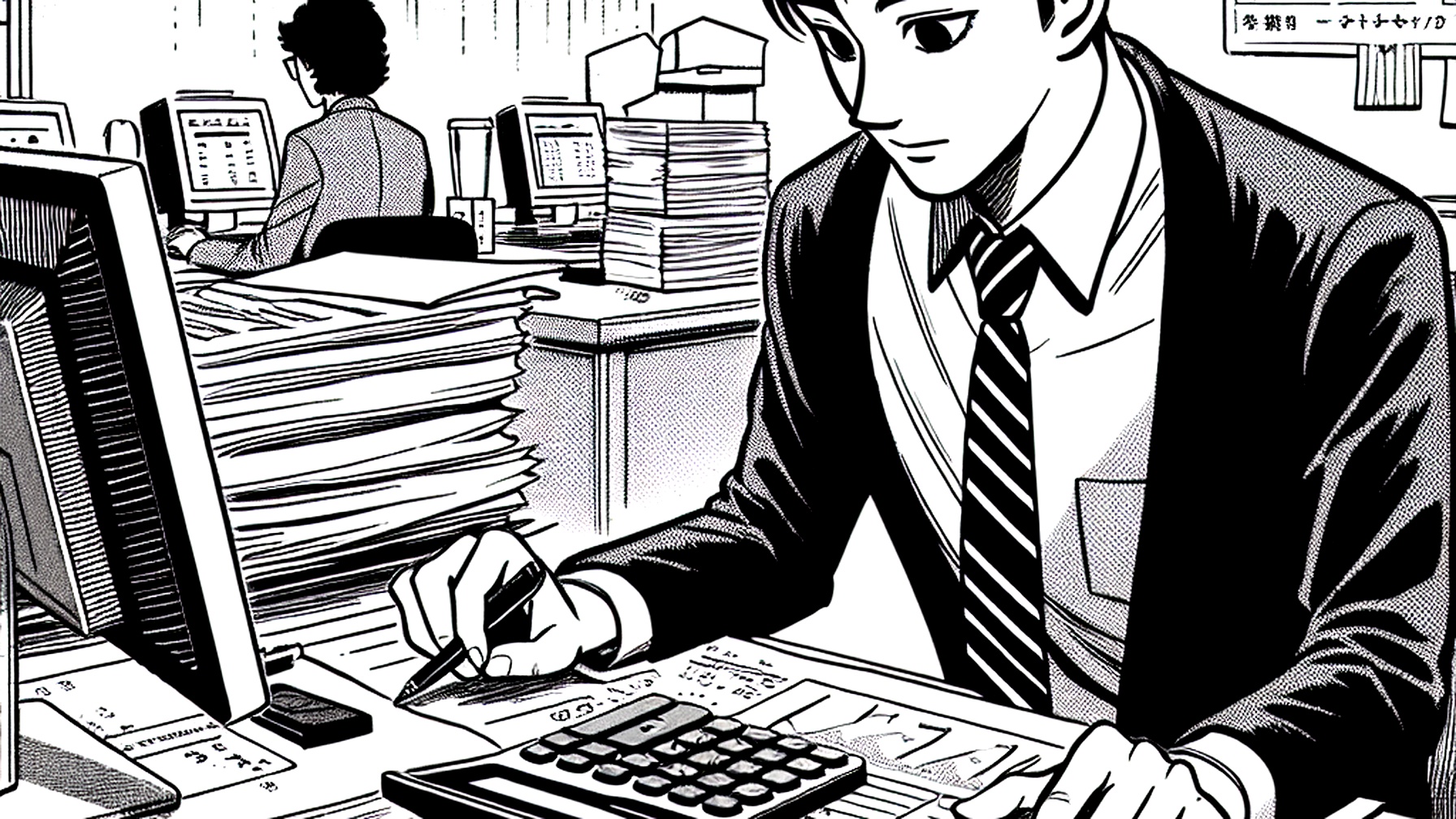
まず押さえておきたいのは、自己資金と融資割合のバランスです。金融機関は築浅アパートを評価しやすく、2025年時点で金利1.0〜2.0%台の長期ローンが組めるケースが増えています。自己資金を物件価格の20〜30%用意できれば、金利条件が優遇され返済比率も抑えられるため、手取りキャッシュフローが出やすくなります。
次にシミュレーションでは「空室率15%」「家賃下落年1%」「金利上昇1%」といった厳しめの前提を入れると、実態に近い数字が把握できます。家賃収入からローン返済、管理費、固定資産税、修繕費を差し引き、年間手残りがプラス10万円以上なら堅実といえるでしょう。逆にマイナスが続く場合は建築費の見直しや自己資金の追加が必要です。
さらに築浅であるほど大規模修繕費は10年程度発生しにくいものの、毎年家賃収入の5%を修繕積立として別口座に確保しておくと安心です。こうした備えがあれば、相続で物件を引き継いだ家族も急な費用負担に悩まされずに済みます。
2025年度の税制優遇を活かすポイント
ポイントは、現行制度を正しく組み合わせることです。まず「小規模宅地等の特例」を活用すれば、アパート敷地200㎡までの評価額を50%減額できます。2025年度も制度は継続しており、賃貸事業を継続することが適用要件です。
建物については「相続時精算課税制度」を使うと、親からの贈与を2,500万円まで非課税で受け取れます。これを建築資金に充当すれば、ローン残高を減らしつつ将来の相続税も抑えられます。
また、2025年度も適用される「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」により、賃貸アパートは120㎡までの部分が3年間1/2に軽減されます。築浅アパートなら満額で受けられるため、初期キャッシュフローを大きく改善できます。
さらに環境性能の高い建物に対しては「住宅省エネ2025支援事業」の補助金が上限100万円/戸で利用可能です(2026年3月交付申請締切予定)。高断熱仕様や高効率給湯器を採用すれば、家賃プレミアムに加えて高稼働が見込める点も見逃せません。
失敗を防ぐ物件選びと管理体制
実は立地選定と建物仕様のバランスが、長期収益の安定を左右します。都心部は土地値が高いものの人口流入が多く、ファミリー向けより単身用ワンルームが高稼働です。一方、郊外でも駅徒歩10分以内で生活インフラが整っていれば、家賃単価は下がっても土地取得費が抑えられ、利回りは高まります。
建物仕様では、Wi-Fi無料設備や非対面宅配ボックスなど入居者ニーズの高い設備を初期導入すると競争力が維持しやすくなります。築浅であっても設備更新を怠ればすぐに「古さ」を感じさせるため、5年ごとに共用部のLED化や外壁点検を計画に組み込みましょう。
管理面では、自主管理よりも専門管理会社の利用がトラブル防止に有効です。特に相続後にオーナーが変わると、入居者とのコミュニケーションが滞りやすくなります。管理委託契約で「24時間クレーム対応」「退去精算の透明化」を明文化しておくと、家族が引き継いだ後も運営がスムーズです。
専門家とのチームづくりが成功の鍵
まず、税理士と不動産会社を別々に選ぶのではなく、相続対策に強いチームを組むことが大切です。税理士は最新の税制変更をフォローし、融資交渉の場では金融機関に事業計画を的確に説明してくれます。不動産会社はエリアの空室データを基に賃料設定と広告戦略を立て、管理会社は入居者クレームを早期に解決します。
一方で、建築会社だけの提案に任せると「建てたら終わり」になりがちです。必ず第三者の不動産投資コンサルタントに事業計画を査定してもらい、初年度利回りと10年後の残債割合をチェックしましょう。専門家の視点が加わることで、相続税の節減効果と収益性を両立できる計画に磨き上げられます。
加えて、家族会議を定期的に開き、物件の収支報告と将来方針を共有しておくと、相続時の意思決定が格段にスムーズになります。築浅アパートは長期資産だからこそ、家族と専門家を交えたチーム経営が不可欠なのです。
まとめ
本記事では築浅アパートを活用した相続対策のメリットと注意点を解説しました。貸家建付地評価による相続税圧縮、固定資産税の軽減、2025年度の補助金活用など多面的な恩恵が得られる一方、厳格な資金計画と立地選定が欠かせません。結論として、家族が長期にわたり安心して運営できるよう、専門家チームと連携して数字に基づいた計画を作成することが成功への近道です。まずは所有土地の評価と資金調達力を確認し、3パターン以上のシミュレーションを作成するところから始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査(2025年8月速報) – https://www.mlit.go.jp
- 財務省 相続税法令解説(2025年度版) – https://www.mof.go.jp
- 国税庁 No.3308 小規模宅地等の特例 – https://www.nta.go.jp
- 環境省 住宅省エネ2025支援事業 事業者向け資料 – https://www.env.go.jp
- 総務省 固定資産税に関するFAQ(2025年4月改訂) – https://www.soumu.go.jp

