働きながら安定した副収入を得たいと考えるサラリーマンは多いものの、「本当に黒字になるのか」「時間や知識が足りないのでは」と二の足を踏みがちです。実は、仕組みさえ理解すればアパート経営は本業と両立しやすく、将来の資産形成にも直結します。本記事では、収益性を軸にアパート投資の基本から資金計画、2025年度に使える支援制度まで網羅的に解説します。読み終えるころには、自分に合った投資戦略の輪郭が見え、次の行動へ踏み出す自信が得られるでしょう。
アパート投資がサラリーマンに向く理由
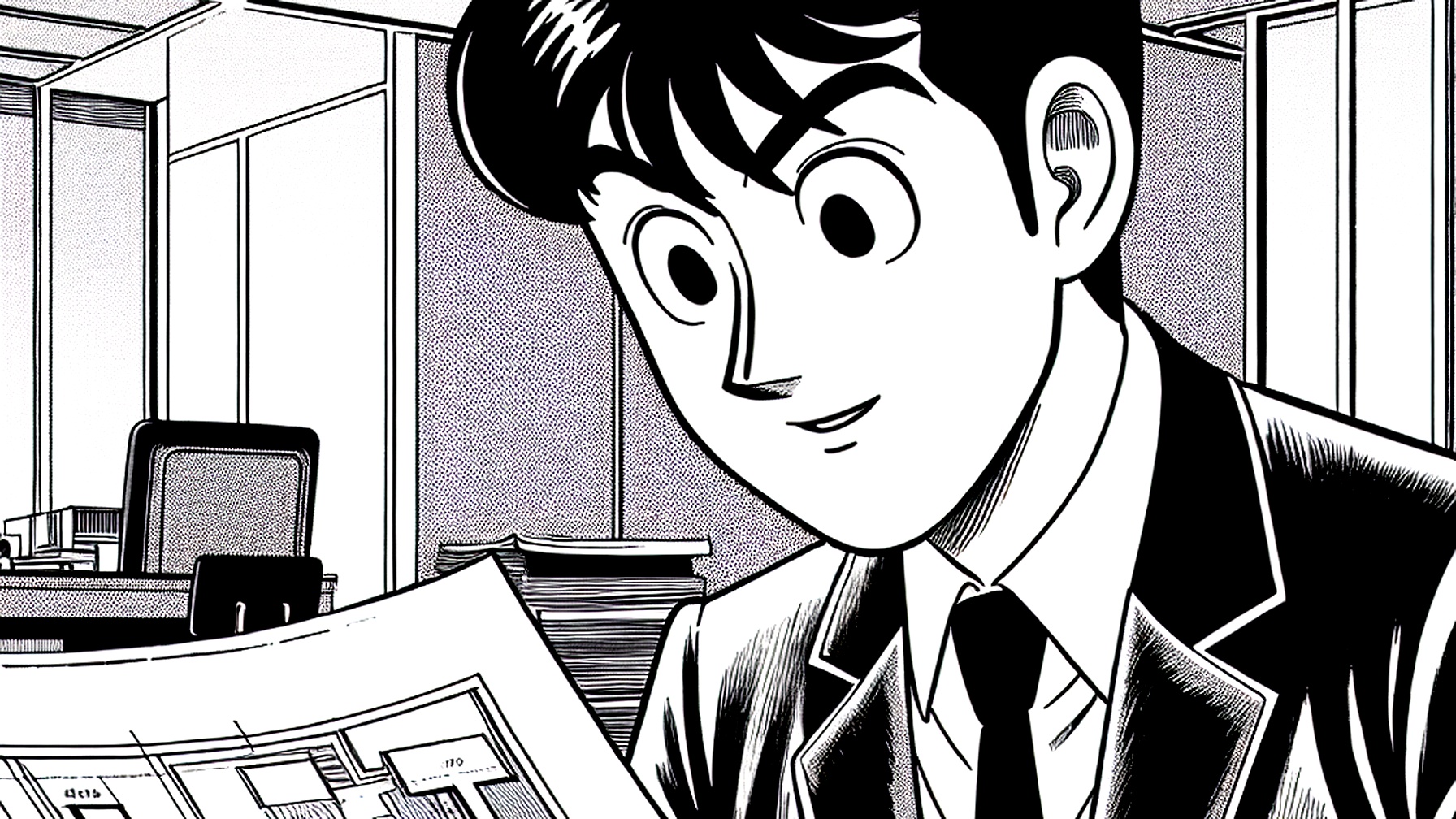
まず押さえておきたいのは、給与所得があるサラリーマンは金融機関の信頼を得やすい点です。この安定収入が融資審査を通過するうえで大きな武器となり、少ない自己資金でもアパートを取得できる可能性が高まります。
一方で、物件管理や入居者対応に時間を割けない不安もあります。しかし、管理会社へ業務を委託すれば、家賃集金やクレーム対応の大半を任せられるため、実際の手間は月に一度のレポート確認程度で済むケースが一般的です。つまり、本業を続けながらも収益源を複線化できる点が大きな魅力になります。
さらに、所得税の節税効果も見逃せません。減価償却費という帳簿上の経費を計上することで、実際のキャッシュアウトを伴わずに課税所得を圧縮できるため、税引き後の手取りが向上します。この仕組みは給与所得者ほど恩恵が大きく、結果として投資効率を高めやすいのです。
収益性を左右するキャッシュフローの考え方
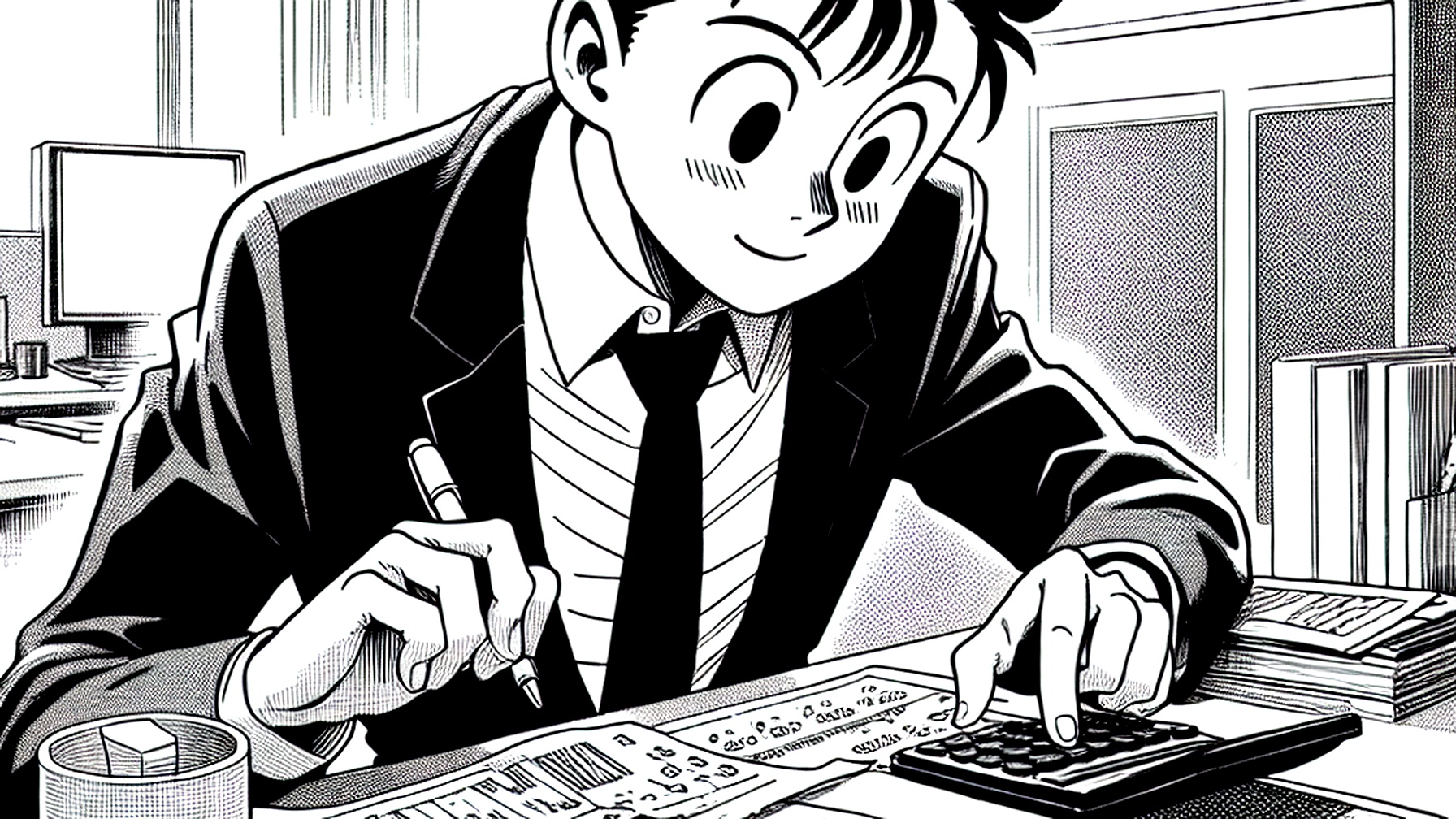
ポイントは、月々のキャッシュフローを正しく把握し、長期的に黒字を維持できるシミュレーションを組むことです。家賃収入だけでなく、空室損失や修繕費を含めた総支出を見積もる姿勢が欠かせません。
国土交通省の2025年8月データによると、全国のアパート空室率は21.2%でした。前年比では0.3ポイント改善したものの、依然として5戸に1戸は空いている計算になります。したがって、満室想定で収支を組むのは危険で、少なくとも空室率20%のシナリオを反映させましょう。
家賃収入から管理委託料・修繕積立・固定資産税を差し引き、さらにローン返済を控除した後に残る金額が実質のキャッシュフローです。ここがプラスであれば、毎月の手取りが増え、突発的な工事にも備えられます。逆にマイナスが続くと追加の自己資金が必要になり、精神的な負担が大きくなります。
実は、利回りだけを追うと郊外の築古物件に目が向きがちです。しかし修繕コストや入居者ニーズを考慮すると、トータルキャッシュフローで都心近郊の築浅物件が有利になるケースも多いものです。数字の裏にあるリスクを読み解き、複数シナリオで耐性を確認することが成功の近道といえます。
物件選びで失敗しない立地と間取り
重要なのは、将来的な入居需要が落ちにくいエリアを選ぶことです。駅からの距離、周辺の雇用環境、生活インフラの充実度が三本柱となります。
まず駅徒歩10分以内であれば賃料設定に強気の交渉余地が生まれ、空室リスクも軽減できます。加えて、大学や病院の近くは単身者の転入が安定しており、家賃下落も緩やかな傾向があります。一方で郊外の大型ショッピングモール周辺は一時的に人口が増えても、退去率が高くなるケースがあるため注意が必要です。
間取りに関しては、ワンルームだけでなく1LDKや2DKを組み合わせると、単身からカップルまで幅広い層を取り込めます。総務省の家計調査によれば、20〜30代の二人暮らし世帯はここ5年で4.1%増えており、このニーズをとらえると入替えコストを抑えられます。つまり、賃料の層を分散させることで安定性が高まるのです。
最後に、現地調査を怠らないことが大切です。昼夜で騒音が変わる場合や、周辺道路が狭く消防車が入りにくいエリアでは、保険料や安全面のリスクが増します。データだけでなく、自分の目と耳で確認するひと手間が長期的な収益を守ります。
融資と税制を味方にする資金計画
まず、金融機関の融資条件を比較検討する姿勢が欠かせません。サラリーマンの場合、メガバンクよりも地元の信用金庫やノンバンクの方が積極的に融資してくれることがあります。
金利が0.5%違うと、借入額7,000万円・期間30年の場合、総返済額は約600万円変動します。固定と変動の選択はリスク許容度によりますが、2025年現在の低金利環境でも金利上昇に備えたバッファを設定しておくと安心です。また元金均等返済は初期キャッシュフローが苦しくなるものの、最終的な利息総額を抑えられるため、長期で保有するなら検討する価値があります。
税制面では、木造アパートの法定耐用年数22年を超える中古物件を買えば、4年で減価償却できる特例が使え、初期数年間の節税効果が大きくなります。ただし物件の実質価値が伴わないと意味がないので、インスペクション(専門家の建物診断)を併用して安全性を確認しましょう。
加えて、赤字が出た場合には給与所得との損益通算が可能です。これにより所得税と住民税が軽減され、その還付金を再投資に回せば複利効果を高められます。この一連の資金循環を計画的に設計することが、収益性向上のカギとなります。
2025年度に活用できる支援制度
実は、国や自治体が用意する制度を活用することで投資効率をさらに引き上げられます。以下では、2025年10月時点で有効な代表的仕組みを紹介します。
まず、「建築物省エネ改修推進事業(2025年度)」では、アパートの断熱改修や高効率設備導入に対し工事費の最大3分の1が補助されます。申請には工事前のエネルギー計算が必須ですが、補助金が出ることで表面利回りを改善し、入居者募集時の訴求力も高まります。
次に、「耐震改修促進税制(2025年度末まで)」を利用すると、旧耐震基準の物件を一定基準まで改修した場合、固定資産税が翌年度から2年間半額になります。収支シミュレーションに入れると、実質利回りが0.3〜0.5ポイント上昇するケースも珍しくありません。
さらに、中小企業経営強化税制が2025年3月まで延長されており、賃貸住宅の設備投資にも即時償却または税額控除が選択できます。給湯器や太陽光発電など高単価設備を導入する際には、初年度で投資負担を一気に圧縮できるため現金流出を抑えやすいです。
これらの制度は年度ごとに予算枠があり、早期終了の可能性もあるため、工事計画が固まった段階で速やかに専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
この記事では、サラリーマンがアパート経営で収益性を高めるための視点を整理しました。安定した給与を信用力に変え、空室リスクを織り込んだキャッシュフローを組み、立地と間取りで需要を押さえ込み、融資と税制を駆使すれば、着実に黒字化を目指せます。加えて、2025年度も利用できる補助金や税優遇を活用すれば投資効率はさらに向上します。まずは気になるエリアを歩いて情報を集め、簡易シミュレーションを試みるところから一歩を踏み出しましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅局「住宅市場動向調査」2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局「家計調査年報」2025年 – https://www.stat.go.jp
- 中小企業庁「経営強化税制の手引き」2025年度 – https://www.chusho.meti.go.jp
- 環境省「建築物省エネ改修推進事業 交付要綱」2025年度 – https://www.env.go.jp
- 財務省「租税特別措置法通達 耐震改修促進税制」2025年4月改訂 – https://www.mof.go.jp

