家賃がじわじわ下がる時代に「築古でも収益は出せるのか」と不安を抱く方は少なくありません。実は、適切な選定と運営を行えば築年数の古い物件でも安定したキャッシュフローを生み出せます。本記事では、2025年10月時点で有効なデータを基に、収益物件ランキングで築古物件が評価される背景と、初心者が押さえるべきリスク管理のポイントを解説します。読み進めれば、物件探しから融資、再生のコツまで一連の流れを具体的にイメージできるはずです。
築古物件が注目される背景
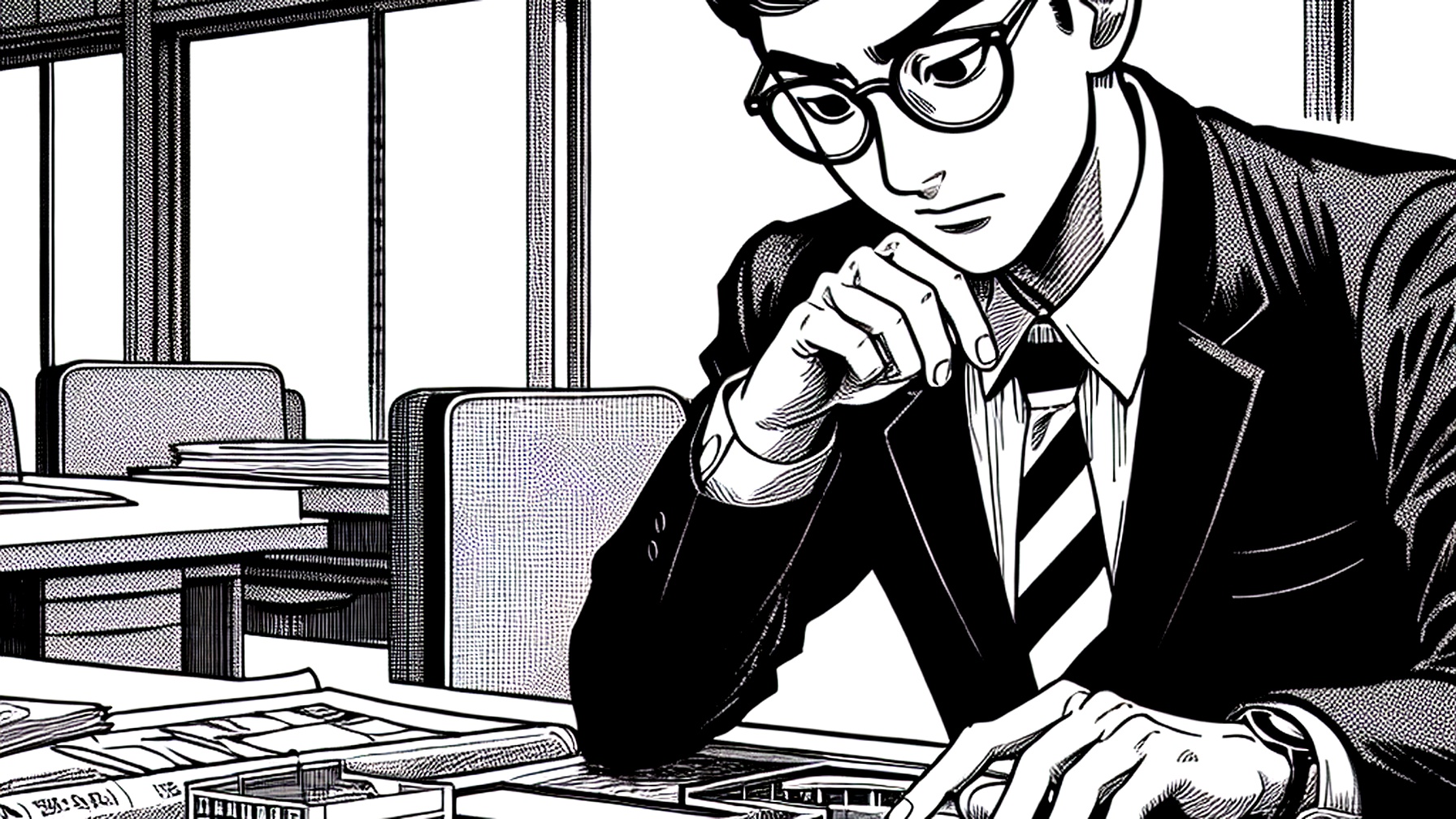
重要なのは、築古物件ならではの購入価格の低さと賃料の下げ止まり効果に着目することです。国土交通省の「不動産価格指数」によると、築30年超でも立地が良ければ賃料は築20年物件と大差ないケースが増えています。一方、物件価格は築20年でおおむね新築時の半額、築30年で3分の1まで下がる傾向があり、利回りを押し上げる大きな要因となります。
まず購入コストが低いことで自己資金の割合を高めやすく、金融機関の融資審査にも通りやすくなります。また、減価償却期間が短くなるため、所得税や住民税を抑える節税効果が期待できます。つまり、キャッシュフローと税引後の手残りを同時に改善しやすいのが築古物件の強みです。
しかし、設備の老朽化リスクは避けられません。配管の腐食や屋上防水の劣化が放置されると、漏水や空室増につながります。購入前に長期修繕計画を確認し、2025年度の「既存住宅性能表示制度」で公開が義務化されたインスペクション報告書も必ずチェックしましょう。これが後の予期せぬ出費を防ぐ鍵になります。
収益物件ランキングの読み解き方
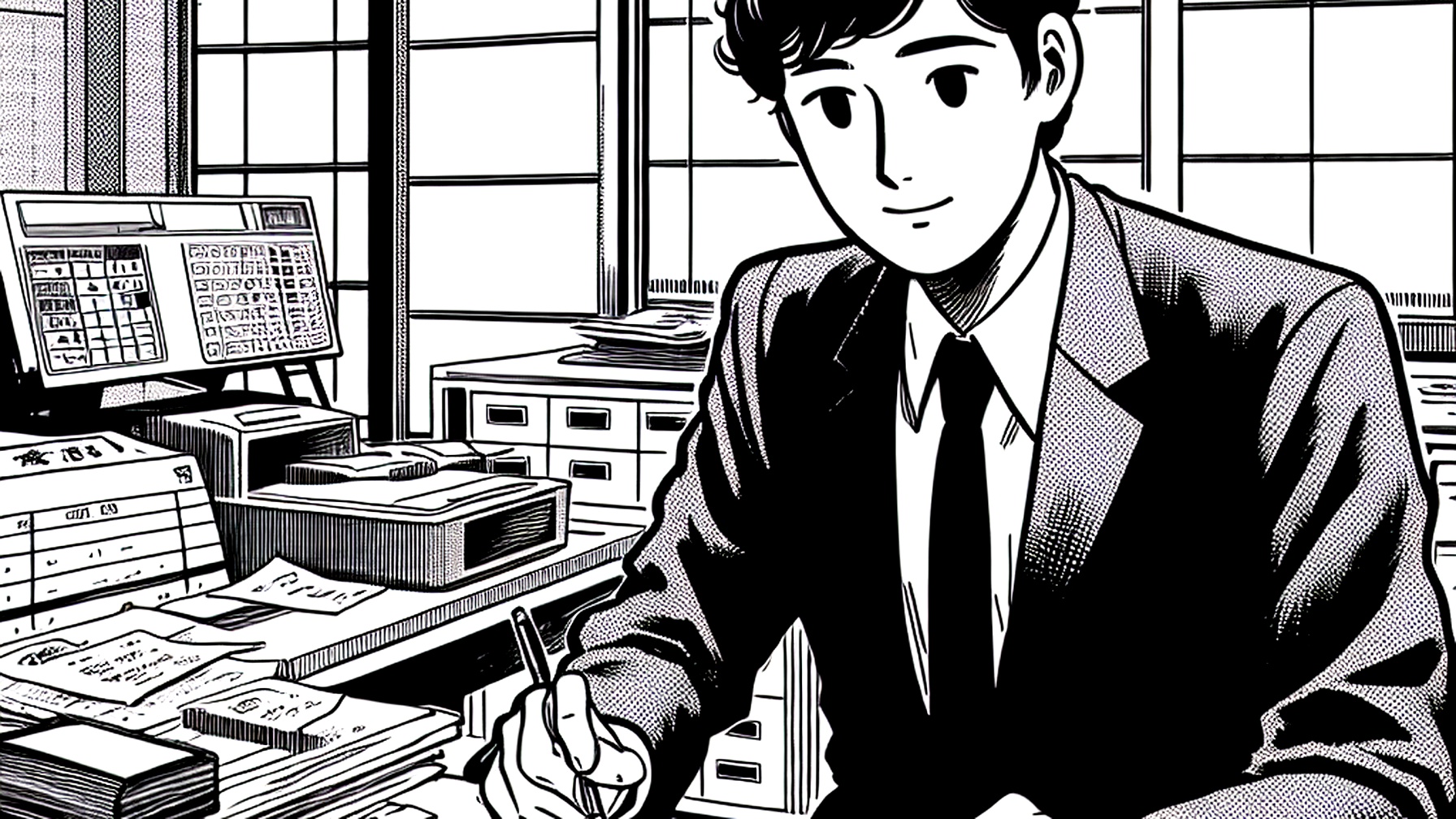
ポイントは、表面利回りだけでなく「実質利回り」「エリアの人口動態」「修繕履歴」を総合評価しているランキングを選ぶことです。大手ポータルが公表する2025年上半期のランキングでは、地方中核都市の築25~35年アパートが上位を占めました。人口10万人以上、大学や工業団地があるエリアが共通点で、「空室率10%以下」「実質利回り9%以上」が目安です。
ランキングを使う際は、①掲載基準、②算出時期、③取引事例数を必ず確認しましょう。掲載基準が不明確なサイトでは、広告目的で利回りが高く見える物件が混在しています。また、2025年4月に施行された「不動産取引情報提供制度」により、直近1年以内の成約データ公開が拡充されました。これを参照すれば、ランキングの数字が市場実勢とかい離していないかを検証できます。
さらに、ランキング上位でも空室保証やサブリース利回りを含む「見かけの数値」には要注意です。実質利回りを計算する際は、管理費・修繕積立金・固定資産税を差し引いたネット収入で判断しましょう。こうした裏付け作業を通じて、ランキングを鵜呑みにせず自分の投資基準に落とし込む習慣が身につきます。
築古アパート再生の成功事例
実は、築古でもターゲットを絞った改修を行えば賃料UPと入居期間の長期化を同時に達成できます。たとえば埼玉県川口市の築32年木造アパートを取得した事例では、購入価格2,900万円、表面利回り11%でスタートしました。取得後に国の「住宅省エネ2025事業」補助金(最大120万円)を活用し、断熱窓と高効率エアコンを導入。工事費総額180万円のうち補助対象部分で100万円をカバーし、実質負担を抑えています。
改修後の募集では、近隣相場より月5,000円高い賃料設定でも入居が決まり、満室時の実質利回りは当初の11%から12.5%へ改善しました。さらに、エネルギーコスト削減を前面に出した広告が奏功し、平均入居期間は従来の2年から3.5年に延伸。空室期間も短縮されたため、キャッシュフローは年間約40万円増えています。
この事例が示すのは、高利回りを狙うだけでなく「エコ+快適さ」を加えることで入居者満足度が上がり、運用リスクが下がるという点です。築古ゆえに発生しがちな設備トラブルも、断熱改修と給湯器交換を同時に行うことで予防できました。補助金申請には着工前の申請と工事後の実績報告が必要なため、スケジュール管理が成否を分けることも覚えておきましょう。
キャッシュフローを底上げする具体策
まず押さえておきたいのは、運営コストの最適化です。管理会社と交渉し、2025年から義務化された「管理業務報告書」のデジタル化により事務手数料が下がるケースが出ています。報告書がオンライン閲覧できる管理会社へ切り替えれば、月々3,000円前後コストを削減できる例も珍しくありません。
一方で、賃料収入を増やす方法としては家具・家電設置による「マイクロリノベ」が有効です。総務省「住宅・土地統計調査」では、単身者の約65%が家電付き物件に興味があると答えています。10万円程度の家電パッケージ投資で月額賃料を3,000円引き上げれば、投資回収期間は約3年と試算できます。
固定費の見直しでは、長期火災保険の一括契約がポイントです。5年契約を10年契約に変更すると保険料総額が約15%下がることがあります。さらに、地方銀行や信用金庫へ借り換えを相談し、金利を1.8%から1.3%へ引き下げた場合、3,000万円元利均等返済で年間約8万円の支出削減が可能です。このように、小さな改善を積み重ねることで築古物件でも安定した余裕資金を確保できます。
2025年度の融資・補助支援最新動向
実は、金融機関の評価基準が「建物年齢」から「収益性とメンテナンス履歴」へ移行しつつあります。日本政策金融公庫のアパートローンでは、築35年以内で耐震基準適合が証明できれば最長20年融資が検討されるようになりました。耐震基準適合証明書の取得費用は10〜15万円ですが、金利優遇が0.3%得られれば回収は難しくありません。
また、2025年度の「省エネ性能向上リフォーム補助」では、窓改修・高効率給湯器交換を組み合わせると1戸あたり最大45万円が交付されます。期間は2025年4月〜2026年3月末の契約・着工分が対象です。築古物件の断熱性能を底上げする好機となるため、投資計画に組み込む価値があります。
自治体レベルでも、東京都は「老朽建築物除却補助」を継続し、木造耐火改修で延べ床80㎡以上の場合は最大200万円を支援しています。補助要件には、工事完了後10年間の賃貸継続が含まれる点に注意してください。このように、国と自治体の制度を併用すれば改修費の2〜3割を公的資金で賄える可能性があります。
まとめ
本記事では、収益物件ランキングで築古物件が評価される理由と、選定・再生・運営のポイントを解説しました。築古物件は購入価格の安さと賃料下げ止まり効果で高利回りを狙える一方、設備老朽化や資金繰りのリスク管理が欠かせません。インスペクション報告や公的データを活用し、実質利回りと長期修繕計画をセットで評価する姿勢が重要です。さらに、2025年度の補助金や融資優遇を組み合わせれば、キャッシュフローを押し上げながら物件価値を高められます。まずは気になるエリアの最新成約事例を調べ、実質利回り8%以上を目指す物件をピックアップしてみましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数ポータル – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 既存住宅性能表示制度ガイド – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 総務省 住宅・土地統計調査 2023年結果 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫 2025年度アパートローン資料 – https://www.jfc.go.jp
- 東日本不動産流通機構(レインズ) 成約事例データベース – https://www.reins.or.jp
- 東京都都市整備局 老朽建築物除却補助制度 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

