投資用不動産を探していると「高利回りは築古、築浅は利回りが低い」という声をよく耳にします。しかし実際には、築年数が浅くても物件の選び方と運用方法しだいで安定した高利回りを確保できます。本記事では、築浅物件に興味はあるものの「本当に収益化できるのか」と不安を抱える方へ向けて、2025年10月時点の最新データと制度を交えながら、具体的な投資手順をわかりやすく解説します。読み進めることで、築浅ならではのメリットを活かしつつ利回りを最大化するコツが見えてくるはずです。
築浅物件が狙い目になる背景
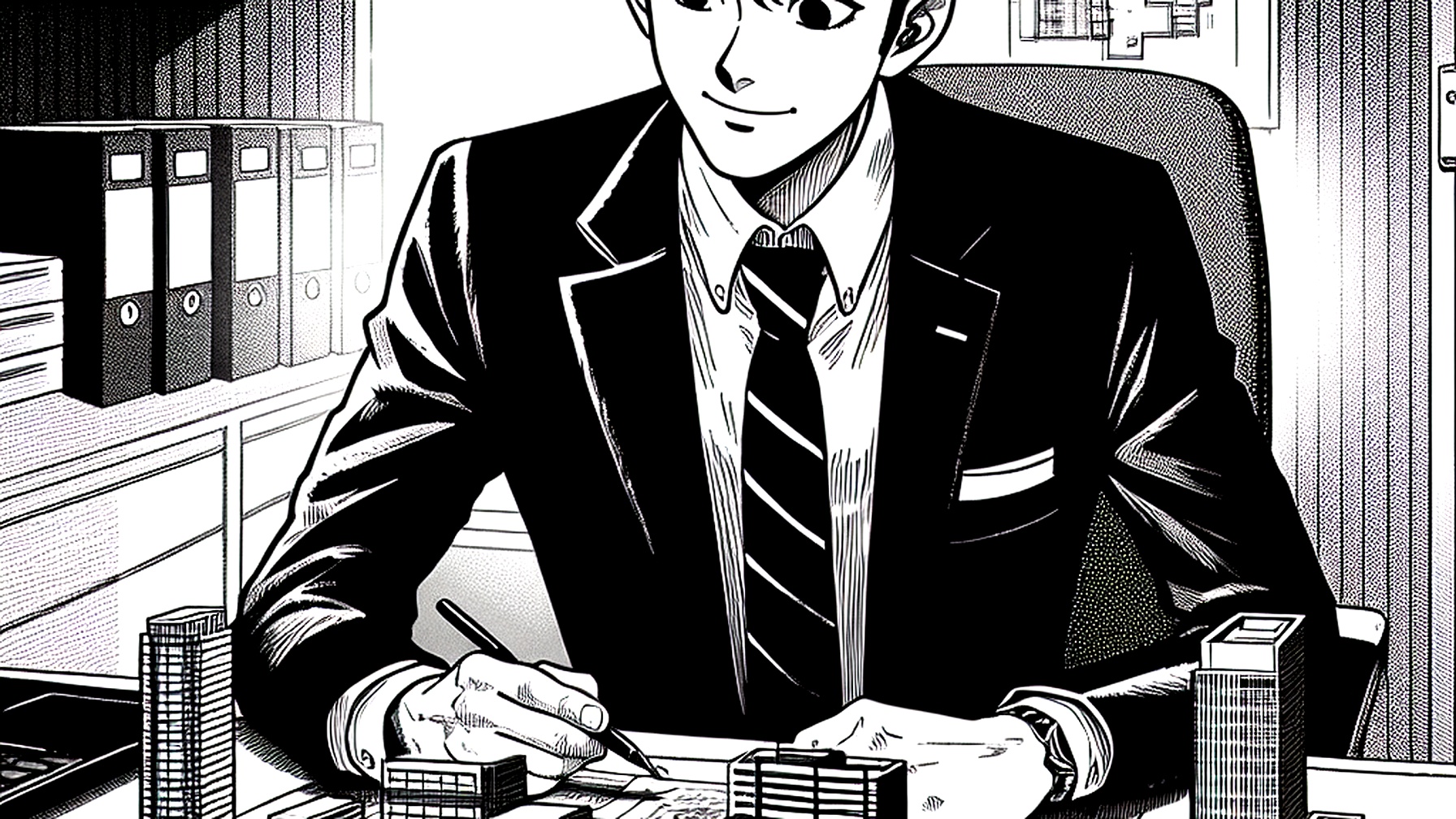
まず押さえておきたいのは、築浅物件が抱える一般的なイメージと実態のギャップです。築浅は価格が高く利回りが低いという先入観がありますが、近年は建築コストの高騰と金融緩和の長期化で中古価格が相対的に上昇し、築浅との差が縮小しています。
日本不動産研究所の2025年調査によると、東京23区のワンルームマンション平均表面利回りは築年を問わず4.2%ですが、築5年以内に絞ると3.9%にとどまります。一方で、築浅の修繕費や空室リスクは築古より明らかに低いため、ネット利回り(実質利回り)で比較すると差がわずかになるケースが多いのです。
また、若年層を中心に設備性能を重視する入居者が増えています。そのため、築浅で最新の設備がそろう物件は家賃下落のスピードが緩やかになりやすい点も見逃せません。つまり、利回りの見かけの数値だけでなく、維持コストと収益安定性を合わせて評価すると築浅が有利な場面が増えています。
さらに、築20年超の物件では金融機関が融資期間を短く設定する傾向がありますが、築浅なら最長35年まで引けるケースも多く、返済負担を抑えながらキャッシュフローを確保しやすい点も魅力です。
高利回りを実現する三つの視点
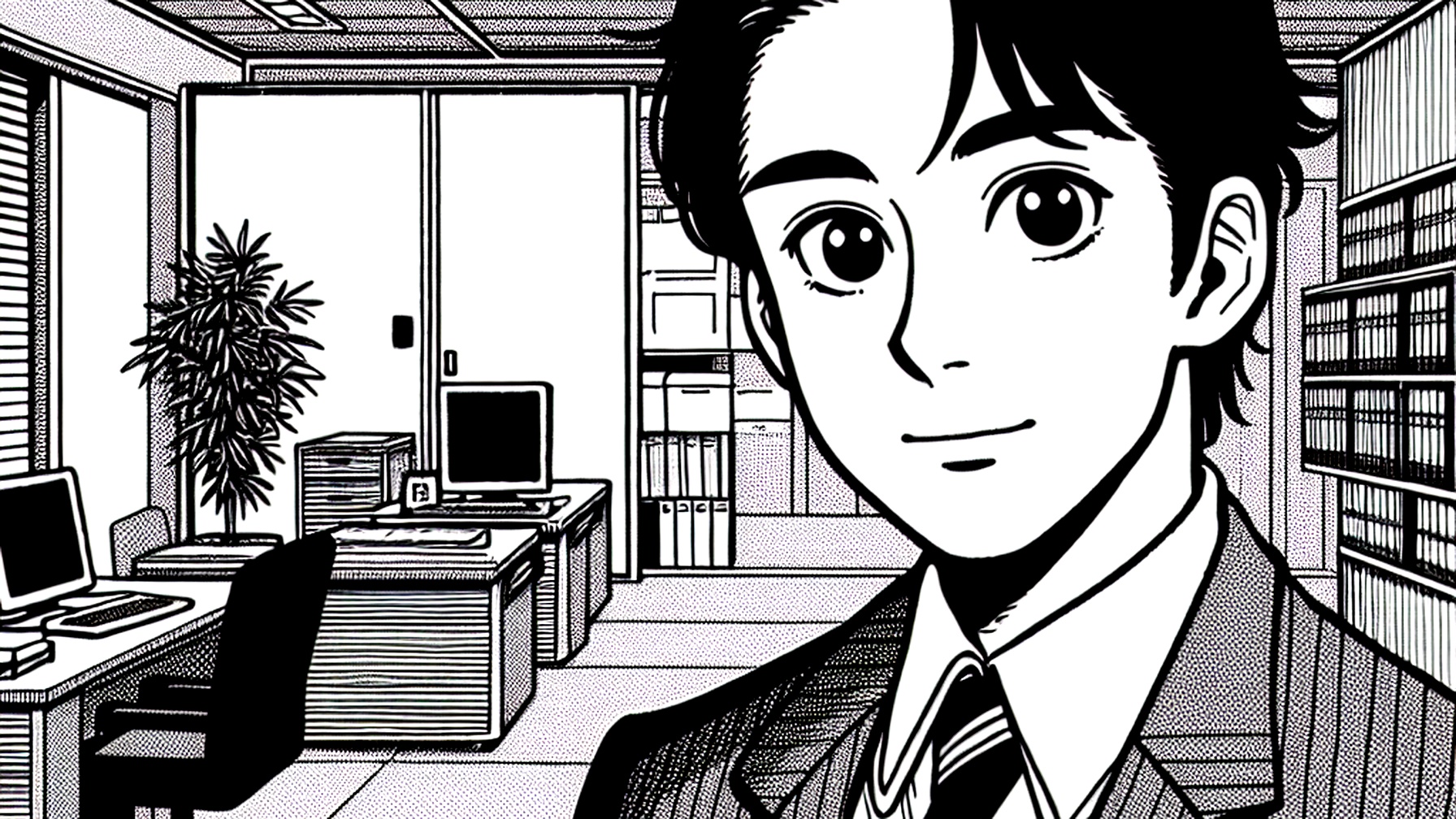
重要なのは、購入時点の表面利回りをそのまま受け入れるのではなく、プラス α の工夫で利回りを引き上げることです。具体的には「融資条件」「運営コスト」「付加価値創出」の三つの視点からアプローチできます。
最初に融資条件ですが、2025年の個人向け投資ローン金利は変動0.9%台が下限で、固定でも1.3%台が珍しくありません。築浅なら評価が高いため低金利で長期借入がしやすく、返済比率を家賃収入の40%以下に収めるとキャッシュフローが大幅に改善します。
次に運営コストの見直しです。築浅は大規模修繕が当面不要なため、毎年の修繕積立を月2000円程度に抑えられることも多く、築古で想定する月5000円以上より実質利回りが1%程度改善することがあります。また、インターネット無料設備を一括導入する場合でも築浅は配管が対応済みで工事が軽く、初期費用を抑えて差別化が可能です。
最後に付加価値創出として、家具家電付きのマンスリー賃貸やペット可仕様への変更が挙げられます。築浅であれば間取りや設備が現代基準なので追加投資が小さく、家賃を1〜2割上げても需要が伸びやすい点がポイントです。こうした施策を組み合わせることで、購入時3.9%だった表面利回りを実質6%台に引き上げた事例も珍しくありません。
立地と物件タイプ別の攻め方
実は同じ築浅でも、立地と物件タイプによって利回りの伸び幅が大きく異なります。ここでは都心ワンルーム、郊外ファミリー、木造アパートの三パターンに分けて考えます。
都心ワンルームは空室リスクが低い一方、価格が高いため利回りは控えめです。しかし、法人契約がつきやすく、礼金・更新料で年次収入を底上げできるメリットがあります。新橋駅徒歩10分圏で築3年の事例では、家賃月11万円に対し礼金1カ月、更新料1カ月が2年ごとに発生し、実質利回りが0.7ポイント改善しました。
郊外ファミリータイプは購入単価が下がるため表面利回りが取りやすいものの、人口動態を見極める必要があります。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2025年から2035年にかけて埼玉南部は5%の人口増が見込まれる一方、茨城県西部は7%減とされています。つまり、郊外でも将来人口がプラスのエリアを選べば家賃の下落リスクを抑えられ、高利回りを維持しやすくなります。
木造アパートは建築費がRCより約30%低い分、利回りを上げやすい点が特徴です。ただし、築浅でも10年目以降に外壁塗装や防水工事が必要になるため、長期修繕計画のシミュレーションを忘れないでください。耐用年数に余裕がある築5年以下なら、金融機関が木造でも30年融資を出すケースが増えており、キャッシュフローを確保しやすくなっています。
築浅で活用できる2025年度制度と融資
ポイントは、公的制度を味方に付けて自己資金効率を高めることです。2025年度は「省エネ賃貸住宅推進事業」が継続しており、断熱性能を一定基準に引き上げると1戸あたり最大40万円の補助金を受け取れます。築浅物件であれば追加工事が少なく、補助金をほぼそのままキャッシュインできるため、実質利回り向上につながります。
また、住宅金融支援機構の「賃貸住宅融資(省エネ配慮型)」では、断熱性能等級5以上の築浅アパートに対し、固定金利が通常より0.2%低い特例が2026年3月申込分まで適用されます。金利が0.2%下がると、借入5000万円・30年の場合で総返済額が約170万円減少し、年間キャッシュフローは6万円ほど改善します。
さらに、地方自治体が独自に行う家賃補助や子育て世帯向け入居促進策も見逃せません。たとえば、神奈川県相模原市では2025年度に子育て世帯が転入した場合、大家へ5万円の協力金を支給しています。対象要件を満たす築浅ファミリー物件を選ぶことで、入居付けと利回り改善を同時に実現できます。
シミュレーションで見る築浅高利回り戦略
まず、築4年RCワンルーム(東京23区内、購入価格2200万円、家賃10.5万円)を想定しましょう。変動金利0.9%、融資期間35年、自己資金400万円で試算すると、表面利回りは5.7%、年間キャッシュフローは約18万円にとどまります。
ここで、礼金・更新料を家賃1カ月相当ずつ設定し、インターネット無料を導入して家賃を0.5万円アップします。同時に省エネ改修による補助金40万円を活用し、初期費用を圧縮します。結果としてネット利回りは6.8%、年間キャッシュフローは52万円へ改善しました。
次に、築5年木造アパート(埼玉県南部、総戸数8戸、購入価格7800万円、平均家賃6.5万円)で検証します。長期固都税30%減免地域に該当し、固定金利1.2%・30年融資を受けた場合の表面利回りは8.0%です。10年目に外壁修繕150万円を見込みつつ、子育て世帯の入居促進協力金を毎年2戸で受け取ると、実質利回りは9.2%まで上昇します。
これらのシミュレーションから分かるのは、築浅でも補助金や融資特例を組み合わせ、家賃外収入を設計することで高利回りを十分に実現できるという事実です。数字で検証する習慣を付ければ、物件広告の表面利回りに左右されず、再現性の高い投資判断が可能になります。
まとめ
築浅物件は価格が高いという思い込みだけで敬遠されがちですが、実は修繕費の低さや融資条件の良さを活かせば高利回りを狙える市場です。重要なのは、融資・運営コスト・付加価値の三方向から利回りを底上げする発想と、自分の資金計画に合う立地と物件タイプを選ぶ目線です。今回紹介した補助金や制度は2025年度時点で利用可能なので、情報を確認しながら早めに動くことをおすすめします。行動を後回しにせず、まずは信頼できる不動産会社とシミュレーションを作成し、築浅で高利回りを実現する第一歩を踏み出しましょう。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp/
- 国立社会保障・人口問題研究所 – https://www.ipss.go.jp/
- 住宅金融支援機構「賃貸住宅融資」 – https://www.jhf.go.jp/
- 国土交通省「省エネ賃貸住宅推進事業」 – https://www.mlit.go.jp/
- 相模原市公式サイト「子育て世帯入居促進協力金」 – https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/

