アパート経営を始めたいものの、長期視点で考えるとどのエリアを選べばいいのか迷う人は多いです。立地を誤ると空室が増え、計画したキャッシュフローが崩れてしまいます。そこで本記事では、長期投資という観点から立地選定の手順と判断基準を詳しく解説します。読むことで「人口動態」「交通利便性」「制度活用」という三つの軸を同時に押さえられるようになり、自信を持って物件を選べるようになります。
長期投資で考えるアパート経営の全体像
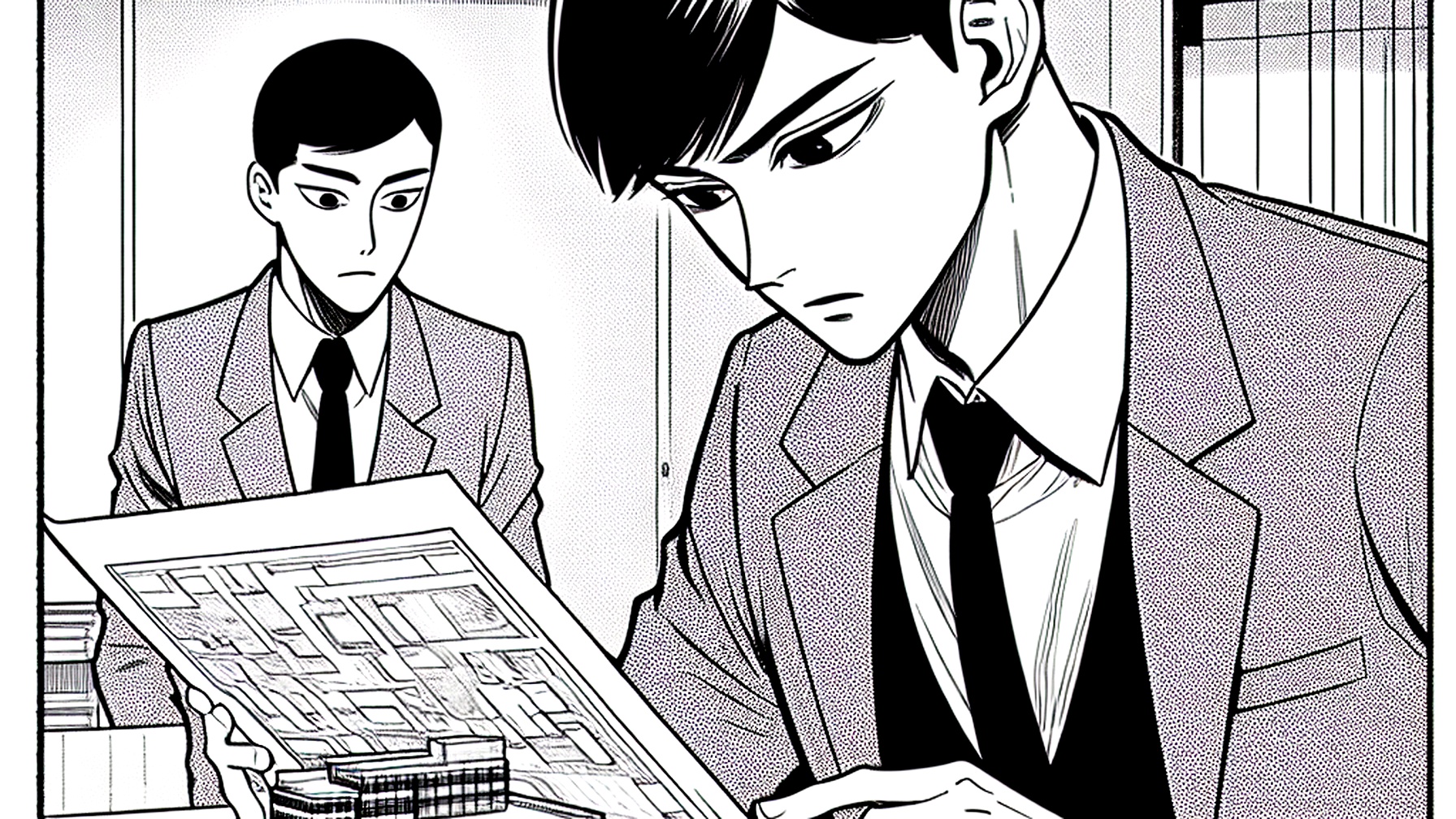
重要なのは、アパート経営を「30年の事業」と捉えることです。購入時の利回りだけを追うと、数年後の地域変化に対応できません。長期投資では、資産価値と収益力が将来も維持できるかを見極める必要があります。つまり、人口推移や地価の安定性を読み解き、出口戦略まで設計して初めて安全な投資と言えます。
まず、2025年8月時点の全国平均空室率は21.2%で、前年比0.3ポイント改善しています。これは新築供給の抑制とリノベーション需要の拡大が要因とされます。一方、地域間格差は広がっており、地方部では30%を超えるエリアも珍しくありません。したがって、平均値に安心せず、投資対象エリア固有のデータを必ず確認しましょう。
次に、資産価値を左右するのが地価動向です。国土交通省の2025年地価公示によると、三大都市圏の住宅地は前年比1.9%上昇し、地方中核都市も0.8%の上昇を見せています。しかし、人口減少が顕著な地方郊外では2%前後の下落が続いています。地価が下がると担保評価も下がるため、リスク管理の観点からも立地選定が肝心です。
さらに、長期投資では融資条件の変化にも注意が必要です。日本銀行は2025年7月に政策金利を0.1%から0.25%へ微調整しました。金利上昇時には月々の返済が増え、表面利回りが良い物件でもキャッシュフローが圧迫されます。したがって、立地選定と同時にストレスシナリオを組み込んだ返済計画を作成しましょう。
立地選定でまず押さえておきたい人口動態
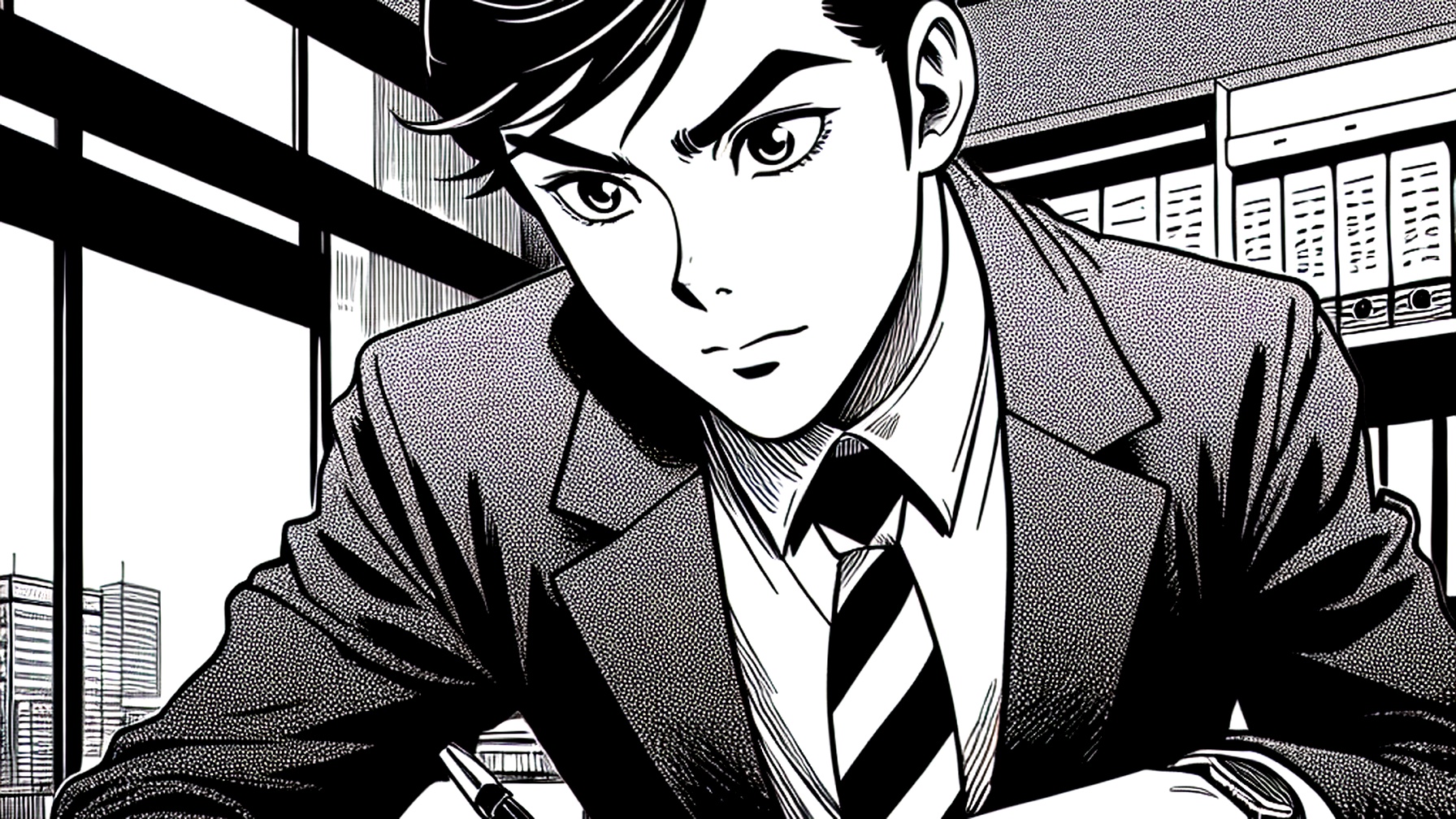
ポイントは、人口の絶対数ではなく「構成比」と「変化率」に注目することです。総務省の2025年住民基本台帳によると、20~39歳の生産年齢人口が増えている市区町村は全国の18%しかありません。この層は賃貸需要の中心であるため、増加傾向にあるエリアを優先的に検討するべきです。
実は、同じ県内でも市単位で人口動向は大きく異なります。たとえば、愛知県では名古屋市が微増を維持している一方、周辺の中山間地域は5%以上減少しています。県全体の数字だけを見て安心すると、空室リスクを過小評価してしまいます。市区町村ごとのデータを取り寄せて、最低でも過去5年の推移を確認してください。
また、単身世帯比率の高いエリアは1Kやワンルームの需要が強くなります。東京都江東区では単身世帯比率が55%に達しており、比較的家賃が高めでも入居が決まりやすい状況です。一方、ファミリー世帯が多い郊外では2LDK以上でないと競争力を保ちにくくなります。物件タイプと地域属性を一致させることで、将来的なリフォームコストも抑えられます。
さらに、自治体の将来人口推計も有用です。国立社会保障・人口問題研究所の中位推計では、2025年から2035年にかけて福岡市の人口は2.5%増える見込みです。増加が見込まれる都市はインフラ整備や再開発が進むため、家賃上昇という副次的メリットが期待できます。逆に、減少率が高いエリアでは固定資産税の負担だけが残るリスクが高まるため、慎重に判断してください。
交通インフラと生活利便性の見極め方
まず押さえておきたいのは「駅距離だけで判断しない」ことです。都心では徒歩10分以内が目安ですが、地方都市では駐車場完備で最寄りバス停徒歩3分の方が実用的な場合があります。周辺入居者が実際にどの交通手段を使うのかを把握することで、空室リスクを大幅に減らせます。
一方で、交通インフラは万能ではありません。2024年に開業したJR大阪東線の新駅周辺では、開業前後で家賃が7%程度上昇しましたが、ライバル物件も急増しました。供給が増えると差別化が難しくなり、広告費やリフォーム費用がかさむケースもあります。駅前再開発と同時に供給バランスも調査し、過当競争に陥らないか確認しましょう。
生活利便性の評価では、スーパーや病院までの距離だけでなく「営業時間」と「品揃え」を調べると精度が上がります。24時間営業のスーパーが徒歩圏内にあるエリアは、単身者の人気が高く、家賃設定を5000円ほど高めにしても成約に至る事例が多いです。また、保育園の待機児童数が少ない地域は、共働きファミリーの流入が見込め、長期の入居が期待できます。
さらに、自然災害リスクも忘れてはいけません。国土交通省のハザードマップポータルサイトで事前に浸水想定区域を確認し、リスクの高い土地は避けるか保険料を織り込んだ利回り計算を行いましょう。最近では、リスク情報をウェブ上で確認する入居者が増えており、水害履歴があるエリアの物件は成約まで時間がかかる傾向があります。
実際のキャッシュフローに響く立地の数値
重要なのは、家賃と稼働率の掛け算である「年間収入」を現実的に試算することです。たとえば、家賃6万円の物件で稼働率が90%なら年間収入は64万8000円になります。しかし、立地次第で稼働率が80%に下がると、同じ家賃でも51万2000円まで落ち込みます。10ポイントの稼働率差が利回りに与える影響は非常に大きいと理解してください。
次に、修繕費の地域差です。寒冷地では凍結防止の設備や融雪のためのランニングコストがかさみます。北海道札幌市で築15年の木造アパートを所有する場合、年間修繕費は家賃収入の12%前後に達するという調査もあります。一方、温暖な九州では8%程度に収まる傾向があります。立地が異なるだけで手元に残るキャッシュが変わるため、利回りだけでなく実質的な手残りを比較しましょう。
また、固定資産税も無視できません。地価が高い都心部は税額も高いですが、空室率が低いため収益で吸収しやすい構造です。地方郊外では税額が低くても空室リスクが高く、最終的に収益が削られることがあります。自治体の課税評価額を確認し、税額を想定キャッシュフローに組み込むことが長期投資では欠かせません。
さらに、出口戦略としての売却価格も立地で決まります。東京23区内の中古アパートは、築20年でも新築価格の60%以上で売れるケースが多いです。一方、人口減少地域では築15年で新築価格の20%にも届かない事例があります。売却益を期待するのか、それとも減価償却による節税を狙うのかを明確にし、その目的に合った立地を選びましょう。
2025年度制度と融資環境を味方にする
まず理解しておきたいのは、2025年度時点で利用できる賃貸住宅向けの国の補助制度が限定的であることです。代表的なものに「2025年度 賃貸住宅省エネ改修補助金」があり、断熱性能向上工事に対して1戸あたり最大50万円が支給されます。立地選定時に既存物件を購入してリノベーションする場合、この補助を活用すると競合物件より家賃を5000円程度高めに設定できるケースもあります。
一方、融資環境については金融機関の姿勢が二極化しています。都市銀行は都心部の高稼働エリアに融資を絞る傾向が強まり、地方物件は地元信用金庫か日本政策金融公庫を利用する流れが一般的です。日本政策金融公庫のアパートローン(2025年10月時点)は、金利1.3%~2.1%で融資期間20年以内が目安です。立地が優良であれば金利優遇が受けられるため、事前に複数行へ事業計画を持ち込んで比較しましょう。
さらに、自治体独自の低利融資制度にも注目してください。例として、さいたま市は「民間賃貸住宅耐震改修融資」を最大5000万円、年0.9%で実施しています(2025年度末まで)。駅近の旧耐震物件を取得して改修する場合、金利負担を抑えつつ資産価値を高められる有効な手段です。
最後に、インバウンド需要への対応策も検討が進んでいます。国土交通省は2025年4月に旅館業法を改正し、一定条件下で賃貸住宅を短期賃貸に転用しやすくしました。観光地立地のアパートで空室が出た際、短期賃貸へ転用できれば稼働率を底上げできます。ただし、届出や用途制限があるため、地域の条例を事前に確認してから事業計画に組み込みましょう。
まとめ
長期投資としてのアパート経営では、立地選定が成否を左右します。人口構成や地価動向を読み、交通利便性と生活インフラを具体的にチェックすれば、空室率の見通しが立ちます。さらに、修繕費や固定資産税の地域差を把握し、実質キャッシュフローで比較する姿勢が不可欠です。2025年度の補助金や低利融資を賢く利用すれば、設備投資と金利負担を抑えつつ競争力を高められます。まずは気になるエリアの詳細データを集め、小さく試算を始めることで安全な第一歩を踏み出してください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp/
- 国土交通省 地価公示 2025年 – https://www.land.mlit.go.jp/
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 2025年 – https://www.soumu.go.jp/
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 2025年7月 – https://www.boj.or.jp/
- 国立社会保障・人口問題研究所 将来人口推計 2025年 – https://www.ipss.go.jp/
- さいたま市 住宅政策課 市内民間賃貸住宅耐震改修融資制度 2025年度 – https://www.city.saitama.jp/
- 国土交通省 ハザードマップポータルサイト – https://disaportal.gsi.go.jp/

