家計の低金利時代が長引き、預金を超える運用先を探す人が増えました。株式は値動きが大きくて怖い、しかし不動産を丸ごと買う資金もない——そんな悩みに対し、少額で始められるREITが注目されています。本記事では「REIT 人気」の背景から仕組み、2025年時点の市場データ、始め方、そしてリスク管理まで順序立てて解説します。読み終えれば、自分に合った投資判断を下すための基礎知識と最新情報をまとめて得られるでしょう。
REITとは何か、仕組みを押さえよう
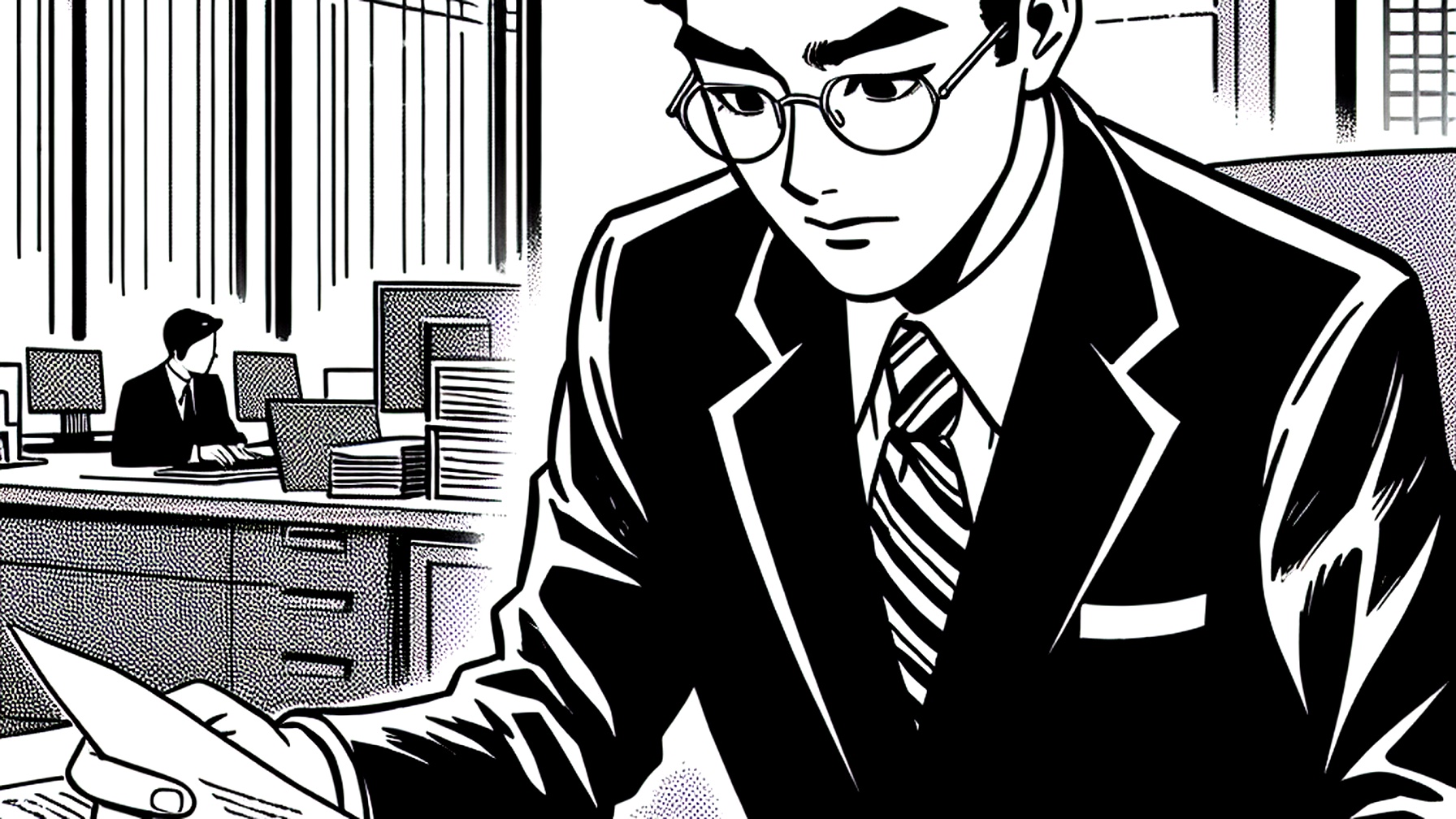
まず押さえておきたいのは、REITが不動産を証券化した投資信託だという点です。個人投資家は一口数万円から参加でき、実物のビルやマンションの賃料収入を分配金として受け取れます。
REIT(Real Estate Investment Trust)は投資家から資金を集め、複数の不動産を取得・運営し、その収益をほぼ全額分配する仕組みです。法律上は投資法人として上場し、売買は株式と同じ証券取引所で行われます。つまり価格は市場で変動しますが、裏付けとなる実物資産があるため、株式だけより値動きが緩やかな傾向があります。
また、REITは税制面でも特徴があります。投資法人が利益の九割超を分配すれば、法人税が実質免除となるため、高い利回りを維持しやすいのです。投資家は受け取る分配金に対して所得税・住民税を納めますが、NISAなど非課税制度を活用すれば手取りを最大化できます。
東京証券取引所によると、2025年10月時点で上場J-REITは65銘柄、時価総額は約19兆円です。平均分配金利回りは3.7%前後で、長期国債利回りを2%以上上回っています。この差が「REIT 人気」を支える大きな要因になっています。
人気が高まる理由は安定利回りと手軽さ
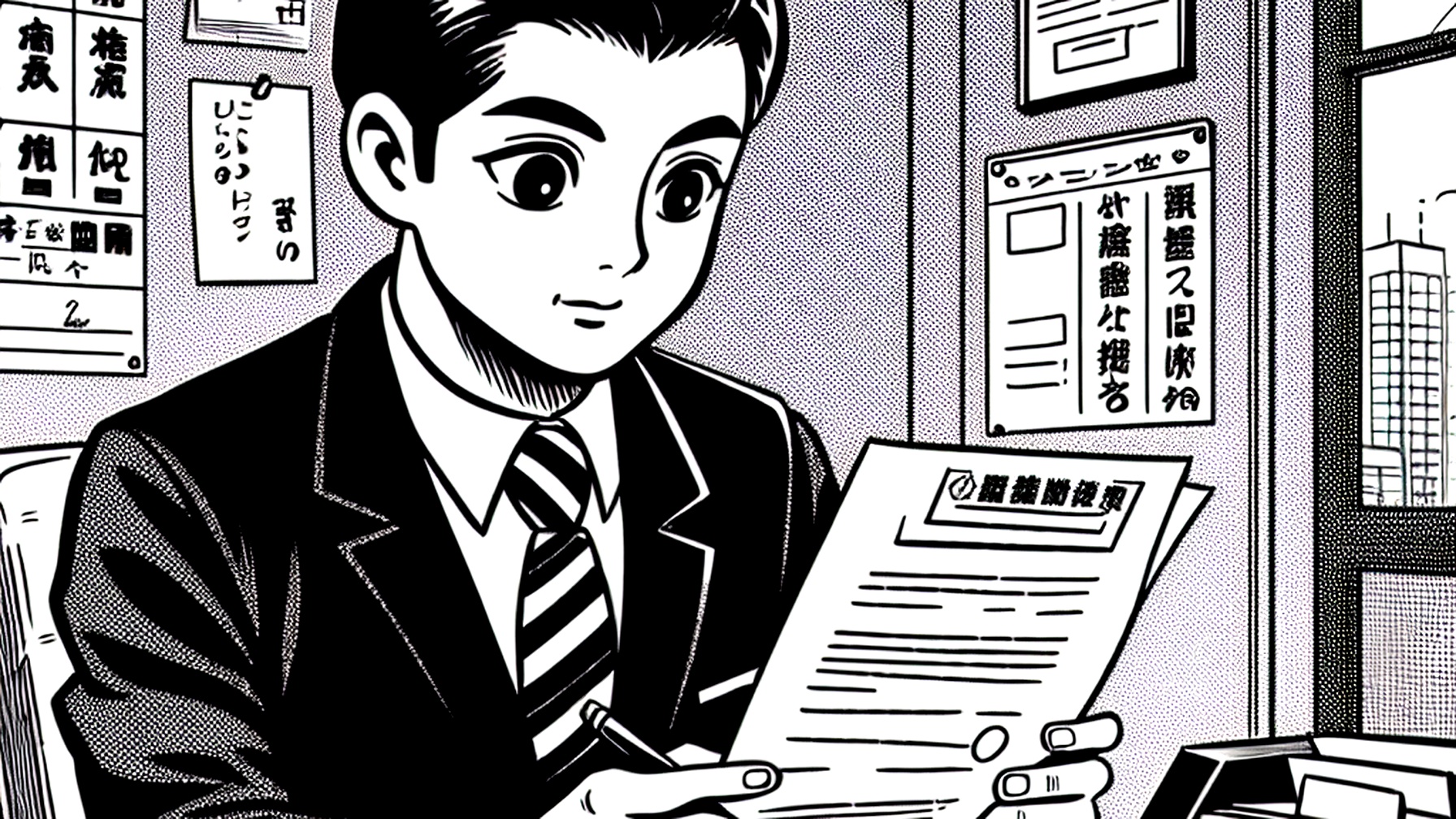
重要なのは、REITが配当と値上がり益の両方を狙える点です。銀行預金が年0.001%台のなか、分配金利回り3%超は魅力的に映ります。さらに、1口単位で簡単に売買できるため、流動性も確保されています。
まず分配金の源泉は賃料収入です。オフィスビルなら複数のテナントから賃料が入り、住宅系REITなら居住者から家賃が入ります。空室が出ても物件を分散保有しているため、一棟買いより収益変動が小さくなります。一方で街全体の賃料相場が下がると影響を受けるため、立地と用途の多様化がカギになります。
次に、手軽さを支えるのが証券口座とネット取引の普及です。スマホ一つで売買注文を出せ、購入の最小単位は株と同様に市場価格×1口のみです。例えば2025年10月時点の平均価格は16万円前後で、クレジットカード払いの積立を使えば月1万円台からでも投資が可能です。
実は制度面の追い風も続きます。2024年に刷新された新NISAでは非課税投資枠が恒久化され、年間成長投資枠240万円の対象にJ-REITが含まれています。金融庁資料によると、2025年度上半期だけでNISA経由のJ-REIT買付額は前年同期比1.8倍に拡大しました。この数字が「REIT 人気」をいっそう後押ししています。
2025年の市場動向と資金流入を読み解く
ポイントは、金利と空室率という二つの指標が価格に直結することです。日本銀行がマイナス金利を解除し、政策金利を0.25%に引き上げた2025年4月以降も、J-REIT指数は下落幅を限定的にとどめました。これは賃料収入の底堅さと投資資金の流入が支えたためです。
東京証券取引所の月次レポートでは、2025年1〜9月のJ-REITへの新規資金流入額が約4,200億円に達し、前年同期間比で12%増となりました。背景には国内投資家だけでなく海外年金基金の参入があり、円安局面で相対的に割安とみなされた点が挙げられます。
一方、セクターごとの格差も拡大しています。オフィス系はテレワーク定着で空室率が上昇し、分配金利回りが4%台まで上がる銘柄が目立ちます。対照的に物流施設系はEC需要の増加で稼働率が高く、価格上昇が映えるため利回りは3%を切ることもあります。用途と地域のバランスを見極める姿勢が今まで以上に重要です。
総務省統計局の人口動態によれば、三大都市圏への転入超過は続いており、住宅系REITは安定的な賃料成長が期待できます。ただし郊外物件の空室リスクは高まる可能性があり、保有物件の所在地に注目した選別が欠かせません。
投資の始め方とNISA活用ステップ
実は、REIT投資は証券会社の口座さえあれば即日スタートできます。それでも成功のコツは、三つのステップを順序良く踏むことにあります。まずは非課税枠の有無を確認し、次に分配金と値動きのシミュレーションを行い、最後に購入タイミングを分散する方法を選びましょう。
第一のステップは口座開設と制度選択です。新NISAの成長投資枠を使えば分配金も売却益も非課税となり、手取りが大きくなります。年間240万円の枠を一気に使う必要はなく、月2万円ずつ24回に分けて積立購入することもできます。これにより価格変動リスクを平準化できます。
第二に、収支シミュレーションでは空室率10%、金利上昇1%といった悲観シナリオを必ず試算してください。信託報酬や物件入替費用が差し引かれるため、表示利回りから年0.3〜0.5ポイント程度低く見積もると現実的です。資金繰り計画を立てる際に、この保守的な想定が将来のストレスを軽減します。
最後に、購入タイミングの分散が鍵を握ります。一括購入は楽ですが、価格変動が読めない局面ではリスクが集中します。毎月定額の積立や四半期ごとのスポット買いを組み合わせることで、平均取得価格を下げる効果が期待できます。証券会社各社は2025年時点で自動積立機能を提供しており、初心者でも手間なく実行できます。
リスク管理と物件選びの視点
まず押さえておきたいのは、REITも株式と同様に市場価格が下落するリスクを負うという事実です。価格要因は金利動向、景気循環、そして災害リスクなど多岐にわたります。したがって、分配金利回りだけで判断するのは危険です。
具体的な注目点は三つあります。一つ目はLTV(負債比率)で、50%を超える銘柄は金利上昇局面で返済負担が膨らむ可能性があります。二つ目は物件の築年数とリノベーション計画で、古い建物ほど修繕費用がかさみ利回りが削られます。三つ目はテナント分散度で、特定企業への依存度が高いと退去時の空室リスクが跳ね上がります。
また、自然災害リスクは見落とせません。国土交通省のハザードマップと運用報告書を突き合わせれば、水害リスクの高い低地に倉庫を集中保有しているREITを避けられます。さらに、ESG評価が高い銘柄は環境性能向上工事を積極的に行い、長期の競争力を維持する傾向があります。
結論として、リスクを抑える最善策は分散です。複数セクターへ分けて投資する、あるいは国内REITと海外REITを組み合わせることで、一つの要因がポートフォリオ全体に与える影響を和らげられます。
まとめ
この記事では、REIT 人気の背景、仕組み、市場動向、始め方、そしてリスク管理の視点を順に解説しました。分配金利回り3%台の安定収益と少額投資の手軽さが支持を集める一方で、金利や空室率の変化には常に目を配る必要があります。まずは新NISA枠を活用し、複数銘柄への長期分散投資を検討しましょう。適切な情報収集とシミュレーションを行えば、不動産投資のメリットを享受しながらリスクを抑えた資産形成が可能になります。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp/
- 東京証券取引所 – https://www.jpx.co.jp/
- 不動産証券化協会 – https://www.ares.or.jp/
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp/
- 国土交通省 – https://www.mlit.go.jp/

