不動産投資に興味はあるものの、区分所有より難しそうに感じていませんか。特に「マンション投資 一棟買い 未経験」という条件がそろうと、資金計画やリスク管理のハードルが高く見えるかもしれません。しかし、一棟買いは管理コストを抑えやすく、空室リスクを分散できるなど、区分所有にはないメリットが多い投資手法です。本記事では未経験者でも理解できるように、一棟買いの魅力と注意点、資金計画、物件選定のコツ、2025年度の税制ポイントまでを体系的に解説します。読み終えるころには、自分に合った始め方が見えてくるはずです。
未経験者が一棟買いを選ぶ理由
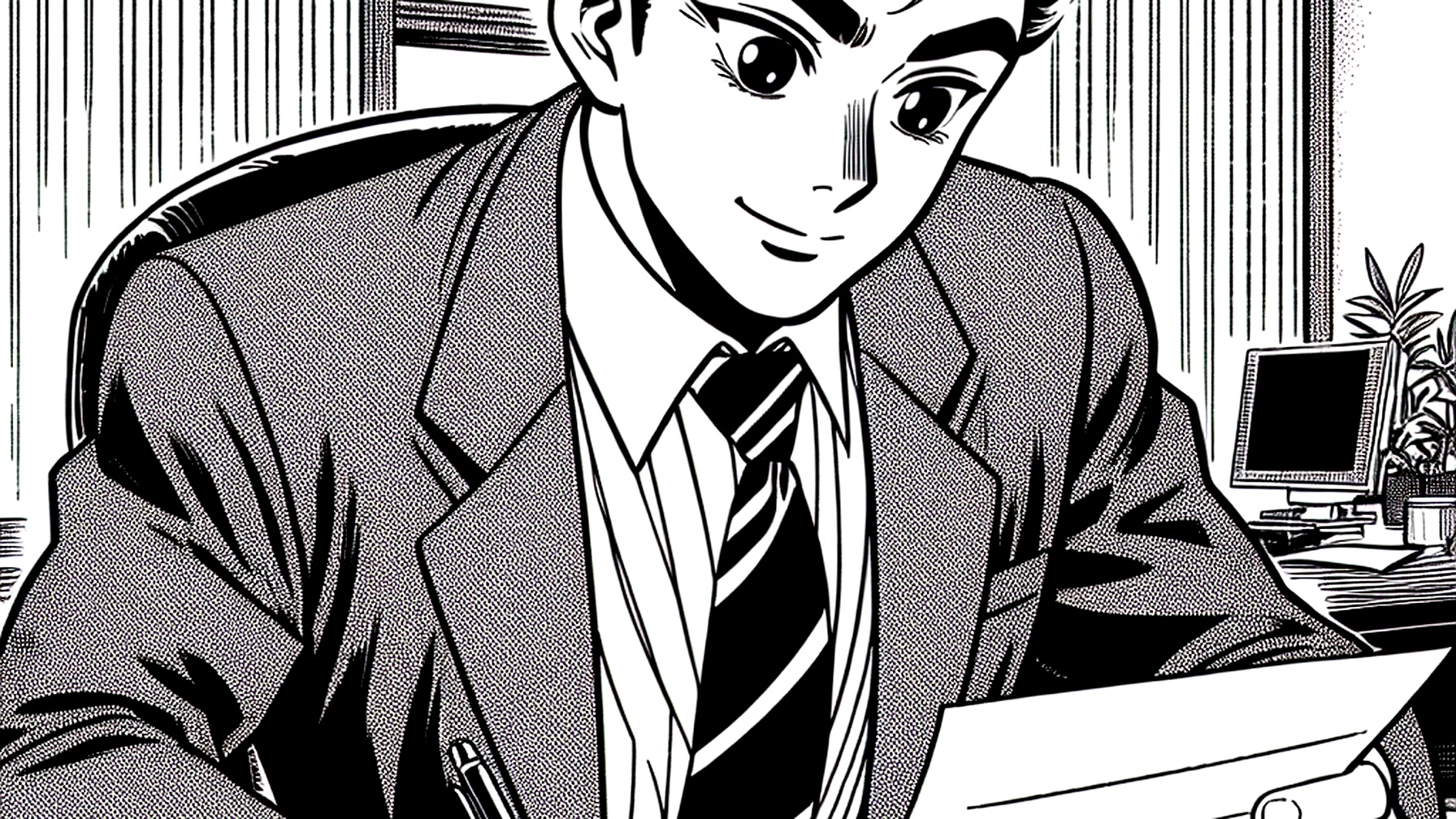
ポイントは、一棟買いが持つ「収益のコントロール性」と「スケールメリット」です。区分所有では他オーナーの意向に左右される共用部管理も、一棟投資なら自分で方針を決められます。また、複数戸をまとめて保有するため、空室が出ても家賃収入がゼロにはならず、キャッシュフローが安定しやすい利点があります。
まず、運営方針を一括で決められるため、修繕計画やリノベーションのタイミングを自分の資金繰りに合わせられます。管理会社の選定や賃料設定の裁量が大きいので、市況に応じて柔軟に対応できる点は大きな魅力です。
さらに、金融機関の評価も比較的高くなります。土地と建物を丸ごと取得する一棟物件は担保価値が明確になりやすく、融資期間が長く取れるケースが多いです。未経験でも事業としての計画を示せば、個人属性だけに依存しない融資交渉が可能になります。
一方で、修繕費が一度に発生しやすい、大規模空室時のインパクトが大きいなどのリスクも忘れられません。未経験のまま突き進むのではなく、後述するシミュレーションや管理体制を整えることで、これらの課題は十分コントロールできます。
収益シミュレーションの基本
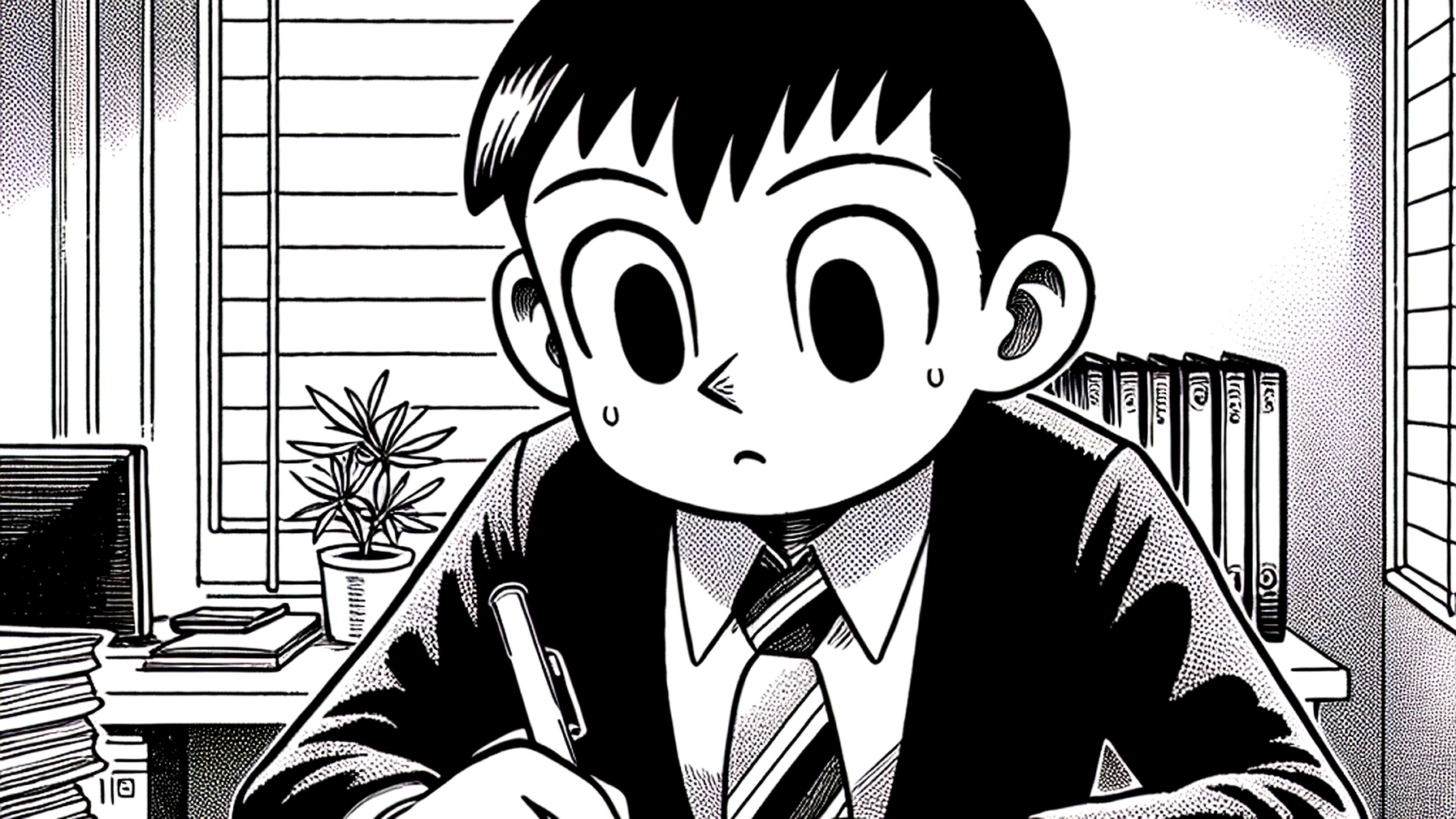
重要なのは、期待利回りだけで判断しないことです。家賃収入、空室率、運営費、修繕積立を組み合わせたキャッシュフローを継続的に確認することで、一棟買いの実質的な収益力が見えてきます。
最初に家賃水準を設定するときは、国土交通省「不動産取引価格情報」や近隣の募集広告を参照し、楽観・標準・悲観の三つの家賃シナリオを作成します。空室率は総務省の人口推計を踏まえ、周辺エリアの将来人口もチェックしておくと現実的な数字になります。
次に、運営費として管理委託料、共用部電気代、清掃費、法定点検費を合計し、年間賃料収入の15〜20%を目安に計上します。さらに、築年数に応じて5〜10年おきに大規模修繕を行う想定を入れ、毎月の積立額を計上すれば、突発的な出費で資金繰りが崩れるリスクを抑えられます。
最後に融資条件を加味します。日本銀行の統計によると、2025年10月時点の不動産向け貸出平均金利は1.6%前後です。金利が1%上昇した場合の返済額も試算し、返済比率(年間返済額÷年間家賃収入)が40%を超えないように調整すると、金融機関の評価だけでなく実際の運営でも余裕が生まれます。
融資と資金計画のつくり方
まず押さえておきたいのは、自己資金と融資額のバランスです。未経験であっても、物件価格の20~30%を自己資金として用意できれば、金融機関は事業への本気度を評価しやすくなります。加えて、諸費用(登記費用や仲介手数料など)として物件価格の7%前後が必要になるため、資金計画には余裕を持たせましょう。
融資先はメガバンクだけでなく、地元の信用金庫やノンバンクも比較すると選択肢が広がります。金利が多少高くても融資期間を長く取れる場合、月々の返済額が下がりキャッシュフローは改善します。複数行から見積もりを取り、総返済額と毎月の支払い額をセットで比べる視点が欠かせません。
加えて、金利タイプの選択も重要です。固定金利は将来の金利上昇リスクを抑えられる一方、変動金利に比べ初期コストが高くなる傾向があります。市場金利が低い今だからこそ固定期間を長めに設定して安定を優先するか、変動で初期負担を軽くし、浮いたキャッシュを繰上げ返済に充てるか、シミュレーションを重ねて判断しましょう。
繰上げ返済の効果を検証するときは、利息軽減額だけでなく手元キャッシュの安全余裕資金(半年分の返済額が目安)を確保してから実行するのが基本です。資金が尽きてしまえば、どれほど利息を削減しても運営は継続できません。
物件選定で外さない三つの視点
実は、未経験者がつまずきやすいのは利回りよりも「需要」の読み違えです。立地、築年数、そして建物構造の三つを総合評価することで、長期的に空室リスクを抑えられます。
立地では駅距離と周辺施設に着目します。東京都心であれば徒歩10分以内が目安ですが、郊外や地方中核都市ではバス便でも大学や工業団地が近ければ需要が見込めます。人口推計で20年後も人口減が緩やかな自治体を選ぶと、長期保有でも安定運営が期待できます。
築年数は、築20年を超えると表面利回りが高く見えますが、修繕費が膨らむ点に注意が必要です。建物診断(インスペクション)を行い、屋上防水や配管の交換時期を見極めることで、将来コストを具体的に把握できます。
建物構造は鉄筋コンクリート(RC)、鉄骨(S)、木造でコストと耐用年数が変わります。国税庁の耐用年数では木造22年、鉄骨34年、RC47年ですが、実際の寿命はメンテナンス次第です。融資期間は耐用年数を超えて取れない場合が多いため、築古木造は短期返済になりキャッシュフローが圧迫されがちです。未経験者ほど構造と築年数に応じた融資期間の上限を確認しておきましょう。
2025年度の税制・補助制度を味方にする
まず、2025年度も不動産所得は青色申告特別控除が適用可能です。正規の帳簿付けと電子申告を行えば最大65万円を所得から差し引け、実効税率分の節税効果が得られます。
建物の減価償却も引き続き大きな節税手段です。RC造なら築25年以内の取得で定額法を選択すれば毎年2.2%程度を経費計上できます。これにより、キャッシュアウトを伴わない経費で課税所得を圧縮できる点が魅力です。
2025年度の国土交通省「賃貸住宅エコリフォーム支援事業」は、省エネ性能を高める改修を行う場合に上限120万円の補助が受けられます(募集は2026年3月末まで)。補助対象は断熱窓や高効率給湯器の導入で、工事費の1/3以内が補助されるため、家賃アップと同時に修繕費の負担軽減が可能です。
加えて、固定資産税の軽減策として、中小事業者が保有する住宅用設備の省エネ改修を行った場合、翌年度の固定資産税が1/3減額される制度(2025年度適用)が継続中です。これらの制度を組み合わせると、初期投資を抑えつつ物件価値を高められるため、未経験者が一棟買いで躊躇しがちな修繕コストの不安を和らげられます。
まとめ
ここまで、一棟買いの魅力とリスク管理、収益シミュレーション、融資戦略、物件選定、2025年度の税制・補助制度までを解説しました。マンション投資は未経験でも、事前の情報収集と具体的な数字に基づく計画を立てれば再現性の高いビジネスになります。まずはシミュレーションを作り、地元金融機関に相談するところから始めてみてください。行動を起こすことでしか経験は積めません。正しい知識と慎重な計画を武器に、一棟買いの可能性を自分のものにしましょう。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 不動産取引価格情報検索 – https://www.land.mlit.go.jp
- 総務省統計局 人口推計 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁 タックスアンサー「減価償却」 – https://www.nta.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート – https://www.boj.or.jp

