年収700万円の会社員でも、アパート経営で安定した家賃収入を得られるのか――この疑問は、多くの読者に共通する悩みだと思います。実は、適切な資金計画と物件選びさえできれば、給与所得に加えて月々数万円から十数万円のキャッシュフローを生み出すことは十分に可能です。本記事では、年収700万の方を想定し、初期資金の目安、融資条件、物件の選定基準、さらに2025年度の税制や補助制度まで、最新情報をもとに詳しく解説します。読み終える頃には、自分にも再現できる具体的なステップが見えてくるはずです。
年収700万円でアパート経営は本当に始められるのか
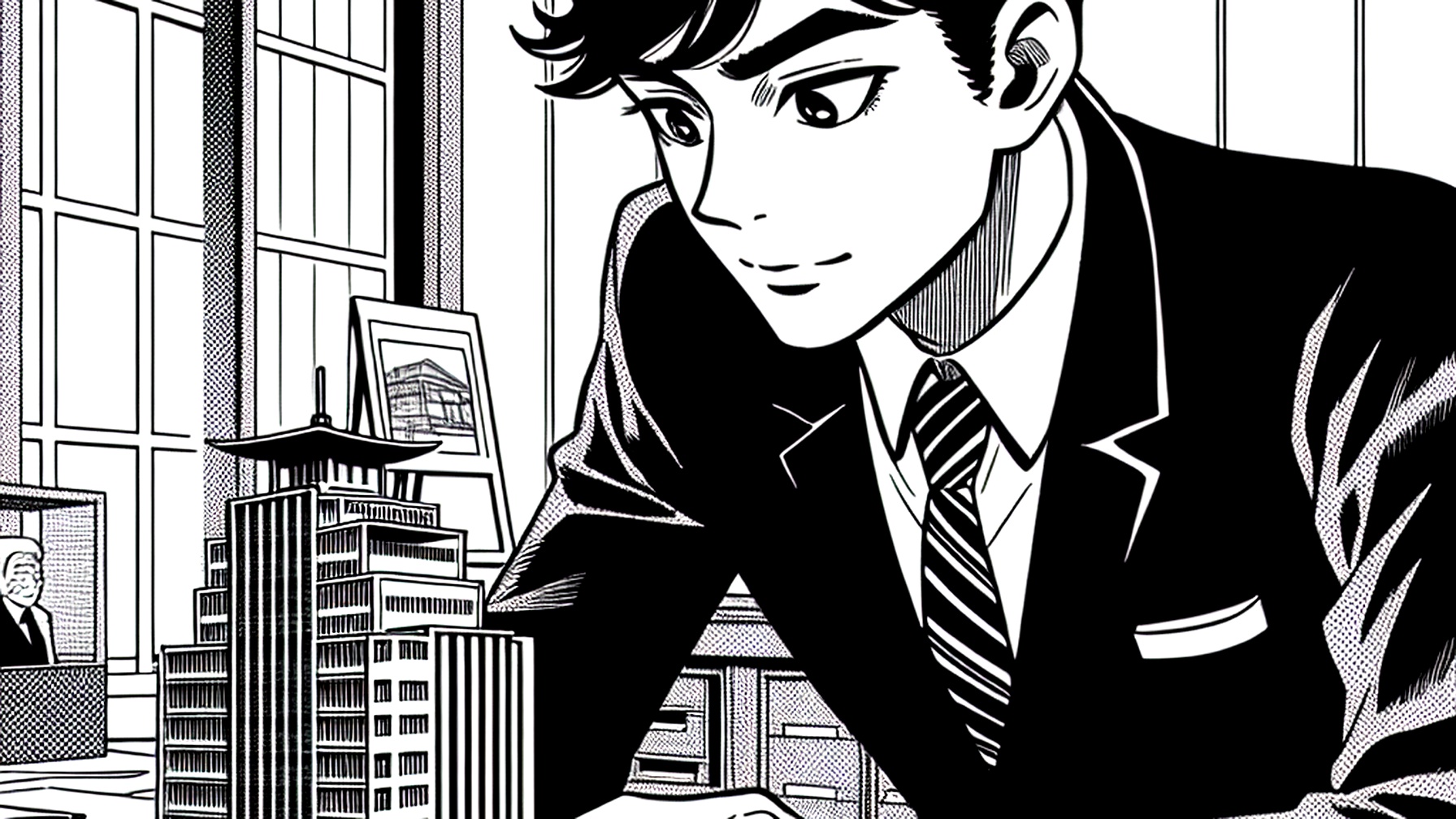
まず押さえておきたいのは、金融機関が年収に対してどの程度の融資枠を認めるかという点です。一般的に、年収の7〜10倍が融資上限の目安とされ、年収700万円なら4,900万〜7,000万円程度まで借入が可能と試算できます。もちろん、勤続年数や負債の有無によって変動しますが、自己資金1割と組み合わせれば、総事業規模8,000万円前後のアパート取得も視野に入ります。
次に、キャッシュフローのイメージを具体化してみましょう。仮に都心近郊で築10年、総戸数6戸、表面利回り7%の木造アパートを6,500万円で購入した場合、年間家賃収入は455万円です。空室率を国土交通省の2025年8月データ(全国平均21.2%)より保守的に25%で計算すると、実効収入は341万円になります。運営費率30%、返済比率50%と置くと、年間キャッシュフローは約68万円、月ベースで5万6千円前後が手元に残る計算です。つまり、給与以外の副収入としては十分インパクトがあります。
一方で、融資金利は物件評価に大きく左右されます。日本銀行の統計によると、2025年6月の投資用住宅ローン平均金利は2.1%ですが、信用情報や共同担保の有無により±0.5%程度振れます。金利が0.5%上昇するだけで年間返済額が約30万円増えるケースもあるため、収支シミュレーションには余裕を持たせることが重要です。
収益性を高めるための資金計画と自己資金戦略
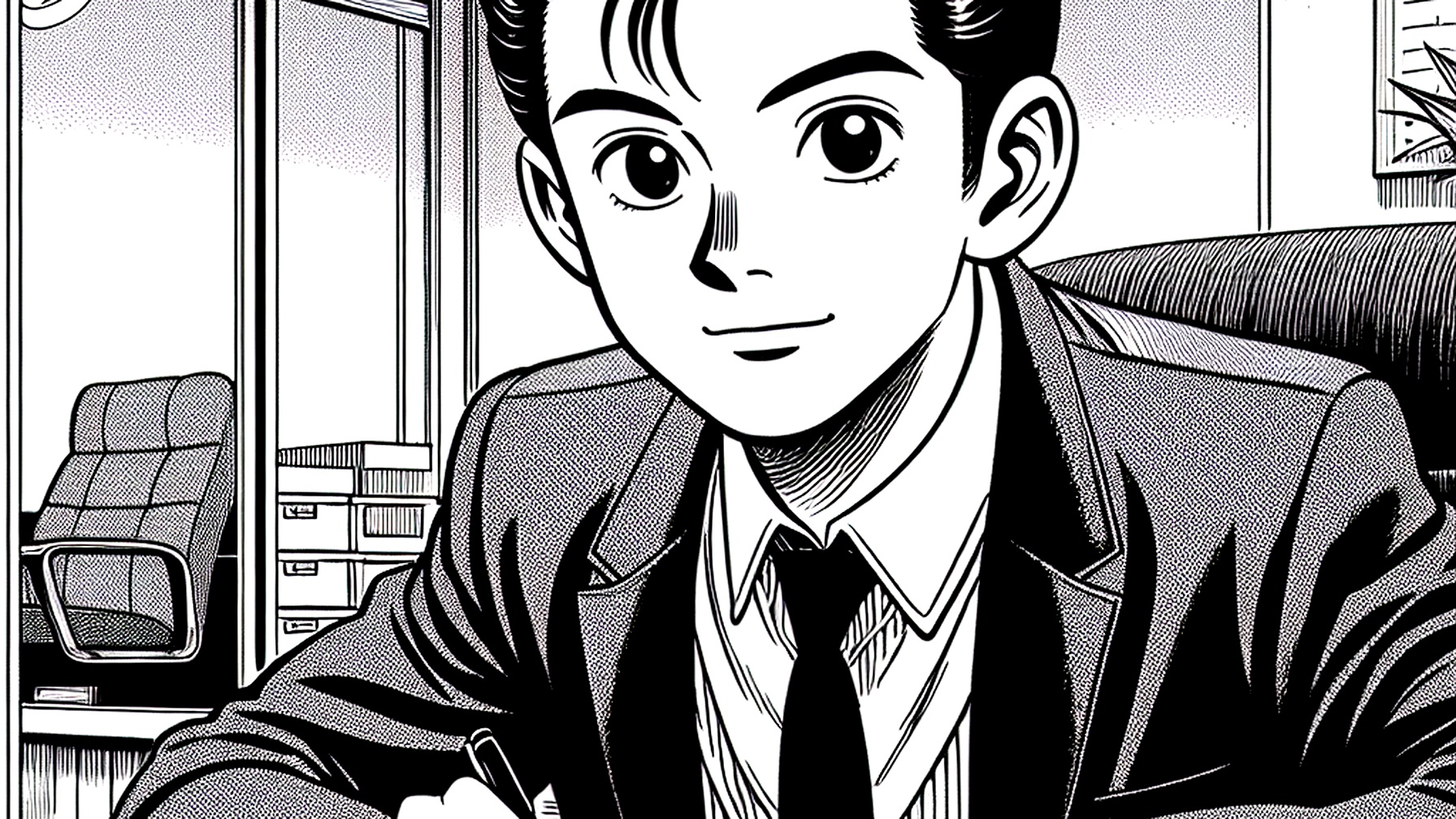
ポイントは、自己資金をどこまで投入するかで収益性と安全性のバランスが変わることです。自己資金を物件価格の20%用意すると、融資審査が通りやすくなるだけでなく、毎月の返済額も圧縮できます。例えば先ほどの6,500万円の物件に1,300万円の頭金を入れると、ローン残高は5,200万円になります。同じ2.1%・25年返済でも、月返済額は約22.1万円から17.7万円へ下がり、年間キャッシュフローは約110万円に向上します。
しかし、自己資金を全て物件購入に充ててしまうと、突発的な修繕や退去リフォームに備えられません。国交省「長期修繕計画ガイドライン」では、築10年超の木造アパートでも年間家賃の5〜7%を修繕積立として確保することを推奨しています。よって、最低でも家賃収入の6か月分、できれば100万円以上の予備資金を別口座に残しておくと安心です。
また、団体信用生命保険(団信)の内容も見逃せません。がん・三大疾病保障付帯プランを選んでも、金利上乗せが0.2%程度であれば、家族への保障と比較して費用対効果が高いと言えます。家計全体を見渡しながら、投資と保険のバランスを設計する発想が収益性向上につながります。
物件選びとエリア分析で失敗を防ぐ
重要なのは、表面利回りだけに惑わされず、需要と供給のバランスを見ることです。総務省「住民基本台帳人口移動報告」によれば、2024年から2025年にかけて都心5区の人口は微増を維持していますが、郊外では減少傾向が続いています。したがって、単身者向け6〜8戸規模のアパートは、駅徒歩10分圏内かバス便でも商業施設が近いエリアに絞るのが無難です。
さらに、築年数ごとのリフォーム費用を把握しておくと、購入後の想定外コストを減らせます。木造なら築15年で外壁塗装が必要になり、1戸あたり15〜20万円が目安です。それらを踏まえ、利回り7%前後でも実質利回り5%を確保できる物件を探すと、手残りが安定します。
エリア選定の際は徒歩・昼夜それぞれの現地調査が欠かせません。昼間の人通りが多くても夜に街灯が少なければ女性入居者の募集が難しくなります。また、敷地内ゴミ置き場や宅配ボックスの有無は、賃料水準に直接影響するため、物件写真だけで判断しない姿勢が大切です。
運営コストと長期リスクをどう管理するか
まず、運営コストの約半分を占めるのが修繕費と管理費です。管理会社の委託手数料は家賃の5%が相場ですが、複数社を比較し、入居付け実績と原状回復の見積もり透明性を確認してください。安さだけで選ぶと、結果的に空室期間が長引き、収益性が落ちるケースが多発します。
一方で、空室リスクはエリア需給だけでなく、物件の差別化でも軽減できます。Wi-Fi無料設備やスマートロック導入は、1戸あたり初期費用が4〜6万円ですが、家賃を月1,000円上げられれば2年半で回収可能です。入居者満足度が高まれば、退去抑制にもつながり、中長期的に広告費を圧縮できます。
火災保険と地震保険は、保険料が経費計上できるうえに、災害発生時の復旧費をカバーします。ハザードマップで浸水リスクが高い地域なら、免責金額を下げて補償額を手厚くするほうが結果的にコストパフォーマンスが良くなる場合もあります。つまり、リスクを見える化し、対策コストを前向きに投資する発想が欠かせません。
2025年度の税制優遇と補助制度を味方に付ける
実は、2025年度税制改正では、中小規模の賃貸住宅オーナーを支援する措置が継続しています。たとえば、不動産所得の青色申告特別控除65万円は、電子帳簿保存とe-Tax提出を前提に適用されるため、クラウド会計ソフト導入が必須です。控除額が上限まで使えれば、課税所得を抑えつつ、キャッシュフローを維持できます。
減価償却については、木造アパートの法定耐用年数22年が維持されており、築浅物件を購入すると償却費が少なくなる点に注意が必要です。逆に、築25年以上の木造を購入すると、4年で償却できる「旧耐用年数超過」の特例が引き続き使えます。ただし、耐震基準適合証明を取得しないと金融機関の評価が下がりやすいので、構造計算書や図面の確認を怠らないようにしましょう。
補助制度では、国交省の「賃貸住宅省エネ改修等推進事業」が2025年度も継続し、窓断熱や高効率給湯器の導入に対して工事費の1/3(上限120万円)が補助されます。補助対象は2026年3月31日着工分までの予定です。省エネ性能を高めると入居者満足度が上がり、長期的な空室リスク低減にも直結するため、活用しない手はありません。
まとめ
ここまで、年収700万の会社員がアパート経営で収益を確保するための要点を整理しました。融資枠の目安、自己資金のバランス、エリア分析、運営コストの最適化、そして2025年度の税制優遇と補助制度までを押さえれば、毎月5万円超のキャッシュフローを実現するシナリオは現実的です。最後に行動に移すかどうかが最大の分岐点になります。まずは金融機関への事前相談と、気になるエリアの現地調査から始めてみてください。今の一歩が、将来の安定収入への近道になります。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅局「住宅市場動向調査2025年版」 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省「全国賃貸住宅空室率調査(2025年8月)」 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行「貸出約定平均金利等の推移」 – https://www.boj.or.jp
- 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告 2025年版」 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁「令和7年度所得税及び復興特別所得税の手引」 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省「賃貸住宅省エネ改修等推進事業 2025年度概要」 – https://www.mlit.go.jp

